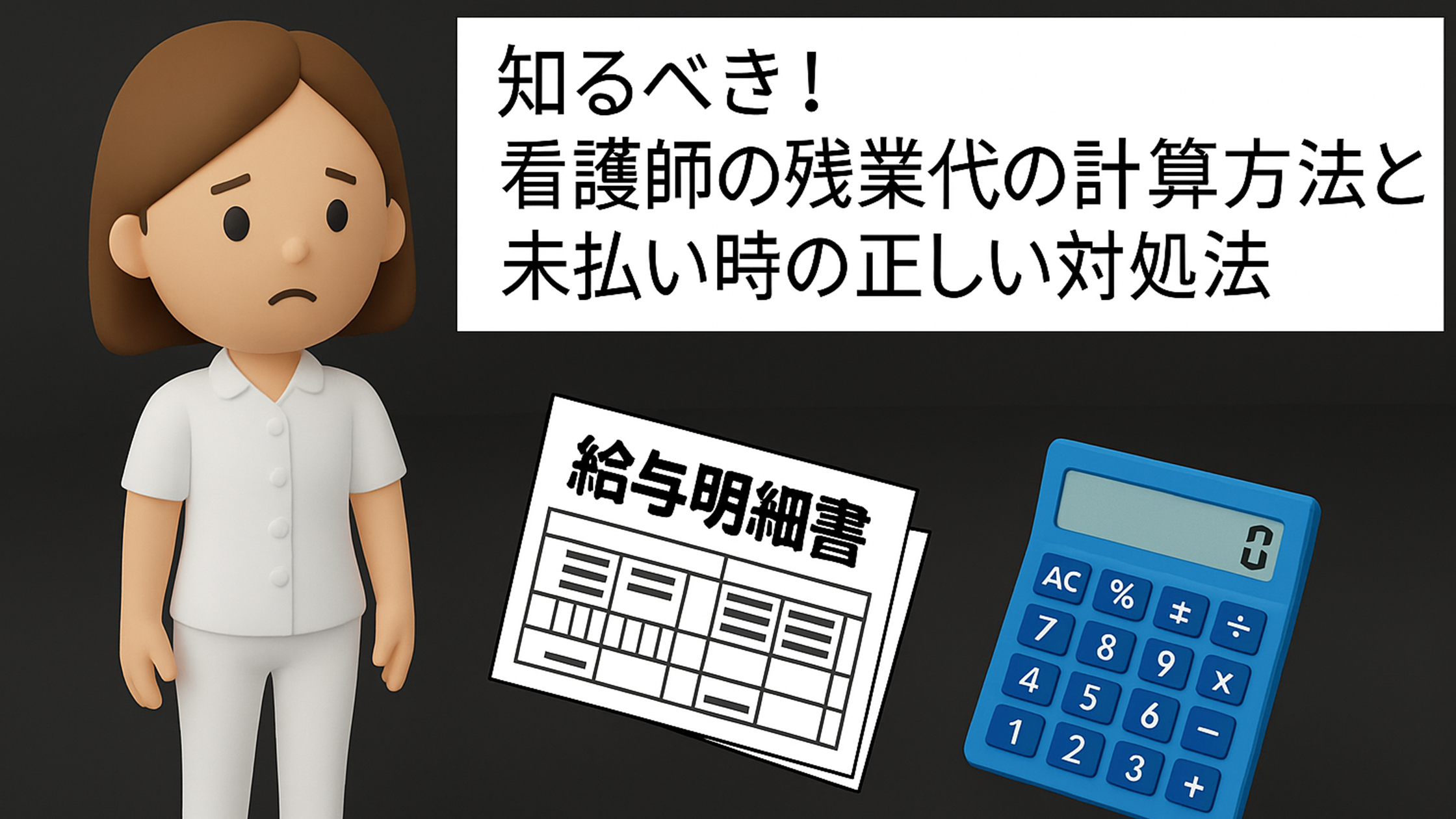
「結構残業しているのに給料が少ない…」と感じていませんか。
看護師の多くが残業をしながらも、適切な残業代が支払われていないケースが少なくありません。これは「みなし残業」制度の理解不足や記録の残し方に問題があることも。
この記事では、看護師の残業代がどのように計算されるのか、その基本ルールや計算方法、そして実際に役立つアプリやチェックポイントをわかりやすく紹介します。
看護師の残業、どこからが「残業」になるの?
終業時刻になっても、申し送りや突発的な処置、看護記録の入力が残っており、「なかなか病棟から離れられない」という経験は、多くの看護師にとって日常茶飯事かもしれません。
しかし、「まだ業務の延長だから」と曖昧にしてしまうと、本来受け取れるはずの残業代を取りこぼしてしまうリスクがあります。どこからが「残業」になるのかをきちんと理解しましょう。
法定労働時間とは?
法定労働時間とは、労働基準法で「上限」として定められた労働時間を指します。具体的には1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないと規定されており、この範囲を超えると時間外労働(残業)となります。
また、病院の就業規則に書かれている勤務時間は「所定労働時間」と呼ばれます。たとえば、日勤が7時間30分で設定されている職場の場合、7時間30分~8時間の間は「法定内残業」扱いで割増賃金の対象外、8時間を超えた分が初めて時間外労働となる点に注意が必要です。
※参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧、厚生労働省
看護師特有の勤務形態と「みなし残業」「変形労働時間制」
夜勤を含む二交代(16時間夜勤)や三交代(準夜・深夜各8時間)といったシフトは、勤務と勤務のあいだが6時間未満になるケースも珍しくありません。日本看護協会の調査によると、三交代勤務者の57.9%が「日勤→深夜勤」のような超短間隔シフトを経験したと回答しており、看護師の働き方はそもそも不規則で残業が混在しやすい構造になっています。
こういった環境でよく話題に出るのが「みなし残業(固定残業代)」です。これは、一定時間分の時間外・休日・深夜労働をまとめて定額で支給する制度のこと。日本看護協会「残業・休日出勤」Q&AのQ15では、病棟看護師長の定額手当に残業代を含める場合でも「含まれる時間数の明示」「超過分は別途支給」が必要と回答されています。看護職向けに固定残業代の基本を示しています。
また、多くの病院が採用しているのが「変形労働時間制」です。1か月または1年単位で労働時間を平均し、週40時間を超えない範囲で日ごとの勤務時間を伸縮させる仕組みであり、夜勤を含むシフトを法定内に収めやすいメリットがあります。しかし、導入には労使協定(就業規則への規定を含む)と具体的な勤務カレンダーの作成・事前提示が必須で、協定で定めた枠を超えた分には割増賃金が発生します。
※参考:厚生労働省
実は見逃されやすい! 休憩・仮眠時間の扱い
勤務中、「一応“休憩”とされているが、ナースコールが鳴れば即対応」や「仮眠時間でも患者の容体を気にしながらの待機」といった状況は、決して珍しくありません。これらの時間は本当に“労働時間外”として扱って良いのでしょうか。
労働基準法では、休憩時間は「労働から完全に解放されている時間」でなければなりません(労基法第34条)。形式上の休憩でも実際に業務指示に応じる義務があれば「労働時間」です。これは夜勤中の仮眠時間にも適用されます。「仮眠が取れているから大丈夫」という思い込みが残業代の未払いにつながる可能性があるため、注意しましょう。

研修のときはどうなる?
看護師の世界では、院内研修や勉強会、委員会活動、資格取得のための外部講習などがよく行われます。特に新人教育や事故防止研修などは、業務の一環として義務づけられている場合も多いでしょう。では、これらの「研修時間」は労働時間に含まれるのでしょうか。
労働基準法上、研修や教育の時間が「労働時間と認められるかどうか」は、「使用者の指揮命令下にあるか」が基準となります。たとえば、以下のような条件を満たす場合、その時間は労働時間にあたると考えられます。
- 出席が義務づけられている(参加しないと不利益がある)
- 時間や場所を職場側が指定している
- 業務に必要な内容であり、実質的に業務の一部とみなされる
つまり、たとえ「任意参加」と名目上は書かれていても、事実上出なければならない雰囲気がある、または上司からの出席指示があった場合などは、「労働時間」として扱い、残業代を計算する必要があります。
特に勤務時間外に実施される研修や、夜勤明けに連続して開催される勉強会などでは、参加時間が「時間外労働」に該当するかどうかの見極めが大切です。実際に厚生労働省の通達でも、「使用者の指揮命令下にある教育訓練の時間は労働時間に含まれる」と明記されています。
残業代はどうやって計算する? 基本の計算式の手順をチェック
看護師の残業の実態は理解できたけど、「この残業って何分からつくの?」「そもそも時給換算するといくら?」といった疑問を感じているのではないでしょうか。
この章では、労働基準法に基づいた残業代の計算方法を、看護師にもわかりやすくステップごとに解説していきます。割増率や計算に使う「1時間あたりの賃金」の求め方、さらには深夜・休日労働が関わる場合の扱いまで、基本のルールをしっかり押さえて、働いた分の対価を正しく受け取りましょう。
ステップ1. 基本時給を算出してみよう(月給÷月の平均所定労働時間)
まず、「残業代の土台になる1時間あたりの賃金」を決めます。月給制の看護師の場合、次の順で計算してみましょう。
- 月給(残業計算に含める手当だけを合算)を用意
- 月の平均所定労働時間で割って時給を出す
<計算式>
基本時給 = 月給 ÷ 月の平均所定労働時間
※月の平均所定労働時間の一般的な値:173.3時間/月(年間休日105日、1日8時間勤務の場合)
<計算例>
月給280,000円の場合:280,000円 ÷ 173.3時間 ≒ 1,615円(基本時給)
ステップ2. 割増率を確認してみよう(通常残業25%・深夜50%・休日35%)
労働基準法37条に定められた割増率(割増賃金率)を確認していきましょう。看護師の残業計算でも、以下の最低ラインを押さえておくことが大切です。
- 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分)… 基本時給の25%以上
- 深夜労働(22:00〜翌5:00)… 基本時給の25%以上
- 法定休日労働(病院が就業規則で定める「法定休日」に勤務)… 基本時給の35%以上
- 月60時間を超える時間外労働… 基本時給の50%以上(2023年4月から中小病院にも適用)
ステップ3. 実際に計算シミュレーション(月30時間残業の場合)
「月給28万円、基本時給1,615円、残業30時間(通常20時間+深夜10時間)」の場合:
通常残業:1,615円 × 1.25 × 20時間 = 40,380円
深夜残業:1,615円 × 1.50 × 10時間 = 24,230円
合計:64,610円
このモデルケースでは月30時間の残業で約6.5万円の割増賃金が発生します。
看護師の残業代の相場ってどれくらい?
厚生労働省「令和5年 賃金構造基本統計調査」と日本看護協会「2023年 病院看護実態調査 報告書」を参考にして計算すると、常勤病棟看護師の残業手当は月1.5万~2万円前後が平均的となります。
<計算例(通常残業=25%割増の場合)>
2,556円(*1) × 1.25 × 5.2時間(*2) ≒ 16,600円/月
*1:1時間あたりの基礎賃金(所定内)(「令和5年 賃金構造基本統計調査」より)
*2:月間平均時間外労働時間(「2023年 病院看護実態調査 報告書」より)
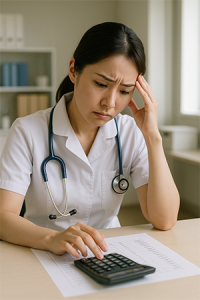
簡単に残業代を計算できる! 無料で使えるソフトとアプリ
自分で残業時間や割増率を正しく計算するのは意外と難しいもの。そんなときに役立つのが、無料で使える残業代計算ソフトやアプリです。手軽に入力するだけで正確な残業代を導き出してくれるため、忙しい看護師の強い味方となるでしょう。
エクセルで簡単に作れる! 残業代自動計算シート(ソフト)
エクセルを使えば、特別なソフトをインストールしなくても、簡単に残業代を自動計算するシートを作成できます。関数や条件付き書式を活用すれば、勤務時間を入力するだけで自動的に残業時間や割増賃金を算出する仕組みが完成します。
![]()
<各項目の説明と計算方法(関数例)>
- 勤務時間 = 退勤時刻 – 出勤時刻 – 休憩時間
例:=(D2-C2)*24 – E2(単位は「時間」にする) - 所定外労働(残業) = 勤務時間 – 8時間(所定労働時間)
例:=IF(F2>8, F2-8,0) - 深夜労働 = 22:00〜翌5:00に該当する勤務時間部分(少し複雑な計算になります)
- 残業代 = 残業時間 × 時給 × 割増率
例:
– 通常残業(25%割増)→ =G2*時給*1.25
– 深夜残業(50%割増)→ =H2*時給*1.5
最終的には =通常残業代 + 深夜残業代
時給と残業時間を入力するだけ!「時間外給与計算電卓 -残業代計算-」(アプリ)
これは、iPhone向けの無料アプリであり、時給と残業時間を入力するだけで簡単に残業代を計算することができます。手軽に給与の目安を把握できるので、とても便利なアプリです。

※ダウンロードは、コチラヘ
残業の証明に! 残業代の計算も◎「残業証明アプリ」(アプリ)
このアプリでは、出退勤時刻や業務内容を記録し、残業時間を自動で集計できます。アプリ内に記録されたデータはPDFとして保存・共有が可能で、もしものときに「残業していた証拠」として活用することが可能。
また、記録された残業時間から残業代の自動計算も行えるため、給与の確認にも役立ちます。働いた時間を“見える化”しておきたい方や、万が一の労働トラブル対策をしておきたいときに頼れる存在に。シンプルな操作性で、日々の労働記録を無理なく続けられます。

※ダウンロードは、コチラヘ
ソフト・アプリで残業代を計算する上で気をつけること
残業代計算アプリやソフトは、簡単な操作でおおよその支給額を把握できる便利なツールですが、いくつか注意が必要です。
たとえば、法定内残業と法定外残業の違いを正しく反映できているか、深夜手当や休日出勤手当が自動で加算されるかどうかは、アプリやソフトによって異なります。また、割増率が最新の労働基準法に準拠しているかも重要な確認事項です。
そのほか、労働時間の入力方法によって計算結果にズレが生じることもあります。たとえば、始業・終業時間の打刻タイプか、実働時間を手動入力するタイプかで、記録精度が異なります。勤怠記録と照らし合わせたチェックを行うことで、より正確な残業代を把握できるようになります。
実際の給与支給額は会社の就業規則や雇用契約に基づいて計算されるため、アプリの結果はあくまで「参考値」として活用するようにしましょう。
よくある「未払いパターン」に要注意!
一見、適正に支払われているように思えても、実は見落とされがちな「未払い残業代」のパターンがあります。特に、曖昧な労働時間の管理や、就業規則に基づく説明の不徹底などが原因で、知らないうちに本来支払われるべき残業代がカットされているケースも少なくありません。見落とさないように気をつけましょう。
みなし残業で上限を超えている
たとえば、月20時間分の残業代が給与に含まれているにもかかわらず、実際には30時間、40時間と残業しているような場合、その差分については本来、追加で支払われるべきです。しかし、「みなしで払っているから大丈夫」と誤認され、そのまま未払いとなってしまうのが典型的です。
みなし残業制度が適用されている場合は、契約書や就業規則に明記された上限時間をしっかり確認し、それを超える労働については別途請求が可能かどうかをチェックしておくことが重要です。
休憩時間とみなされているが実質働いている
労働基準法では、6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えることが義務づけられています。しかし実際には、「休憩時間」とされているにもかかわらず、業務から完全に離れられないケースも。
たとえば、電話番をしながらの休憩、来客対応を求められる状況、あるいは「とりあえず席にいてね」と言われるだけの休憩など、形式的には休憩でも、実質的には業務の延長といえる状態は注意が必要です。こうした場合、法的には「労働時間」として扱われる可能性があり、本来であれば賃金の支払い対象となります。
「休憩中でも気が抜けない」「常に上司や患者さんに対応できる状態にしておくよう言われている」と感じたら、それは単なる“休憩”ではないかもしれません。曖昧な休憩時間の扱いにより、気づかぬうちに未払いが発生していることもあるため、勤務実態をしっかり振り返りましょう。

タイムカードと給与明細が一致していない
タイムカードで正確に出退勤時間を記録していても、その内容が給与明細に反映されていないケースは意外と少なくありません。たとえば、タイムカード上では21時まで働いているのに、給与明細には19時までの勤務として処理されていたり、残業時間が少なく計上されていたりする場合です。
こうしたズレは「集計ミス」として片づけられてしまうこともありますが、悪意のある操作や不透明なルールによって意図的に調整されている場合もあるため注意しましょう。特に、手書きの勤怠表への転記や人事・総務部門による独自の修正が入る職場では、差異が発生しやすくなります。
自分の働いた時間が正しく賃金に反映されているかどうかを確認するためにも、毎月のタイムカード記録と給与明細を照合する習慣をつけることが大切です。少しでも疑問を感じたら、記録を元に勤務実態を整理し、必要に応じて説明や確認を求めるのもひとつの手段です。
「残業代が支払われていないかも…」と感じたら? 確認したい5つの対処ステップ
「なんとなく給料が少ない気がする」「毎日残業しているのに手当がついていない」などの違和感を抱いたときこそ、まずは冷静に状況を確認しましょう。残業代の未払いが疑われる場合、いきなり会社に訴えるのではなく、客観的な記録や契約内容を整理しながら、段階的に確認と対応を進めるのが基本です。
ここでは、トラブルを避けつつ自分の権利を守るために確認しておきたい5つのステップを紹介します。「言いにくい」「証拠がない」と感じる方でも実行しやすい内容になっているので、1つずつチェックしていきましょう。
ステップ1. 勤務記録と給与明細を見直して証拠を集める
まず、行うべきなのは「証拠の整理」です。具体的には、自分が実際に働いた時間と、それに対して支払われた給与の内容を突き合わせて確認します。タイムカード、勤怠管理アプリのスクリーンショット、業務日報、メールの送信時刻、PCのログオン記録など、客観的に勤務時間を示せるものはすべて保存しておきましょう。
同時に、毎月の給与明細もチェックして、基本給や支給されている残業代の内訳、残業時間数の記載が実際の働き方と一致しているかどうかを見直します。「みなし残業」が含まれている場合は、その上限時間と実際の労働時間に差がないかも忘れずに確認しましょう。
ステップ2. 就業規則・労働契約書を確認する
次に会社との間で取り交わされた労働契約書や、社内で定められている就業規則の内容を確認します。これらには、残業代の支払い条件や計算方法、みなし残業の時間数、割増率などが明記されているはずです。
たとえば、「みなし残業が月20時間分まで支給される」と記載されている場合、それを超える労働に対しては別途支払いが必要です。また、「残業代は○分単位で支給」といった細かなルールがあることもあるため、見落としに気をつけましょう。
万が一、契約書のコピーが手元にない場合は、会社の人事担当者に確認を取るか、社内ポータルや労務システムに掲載されている規定を参照するのがおすすめです。「何がルールか」を知らなければ、自分の労働時間がルール通りに扱われているかどうか判断することはできません。契約内容と自分の勤務実態を照らし合わせることで、未払いの有無をより明確に把握できるようになります。
ステップ3. 上司や人事に冷静に相談する【穏やかな交渉フレーズ集】
証拠と契約内容を整理できたら、次は職場内での相談です。未払いが確定的であっても、いきなり強い言葉で詰め寄るのではなく、冷静かつ丁寧な姿勢で伝えることが円満な解決に繋がります。上司や人事担当者に「話し合いの場」を設けてもらうよう働きかけましょう。
主張を伝えやすくする穏やかな交渉フレーズ例:
- 「すみません、少しお時間よろしいでしょうか。最近の勤務時間と給与の件で気になることがありまして…」
- 「自分でも確認したのですが、勤務記録と給与明細に少しズレがあるように感じています。ご確認いただけますか?」
- 「就業規則にある残業の取り扱いについて伺いたいのですが、詳しく教えていただけますか?」
- 「間違いだったら申し訳ないのですが、念のため確認をさせていただければ安心できると思いまして…」
重要なのは、「責める」のではなく「確認させてください」というスタンスを保つこと。相手が防御的にならず、対話の余地が生まれやすくなります。相談内容は日付・相手・話した内容をメモやメールで記録しておくのも忘れないようにしましょう。

ステップ4. 無料の相談窓口を活用する(労基署・労働組合・ホットライン)
社内での話し合いで解決が難しい、あるいはそもそも相談するのが難しい環境にある場合は、第三者の無料相談窓口を利用してみましょう。特に、労働時間や賃金に関するトラブルは専門的な知識が必要になることもあるため、プロの視点でアドバイスを受けることで道が開けることがあります。
<主な相談先>
- 労働基準監督署(労基署)
各地域に設置されており、労働基準法に違反する可能性のある企業に対して指導・調査を行います。匿名相談も可能で、必要に応じて是正勧告などの行政対応が行われることも。 - 労働組合(ユニオン)
企業内の組合だけでなく、誰でも加入できる「個人加盟型ユニオン」もあります。交渉のサポートや、会社との話し合いに同席してくれるケースも。 - 厚生労働省の相談ホットライン(労働条件相談ほっとライン)
土日祝日も対応しており、電話やメールで気軽に相談できます。専門スタッフが残業代や契約内容に関する疑問に答えてくれます。
→ 厚生労働省 労働条件相談ほっとライン
これらの窓口は無料で利用できる上、匿名での相談も可能な場合が多いため、「会社に知られたくない」という方でも安心。ひとりで抱え込まず、外部の力を借りて解決への第一歩を踏み出しましょう。
ステップ5. 法的手段に出る前に確認すべきことと請求の流れ
社内交渉や相談窓口を活用しても解決しない場合、最終的な選択肢として「法的手段(未払い残業代の請求)」を検討することになります。ただし、訴訟や労働審判に踏み切る前に、いくつか確認しておくべき重要なポイントがあります。
まず大切なのは、証拠の整理が十分にできているかということ。勤務記録・給与明細・就業規則・相談の履歴などを、時系列でわかりやすくまとめておくと、第三者機関や弁護士にもスムーズに伝えることができます。また、未払いが発生してから2年(または3年)以内のものしか請求できないとされる「時効」にも注意が必要です。
<一般的な請求の流れ>
- 内容証明郵便で会社に請求書を送る(自分でも可、弁護士に依頼も可能)
- 交渉が決裂した場合は労働審判や訴訟へ移行
- 最終的に裁判所の判断により支払いが命じられる場合も
初回相談無料・成功報酬制の事務所も多いため、費用面が気になる人でも一度相談してみる価値はあります。
法的手段は精神的にも体力的にも負担がかかるプロセスですが、泣き寝入りせず、自分の正当な権利を守るための最後の選択肢です。慎重に準備を進め、信頼できる専門家のサポートを受けながら行動しましょう。
退職した場合でも残業代はもらえる! 請求書の書き方は?
「もう病院を辞めたから、今さら残業代なんて請求できない…」と諦めていませんか。 実は、退職後であっても未払いの残業代を請求することができます。労働基準法では、労働者が辞めた後でも、一定期間内であれば会社に対して正当な賃金を請求できる権利が認められています。
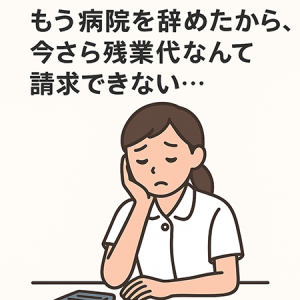
もちろん、退職後の請求には少しだけ注意が必要です。たとえば、証拠の保管状況や会社との連絡方法、そして何よりも「きちんと伝わる請求書」の書き方など、押さえておきたいポイントがあります。
この章では、退職後に残業代を請求するための基本知識と、実際に使える請求書の書き方の例を紹介します。退職後も正当な残業代をもらうために、ぜひ参考にしてみてください。
請求できる期間(時効)に注意しよう
忘れてはいけないのが「時効」の存在。労働基準法の改正により、2020年4月以降は賃金の時効が原則3年に延長されました。ただし、改正前に発生した賃金については2年が適用されるケースもあるため、時期によって確認が必要です。
時効のカウントは、賃金の支払日(通常は翌月の給与支給日)から起算されます。たとえば、2022年3月に働いた分の残業代であれば、2025年3月の支払日までが請求のリミットとなります。これを過ぎると、たとえ未払いがあっても法的に請求する権利が消滅してしまいます。
退職時点で「過去の残業代が未払いかもしれない」と感じた場合は、なるべく早めに記録を整理し、請求の準備を進めることが大切です。迷っているうちに請求できる期間が過ぎてしまわないよう、時効を意識して行動しましょう。
請求する際の流れを確認しよう
トラブルを避けながら、きちんと請求できるように基本的な請求の流れを把握することが大切です。
<基本的な請求の流れ>
- 証拠の整理
タイムカード、業務メール、PCのログ履歴など、実際の労働時間がわかる資料を集めます。給与明細や雇用契約書、就業規則も必要です。 - 請求内容の計算
集めた記録をもとに、自分が請求すべき残業時間と残業代を計算します。自動計算アプリを使うのも便利ですが、割増率(25%、深夜なら50%など)が適用されているかを忘れず確認しましょう。 - 請求書を作成する
請求金額・対象期間・支払期限などを明記し、相手に伝える書面を作成します。フォーマルな形式である必要はありますが、難しい法律用語を使う必要はありません。ポイントは「いつ」「どれだけ」「なぜ」請求するかを明確にすることです。 - 郵送またはメールで送付する
請求書は、内容証明郵便で送ると後の証拠として有効です。メール送付でも可ですが、必ず送信履歴を残しておきましょう。 - 回答を待つ・必要に応じて交渉または相談へ
会社側からの連絡を待ち、誠実な対応があれば話し合いを進めます。もし対応がない・拒否された場合は、労働基準監督署や弁護士など第三者の力を借りる判断も視野に入れておきましょう。
請求はあくまで事実に基づいた正当な行為。感情的にならず、段階を踏んで対応することで、相手の反応も変わってくるはずです。
残業代請求書は、特別な法律知識がなくても基本の構成に沿って丁寧に書けば問題ありません。ただ、相手にとって分かりやすく、具体的な内容が整理されていることが重要です。誤解やごまかしが入り込まないよう、事実ベースで構成することが信頼性にもつながります。
<主な構成要素>
- 宛先(会社名・代表者名)
正式名称を使用し、可能であれば代表取締役の名前を明記します。 - 差出人(自分の氏名・連絡先)
退職済みであっても、連絡がとれる住所・電話番号・メールアドレスを記載しましょう。 - 請求の趣旨(目的・対象期間)
「〇年〇月〜〇年〇月までの未払い残業代について、下記の通りご請求申し上げます」といったシンプルな書き出しでOKです。 - 請求内容の詳細(時間数・金額・内訳)
「〇時間 × 時給〇円 × 割増率〇% =〇円」など、具体的な計算根拠を記載。対象となる月ごとにまとめると親切です。 - 支払方法と期日
「〇年〇月〇日までに、以下の口座へお振り込みください」など、明確に支払期限を設定し、振込先情報を添えます
今の職場での改善が難しいなら、転職も視野に
残業代の未払いに悩み、社内での相談や外部機関への問い合わせ、請求など、できる限りの対応をしても状況が改善しない場合、転職を考えるのもひとつの手段です。
正当な権利を主張しても認められない職場に居続けることは、心身の消耗やキャリアが停滞してしまうかもしれません。そんな労働環境から抜け出し、健全な職場で能力を発揮することこそ、自分自身を守る一歩です。
残業代がしっかり支払われる職場の見極め方
次の職場では「残業代がちゃんと支払われるかを重視したい…」というのが本音。とはいえ、求人票だけでは見抜きにくいことも多いため、いくつかの視点から事前にチェックすることが重要です。
<残業代の支払い状況を見極めるためのポイント>
| チェックポイント | 内容・確認の観点 |
| 求人情報の記載内容 | 「残業代は全額支給」と明記されているかを確認。「固定残業代含む」「当社規定による」など曖昧な表現には注意し、支給条件や時間数の記載をチェック。 |
| みなし残業制の明示 | 「月〇時間分の固定残業代含む」など、時間数・制度の内容が明示されているかを確認。超過分の支払い有無も重要。 |
| 口コミ・第三者情報 | 転職会議・OpenWorkなどの口コミサイトを活用。現場の声や労働時間・給与満足度などのレビューを確認。 |
| 面接での質問 | 「月平均の残業時間は?」「残業代の支給ルールは?」など、具体的な質問を通じて企業の姿勢を見極める。 |
| 労働条件通知書・契約書の確認 | 内定後に交付される書類に、残業代の取り扱いが明記されているかを確認。不明点は署名前に質問することが重要。 |
しっかりした企業ほど、労働条件を開示する姿勢も丁寧な傾向にあります。「曖昧にされたら要注意」という視点で選ぶことで、次の職場での不安を大きく減らすことができるでしょう。
実際に残業少なめ・高待遇の求人事例(紹介形式も可)
「残業が少なく、なおかつ待遇も良い仕事なんて本当にあるの?」と思ってしまう方もいるかもしれません。ですが、実際には働きやすさと待遇を両立させた求人は確実に存在します。ここでは、求人事例の一部をご紹介します。
【事例:クリニック勤務/内科・皮膚科(東京都・正社員)】
勤務時間:8:30〜17:30|残業:月5時間以内|年収:450万円〜|日祝休み
特徴:
- 完全予約制で患者対応がスムーズ
- 電子カルテ導入により記録業務の効率化
- 土日休みで夜勤なし、プライベートを大切にできる
- 小規模クリニックで人間関係も良好、離職率低め
【事例:訪問看護ステーション(神奈川県・正社員)】
勤務時間:9:00〜18:00|残業ほぼゼロ|年収:500万円〜+手当充実|オンコール当番は月2〜3回程度
特徴:
- 訪問件数は1日4〜5件で無理のないスケジュール
- 直行直帰・電子カルテ入力の効率化で残業削減
- 子育て中のスタッフも多く、柔軟な働き方が可能
※内容は一例です
転職エージェントの活用もひとつの手段
自力で求人を探すのが不安な方や、「今より良い職場に出会えるか心配」という方には、転職エージェントの利用もおすすめです。特に看護師や医療系の職種に特化したエージェントでは、非公開求人や条件交渉の代行など、個人では得にくい情報やサポートを受けることができます。
また、エージェントは応募先とのやりとりや面接日程の調整、履歴書・職務経歴書の添削、場合によっては労働条件の「裏事情」まで教えてくれることもあります。なかには、「残業代の支払い実態」や「職場の雰囲気」「離職率」など、求人票だけでは見えない内部情報を教えてくれる担当者もいます。
無料で利用できるエージェントが多いので、「ちょっと相談してみる」くらいの気持ちで登録しておくのも良いでしょう。自分一人では見つけられなかった“理想に近い働き方”に出会えるかもしれません。
まとめ|自分の働き方と給与を見直そう
残業代の未払いは、「たかが数時間」と軽く見られがちですが、月単位・年単位で積み重ねると、大きな金額になる可能性があります。さらに、本来受け取るべき対価が支払われないまま働き続けることは、心身の疲弊やモチベーション低下にも繋がってしまいます。
この記事で紹介してきたように、まずは勤務記録や給与明細の見直しから始め、必要に応じて社内相談、外部機関の利用、さらには転職という選択肢まで、自分の権利を守るための行動を段階的にとっていくことが大切です。
看護師としてより力を発揮できるよう、きちんした給与、無理のない勤務時間、信頼できる職場で働きましょう。





