
看護師のボーナスが一体どれくらいなのか、気になりませんか?
「別の病院で働く友達の看護師より少ない気がする…」
「ボーナスを上げるにはどうすればいいの?」
仕事のモチベーションにもなる「ボーナス」の平均額が知りたくなるもの。ズバリ、看護師のボーナスの平均額は約85万円です。「え…平均額より下なんだけど…」と悩む看護師もいるのでは?ボーナスが少ない理由や増やす方法を一緒に考えていきましょう。
この記事では、以下のような内容を紹介します:
看護師のボーナスの平均額
ボーナスの計算方法と内訳
ボーナスが少ないと感じたときにすべきこと
ボーナスを増やすためのキャリア戦略
Q&A
プロの現場を知る看護師目線で、「看護師のボーナス事情」を解説しています。ぜひブックマークして、ボーナスについて不安があるときに役立ててくださいね。
看護師のボーナス、あなたは平均より上?下?【最新データ】
自分の給料が一般的な看護師のボーナスの平均より上か下か、どうしても気になってしまいますよね。もしかしたら、「頑張っているのに、実は平均以下だったら…」と不安に感じることもあるかもしれません。
そこで、最新のデータに基づき、看護師のボーナス平均額を解説します。経験年数、地域、病院の規模や種類によるボーナスの傾向まで紹介するので、ぜひご参考に!

看護師ボーナスの平均額は約85万円!
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、看護師のボーナス平均額は年間約85万円です。この数字はあくまで目安であり、実際には個人の経験年数や勤務先の種類によって大きく変わる可能性があります。
特に、公立病院や大学病院のような大規模医療機関では、安定したボーナスが期待できる傾向に。しかし、クリニックや小規模施設では、平均を下回るケースも少なくないでしょう。
【経験年数別】1年目からベテランまでの推移を見てみよう
看護師のボーナスは、経験年数とともに増加する傾向に!たとえば、看護師1年目は寸志程度か支給されないこともありますが、3年目、5年目と経験を積むにつれて徐々にボーナスは上がっていくのが多くの場合に当てはまります。
これは、経験とともに専門知識やスキルが向上し、病院への貢献度が高く評価されるためです。さらに、経験10年を超えるとボーナスは安定し、役職手当などが加わることでさらに増える可能性もあるでしょう。
ボーナス推移(例)
| 経験年数 | ボーナスの年間平均額(推測) |
| 1年目 | 20万円程度 |
| 2〜3年目 | 40万円〜70万円程度 |
| 4〜6年目 | 70万円〜90万円程度 |
| 6〜10年目 | 80万円〜100万円程度 |
| 11年目以上 | 90万円〜120万円程度 |
地域・病院の規模・種類でこんなに違う!ボーナス傾向
看護師のボーナス額は、地域や病院の規模、種類によって大きく異なります。都市部の病院は地方に比べて基本給が高く、ボーナスも高額になりがち。
また、大学病院や総合病院といった大規模病院は、経営基盤が安定しているため、ボーナスも手厚い傾向が見られます。一方で、クリニックや介護施設など、規模が小さい施設ではボーナス額が抑えられることも少なくないでしょう。
ボーナス傾向(例)
| 分類 | ボーナスの年間平均額 |
| 地域別 | |
| 都市部(東京、大阪、愛知など) | 85万円〜120万円以上 |
| 地方都市(主要な県庁所在地など) | 70万円〜90万円程度 |
| 地方(過疎地域など) | 50万円〜80万円程度 |
| 病院の種類・規模別 | |
| 大学病院・総合病院(大規模:500床以上) | 90万円〜130万円以上 |
| 一般病院(中規模:100~499床) | 70万円〜100万円程度 |
| 専門病院(精神科、小児科など) | 60万円〜90万円程度 |
| クリニック・診療所(小規模:病床なし~19床) | 0〜50万円程度 |
| 介護施設・訪問看護ステーション | 0〜60万円程度 |
| その他(健診センターなど) | 50〜80万円程度 |
「手取り」はいくら?ボーナスの計算方法と内訳
給与明細を見て「思ったより手取りが少ないな…」と感じた経験はありませんか?看護師のボーナスも、支給額がそのまま手元に入るわけではありません。
実は、額面からさまざまなものが差し引かれて、最終的な「手取り額」が決まるのです!さて、ここでは、ボーナスから具体的に何がどのくらい引かれるのか、その計算方法と内訳を紹介します。

ボーナスから引かれる税金・社会保険料はどのくらい?
看護師のボーナスから差し引かれるのは、主に社会保険料と税金。社会保険料には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が含まれます。これらの保険料は、ボーナスの総支給額(額面)に対して一定の料率を掛けて算出されます。
具体的には、以下の要素が控除されます。
- 健康保険料:
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なり、毎年見直しが行われます。たとえば、東京都の場合、2025年度(令和7年度)の協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.91%です。
この料率は労使折半となるため、従業員である看護師の方の負担分は約4.955%が目安となります。「標準賞与額」(賞与から1,000円未満を切り捨てた額)にこの料率を掛けて計算される仕組みになっています。
参考:協会けんぽ「令和7年度都道府県単位保険料率」 - 厚生年金保険料:
厚生年金保険料率は、平成29年9月以降、18.3%で固定されています。これを労使折半するため、従業員負担分は9.15%に。ボーナスからは「標準賞与額」(賞与の総支給額から千円未満を切り捨てた額)にこの料率を掛けて計算されます。
参考:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」 - 雇用保険料:
雇用保険料率は、毎年見直しが行われ、業種によって異なります。たとえば、一般の事業の場合、労働者負担分の雇用保険料率は、2025年度(令和7年度)の4月1日以降、0.55%(5.5/1000)が適用されています。
参考:厚生労働省「令和7年度の雇用保険料率について」
社会保険料が控除された後の金額に対して、所得税と住民税が課税されます。所得税は、ボーナスが支給された月の「前月の給与額」と「扶養親族の人数」によって税率が変動する傾向があります。
また、住民税は、前年の所得に基づいて計算されるため、ボーナスが支給される月の給与から控除される形で徴収される形です。
【シミュレーション】ボーナス手取り額を具体的に計算してみよう
では、ここで実際に看護師のボーナス手取り額をシミュレーションしてみましょう。たとえば、夏のボーナスが50万円(額面)支給されたと仮定します。
- 社会保険料を計算する。
健康保険料(例:東京都在住、協会けんぽの場合):500,000円 × 約5% = 25,000円
厚生年金保険料:500,000円 × 9.15% = 45,750円
雇用保険料:500,000円 × 0.6% = 3,000円
社会保険料の合計額は、25,000円 + 45,750円 + 3,000円 = 73,750円となります。 - 社会保険料控除後の課税対象額を計算する。
500,000円 – 73,750円 = 426,250円
この課税対象額に対して所得税を計算します。所得税の税率は、前月の給与額や扶養人数によって決まるため一概には言えませんが、ここでは仮に10%とします。
- 所得税:426,250円 × 10% = 42,625円
住民税は前年の所得によって決まり、今回のボーナスからは差し引かれません。そのため、ボーナス月の給与から住民税が控除されることになります。
したがって、この場合の看護師のボーナス手取り額は、
- 500,000円(額面) – 73,750円(社会保険料) – 42,625円(所得税) = 383,625円
このように、額面の約7〜8割が手取り額の目安となることが一般的です。支給額や個別の状況によって変動するため、あくまで一例として参考程度に!正確な手取り額を知るには、実際の給与明細を確認し、控除されている項目とその金額を把握しましょう。
ボーナスが少ないと感じたら…?その理由と取るべき行動
ボーナスは日頃の頑張りが評価される指標の一つ!期待を下回ると、モチベーションの維持にも関係します。
ここでは、看護師のボーナスが「少ない」と感じる理由、コロナ禍の影響、そして悩みを解決するために取るべき具体的な行動を解説します。納得のいくボーナスを得るヒントを見つけましょう。
「ボーナスがもらえない」「少ない」はなぜ?
看護師のボーナスが「もらえない」あるいは「少ない」と感じる背景には、いくつかの理由があります。最も大きな理由は、病院の経営状況。
収益が悪化している病院では、人件費であるボーナスが削減されるケースがあります。地域医療を支える中小規模病院や、経営基盤が盤石でない医療法人でこの傾向は顕著なのです。
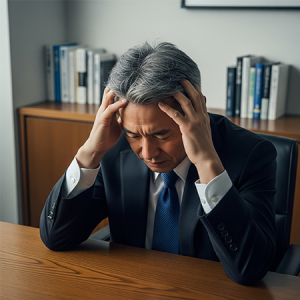
また、評価制度もボーナス額に大きく影響するでしょう。中には、個人の業績や貢献度、勤務態度が査定に反映される病院も。この評価が適切に反映されていない、あるいは評価基準が曖昧な場合、期待よりボーナスが少なってしまうかもしれません。
さらに、勤続年数や役職も重要!一般的に、勤続年数が浅い看護師や役職が低い看護師は、ボーナス額が少ない傾向があります。
これは、経験、スキル、責任の度合いがボーナスに反映されるため。転職直後で満額支給されないケースや、評価期間中に退職予定がある場合も減額されることが予想されます。
コロナ禍が看護師のボーナスに与えた影響と現状
新型コロナウイルス感染症は、看護師の働き方だけでなく、ボーナスにも大きな影響を与えました。感染拡大初期には、患者数の変動や緊急対応コスト増、通常診療の抑制などから、多くの医療機関が経営難に直面し、一時的にボーナスの減額や不支給に踏み切った病院も…。
一方で、コロナ患者対応やワクチン接種に携わった看護師には、特別手当や慰労金が支給されるケースもありました。これは、通常ボーナスとは別に支給され、一時的に収入が増えた側面も!
現在(2025年6月時点)では、新型コロナウイルスの位置づけも変わり、医療提供体制も通常に戻りつつあります。多くの病院では経営状況が回復傾向にあり、ボーナス支給額もコロナ禍以前の水準に戻る、あるいは超える事例も見られます。
しかし、地域や病院の種類によって経営状況に差があり、ボーナス水準もばらつきが見られます。コロナ禍を経て、医療機関の経営状況はより多様化しているのが現状です。
ボーナスにまつわる悩みと解決策
「ボーナスが少ない」、あるいは「もらえない」というのは、看護師にとって大きな悩みの一つ。この悩みを解決するためには、まず現状を正確に把握し、具体的な行動を起こしましょう。
- 支給規定・評価基準の確認:
まずは、病院のボーナス支給規定や人事評価基準を再確認します。評価項目や査定方法が不明な場合は、上長や人事担当者に説明を求めましょう。基準を理解すれば、ボーナスアップにどうつなげるかが分かります。 - 労働組合や部署内での相談:
もし病院全体でボーナスが低い、あるいは不当な評価を受けていると感じるなら、労働組合がある場合は相談するのも手!組合がない場合でも、信頼できる同僚や上司に相談し、部署全体で改善を検討することもできます。一人で抱え込まず、情報を共有することが解決への第一歩になるのです。 - スキルアップ・資格取得の検討:
ボーナスは、個人のスキルや専門性も評価されることがあります。認定看護師や専門看護師などの資格取得や、特定分野でのスキルアップは、ボーナスアップに直結するだけでなく、キャリア全体の価値を高めます。 - 転職も視野に入れる:
もし、現在の病院での改善が見込めず、自身の評価や努力が適切にボーナスに反映されないと感じるなら、転職を考えてみるのも良いでしょう。同じ看護師でも、医療機関の規模や種類、地域によってボーナス水準は大きく異なります。
スキルや経験を高く評価してくれる病院に転職することで、ボーナス額の大幅な向上が期待できるはず。転職を考える際は、転職エージェントなどを活用し、ボーナス水準や評価制度について事前にしっかり情報収集を行うことが成功の鍵!
ボーナスを増やす!看護師のキャリア戦略
「ボーナスがもう少し増えたら…」と願う看護師は少なくないでしょう。日々の業務に追われる中で、将来への不安を感じることもあるかもしれません。
しかし、ボーナスを増やすことは、決して非現実的な話ではありません。戦略的にキャリアを築くことで、あなたの努力は着実に収入として返ってきます!ここでは、看護師がボーナスアップを実現するための具体的なキャリア戦略を具体的に探っていきましょう。
ボーナスアップに直結する資格・スキルの習得法
看護師がボーナスを増やすには、専門性を高めるための資格取得やスキル習得が非常に効果的!特定の資格を持つ看護師は医療機関にとって貴重な存在であり、その専門性が給与やボーナスに反映されるのが一般的です。
特に、次のような資格はボーナスアップに繋がりやすいでしょう。
- 認定看護師・専門看護師:
高度な知識と技術を持つことを証明し、資格手当や基本給アップを通じてボーナス額も増加する傾向に。 - 特定行為研修修了看護師:
医師の指示なしで行える医療行為が増えるため、より高度な業務に携わり、職能手当やボーナスアップに繋がる可能性があります。 - 助産師・保健師:
看護師資格に加えこれらの資格を持つことで、活躍の場が広がり、専門職としての手当が支給されることも!
これらの資格習得には時間も費用もかかりますが、長期的に見ればキャリアアップと収入増への大きな投資になります。病院によっては資格取得支援制度があるため、上手に活用しましょう。
そのほか、資格がなくても、特定の疾患や治療の専門知識を深めたり、リーダーシップやマネジメントスキルを磨いたりすることも、評価向上とボーナスアップに繋がる大切なスキル習得です。
役職手当・職能手当を狙う!昇進・昇格でボーナスアップ
看護師のボーナスアップにおいて、役職手当や職能手当の獲得は非常に現実的な方法と言えます。これは、組織内での責任や役割が増すことに伴い、手当が加算される仕組みが関係しているのです!
一般的に、役職が上がると次のような手当が支給される傾向があります。
- 主任・副主任:
特定の病棟やチームの管理・指導を行い、役職手当が支給されます。 - 看護師長・副看護師長:
病棟全体の管理運営やスタッフ育成など、より広範なマネジメント業務を担うため、役職手当も高額になるでしょう。 - 看護部長:
看護部全体の統括責任者であり、病院経営にも深く関わるため、最も高い役職手当が見込まめす。
昇進・昇格を目指すには、日々の業務で高いパフォーマンスを発揮するだけでなく、リーダーシップや周囲のスタッフ育成能力が求められます。
人事評価制度に基づき、定期的な面談や目標設定が行われる病院も多いため、積極的に評価面談を活用し、キャリアプランや昇進への意欲をアピールすることも大切です。

「転職」はボーナスアップの近道?
現在の病院でボーナスアップが難しいなら、転職はボーナス増額の有力な選択肢!看護師のボーナスは、医療機関の規模、経営母体、地域、専門分野で大きく変わります。
たとえば、次のような転職先はボーナスアップを期待できます。
- 経営が安定している大手病院や高収益の専門病院
- 大学病院や大規模な総合病院(福利厚生も手厚い傾向)
- ボーナス比重の高い給与体系の病院
- 専門スキルや資格を高く評価し、手当で還元してくれる病院
ただし、転職には新しい環境への適応や人間関係の構築といったリスクも…。転職を考えるときは、希望する病院のボーナス実績、評価制度、福利厚生を事前にしっかり調べることをおすすめします。
【Q&A】看護師のボーナスに関するよくある疑問を解決しよう
看護師のボーナスにまつわる悩みは様々。そこで、ここでは、准看護師や助産師・保健師のボーナス事情から、パート・契約社員の場合、さらにはボーナスを賢く貯蓄・運用する方法まで、よくある疑問にQ&A形式で紹介します。疑問を解消し、ボーナス問題をスッキリさせましょう。
准看護師、助産師、保健師のボーナスは看護師とどう違う?
准看護師、助産師、保健師はそれぞれ役割が異なり、ボーナスにも違いが見られます。職種が持つ専門性や業務内容、勤務先の特性がボーナス額に影響を与えるのです!
- 准看護師:
一般的に、正看護師より基本給やボーナス額は低い傾向。業務範囲の限定や教育課程の違いが影響しています。経験を積んだり、正看護師資格を取得したりすることで、ボーナスアップも! - 助産師:
専門性の高い分娩介助や妊産婦ケアを担うため、正看護師より基本給が高く、ボーナス額も高い見込みがあります。出産件数の多い病院やNICUなどで働く助産師は、特に高いボーナスが支給されることも。 - 保健師:
地域住民や企業で働く人々の健康支援を行う専門職です。行政機関(公務員)で働く場合、安定したボーナスが一般的です。企業の産業保健師も、専門職手当が加算され、看護師より高いボーナスを得られるケースもよく見られます。
パート・契約社員の看護師もボーナスはもらえる?
パートや契約社員の看護師がボーナスをもらえるかは、勤務先の規定や雇用契約で大きく異なる場合があります。パートや契約社員でもボーナスを重視するなら、求人情報をよく見て、支給実績のある医療機関を選びましょう。
- 支給の有無:
正社員と同様に支給される場合もあれば、支給されない、あるいは寸志程度になることも少なくありません。短時間勤務のパートや契約期間が短い契約社員の場合、ボーナス対象外となるケースも。 - 計算方法:
支給される場合でも、計算方法は正社員と異なります。勤務時間や日数に応じた割合で支給されたり、あるいは固定額が定められていたりする傾向が見られます。 - 確認すべきポイント:
入職前に必ず雇用契約書でボーナス支給条件、計算方法、査定期間などを確認しましょう。曖昧な場合は、採用担当者や人事部に直接問い合わせ、書面で確認する必要があります。

ボーナスを効率的に貯蓄・運用する方法は?
せっかくのボーナス、ただ口座に置くだけではもったいない!という人必見です。看護師のボーナスを効率的に貯蓄・運用する方法をいくつか取り上げます。
- 目的別の口座に分ける:
「旅行資金」「老後資金」など、ボーナスを使う目的を明確にし、目的別に口座を分けるのがおすすめ。計画的に貯蓄を進められますよ。 - 先取り貯蓄・自動積立:
ボーナスが入ったら、まず一定額を貯蓄用口座へ「先取り」で移すのが鉄則!自動積立サービスを活用すれば、手間なく着実に貯められます。 - 資産運用を検討する:
ボーナスの一部を資産運用に回し、効率的に資産を増やすことも期待できます。NISA(新NISA) 非課税で投資ができ、初心者にも◎。ボーナスを活用した長期的な資産形成向き。 iDeCo(個人型確定拠出年金) 掛金が全額所得控除になるため節税効果が高く、老後資金形成に最適。 投資信託 少額から始められ、プロが運用するため知識が少なくても始めやすい。 - 固定費の見直し:
ボーナスを機に、毎月の固定費(通信費、保険料など)を見直しましょう。固定費削減は、毎月の貯蓄額を増やし、次回のボーナスでの貯蓄・運用に回せる金額増にもつながります。
貯蓄や運用は、自身のライフプランやリスク許容度に合わせて計画することが重要です。無理のない範囲で、将来を見据えた賢いボーナス活用を実践しましょう。
まとめ|ボーナスの悩みを解決して、理想の未来へ
看護師のボーナスは、病院の経営状況や個人の評価、役職、勤務形態で大きく変動するケースが多いです。なので、決して「思ったより少ない」と一人で悩まなくて良いのです!
もし今、ボーナスに不満があるなら、資格取得、昇進、そして転職といったキャリア戦略を検討する良い機会なのかもしれません。ボーナスに関する疑問や悩みを解決し、現状を把握することで、将来に向けた具体的な行動が見えてきます。
あなたの努力と知識が理想の未来、そして納得のいくボーナスへと繋がるはず。少しずつ、確実に行動を起こし、思い描く未来を実現しましょう。





