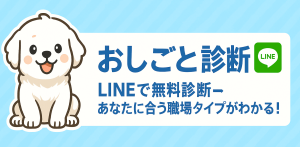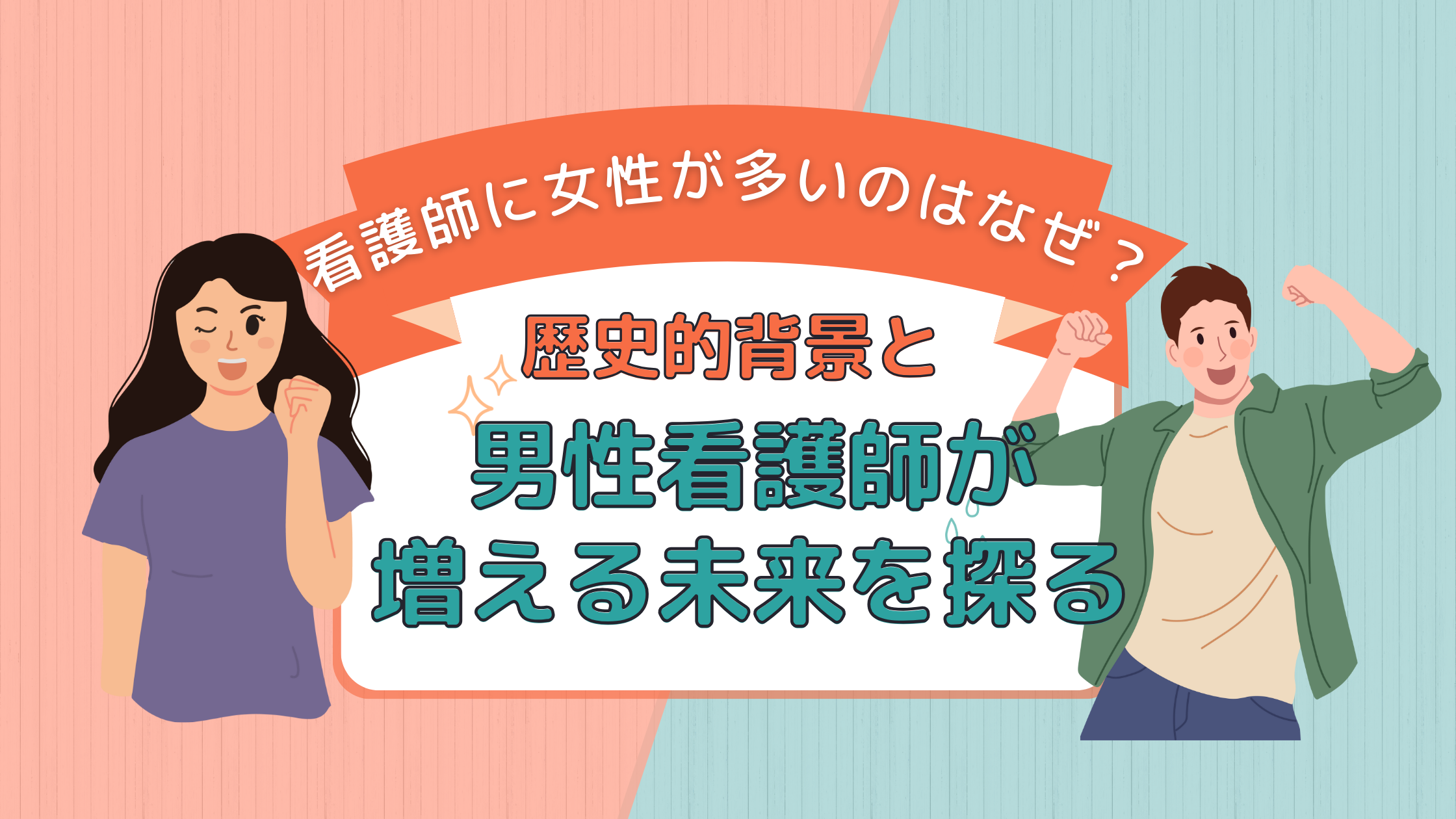
看護師というと女性の仕事というイメージがありますよね。
実際には男性看護師も増えていますが、厚生労働省によると2022年時点で看護師全体の10%以下と女性の仕事のイメージが拭えないのも納得です。
昔は男性が看護の資格を取ることができなかったことや世話をするという行為は女性のものという固定観念などが要因として挙げられそうです。
今回この記事では、
・なぜ看護師は女性が多いのか
・現代医療における課題
などを解説します。
男性も女性も関係なくいつでも見返せるようブックマークをお忘れなく!
なぜ看護師は女性が多い?
看護師は、医療専門職で五感をフルに使い患者さんのケアにあたる高い専門知識とスキルが必要な仕事です。
ただ、看護「師」となったのはだいぶ最近のことなのをご存じでしょうか。
以前は、看護「婦」と呼ばれていました。
1915年に制定された看護婦規則によって、看護婦という名称が定着し、この規則では、看護婦の資格は女性でなければならないと定められていました。
社会的背景
1950年代は男性が働き、女性は家を守るものとされてきたため、外での仕事の少なかった女性が、看護婦という職業を確立してきたという社会的背景も根底にあります。
現代では、男女平等が叫ばれていますが、長い間日本社会では、家事や育児など人の世話は女性が担うべきという固定観念がありました。
そうした固定観念がゆえに患者を世話する看護行為は女性が行うというイメージが定着していたとされています。
戦後はGHQ指導のもと保健婦助産婦看護婦法が制定され、看護行政基盤が整備されていきました。
1985年に成立した男女雇用機会均等法の影響もあり、徐々に男子学生が増加しましたが少数でした。
1992年に看護士などの人材確保促進に関する法律が施行されたり、1994年には訪問看護制度が開始、以前は助産師にのみ認められていた独立開業権が看護師にも認められたため、在宅介護サービスや福祉施設などのさまざまな場で看護師が活躍できるようになりました。
その後、男女雇用機会均等法が発表された影響で、仕事における男女平等という考え方が浸透し、2002年に男女共に看護「師」と呼ぶことに統一されることになりました。
こうした日本社会の変化で呼称も変化してきたことは大きな変化と言えるでしょう。
法改正によって性別による差がなくなったことで、2008年にはたった5.1%だった男性看護師も現在まで増加傾向が続いています。
もともと、女性にしか看護師になる権利が与えられていなかったことが女性看護師が多くなった理由なのですね。
歴史的背景
フロレンス・ナイチンゲールが看護の仕事を社会的に確立させました。
当時、イギリスにおいて病人や負傷者への看護は、主に身内によって行われていました。病院という施設は存在したものの、そこで働く看護師は、資格はおろか教育も受けられていない当時の言葉で最下層の女性たちによって担われていました。
その後、ナイチンゲールは看護のあり方や考え方を説いた看護覚え書を書きました。
この覚え書によって人類史上初めて「看護とは何か」という定義が明らかになったのです。
またナイチンゲールはイギリスのロンドンに看護婦養成所を設立し、本格的な養成教育をスタートさせました。
この教育システムはナイチンゲール方式と呼ばれ、日本にも多大な影響を与えることになりました。
こうしたナイチンゲールの教えは日本にとっても看護の礎となったのです。
日本においては、明治政府が取り入れた新しい西洋医学が導入されるまでは、病院と呼ばれる施設は存在しませんでした。
もちろん、看護を担う専門家としての職業看護師は存在しませんでした。
1886年に日本での看護教育創設が行われ、1890年には後の日本赤十字社病院となる博愛社病院で救護看護婦の育成が開始されました。
戦時の救護活動が当初の目的とされ、実際に戦地に多くの救護看護婦が派遣されました。
太平洋戦争が激戦になるにつれて看護婦の補充が急務になり、1942年には当時の高等小学校を卒業していれば入学することが認められただけでなく、2年で乙種救護看護婦になれる戦時措置が取られることになりました。
あくまでも戦時中の措置であったため、終戦と同時に撤廃された制度です。
その後、濃尾大地震での救護活動にも協力したことで災害時にも救護を行うことも目的に加わりました。
日本赤十字社は1896年に看護学教程の刊行も行っています。
男性看護師の割合はどれくらい?
冒頭でも触れたとおり、厚生労働省の発表によると2022年末時点での男性看護師の占める割合は8.6%となっています。
こう見ると全体の割合はまだまだ少ない印象を受けますが、職場に男性看護師はいるかどうかのアンケートによると、約60%の職場で男性看護師が在籍していることが分かりました。(ナース専科)
実際の職場では半数を超える男性看護師が活躍してることが分かります。
看護師の男女比
厚生労働省の統計によると、2022年時点では約90%が女性看護師で、男性看護師は8.6%と圧倒的に女性の占める割合が大きいのが現実です。
ただ、看護師の男女比率は過去10年間で変化していて、男性看護師は2012年には約6.2%だったので割合が上昇したことがわかります。
この偏りにはやはり女性が看護するものとされていた歴史的背景が大いに関係があります。
ですが、近年の医療の高度化やそれに伴う患者さんのニーズが多様化していることによって、男性看護師の需要が高まっているのです。
特に救急医療や集中治療室、精神科といった分野での需要が男性看護師の進出の後押しとなっています。
日本看護協会の調査によれば、看護師を目指す男子学生の割合は2021年時点で約10%に達しています。
将来的な変化をもたらす可能性が大いにある数字となっています。
男性看護師は増加傾向にある
2002年に、かつて女性=看護婦、男性=看護士という名称で呼ばれていましたが、性別にかかわらず看護師という名称を使うようになりました。
それ以降、男性看護師の就業者数は年間で1.8倍程度と緩やかではありますが、少しずつ増えています。
女性ほど男性看護師が増えにくい背景には、看護師は女性の仕事であるという社会のジェンダーバイアスが長年にわたり刷り込まれてきたことを筆頭に、長期的なキャリアパスの描きづらさなどの課題が考えられます。
しかし、高度な医療技術や知識を高めていくために、性別を問わず看護師として活躍できる環境へと変化させていくことが大切です。
自分に合う職場を見つけたいなら、“おしごと診断”を♪
「男性看護師・女性看護師というより、そもそも今の職場が自分に合ってるか分からない」と悩む方は、「おしごと診断」をやってみませんか?
あなたがどのようなタイプの職場に合うのかが分かりますよ!
LINEから診断できるので、いつでも・どこでもできます♪
〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜
医療業界における男女共同参画
そもそも男女共同参画社会とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と男女共同参画社会基本法第2条に定められています。
また、男女共同参画の基本的方針は「性別に関わらずすべての個人が互いにその人権を尊重し、各人が個性と能力を十分に発揮できる社会を実現すること」とされています。
男女共同参画社会の構築というと女性の男性に対する性差別の撤廃と社会参加をめざすイメージですが、看護界は逆です。
看護が女性の性役割から発生した歴史があるため、男性にとって協働しにくい職業となっていることから男性看護職からみると看護界においてはいまだに男女共同参画に至っていないと考えている方も多いようです。
看護教育現場の男女共同参画社会を整えるためには、男子学生を受け入れる設備の充実や教育の工夫、実習での差別をしない、自由な就業場所の選択などが必要です。
現状
古くは戦時中の男性負傷者の対応をするために女性が看護業を始めたことが看護師(婦)の始まりです。
炊事、洗濯などの家事も女性の仕事とされていたため、看護は女性の当然の任務と言われ、家事労働の一つとして存在し、その後、女性が生計を立てる職業として確立していきました。
1999年に男女共同参画社会基本法が公布となり施行され、2020年12月には、第5次男女共同参画基本計画が決定されました。
男女共同参画社会基本法が制定されるまでには、1985年の女子差別撤廃条約がもとになり、国籍法の改正や男女雇用機会均等法の制定、労働基準法の一部改正、家庭科教育に関する検討会議報告などが行われていきました。
。
ただ、2019年のジェンダー・ギャップ指数は、対象国153か国中、日本は121位でした。
このランキングは、経済・政治・教育・健康の4分野の指標を総合して算出するもので、日本の社会課題は、諸外国に比べジェンダー平等の推進のスピードが遅いことにあります。
特に経済分野と政治分野においては他国に比べ遅れを取っています。
その後制定された第2次男女共同参画基本計画以降、目標数値が決められ、さまざまな取り組みが進められてきましたが、多くの分野において目標は達成されていないのが現状です。
課題
家事・育児・介護などはまだまだ女性が担うべきという固定的な役割分担の意識が課題となっています。
こうした固定概念に近い認識は、スタッフの大多数が女性である看護の現場において、家庭や家族の事情によって退職や休職・急な休みが多くなってしまう現状に頭を抱えているのが現実です。
この現状は、看護師としてキャリアを積み続ける上で、妊娠・出産などのライフイベントとの両立の難しさを示すことにもなっています。
ただ、近年妊娠・出産・育児に関わる時期の職員に対する労働条件や労働環境の整備はかなり進み、育児休業を取得した後の復職も当たり前になりつつあります。
一方で、妊娠・出産などをせずに働く職員にしわ寄せがきてしまったり、不平等感があるといった声も上がっています。
また、男女が働きやすい職場づくりには、労働条件や環境を整備することだけではなく、多様な働き方を相互に尊重しあう風土の維持が必要になります。
さらに働き方に応じた評価や処遇もきちんと整える必要があります。
医療現場という命の危機と隣り合わせの現場では、緊急時や急変時において暴言などのハラスメントで人権が侵害されることが未だにあるということを認識しないとなりません。
(聖隷横浜病院が発表した資料より)
男性が看護師になるメリットは
歴史的にも看護師になることが許されていなかった時代もある男性看護師の存在ですが、現代では徐々に母数も増えつつある需要の高い仕事になっています。
とはいえ、まだまだ数にすると女性看護師よりも少ないですが、女性が一人では対応できない患者さんの介助や力仕事の場面、サポートなどで活躍できるメリットがあります。
また、同性の患者さんに安心感を与えられたり、体力勝負である夜勤でも活躍できます。
体力面
何と言っても医療の現場は体力勝負。
まず介護補助などは体位変換が必須になるため、男性看護師の腕力は大いに必要となるポテンシャルです。
メタボリックシンドロームや生活習慣病を患っている患者さんも最近では少なくはなく、そのような患者さんの介護をするには女性一人ではなかなか難しいため、男性看護師の腕力が必要となる場面です。
また、訪問看護の現場でも男性看護師の需要は高く、介助や介護を一人で担える体力は女性にはない強みであると言えるでしょう。
安定した体力は、夜勤のある看護師の仕事において重要なポイントです。
こうした場面で体力・腕力のある男性看護師がいると、人数を割かずに済み、スムーズに仕事が進むので頼りになります。
安定性
男性看護師の平均年収は約570万円と女性看護師の平均である400万円台から500万円台よりもかなり高くなっています。
高水準となっている理由の一つには、男性看護師が夜勤や特殊な診療科での勤務が多いことが影響していると考えられています。
また、出産や育児でキャリアを中断することもある女性看護師に対して、キャリアを継続しやすい男性看護師の方が年収の上がり幅が大きいと考えられます。
ただ、全ての病院がそうではなく、扶養手当や住宅手当などによって男女差を少なくする工夫がされていることも多くなっています。
このように男性看護師の平均年収は他業種や女性看護師と比較しても高く安定している職業ですが、勤務する病院によって設定額や基準額に違いが出てくるので、しっかり把握しておきましょう。
さらに安定を図るには、夜勤にも対応することが重要です。
体力もあり、力もあるので、夜勤でも重宝されるので、収入を上げたい・安定させたい場合は積極的に夜勤を行うことも手段の一つです。
男性看護師ならではの強みを生かし、安定した需要の元で平均年収をアップさせることができます。
同性患者からの支持
男性看護師が関わることで男性患者やそのご家族とのコミュニケーションがスムーズに進むケースがあります。
女性看護師が年配の男性患者に対して指導をしても聞き入れてもらえない場合に、男性看護師が伝えると素直に受け入れてくれることがあります。
男性同士の共感という面もありますが、それと同時に古くから社会に根付いてきた男のほうが偉いという女性蔑視の表れでもあるのかと思います。
もちろん、こうした状況を受け入れ続けるというわけではなく、例に挙げたような患者さんとコミュニケーションを取るべく、男性看護師が先陣を切り、環境を整えることでその後のコミュニケーションにつなげることが役割になるはずです。
また、男性特有の悩みに対する対応も男性看護師の重要な役割です。
女性看護師には話しにくいAGA治療内科や美容に関する悩みは同性に相談できるといいですよね。
悩みの内容もそうですが、思春期の患者さんであれば、年齢もあり、女性看護師には尚のこと相談しにくい悩みもあるので、こうした職場は男性看護師の需要が高いです。
女性看護師に厳しい言葉をかけたり、高圧的な態度を取る患者さんへの対応や感情的になった患者さんと上手くコミュニケーションを取ることで看護業務をスムーズに進むような対応が期待されています。
男性看護師の存在がトラブルを避けられることもあるので、こうした場面でも活躍できます。
男性看護師の声
男子看護師の需要は年々高まりつつあり、すでに活躍している男性看護師も非常に多いです。
実際に働いている方の声をいくつか紹介します。
男性看護師になってよかったと思うこと
https://ns.gyo-toku.jp/voices/v4.html
都内の病院に勤めるAさん。
男性看護師も働きやすい雰囲気で、教育体制もプリセプターシップを取り入れているため整っていて、一人ひとりのペースに合わせて学んでいくことができるのだそう。
自身の所属する病棟は、雰囲気が良いところが一番の魅力で、プライベートでも先輩や後輩関係なく遊びや旅行に行ったりと仲が良い関係性のため、困ったことや疑問に思ったことなどが聞きやすい雰囲気になっていると言います。
仕事へのやりがいも感じていて、特に患者さんが笑顔で退院するところを見送るときが一番だそうです。
他にも、患者さん本人やご家族が望んだ退院先に帰る姿を見ると「看護師として関われてよかった」と思えると話していました。
また、些細ではありますが、患者さんやその家族に名前を覚えてもらえるのも嬉しいとのこと。
チームリーダーを担うAさんは、今後も後輩たちの見本となるような忙しい時でも丁寧な対応を行い、リーダーシップを今以上に発揮し、患者さんに対してもチームに対しても良質なコミュニケーションがとれる環境づくりをしていきたいとのことでした。(行徳総合病院)
https://www.tmghig.jp/kango/message/male.html
特定集中治療室で勤務しているBさん。
日々、症状の重い患者さんへの看護ケアや処置を行っています。
急性期で全身状態が不安定な患者さんが集中治療室にはいるため、容体が急変してしまう患者さんも少なくありません。
そのため、重篤化の予防を図れるように、常にモニターや患者さんの状態を観察し、注意を払って介入を行っています。
患者さんは身体的な苦痛だけでなく精神的にも苦痛を感じている方も少なくないため、少しでも苦痛を和らげられるように業務に取り組んでいます。
こうした細やかなケアで、元気になっていく姿を見ると看護師としてのやりがいを感じると言います。
感謝の言葉をかけてもらえた時は、やっていてよかったと強く思うそう。
とにかく患者さんの話に耳を傾けることと笑顔でいることが日々心掛けていることで、話しやすいと思ってもらうことで患者さんも安心し、心の内を話してくれるようになる雰囲気づくりにつながっているのだそうです。
今後、日本は超高齢化社会の需要が高まるはずで、高齢者医療に興味がある方にとってとても働き甲斐がある職場だと感じていると言います。(東京都健康長寿医療センター)
https://fukuda-nurse.com/voice/man/20200316.html
看護師3年目の若手看護師のCさん。
自信が看護師を目指したきっかけになったのは、祖父が糖尿病で通院していたこと。
病院に通った時に目が見えない祖父の横を看護師さんが寄り添って歩いていたり、食事の介助やレクリエーションなどを行う姿を見て、自分もそんな風に患者さんに寄り添いながら役に立ちたいと考えるようになったのです。
前の病院から転職して現在の病院に来たため、前職とのギャップもあった。
入院のとり方や働き方のギャップが少しあり、時間管理に関して前の病院では、きっちり決まった時間に来るというやり方でしたが、今働いている病院では一人ひとりが自分で時間を組んでいるので、自分で考えて行動する時間が増えたと感じていると言います。
ベッドを運んだり力仕事に関しては、男性看護師が起用されやすいことや男性の患者さんの中には同性の看護師がいいと言ってくれるときに男性看護師として働いていてよかったと思うそうです。
他にも、患者さんやご家族から「担当してもらえてよかった」と言ってもらえると本当に看護師をやっていてよかったと感じる。
質の高い医療を提供するためには、コミュニケーションの質が高いチームである必要があると考えているので、コミュニケーションを積極的にとっていきたいと考えているとのこと。
(福田病院)
まとめ
看護師はなぜ女性が多いのかは長く古い歴史や社会的な背景が大きく関係していました。
時代も変わり、男性看護師も活躍する世の中になったからこそ、どんどん男女平等を進めていかなければなりません。
男女それぞれの良い面を活かせる社会づくりが必要ですね。
“おしごと犬索”で最適な仕事を見つけるのも手!
自分に向いてるお仕事を探したいなら、「おしごと犬索」に任せましょう。
LINEを通して、あなたの状況や希望を教えてくれれば、あなたに向いているお仕事を検索します。
〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜