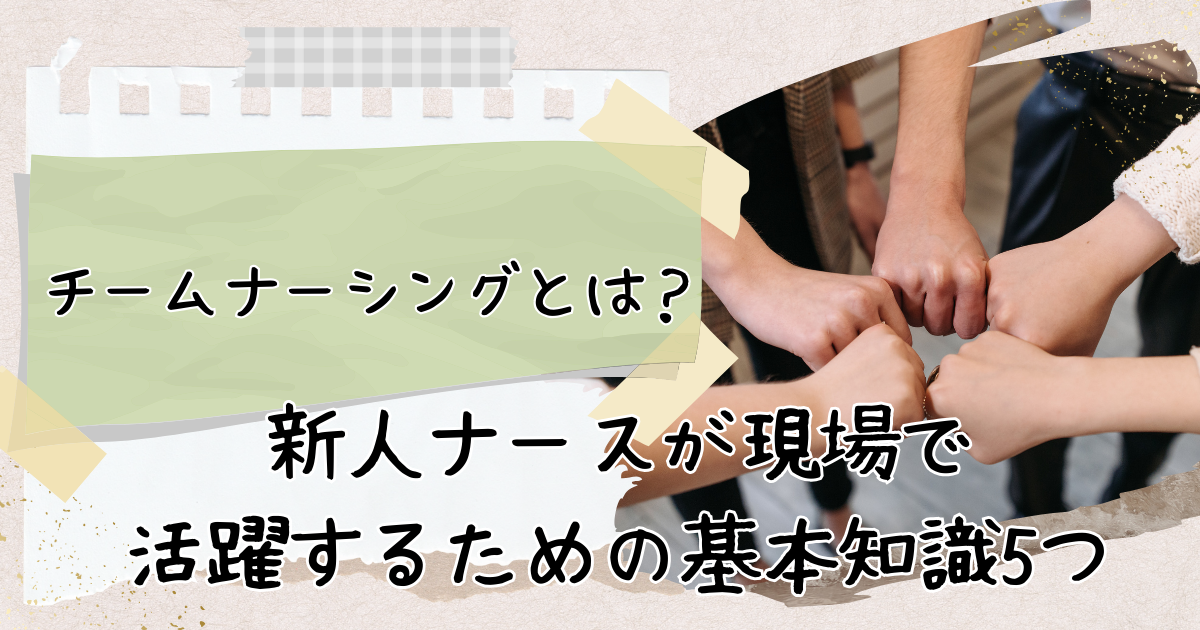
「チームナーシングって何?」「新人看護師として、どんな役割をはたせばいいの?」「なんか先輩にお願いしづらい」などのお悩みはお持ちではないですか?
特に新卒の看護師さんは、学校では完全受け持ちの実習を行っていたのでチームナーシングが何なのかが分からない方もいらっしゃると思います(わたしもサッパリわかりませんでした…)
チームナーシングは、看護師がチームで協力しながら患者さんをケアする看護方式で、新人ナースにとっても安心して成長できる環境が整っています!
チームナーシングの基本的な仕組みや、新人ナースとしての役割、さらにリーダーやメンバーの具体的な仕事内容をわかりやすく解説しますね!
チームナーシングとは?基本的な仕組みと特徴

まず、学生時代の看護実習は「プライマリー制度」になります。
限られた時間、期間ですので、実際のプライマリーナースとは少々違いますが、決まった患者さんを継続的に受け持つという点では共通する部分があると思います。
まずはチームナーシングの基本を学んでいきましょう。
チームナーシングの定義
「チームナーシング」とは看護方式の一つで、病棟内の看護師を複数のチームに分け、各チームが一定数の患者を受け持つ形で看護を提供する方法です。
チームリーダーを中心に、経験年数やスキルが異なるメンバーで構成され、役割分担をしながら患者さんに看護を行うことで円滑で質の良い看護を提供できると言われています。
チームナーシングの歴史と背景
チームナーシングは、1950年代にアメリカで開発された看護方式であり、看護の質を向上させるために導入されました。
当時、医療現場では看護師不足が深刻であり、効率的かつ質の高い看護を提供する必要がありました。
この背景から、複数の看護師が協力して患者をケアする「チーム」という概念が生まれたのです。
そして日本にチームナーシングが入ってきたのが1960年代です。
当時の日本の医療現場では「機能別看護方式」が主流でした。
また日本では、戦後の医療体制の再構築が進む中で、看護師不足や医療の質向上が課題となっており、解消法として取り入れられたのがチームナーシングです。
チームナーシングが採用される理由
チームナーシングは、看護師間の協力を促進し、患者さんに対して多角的な視点からケアを提供することを可能にすると考えられています。
また、新人看護師の育成にも適しており、教育的な側面でもニーズが高まりました。
チームナーシングのメリットとデメリット
多くの看護師からの多角的な視点からのケアを行うことができるチームナーシングですが、簡単にメリットとデメリットを確認していきましょう!

チームナーシングの主なメリット
機能性看護からチームナーシングに変えることは導入時には大きな負担がかかりますよね。
しかし、そこまでして、チームナーシングに変更した背景には以下のようなメリットがあるからなんです。

チームナーシングの主なデメリット
良いメリットがたくさんありますが、多くの病院が「完全チームナーシング制度」を取り入れているわけではなく、チームナーシングを基盤にした「モジュールナーシング」や「PNS(パートナーシップ・ナーシング・システム)」といった新しい看護方式も開発され、現場のニーズに応じた進化を遂げているのはなぜでしょう?
そこにはデメリットがあるからです。
どのようなデメリットがあるのでしょうか?

以上がデメリットとなります。
チームナーシングにおける役割分担
ここまででなんとなくチームナーシングには「リーダー」と「その他の人」がいるのが予測できたと思います。
実際にはどのように分担しあっているのでしょうか?

リーダーの役割と責任
まずはリーダーの重要さが上の文章を見てお分かりだと思います。
実際にどんなことが求められているのか見てみましょう!

以上がリーダーに求められる理想のスキルです。
リーダーに求められるのは、コミュニケーション力と判断力で十分だと個人的には思います。
メンバー看護師の役割
メンバーは、リーダーの指示のもとで患者の看護を担当し、チーム全体で協力しながら業務を進めます。
- 受け持ち患者さんの看護
- リーダーへの報告・連絡・相談
- チーム内での協力とフォロー
- 患者の入退院や転棟の対応
- 患者の安全確保と急変対応
受け持ち制とはいえ、他のメンバーのことを気にかけ積極的にサポートに回る姿勢が必要ということですね。
患者さんも他のメンバーの業務の進行状況も気にしないとならないのは大変そうですよね。
でも安心してください!
初めは自分のことでいっぱいいっぱいだと思いますが、そのうちに「あの人大変そうだなぁ」など見えてくるようになります。
新人看護師の役割と成長のポイント
リーダーとメンバーの気苦労を感じてしまいましたが、一方新人看護師にはどの様な影響があるのでしょうか?

| チーム全体でのフォロー体制 | 孤立しにくい環境と複数の視点からの指導がうけられる |
| 段階的な業務習得 | 成長に応じて徐々に責任のある仕事を任せてもらえる |
| 教育環境 | プリセプター制度との併用で、新人の進捗状況や課題が共有され、適切な指導が行われやすくなる |
| 不安の軽減 | 誰に聞いても教えてもらえる環境である |
| スキルアップの機会が多い | チーム全体で幅広い患者を担当するため、さまざまな症例に触れる機会が得られる(これ結構大切!!) |
| 離職率の低下 | 安心して働ける環境は、長期就業にもつながり、キャリア形成にもつながりやすい |
新人看護師からするとメリットが多いように感じられますね。
ただし、チームの先輩方がみなさん優しく理解のある方だということが前提にはなりますが…。
他の看護方式との違い:固定チームナーシングやプライマリーナーシングとの比較
チームナーシングが日本に入ってきて約80年。
しかし、先述した通り日本ではチームナーシングは独自の進化を遂げ、他の看護方式を併用して利用されていることも多いようです。
ここでは多くの病院で取り入れられている2つの看護方式の特徴も見てみましょう。

プライマリーナーシングとの違い

「プライマリーナーシング」というのは、患者さんの入院から退院までを1人の看護師がずっと担当する看護のやり方のことです。
この担当看護師のことを「プライマリーナース」って呼びます。
プライマリーナースは、患者さんの看護計画を立てたり、それを実行したり、結果を見直したりする役割を担っています。
なので、患者さん一人ひとりに合わせたオーダーメイドのケアができるのが特徴です。
さらに、患者さんだけじゃなくて、そのご家族とも関わる時間が増えるから、信頼関係を築きやすいのもポイント!
でも、良いことばかりじゃなくて、いくつか課題もあります。
例えば、担当する看護師の経験やスキルによってケアの質が変わってしまうことがあるし、他の看護師からの視点が少なくなることで、患者さんの体調の変化に気づくのが遅れることもあります。
固定チームナーシングとの違い
固定チームナーシングは、チームナーシングとプライマリーナーシングのちょうど中間にあたる制度です。イメージとしては、担当の看護師が一定期間患者さんを受け持ちつつ、バックアップとしてチームがサポートする形になります。
この方式では、患者さんにとって担当看護師が固定されているので、安心感を持ちやすいのが特徴です。
また、担当看護師も継続して看護計画に沿ったケアを行えるため、一貫性のある看護を提供しやすいです。
ただし、デメリットもあります。
例えば、チームナーシングでよく挙げられるリーダーの負担が大きいことや、メンバー同士で気を配る必要がある点です。
また、プライマリーナーシングのように患者さんの変化に気づくのが遅れる場合もあるため、注意が必要です。
固定チームナーシングは、メリットとデメリットを理解しながら、チーム全体で協力して運用していくことが大切ですね。
チームナーシングの導入事例と成功のポイント
どの方式もメリットとデメリットがあることが分かりましたね。
実際に、私が過去に勤めていた病院は両方ともチームナーシングでした。
看護師も人間ですので、患者さんとの合う合わない問題はありますよね…。
そういう点では、プライマリーや固定チームナーシングではなくて良かったと思っています。
看護師はもちろんのことですが、患者さん側からも「あの看護師さんは怖い」などというお言葉を聞いたりしますので、今日の担当が分かっていればそれでいいかなーというのが、1か月の入院経験をしている私の意見です。
では、どのようにしたらチームナーシングが円滑にいくのか、参考例を紹介します。
導入事例:成功した病院の取り組み
成功事例1: 経験豊富な看護師と新人看護師の協働
経験豊富な看護師と新人看護師が同じ病室を分担することで、患者ケアの質が向上した事例があります。
新人看護師が気づかなかった患者の異常を経験豊富な看護師が発見し、迅速な対応が可能となりました。
この協働により、新人看護師は先輩から学びやすくなり、成長を実感できる環境が整いました。
成功事例2: 動線の効率化による業務改善
チームナーシングを採用していた病院では、看護師の動線を見直し、必要な物品をカートにまとめて病室間を移動する仕組みを導入しました。
この改善により、スタッフステーションへの往復が減少し、患者ケアに集中できる時間が増えました。
これは人員と、動線を改善したものになりますね。
私の経験上、チームナーシングは部屋持ち制しか行ったことがなかったのですが、同じ病室にベテラン看護師がいればすぐに分からないことも聞けますし、ベテラン看護師も新人看護師の会話や様子からすぐに観察に行くことができますし、対応の仕方に問題があった場合には注意をすることができますよね。これは「チームナーシング」と「PNS」の中間みたいな感じになるかなと思います。
また必要な物品は私の勤めていた病院でも取り入れていましたが、処置カートを使用せずに、必要物品だけを自分の専用カートに乗せて患者さんの所に伺っていました。
しかし、まだまだ万能ツボを使用したり、滅菌ガーゼが小分けになっていない病院などは導入がなかなか難しそうですね。
チームナーシングを成功させるためのポイント
チームナーシングを実際に導入しているものの、うまく機能していなかったり、一部の人だけに負担が多くかかってしまっているということはないでしょうか?
ここでは成功させるポイントを2つ紹介します。
コミュニケーションの重要性
チーム内で定期的にカンファレンスや情報共有の場を作ることで、看護師同士の連携がよりスムーズになり、患者さんの状態に素早く対応できる体制を整えることができます。
実際に私の勤めていた病院も、お昼前に10分間のミニカンファレンスを実施し、お互いの患者さんの情報や、個々の業務の進み具合を報告していました。
それにより、午後の動き方の調整をしたり、手伝えることは事前に役割分担をすることで業務を時間内に終了させることができるようになりました。
適切な役割分担とリーダーシップ
チームナーシングでは、リーダーナースがチーム全体を統括し、業務を効率的に割り振ることが重要です。
とはいっても、私も2年目から妊娠を機にリーダー業務をしていましたが、先輩たちが仕事ができすぎるプロフェッショナルだったので、全然指示などしなくても各々動いてくれていました。
看護計画の評価の日だったり、医師から治療内容変更の指示があったときのみ、その都度伝えるような感じでした。
チームナーシングを活用した新人看護師の成長方法
まさにチームナーシングの中で育ってきた私ですが(病棟全部で1チーム)、チームナーシングで本当に良かったと思っています。
ここでは一般的な例に沿って説明していきますが、ところどころ私の経験も添えさせていただきます。

新人看護師が学べること
まず、学べることとして、ほぼ毎日受け持ち患者さんが変わるので様々な状況を経験できるということです。
というか、様々な疾患を持つ患者さんに向き合わざるを得ない環境といいましょうか。
同じ科のなかでも様々な疾患を持つ方がいらっしゃいますし、同じ疾患名を診断されていても個々の治療内容は変わります。
そうなるとこの患者さんにはこのケアが有効だけど、あの患者さんには有効ではないという判断ができるようになります。
様々な経験ができることは、自分の「できないこと」を知る、いい機会であり、次に学ばなくてならないことが明確になります。
プリセプター制度との連携
プリセプターは看護師歴3年目の歳の近い先輩看護師が、技術面、精神面でサポートをしてくれます。
歳が近いって言うのが悩み相談しやすくていいですよね。
プリセプターの先輩看護師と仲良くなって二人でお出かけしたなんてお話も友人から聞くくらいです。
私の場合はというと、少しだけ触れましたがプリセプターが違う部署にいました。
病棟とCCUなので距離は近いのですが、そばでは見てくれる環境ではありませんでした。
しかも、実母と同じくらいの年代のベテランさん。
しかし、わたしと同じくらいの娘さんを育てているということで、精神面でも理解があり、たくさんはげましてもらいました。
実際に私のプリセプターをしてくださっていたのは、看護師だけにとどまらず、病院に勤める全員でした。
小規模病院ということもあり、全員のスタッフの名前と顔が一致する環境で、それぞれの得意分野を教えてもらいました。
何か分からないことがあっても、誰に聞いても教えてくれて、私の今の実力はこのくらいというのを皆さんが把握してくださっていたのです。
なので、胸水穿刺を私が見たことがない時に「午後から胸水穿刺するからおいで」とCCUの患者さんの処置の見学をさせていただいたり、急変時医師に指示をされて分からず固まってしまった私に対して、「こっちおいで」と医師から怒られないように、かつどうしたらいいのかを説明してくれたりと、全スタッフに育ててもらいました。
もし完全プリセプター制度だったら、プリセプター以外に質問はできないですし、モチベーションも下がっていたと思います。
チームナーシングを通じたキャリアアップ
早い段階から色々な経験をさせていただき、何か資格を取得したなど形に残るものではありませんでしたが、他の病院に勤めている友人に比べ、ステップアップは早かったような気がします。
本来であれば新人の夜勤デビューは半年後からだった予定なのですが、私の場合3か月で夜勤デビューを果たしました。
デビューの日、指導を担当してくれた主任からは「もう半年たつんだね。早いね」と言われ「いや!まだ3か月です!」と説明し「いやぁ、半年っていやに早いな~って思ってたんだよね」と笑った経験があります。
サポート夜勤は2回で終了し3回目からは独り立ち。
病棟を診ながら、救急外来の対応もして、カテーテル室にも入って。
とにかくめちゃくちゃ早かったです。
2年後に就職してくれた、わたしにとっての初めての後輩は、入職後2年たっても独り立ちせず、受け持ちもせず、物品をとってくる係になっていましたが…
恵まれていた環境とはいえ、新人看護師の心構えも大切なんだなと感じた瞬間でした。
ちなみにその新人さんは、答えられなかったところを勉強してノートにまとめて提出してという課題に対し、ウィキペディアを印刷したものをノートに貼って提出したそうで、先輩たちもあきれていました。
(ちなみに私はノートに手書きで全部書いて提出していましたよ!)
新人ナース必見!困ったときのQ&A
新人看護師の皆さん、そしてこれから新人看護師としてデビューするみなさん。
私には同期というものがおりませんでした。
でも、きっと皆さんには助け合える同期がいると思います。
しかし同期は仲間でもあり、ライバルでもあります。
どうか焦らず、分からないことは分からないと正直に言いましょう。
他の同期と自分を比べる必要はありません。
失敗が許されない業界だからこそ、慎重に行動する必要があります。
こんな時どうする?Q&Aをまとめてみましたので参考にしてみてくださいね!
リーダーが忙しそうで報告できないときは?
リーダーが忙しいときは、他のメンバーに聞いて解決することならば聞きましょう。
もちろん、患者さんの状態変化などの急ぎの報告は忙しそうにしていても、話を途切れさせてでも、すぐに報告する必要があります。
また急変の時などはナースコールを押して「〇〇の状態なので応援をお願いします」と言って患者さんのそばから離れないようにしましょう。
他のメンバーが忙しくて助けを頼めないときは?
目に入るメンバーが忙しそうな場合には、廊下で叫ぶのが一番早いです。
特別急ぎじゃないけど、移乗を手伝ってほしいときなどは、「〇〇号室、移乗を手伝ってください!」と叫ぶと集まってきてくれます。
患者さんや家族からクレームを受けたときは?
患者さんや家族からのクレームには基本的には師長が対応します。
ですが、クレームを受けた場合には、謝罪をしたうえで、「上の者に報告をしてまいります」とお伝えし、その後の対応は師長に頼みましょう。
新人に限らずですが、自分に落ち度があってもなくても、言い訳はせずに必ず師長に相談しましょう。
訴訟の多い時代です。自分の発言一つが大きな落ち度になることもあります。
私が実際にうけたクレームは「パジャマが破れている」でした。
ボロボロの今にも縫い目が裂けそうなパジャマをご持参されており、体位変更の際に縫い目が破れてしまったようです。
「大変申し訳ございません。上の者に報告をしてまいります」とだけ伝え、師長にバトンタッチ。
師長がなんとお話したのかは分かりませんが、病院側が新しいパジャマを用意するという形で決着がついたみたいです。
いろんな人がいるんです…。
とにかく、自分だけで判断はせずに師長に報告をすぐにしましょう!
自分のミスに気づいたときは?
正直に気づいた段階でリーダーに報告をしましょう。
場合によっては、加療や検査が必要となる場合もあります。
どんな小さなミスでもきちんと報告する方が、信頼も得られるので隠すことだけは辞めましょう。
裁判などになったときに隠ぺいは余計に自分で自分の首を絞めることになります!
自分もチームの一人であることを忘れないで!
チームナーシングで新人看護師はついつい指示待ちなど受け身になってしまうことも多いと思います。
実際に先輩看護師たちは忙しそうに動き回っていますもんね。
しかし、受け身ではチームの一員とは言えません。
初めはできることが少なく、何をしたらよいのか分からないと思います。
「聞くは一瞬の恥、聞かぬは一生の恥」という言葉があるように、なにを聞いても許されるのが新人看護師の強みだと思っています。
もちろん自分で調べもせずに0から10まで教えてくださいというのは間違いです。
分からない単語はメモに書き出し、自分なりに調べて後日これであっているかの確認を先輩にしたり、病院独自のルールならば、調べても分かるわけではないので、このような場合にはどうしたらいいですか?と積極的に質問をしましょう。
また、物品を準備する、処置の際に患者さんの体を支えるということも立派な業務です。
専門的な知識がなくてもできることがたくさんあります。
さらに、この処置にはこの物品が必要なんだな、このように処置をおこなっているんだなと新しい知識を得る機会にもなります。
高度なことをしようとはせず、「今の自分にできること」を積極的に探しに来てください。
その姿勢は先輩看護師に伝わります。
そして看護師は噂好きなので、どんどん良い印象は、他の看護師たちにも伝わっていきます。
(逆に悪い印象は倍の速さで伝わります。)
どんなベテランの看護師も新人看護師時代がありました。
看護師はすこし体育会系な部分も持っているので、やる気と根性をしっかり見せてアピールしてくださいね!
全員が全員忙しくて一瞬も手を離せないということはなかなかありません。
誰かしら手を貸せる人はいます!
ただし、新人看護師のみなさん!受け身ではダメです!
手が空いているときなどは「わたしにもお手伝いできることはありませんか?」と普段から先輩看護師に声をかける習慣をつけましょう。
状態の判断など一緒にしてもらいたいときは、「リーダーが今指示受けをしていて声をかけられないので、〇〇さんの××の状態を一緒に確認してもらえませんか?」と声をかけましょう。
ポイントはきちんと誰の何について相談したいのかを伝えることです。

