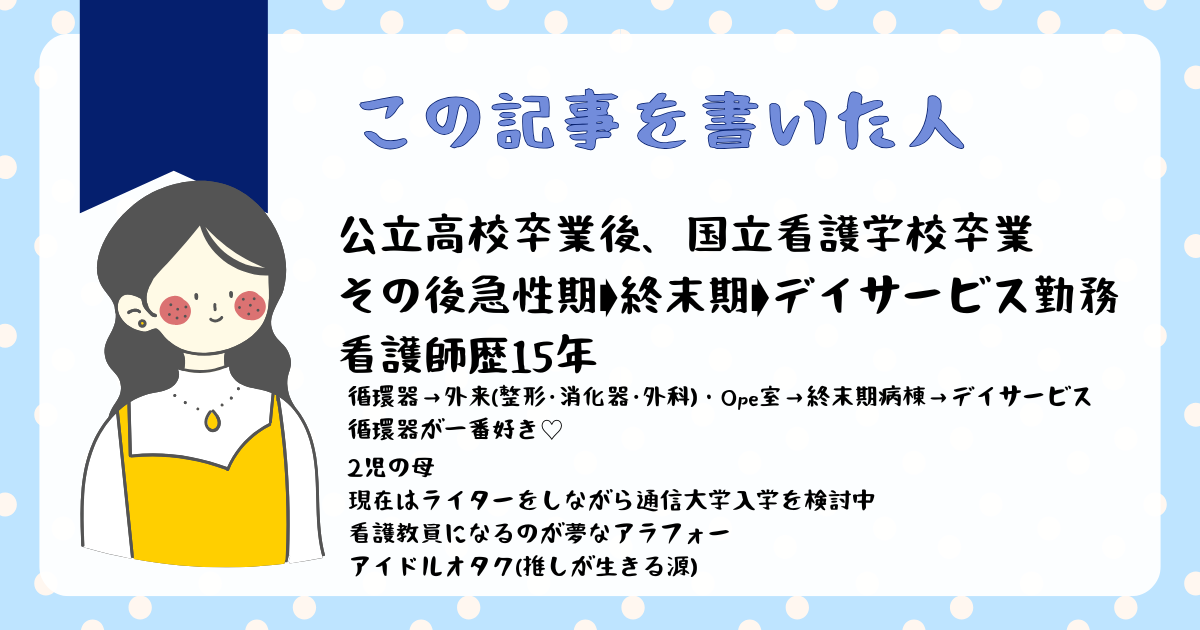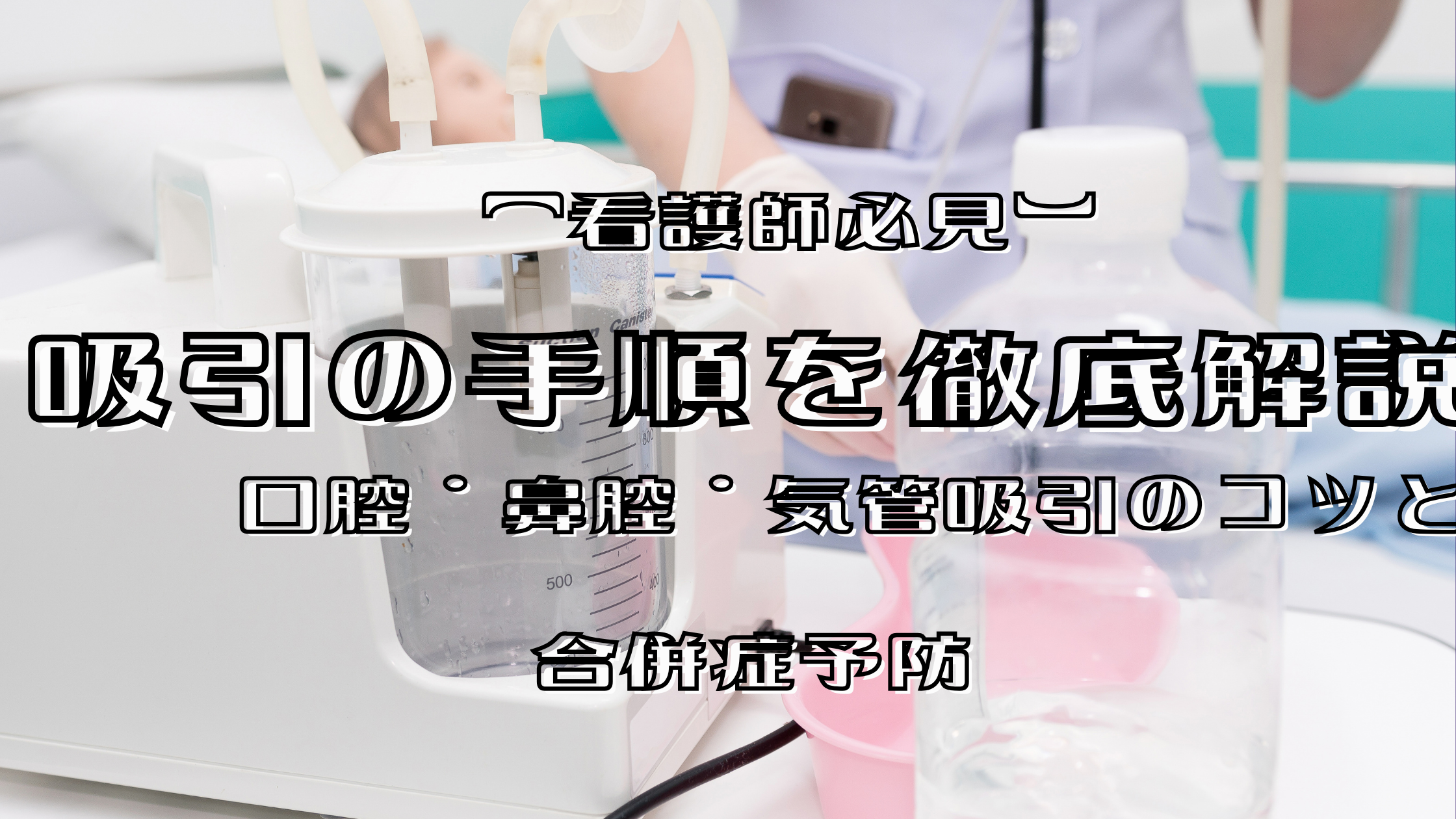
吸引って、ちょっとした手技だけど、患者さんにとってはすごく苦しいもの。
どうしたら少しでも楽にしてあげられるかな?手技に自信がないし、合併症も怖いし…
そんな看護師さん必見✨
吸引の手順をしっかりマスターすれば、患者さんの苦痛を最小限に、そして安全にケアできます!
それぞれの吸引方法のコツを知って、合併症も予防しましょう。
この記事では、口腔、鼻腔、気管吸引の手順、それぞれのコツ、そして合併症の予防について、看護師さんがすぐに役立つ情報をお届けします!

吸引の基本手順をマスターしよう!🩺
吸引って、患者さんの呼吸を助ける大切なケアですよね♪でも「これで合ってる?」って不安になることも…。ここでは、吸引の目的や手順、注意点をわかりやすく解説します!一緒に吸引マスターを目指しましょう😊
吸引の目的と適応:どんな時に吸引が必要?🤔
吸引の目的は、気道に溜まった痰や分泌物を取り除き、呼吸を楽にすることです✨
例えば、痰でゴロゴロしている音が聞こえたり、SpO2が低下している場合、吸引が必要になることが多いですよね。
人工呼吸器を使用している患者さんにも必須のケアです!
適応となる例:
- 痰が多く、呼吸が苦しそうな場合
- SpO2(酸素飽和度)の低下
- 咳をする力が弱く、痰を排出できない場合
- 聴診でゴロゴロ音が聞こえる場合
- 人工呼吸器を使用している場合
吸引に必要な物品と準備:何を用意すればいいの?🧤
吸引器、吸引カテーテル、滅菌手袋、消毒液などが必要です。
吸引圧は成人なら100~150mmHgが目安!
準備をしっかり整えて、感染予防も忘れずに行いましょう😊
口腔、鼻腔、気管吸引:それぞれの基本手順をイラストで解説🌈
- 口腔吸引:お口の中の分泌物を優しく吸引。粘膜を傷つけないように注意!
- 鼻腔吸引:細いカテーテルを使い、鼻腔内を丁寧に吸引します。
- 気管吸引:無菌操作が重要!吸引時間は10秒以内に抑えましょう。
吸引時の体位:患者さんが楽な体位って?🛌
意識がある患者さんならセミファーラー位、意識がない場合は横向きが基本です。
患者さんがリラックスできる体勢を見つけてあげるのがポイントです✨
吸引圧の調整:適切な吸引圧はどれくらい?⚙️
吸引圧が高すぎると粘膜を傷つけるリスクがあるので注意!
成人は100~150mmHg、子どもは80~120mmHgが目安です。
2023年以降の変更点:吸引圧の見直し: 吸引圧の上限が再確認され、150mmHg以下を厳守するよう強調されています!
吸引後の患者さんの状態を観察して、適切な圧を調整しましょう😊
患者さんに優しい吸引ケアのコツ🌸
吸引ケアは患者さんにとって負担が大きい処置ですが、少しの工夫で安心感や快適さを提供できますよね♪
ここでは、患者さんに優しい吸引ケアのポイントを解説します😊
サクッと流れを確認しましょう📣
| 吸引の種類 | 目的 | 手順 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 口腔・鼻腔吸引 | 口腔内や鼻腔内の分泌物を除去し、呼吸を楽にする、感染予防 | 1. 吸引圧を20kPa(150mmHg)以下に設定し、吸引カテーテルに通水する。 2. 患者に声をかけ、吸引カテーテルを挿入する(口腔内10〜13cm、鼻腔内15〜20cm)。 3. 唾液→痰の順に10秒以内を目安に吸引する。 4. 吸引終了後、患者の呼吸状態を観察する。 |
吸引圧をかけずに挿入する。口蓋垂に触れないよう注意。吸引時間は10秒以内。 |
| 気管吸引(開放式) | 気管内の分泌物を除去し、呼吸を楽にする | 1. 吸引圧を13〜20kPa(100〜150mmHg)に設定する。 2. 吸引カテーテルを接続し、吸引圧をかけずに挿入する(10〜12cm)。 3. 吸引時間は7〜10秒以内。 4. 吸引終了後、患者の呼吸状態を観察する。 |
深すぎる挿入は粘膜損傷のリスクがあるため注意。吸引時間を守る。SpO2や心電図をチェック。 |
| 気管吸引(閉鎖式) | 人工呼吸器管理中の患者の気道確保 | 1. カフ圧を調整(20〜25cmH2O)。 2. 吸引圧を20kPa(150mmHg)以下に設定する。 3. 吸引カテーテルを挿入し、吸引する。 4. 吸引終了後、観察を行う。 |
吸引圧を高く設定しない。加湿や体位ドレナージを併用する。 |
| 浅い吸引 | 気管切開チューブコネクターの清掃が必要な場合 | 気管切開チューブコネクターの深さまで吸引カテーテルを挿入し、5秒以内に引き抜く。 | お子様が咳で気道をきれいにできるが、コネクターをきれいにできない場合に推奨。 |
| 深い吸引(緊急時のみ) | 呼吸困難など緊急時 | 抵抗を感じるまで吸引カテーテルを挿入し、わずかに引き戻して吸引する(5秒以内)。 | 気道に外傷を引き起こす可能性があるため、緊急時のみ実施。 |
吸引前の声かけ:安心してもらうために伝えたいこと🗣️
吸引前の声かけは、患者さんの不安を和らげる魔法の言葉ですよね!
「○○さん、痰が溜まっているので吸引しますね。終わったらスッキリしますよ♪」など、具体的に伝えると安心感が増します。
笑顔やアイコンタクトも忘れずに✨
苦痛を和らげる吸引方法:スムーズに吸引するためのポイント🌟
吸引圧は優しく、時間は短く!
吸引時間は10秒以内を目安にし、患者さんの呼吸に合わせてカテーテルを挿入すると苦痛が軽減します。
(ついついムキになって10秒超えがち…はダメです!!!!!)
吸引カテーテルを挿入する時は、患者さんの呼吸に合わせてゆっくりと挿入することも大切。
無理に挿入すると、患者さんが苦痛を感じてしまうことがあるから、注意が必要です。
患者さんの体位を調整することも、吸引をスムーズに行うためには重要!
セミファーラー位や側臥位など、患者さんが楽な体位で吸引できるように工夫してあげましょう😊
粘膜を傷つけないコツ:安全なカテーテル操作をマスターしよう💖
カテーテルは適切なサイズを選び、粘膜に沿ってゆっくり挿入するのがポイント!
無理に押し込んだり、急激な操作は避けるようにしましょう😣

看護rooより引用
吸引圧は成人なら100~150mmHgを目安に調整し、回転させながら引き抜くと粘膜への刺激を分散できます。
吸引後のケア:患者さんの状態観察と口腔ケア✨
吸引後は、呼吸状態やSpO2を観察し、異常がないか確認しましょう。
「お疲れ様でした!」と声をかけると患者さんも安心しますよね。
口腔ケアも忘れずに行い、清潔を保ちましょう✨
吸引の手技を動画で確認しよう!
吸引を拒否されたら?:理由を聞き、安心できる説明を😌
拒否された場合は、まず理由を聞いてみましょう。
「吸引すると呼吸が楽になりますよ」とメリットを伝えたり、無理強いせずに吸引以外の方法で、呼吸を楽にする方法がないか検討することも大切です。例えば、体位ドレナージや加湿など、吸引以外の方法で痰を排出しやすくすることもできますよね🎵

レヴァウェル看護師より引用
患者さんが認知症の場合は、コミュニケーションが難しいこともあるけど、根気強く、恐怖心や苦痛を和らげる方法を考えましょう。
患者さんの「嫌だ」という気持ちを尊重しながら、その人にとって最善の方法を探していくことが大切🌸
患者さんの気持ちに寄り添いながら対応しましょう😊
吸引後の観察ポイントと合併症予防👀
吸引後のケアは、患者さんの状態をしっかり観察し、合併症を防ぐための重要なステップですよね♪
ここでは、観察すべきポイントや予防策を詳しく解説します😊

SpO2、呼吸音、顔色:観察すべきポイントは?🧐
吸引後は、患者さんの呼吸状態をしっかりチェックしましょう!具体的には以下のポイントを観察します:
- SpO2:酸素飽和度が正常範囲(95~100%)に戻っているか確認します。
- 呼吸音:聴診器で呼吸音を聴き、副雑音(ラ音)が改善されているかを確認します。
- 顔色:顔色や唇の色を観察し、チアノーゼがないかチェックします。
患者さんの表情や呼吸のリズムも見逃さないでくださいね✨
合併症の種類と症状:どんな合併症に注意すべき?🚑
吸引後に注意すべき合併症には以下があります:
- 低酸素血症:吸引時間が長すぎると酸素不足になることがあります。
- 気道損傷:カテーテルの操作が不適切だと粘膜を傷つける可能性があります。
- 感染:清潔操作が不十分だと感染リスクが高まります。
症状としては、呼吸困難、不整脈、出血などが挙げられます。異常があればすぐに医師に報告しましょう🚨
感染予防対策:清潔操作の徹底🧼
感染予防の基本は清潔操作です!以下を徹底しましょう:
- 手洗い:吸引前後に手をしっかり洗浄します。
- 使い捨て物品:カテーテルや手袋は使い捨てを徹底します。
- 環境整備:吸引器具の消毒や清潔な作業環境を保つことが重要です。
患者さんの安全を守るために、細かい部分まで気を配りましょう✨
呼吸困難時の対応:緊急時の対処法を知っておこう💨
呼吸困難が起きた場合は、以下の手順で対応します:
- 体位調整:患者さんが楽に呼吸できる体位(起座位や側臥位)を保ちます。
- 酸素投与:必要に応じて酸素を供給します。ただし、酸素濃度は患者さんの状態に合わせて調整してください。
- 医師への報告:異常が続く場合は速やかに医師に報告し、指示を仰ぎます。
緊急時には冷静に対応することが大切ですね😊
観察記録の書き方:正確な記録で情報共有📝
観察記録は、患者さんの状態を正確に共有するための重要なツールです!以下のポイントを押さえましょう:
- 主観的情報:患者さんの訴えや症状(例:息苦しさ)を記録します。
- 客観的情報:SpO2、呼吸音、顔色などのデータを記載します。
- 評価:観察結果から患者さんの状態を分析し、問題点を明確化します。
- 計画:次のケアに向けた具体的な計画を立てます。
記録は簡潔かつ正確に書くことで、チーム内での情報共有がスムーズになりますね✨
吸引器具の選び方と安全な管理方法🛠️

吸引器具の選び方や管理方法って、患者さんの安全を守るためにとっても大切ですよね♪
ここでは、吸引器具の種類や特徴、管理方法について詳しく解説します😊
吸引器の種類と特徴:どれを選べばいいの?🤔
吸引器にはいくつかの種類があり、用途や患者さんの状態に合わせて選ぶことが重要です✨
- 手動式吸引器:電源が不要で、緊急時や停電時に便利です。ただし、吸引力が一定でない場合があります。
- 壁掛け式吸引器:病院などの施設で使用されるタイプで、吸引力が安定しています。
- ポータブル式吸引器:持ち運びが可能で、在宅介護や外出時に便利です。バッテリー式のものは停電時にも対応できます。
選ぶ際は、吸引力(流量や吸引圧)、バッテリーの持ち、メンテナンスのしやすさを考慮しましょう。
吸引カテーテルの種類と選択:患者さんに合ったカテーテルを選ぼう💡
吸引カテーテルはサイズや素材が異なり、患者さんの状態に合わせて選ぶ必要があります✨
- サイズ:気管切開チューブの場合、カテーテルの外径がチューブ内径の半分以下になるように選びます。
- 素材:柔らかい素材のカテーテルは粘膜への負担が少なく、特に小児や高齢者に適しています。
適切なサイズを選ぶことで、気道損傷や低酸素血症のリスクを減らせますよ😊
吸引瓶の管理:清潔な状態を保つために🍀
吸引瓶は使用後に適切に洗浄・消毒することが感染予防の基本です✨
- 洗浄:中性洗剤で汚れを落とし、次亜塩素酸ナトリウム溶液に浸漬消毒します。
- 乾燥:十分にすすぎ、自然乾燥させてから再組立てを行います。
煮沸消毒はプラスチックが破損する可能性があるため避けましょう。
吸引チューブの消毒と交換:感染リスクを減らすために🚨
吸引チューブは個人使用とし、使用ごとに清掃・消毒し、定期的に交換することが重要です✨
- 消毒方法:中性洗剤を溶かした水を吸引して内部を洗浄し、その後消毒用エタノールを吸わせます。
- 交換頻度:延長チューブは1週間に1回の交換が推奨されます。
汚れがひどい場合はその都度交換しましょう😊
在宅での吸引器管理:家族への指導ポイント👪
在宅で吸引器を使用する場合、家族への指導が重要です✨
- 操作方法:吸引器の使い方やカテーテルの挿入方法を具体的に教えます。
- 感染予防:手洗いや器具の清潔操作を徹底するよう指導します。
- 心理的サポート:家族の不安を軽減するために、「いつでも相談してくださいね」と声をかけるなど、共感的な対応を心がけましょう。
吸引器のトラブル時には、メーカーへの問い合わせや予備機の準備も忘れずに😊
吸引中のトラブル対応マニュアル🚑
吸引中にトラブルが起きると焦っちゃいますよね💦 でも大丈夫!
ここでは、よくあるトラブルとその対処法をわかりやすく解説します😊
これで、どんな状況でも落ち着いて対応できますよ✨
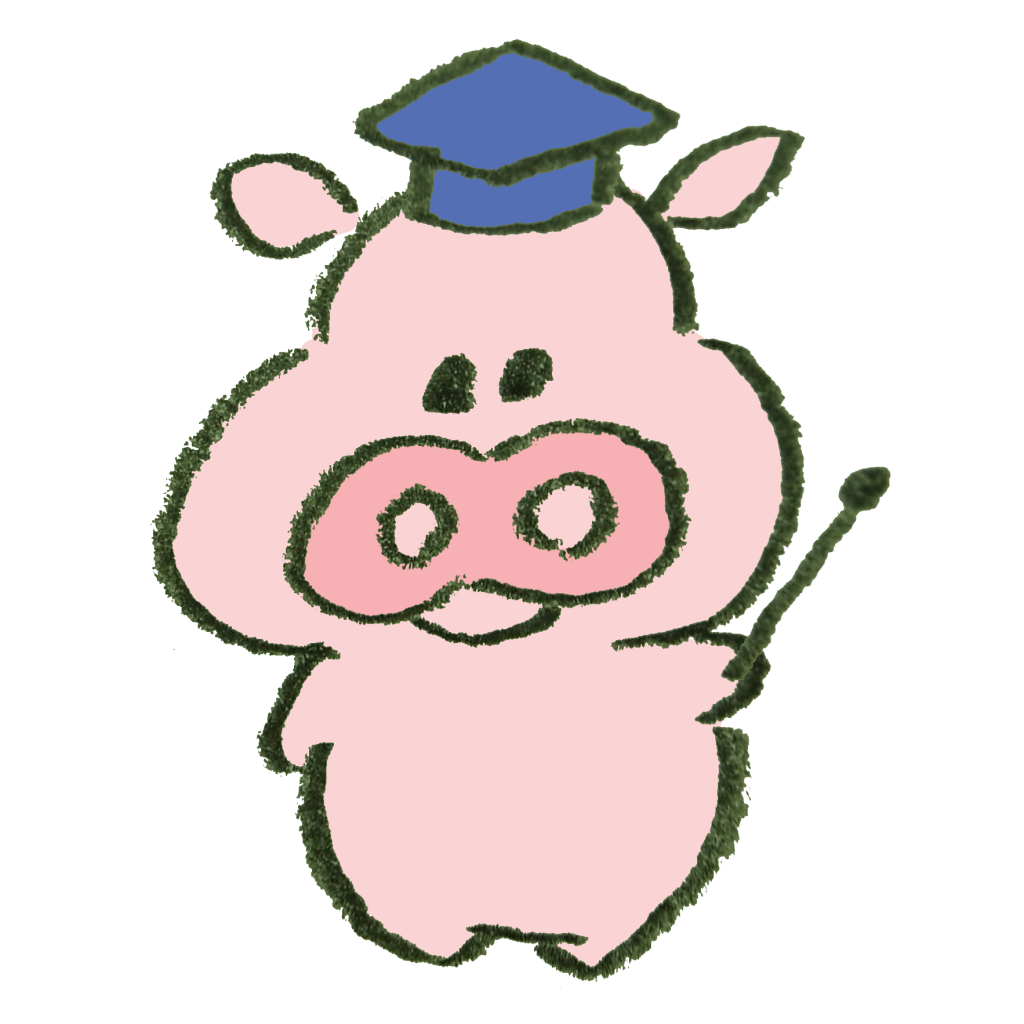
吸引できない!:原因と対処法をチェックリストで確認✅
吸引がうまくいかない時は、以下をチェックしてみましょう!
- 電源🔌:吸引器の電源が入っているか確認しましょう。コンセントが抜けていないかも要チェック!
- チューブの接続🔗:吸引チューブがしっかり接続されているか確認してください。
- 詰まり🧹:チューブ内が痰で詰まっていないか確認し、生理食塩水で洗浄しましょう。
- 吸引圧⚙️:吸引圧が適切か確認。低すぎると吸引できません。
- 吸引瓶の密閉性🫙:吸引瓶の蓋がしっかり閉まっているか確認しましょう。
これでも改善しない場合は、吸引器の故障を疑い、予備の吸引器を使用してください📱
吸引瓶がきちんとはまってなくて圧がかからなくてどうしよう~っていうことはよくあります💦
吸引瓶を交換した際は吸引圧がかかるか確認しましょう!!
SpO2が低下した場合:速やかな酸素投与と原因検索💨
吸引中にSpO2が低下したら、以下の対応を!
- 酸素投与:
酸素マスクや鼻カニューレなどで、酸素を投与します。
呼吸状態があまり良くなく、SpO2が95%以下の患者さんの場合、吸引前に酸素投与をしておくことも大切です。
SpO2低下に気づいたら、まずは患者さんの様子を観察しましょう。
意識レベルが低下している、あるいは呼吸停止といった状態の場合は、緊急の対応が必要です。
酸素投与を受けている患者さんには、設定した通りの酸素を吸入できているか、チューブの屈曲や閉塞がないか確認しましょう。 - 吸引の中断:
SpO2が回復するまで、吸引を一時中断します。
SpO2が85%を下回る場合は特に注意が必要です. - 原因の検索:
SpO2低下の原因を探ります。
吸引時間が長すぎた、吸引圧が高すぎた、などが考えられます。
痰を取り切れていない可能性も考慮しましょう。 - 医師への報告:
SpO2が回復しない場合や、原因が特定できない場合は、速やかに医師に報告・相談しましょう🏥
患者さんには「少し息苦しいですね。すぐに楽になるよう対応しますね😊」と声をかけて安心させてください。
出血した場合:止血方法と観察ポイント🩸
吸引時に出血が見られたら、以下を実施!
- 止血:
出血部位を清潔なガーゼなどで圧迫止血します。
10分以上圧迫しても止まらない場合は、医師に報告しましょう🏥
鼻出血の場合、強く鼻をかむことも原因となることがあります. - 観察:
出血量や出血部位、患者さんの状態(呼吸状態、意識レベルなど)を観察します👀 - 原因の特定:
出血の原因を特定します。
吸引圧が高すぎた、カテーテルが硬すぎた、などが考えられます。
吸引カテーテルが深すぎると、粘膜を傷つけるリスクが高まります。 - 医師への報告:
大量の出血や、止血困難な場合は、速やかに医師に報告・相談しましょう🏥
吸引による出血は、気管粘膜の損傷が原因であることが多いです。
吸引圧を適切に調整し、柔らかいカテーテルを使用するなど、予防に努めましょう🩹
頻繁な吸引や強い咳も出血の原因となることがあります。
患者さんには「少し出血がありますが、すぐに対応しますので安心してくださいね😊」と伝えましょう。
誤嚥した場合:体位ドレナージと吸引で対応🧎♀️
吸引中に患者さんが誤嚥(食べ物や異物が気管に入ってしまうこと)した場合、窒息や肺炎のリスクがあります🚨
誤嚥が起きたら、以下の手順で対応!
- 体位ドレナージ:
患者さんを側臥位にし、頭を低くして、異物を排出しやすくします。 - 吸引:
口腔内や気道内の異物を吸引します。嘔吐や出血が続く場合は、吸引が困難になることがあります. - 観察:
呼吸状態、SpO2、意識レベルなどを観察します👀 - 医師への報告:
呼吸困難やSpO2低下が続く場合は、速やかに医師に報告・相談しましょう🏥
吸引器が故障した場合:代替手段と修理依頼の手順📱
吸引器が故障したら、以下を実施!
- 代替手段:手動式吸引器や予備の吸引器を使用。
- 修理依頼:故障状況を記録し、メーカーに連絡。修理中は他の吸引器を使用します。
患者さんには「吸引器が故障しましたが、すぐに別の方法で対応しますのでご安心ください😊」と説明しましょう。
トラブル時も冷静に対応して、患者さんの安全を守りましょう🌸
詳しいガイドライン
厚生労働省が平成24年度に作成したガイドラインです。
吸引スキルで患者さんの笑顔を守ろう!
今回の吸引手技の解説、いかがでしたか?
この記事が、あなたの吸引スキルをさらにレベルアップさせるお役に立てたら嬉しいです!
患者さんの笑顔のために、これからも一緒に頑張りましょうね!