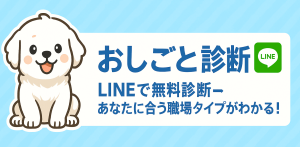「患者さんの皮膚が裂けてしまった…」「テープを剥がしたら皮膚も一緒に剥がれてしまった…」「スキンテアの予防方法が知りたい」
そう悩んでいる看護師さんも多いのではないでしょうか。
スキンテアは高齢者や皮膚の弱い患者さんによく見られる皮膚トラブルですが、適切な知識と技術があれば予防・対処が可能です✨
この記事では
- スキンテア(皮膚裂傷)の正しい理解と見分け方
- STAR分類に基づく適切なアセスメント方法
- 現場ですぐに実践できる予防テクニック5つ
- 発生してしまった場合の効果的な処置手順
- 高齢者の脆弱な皮膚を守るためのスキンケア方法
- 表皮剥離との違いと対応の違い
が分かりますよ♪
実は、スキンテア対策の成功は「予防」と「早期発見・適切な処置」の2つがカギなんです!🔑
日々の看護ケアに取り入れられる実践的な方法を知ることで、患者さんの皮膚トラブルを大幅に減らすことができます。
この記事では、現場の看護師さんがすぐに活用できるスキンテアの予防法から処置方法まで、写真や図解を交えながら詳しく解説していきます。明日からのケアに自信を持って取り組めるようになりますよ!👩⚕️✨
皆さん、患者さんのケアをしていて「あれ?この皮膚の裂け方、どう対応すればいいんだろう?」と悩んだことはありませんか?
ここでは、スキンテアの基本と見分け方について解説します。正しい知識を身につけて、適切なケアにつなげていきましょう!✨
スキンテアとは、主に摩擦やずれの力によって皮膚が裂けてしまう現象です。
特に高齢者や皮膚が脆弱な患者さんに多く見られます。皮膚の表皮と真皮の間、または真皮内で分離が起こり、皮弁(めくれた皮膚)を形成するのが特徴です。
発生原因としては、以下のようなものが挙げられます:
- 移動・体位変換時の摩擦やずれ 🔄
- 医療用テープの剥離 📋
- 衣類や寝具との接触 👕
- 乾燥による皮膚の脆弱化 💧
皮膚の構造上、加齢とともに表皮と真皮の結合が弱くなるため、高齢者ほどリスクが高まります。
また、ステロイド薬の長期使用や栄養状態の悪化も発生リスクを高める要因となっています。
スキンテアと表皮剥離は似ていますが、適切な処置方法が異なるため、見分けることが大切です。

時事メディカルより画像引用
以下の表で主な違いをご確認ください:
| 特徴 | スキンテア | 表皮剥離 |
|---|---|---|
| 定義 | 摩擦やずれによる皮膚の裂傷 | 表皮のみが剥がれる現象 |
| 深さ | 表皮〜真皮に及ぶ | 表皮層のみ |
| 皮弁 | 皮弁(めくれた皮膚)を形成 | 皮弁を形成しない |
| 出血 | 出血を伴うことが多い | 出血は少ないか無い |
| 処置 | 皮弁を元の位置に戻す | 保護・保湿が中心 |
| 治癒期間 | 比較的長い | 比較的短い |
見分けるポイントは、「皮弁の有無」と「傷の深さ」です。
スキンテアでは皮弁があり、真皮まで達していることが多いのに対し、表皮剥離は表面的で皮弁を形成しません。
処置方法が異なるので、アセスメントが重要ですね!👀

「私に合ってる仕事って…?」を“おしごと診断”でチェックしてみよう!
スキンテア予防や処置も大切で責任ある仕事だけど、ふと、「今の仕事、私に合ってるのかな」と思うことも。そんなときは、この診断で最適な仕事や職場を診断してみましょう。
スキンテアを発見したとき、「どのタイプ?どう対応すればいい?」と迷うことはありませんか?
実は、スキンテアには国際的な分類法があり、それに基づいて適切なケアを選択することができるんです。
ここでは、現場で役立つSTAR分類について解説します。
正確なアセスメントで、患者さんに最適なケアを提供しましょう!💫
STAR分類(Skin Tear Audit Research)は、スキンテアの状態を5つのカテゴリーに分類し、それぞれに適した処置方法を示す国際的な評価システムです。皮弁の状態と組織の喪失度合いによって分類されます。

高松赤十字病院より画像引用
| カテゴリー | 皮弁の状態 | 組織喪失 | 特徴 | 推奨される対応方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 皮弁が元の位置に戻せる | なし | 皮弁が無傷で元の位置に戻せる | ・皮弁を優しく元の位置に戻す ・非固着性のドレッシング材で保護 ・皮弁を固定するテープは使用しない 👍 |
| 1b | 皮弁が元の位置に戻せる | なし | 皮弁の端が乾燥している | ・皮弁を湿らせてから元の位置に戻す ・保湿性のあるドレッシング材を使用 💧 |
| 2a | 皮弁の一部が失われている | 部分的 | 皮弁の25%未満が失われている | ・残った皮弁を元の位置に戻す ・湿潤環境を維持するドレッシング材を選択 🌊 |
| 2b | 皮弁の大部分が失われている | 部分的 | 皮弁の25%以上が失われている | ・残った皮弁を可能な限り戻す ・創傷治癒を促進するドレッシング材を使用 🌱 |
| 3 | 皮弁が完全に失われている | 完全 | 皮膚の欠損がある | ・創部を清潔に保つ ・二次感染を防ぐ ・適切な湿潤環境を維持するドレッシング材を選択 🛡️ |
アセスメントのポイント:
-
皮弁の状態(無傷か、乾燥しているか)
-
組織喪失の程度(なし、部分的、完全)
-
創部の状態(感染の有無、滲出液の量)
どのカテゴリーでも共通する対応のコツは、「愛護的な処置」と「適切な湿潤環境の維持」です。
皮弁を引っ張ったり、無理に剥がしたりせず、優しく扱うことが治癒を促進します。
また、ドレッシング材の交換頻度は創部の状態に合わせて調整し、不必要な刺激を避けましょう✨
皆さん、「予防は最良の治療」という言葉をご存知ですよね。
スキンテアも同じで、発生してからの対応より予防が何より大切です。特に高齢者や皮膚の脆弱な患者さんには、日々のケアに予防策を取り入れることで、スキンテアのリスクを大幅に減らすことができます。
ここでは現場ですぐに実践できる予防法をご紹介します!💪
保湿は、スキンテア予防の基本中の基本です!乾燥した皮膚は弾力性が低下し、ちょっとした外力でも裂けやすくなってしまいます。
-
保湿のポイント:
-
低刺激性で伸びの良い保湿剤を使用する 🧴
-
1日2回以上、特に入浴後に塗布するのが効果的
-
保湿剤入りの入浴剤の使用もおすすめ
-
皮膚の乾燥が強い部位(四肢外側など)は重点的にケア
-
保湿を日常ケアに組み込むことで、皮膚の弾力性が改善され、スキンテアのリスクが低減します。
特に高齢者には、ルーティンとして1日2回以上の保湿ケアを行うことが推奨されています。
忙しい業務の中でも、清拭や体位変換のタイミングで保湿ケアを組み込むと効率的ですよ✨
日常のケアや移動介助の際に、ちょっとした工夫で摩擦やずれを防ぐことができます。
| 場面 | 予防テクニック | ポイント |
|---|---|---|
| 身体の支持 | 手を閉じて大きな面で下から支える | つかまず、指の圧力が局所的にかからないように1 |
| 体位変換 | ステイディングシートやビニール袋を活用 | 引きずらない、引っ張らない5 |
| 衣類の選択 | 長袖・長ズボン、アームカバー・レッグカバーの使用 | ボタンやファスナーのないゆったりした衣類を選ぶ5 |
| 環境整備 | 家具の角やベッド柵にカバーを装着 | 転倒予防のため段差をなくす5 |
| テープ使用時 | シリコン性の低刺激テープを選択 | 剥がす際は剥離剤を使用3 |
特に大切なのは「つかまない」「引っ張らない」ということ。
四肢を持ち上げる際は、握るのではなく下から支えるようにしましょう。
体位変換時にはビニール製の手袋を使うと摩擦を軽減できますよ。
患者さんの皮膚を守る意識を持って、愛護的に接することが何より大切です💕
残念ながらスキンテアが発生してしまった場合、初期対応がその後の治癒に大きく影響します。
適切な処置で患者さんの痛みを最小限にし、早期治癒を目指しましょう。
ここでは、発見時の対応から状態別のケア方法までをご紹介します!🏥
スキンテアを発見したら、まずは落ち着いて以下の手順で対応しましょう:
-
👉 必要に応じて圧迫止血を行い、温かい生理食塩水で創部を優しく洗浄します
-
👉 これが最も重要なステップです!湿らせた綿棒や手袋をした指、無鉤鑷子を使って、皮弁をゆっくりと元の位置に戻します
※この処置は痛みを伴うことがあるため、事前に患者さんへの説明が必要です

 ステリなどを使用して皮弁を固定します
ステリなどを使用して皮弁を固定します -
👉 組織欠損の程度や皮弁の色を評価し、適切な処置方法を選択します
-
👉 脆弱性、腫脹、変色、打撲傷の有無をチェックします
初期対応では、「愛護的な扱い」が何より大切です。
皮弁を引っ張ったり無理に剥がしたりせず、優しく扱うことで治癒を促進できます。
また、処置時の痛みに配慮することも忘れないでくださいね🥰
ナース専科、マイナー外科・救急より画像引用
スキンテアの状態によって、適切なケア方法は異なります。
| 状態 | ケア方法 | 使用する被覆材 |
|---|---|---|
| 出血がある場合 | 止血効果の高い被覆材を使用 | アルギン酸塩創傷被覆材(ソーブサン®など) |
| 広範囲に紫斑がある場合 | アルギン酸塩による創傷被覆材を使用 | 早期に紫斑が改善され、皮膚の生着も進みます |
| 感染の恐れがある場合 | 通気性の良い被覆材で保護し、数日は被覆材を交換して感染徴候を観察 | 透明でない被覆材を使用する場合は、剥がす方向を矢印で記しておくと良いでしょう |
| 感染や出血がない場合 | 上皮化を早めるために閉鎖環境を提供 | シリコン製の創傷被覆材 |
| 皮弁の色が蒼白・黒ずんでいる場合 | 24~48時間以内または最初のドレッシング交換時に再評価 | 状態に応じた被覆材を選択 |
どの状態でも、「外傷であり感染に移行しやすい」ことを念頭に置き、定期的な観察と適切なドレッシング材の選択が重要です。
また、皮弁を戻した後は、その位置がずれないよう注意して被覆材を選びましょう。
スキンテアの処置は、「洗浄と出血コントロール」「感染徴候の観察」「撥水と保護」の3つが基本です。
これらを意識しながら、患者さんの状態に合わせたケアを提供していきましょう!💖
活用することで、スキンテアの状態を客観的に評価し、エビデンスに基づいた適切なケアを選択することができます。
日々のケアに取り入れてみてくださいね!📝
高齢者の皮膚は、加齢に伴い薄く、乾燥しやすくなっています。
そのため、日常のケアがスキンテア予防の鍵となります。
ここでは、病院や施設、在宅でも簡単に取り入れられる予防策をご紹介します。
患者さんの皮膚を守るために、ぜひ毎日のケアに取り入れてみてくださいね!✨
高齢者のスキンケアは「保湿」「保護」「愛護的なケア」の3つが基本です。
これらを意識した日々のケアで、スキンテアのリスクを大きく減らすことができます。
| ケアの種類 | 具体的な方法 | 実践のポイント |
|---|---|---|
| 入浴・清拭 | ぬるめのお湯を使用 刺激の少ない石鹸を選ぶ |
・38〜40℃のぬるめの温度 ・ゴシゴシこすらない ・弱酸性の石鹸を使用 🛁 |
| 保湿ケア | 入浴後すぐに保湿 尿素やセラミド配合の保湿剤 |
・特に四肢外側、かかとを重点的に ・1日2回以上塗布 ・皮膚が乾燥する冬場は特に念入りに 💦 |
| 衣類・寝具 | 柔らかい素材を選ぶ ゆったりとしたサイズ |
・綿素材が基本 ・締め付けのない服 ・シーツのシワをなくす 👕 |
| 栄養管理 | タンパク質・ビタミン摂取 水分補給 |
・皮膚の再生に必要な栄養素を意識 ・1日1500ml程度の水分摂取を目標に 🥛 |
| 環境調整 | 適切な湿度維持 ベッド周りの安全確保 |
・湿度50〜60%を維持 ・ベッド柵にクッション材を取り付ける 🏠 |
特に大切なのは「皮膚を乾燥させない」こと。乾燥は皮膚の弾力性を低下させ、ちょっとした外力でもスキンテアを引き起こしやすくなります。
保湿剤は、ハンドクリームのように手軽に使えるものを病室やナースステーションに常備しておくと、忙しい業務の合間にも保湿ケアができますよ💕
また、高齢者自身やご家族にもスキンテア予防の重要性を伝え、セルフケアの方法を指導することも大切です。
「皮膚を守る」という意識を共有することで、より効果的な予防につながります👨👩👧👦
現場でスキンテアに関して疑問に思うことは多いですよね。
ここでは、看護師の皆さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。日々のケアの参考にしていただければ幸いです!📝
: スキンテアの皮弁が乾燥して元に戻せない場合はどうすればいいですか?
A1: 皮弁が乾燥している場合は、まず生理食塩水で湿らせてから元の位置に戻すようにしましょう。
湿らせても戻せない場合は、無理に戻そうとせず、現状のまま保護します。
湿潤環境を維持するドレッシング材を選択し、皮弁が自然に治癒するのを待ちましょう💧
: スキンテア処置時の痛みを軽減する方法はありますか?
A2: 処置前に十分な説明を行い、患者さんの不安を軽減することが大切です。
処置中は愛護的に扱い、必要に応じて局所麻酔薬入りのゼリーや冷却法を用いることもあります。
また、処置の時間をできるだけ短くし、患者さんの表情や反応に注意を払いながら行いましょう😌
: スキンテアと褥瘡の違いは何ですか?
A3: スキンテアは主に摩擦やずれによって発生する皮膚の裂傷であるのに対し、褥瘡は持続的な圧迫や摩擦・ずれによって発生する組織の損傷です。
発生機序、好発部位、処置方法が異なります。スキンテアは皮弁を形成することが特徴的です。
: スキンテアの記録はどのように行うべきですか?
A4: 以下の項目を記録することをお勧めします:
-
発生日時と状況
-
部位と大きさ(cm)
-
STAR分類によるカテゴリー
-
皮弁の状態と色
-
創部の状態(出血、滲出液など)
-
実施した処置内容
-
使用した被覆材
-
次回の交換予定日 📋
: 家族に「虐待ではないか」と疑われないためにはどうすればいいですか?
A5: スキンテアが発生した場合は、家族に対して丁寧に説明することが重要です。
高齢者の皮膚は脆弱で、日常的なケアでも生じうることを説明し、予防策と処置方法について共有しましょう。
また、発生時の状況や処置内容を詳細に記録し、透明性を確保することも大切です。必要に応じて写真記録を残すことも有効です🤝
: スキンテアの治癒が遅い場合はどうすればいいですか?
A6: 治癒が遅い場合は、以下の点を確認しましょう:
-
感染の有無(発赤、熱感、腫脹、疼痛の増強など)
-
栄養状態(特にタンパク質、ビタミン、亜鉛など)
-
全身状態(糖尿病、ステロイド使用など)
-
被覆材の選択が適切か
-
湿潤環境が維持できているか
これらを評価した上で、必要に応じて皮膚・排泄ケア認定看護師や医師に相談することをお勧めします。
栄養サポートチーム(NST)との連携も効果的です。🌱
スキンテアのケアは日々進化しています。最新の知見を取り入れながら、患者さんに最適なケアを提供していきましょう!💪✨
スキンテア予防・ケアで患者さんの皮膚を守りましょう!💪✨
いかがでしたか?スキンテアは適切な知識と技術があれば、多くの場合予防できるものです。
また、発生してしまった場合も、正しい処置で早期治癒を促すことができます。
日々の看護ケアの中で、今回ご紹介した予防策や処置方法を意識していただくことで、患者さんの皮膚トラブルを減らし、QOLの向上につなげることができるでしょう。
特に高齢者が増える中、スキンテアケアの知識はますます重要になってきています。
患者さんの笑顔のために、一緒にスキンテア予防に取り組んでいきましょう!
「私にぴったり合った仕事を探したい!」という方は、“おしごと犬索”!
LINEであなたの状況や希望を教えてくれれば、あなたに合った仕事を検索します。満足するお仕事をぜひ!