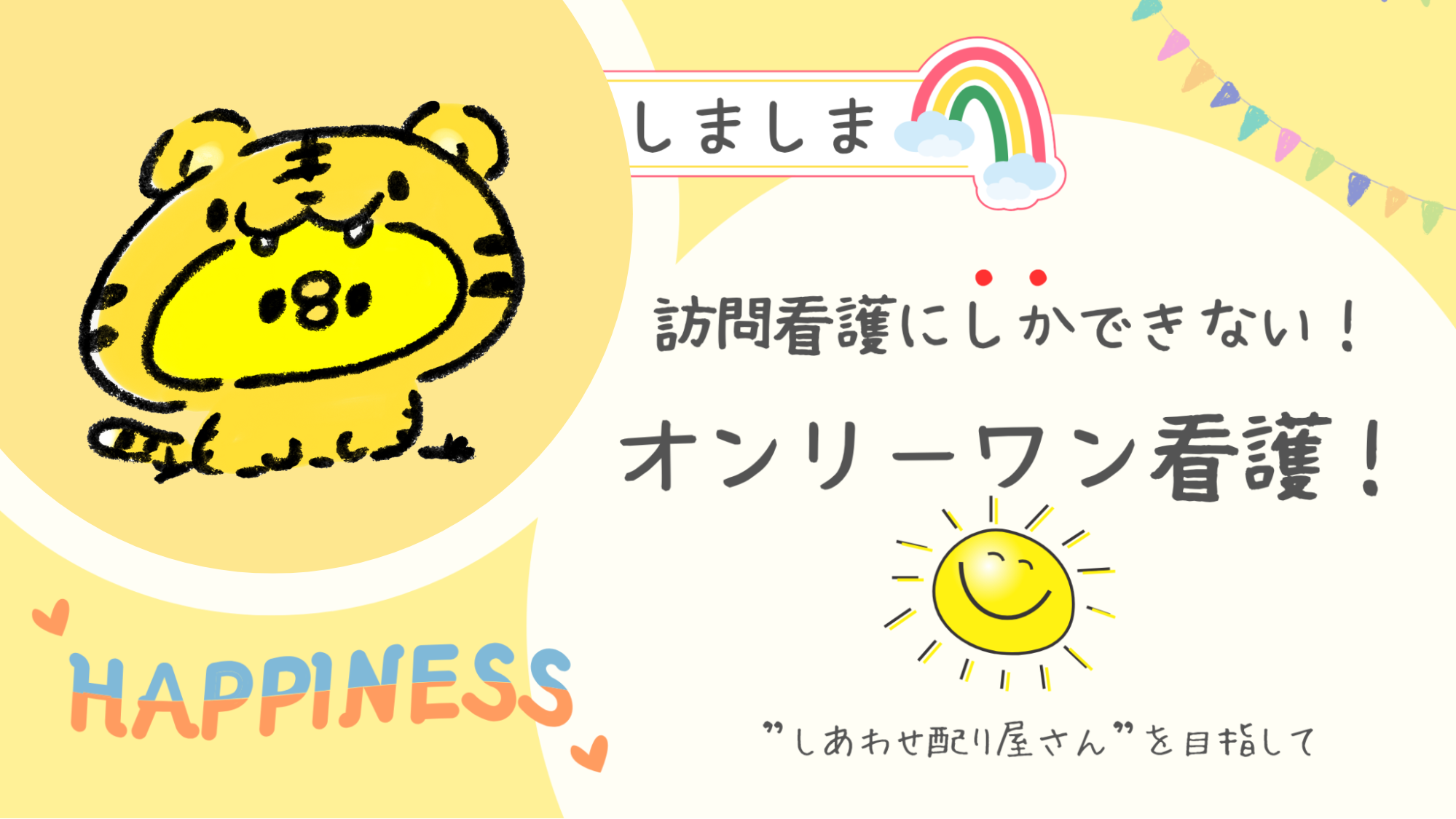
「しごと・レトリバー」は、看護・介護・薬剤師など現場で働く方々に向けて、転職・キャリアの“リアル”を届けるメディアです。
今回お話を伺ったのは、病院勤務10年を経て訪問看護へ転身し、家族と仕事を両立しながら現場で奮闘する しましまさん。
外来や検査室など幅広い経験を積んだのち、「生活に合わせた働き方」を模索して選んだのが訪問看護という舞台。
治療の場である病院とは違い、在宅という“暮らしの現場”で、その人の価値観やペースに寄り添いながらケアを組み立てる――。
そこには、マニュアルでは測れない判断と工夫、そして利用者さんの力を引き出す看護の醍醐味がありました。
最期の過ごし方に寄り添う場面から、認知症のある方が再び生活の喜びを取り戻していく過程まで。
「看護師さん」ではなく「しましまさん」と名前で呼ばれる関係を築き、オンリーワンのケアで変化を導く日々は、
訪問看護に興味がある方はもちろん、「自分らしい働き方」を探している看護職の方にも大きな示唆を与えてくれます。
本インタビューでは、転職のきっかけ、病院との違い、やりがいと葛藤、そして「あなたに会えてよかった」と言われる看護の根っこまで――
しましまさんの“リアル”をたっぷりお届けします。
まずはご経歴から
しごレト編集部:今日はありがとうございます!まずはしましまさんのこれまでのご経歴を簡単に教えていただけますか?

しましまさん:
2012年に東北福祉大学を卒業して看護師・保健師の資格を取得し、横浜市のけいゆう病院に新卒で入職しました。
結婚や妊活をきっかけに病棟を1年で離れ、その後は外来や検査室などで幅広く経験を積みました。
2022年、けいゆう病院を退職後、自宅近くの訪問看護ステーションに転職し、現在は訪問看護師として活動しています。
しごレト編集部:10年間の病院勤務を経て訪問看護に飛び込むなんて、大きな転換ですよね。しかもお子さんのフォローや家庭の事情と両立しながらというのが、すでにストーリーそのもの。ここからどんな気づきがあったのか、とても楽しみです。
1. 訪問看護への転職を後押ししたきっかけ
しごレト編集部:しましまさんは、中規模総合病院で10年間勤務されてから訪問看護に転職されています。まずはその大きな転換の理由を教えてください。

しましまさん:
転職のきっかけは、扶養内で勤務していた病院が人員削減で辞めることになったことです。
私は初め、他人の家に上がり込む訪問看護なんて、絶対やりたくないと思っていました。
しかし、自分の希望した勤務形態にマッチする病院が存在せず、訪問看護ステーションの方が多様な働き方を選べると知りました。
私には自閉症・軽度知的障害の息子がおり、当時は手厚いフォローが必要だったのです。
そういうわけで、やりがいとかそういうことは後回し、あくまで生活にフィットする勤務形態の職場を求め、仕方なく自宅から最も近い訪問看護ステーションに面接を申し込みました。
その訪問看護ステーションはかなり変わっていて(良い意味で)、私が全く知り得なかった新たな世界が見られるはずと確信し、入職を決めた次第です。
しごレト編集部:看護師としての「理想」よりも、まずは家族を守る現実的な選択が出発点だったのですね。
そのうえで、ご自宅から近く、ご自身も未知だった訪問看護の世界に飛び込んだことが、結果的に大きな転機になったわけですね。良い意味で変わっていて、知り得なかった新たな世界っていうのが気になります!

しましまさん:
教科書に書いてあるTHE・医療ではなく、全く新しい方向からのアプローチで利用者さんやご家族を元気にしていく、というケアです。
私たちは日々、「本当に正しいこと」は何かを追究し、実践しています。
薬に頼らず、食生活改善や特別なマッサージ(ゴッドハンドと呼ばれるスペシャリストたちから学んだ手技や、日本では受けることができない世界最先端の手技・知識など)で状態を改善することで「医者いらず」の生活が送れるというものです。
肝硬変末期のパンパンの腹水貯留をぺったんこに回復させたり、「熊に食われたんですか?」レベルに肉が抉れた傷を感染ゼロでまっさらに治したり、身体の痛みで立ち上がれない人を歩けるまでに回復させたり、認知症を改善させたり、アル中で暴れ狂う人を別人レベルに穏やかにしたり(いずれも薬を使っていません)、、
医師が「コレ、どうやったの?教えてほしい」「あり得ない」と驚愕する結果を数々、実績として残しており、従業員数2人(管理者入れて3人)という小規模のステーションにもかかわらず、新規利用者紹介が絶えません。
知る人ぞ知る「人生を変える、訪問看護ステーション」です。
ちなみに、私の息子の自閉症・軽度知的障害、夫のモラハラも治りました。
しごレト編集部:……まさに「常識をひっくり返す」ような実践ですね。
薬を使わず、食生活や特別なマッサージでそこまで改善できるとは正直驚きました。
しかもご自身のご家族――息子さんの自閉症やご主人のモラハラまで改善されたというのは、単なる仕事の域を超えている感じがします。
小規模ステーションだからこそ利用者さん一人ひとりに深く向き合えた結果なのか、それとも技術や考え方に秘密があるのか、とても気になります。
2. 訪問看護で感じたやりがいと価値観の変化
しごレト編集部:訪問看護に転職してから、病院時代とはやりがいや価値観が大きく変わった瞬間はありましたか?

しましまさん:
最期の最期まで医療を拒否し、酒と煙草に溺れながら咽頭癌で、静かに絶命した利用者さんがいました。
身寄りも過去も分からず、ゴキブリだらけのドヤ街の6畳間で生きていた人でした。
暴れ狂うため厄介者扱いされており、初めは私のことも「もういいよ、帰って」などとあしらっていました。
私は帰らず、でも特に何を話すわけでもなく、その人と午後のロードショーを眺めながら、固まった足首を解すマッサージをしていました。
そのうち、無表情だったその人がふふっと笑うようになったり、好きな映画のことや好きな人がいたこと、どんな仕事をしてきたのかなどを話すようになり、「またね、ありがと」と手を振ってくれるようになりました。
ここまでこの人が、他人を受け入れるのは初めてだとケアマネは驚いていましたが。
私がその人の癌(しこり)を発見し、「もし、癌だったら」と切り出すとその人は「何もしねーよ、別に(死んでも)いいよ」と言いました。
その言葉通り、最期まで酒と煙草をやめませんでしたし、私も止めませんでした。
最期まで本当に何もせず、薬ひとつ飲まず、穏やかに酒と煙草に溺れ、消えていきました。
その最期は、見事だと思いました。
この人から学んだのは「利用者さんの人生は、利用者さんのもの」ということ。
医療者がどうのこうのと変えられる部分なんてほんの一部に過ぎないし、変える必要も無いということ。
病院で行われている医療者主体の治療・ケアではなく、利用者さんやご家族が本当に選びたい道を選べるよう、歩めるよう最期の最期まで伴走出来るのが、訪問看護のやりがいであると思います。
しごレト編集部:病院だとどうしても「治す」ことが第一になりがちですが、しましまさんはその方の人生の“選び方”そのものを尊重されたのですね。
「何もしない」という選択を支え、ただ隣で過ごすことで、その方が最期まで自分らしく生ききった――まさに訪問看護ならではの深い関わり方だと感じます。
利用者さんの人生はその人のもの、医療者はその道に寄り添う存在にすぎない。
そのシンプルだけど揺るぎない考えが、しましまさんの看護観を大きく変えていったのだと伝わってきます。
3. 利用者さん自身の力を引き出すケアで印象に残ったエピソード
しごレト編集部:しましまさんは、利用者さんの「できる力」を最大限に引き出すケアを大切にされていると拝見しました。その中で、特に心に残っているエピソードを教えていただけますか?

しましまさん:
認知症治療薬の副作用で起きた腸閉塞で入院されていたBさんが退院され、在宅療養の開始時から約2年半ほど関わりました。
初めは枯れ木のように痩せ細って食事が取れず、歩くことさえままならなかったBさんは重度の認知症を抱えていました。
また、コロナワクチン接種後後遺症や難病を抱える奥さまに対して声を荒らげたり、意味不明な言動を終日繰り返していました。
元々は知的な人だったBさんでしたが、文字を書いたり読んだりする力も喪失していました。
私は奥さまの訪問看護にも携わることができ、時に厳しく、大抵冗談ばかり言い合って笑いながら、その日のご夫婦の状態・ADLに合わせた筋力維持・向上訓練、教科書や病院では絶対に学べない様々なリハビリ、中医学(経絡など)を組み合わせたオンリーワンのケアを継続していきました。
1ヶ月ほどでBさんはたっぷり楽しんで食事が取れるようになり、易怒性は消えて穏やかな笑顔が戻りました。
そして、1年もしないうちに歩くのもやっとだったのが塀や脚立に登って高枝切バサミを華麗に操り、柿や梅、夏みかんなど四季折々の果物を収穫するまでにADLが向上しました。
加えて、認知症を発症する以前のレベルで文書を作成できるようになり、TVで放送されていた世界情勢を奥さまに説明出来るようになりました。
90歳をゆうに超えるご夫婦でしたが、弱っていた姿が嘘のように、お二人だけで生活を営むことが出来るまでに回復されました。
ここに至るまで、うまくいかないこともたくさんありました。
看護師として非常に悩み、力不足を痛感しながらも、そのたびにお二人と真っ向から意見を交わして思いを受け止め、励ましつつ「お二人の可能性を最大限に引き出すこと」を目標に向き合い続けました。
お二人が元気になっていくにつれて、私もまた元気になっていくのを感じました。
最後は残念な別れの形となってしまいましたが、お二人から「しましまさんじゃないとダメなんだよ、他の人は嫌なんだよ。どうか行かないで、もう会えないなんて嫌だ」と、号泣の中で引き止めていただきました。
現代医学では「改善の見込みなし」と切り捨てられてしまう状態の人であっても、その人と真摯に向き合いながら、痒いところに手の届くケアをしていくことの大切さや楽しさを学びました。
しごレト編集部:Bさんの劇的な回復の様子が目に浮かぶようです。
枯れ木のようだった方が果物を収穫し、ニュースを奥さまに説明できるまでになる――その変化は、しましまさんの粘り強い関わりとお二人の努力があってこそですね。
教科書的なリハビリやマニュアルだけではなく、中医学を取り入れたり、ご夫婦の生活そのものに寄り添う「オンリーワンのケア」。
一人ひとりの可能性を信じて引き出していくことが、まさに訪問看護の本質なのだと改めて感じます。
4. 訪問看護で必要だと感じるスキルや心構えの違い
しごレト編集部:病院と訪問看護では、現場の環境や求められる役割が大きく違うと感じます。しましまさんが実際に訪問看護を経験して、「これは病院とはまったく違う」と強く実感したスキルや心構えは何でしょうか?

しましまさん:
病院勤務であれば、自分が判断できないことであっても経験豊富な先輩看護師や医師にすぐ相談できますが、訪問看護は孤独です。
看護を組み立てるのも自分、アセスメントするのも自分、判断してケアするのも自分。
さらに言えば、緊急事態と判断して、その時々でベストな対処をするのもすべて自分。
利用者さんやご家族が、いかに快適な生活を送るかという一点集中での工夫が必要であり、必要物資や環境が揃った病院看護とは、全てが異なります。在宅は治療の場ではなく、生活の場なので。
看護の自由度や裁量は病院と比べ物にならないほど高く、濃いオリジナリティが出せます。
しかし、その分背負うものも大きいのが訪問看護。何年目看護師だろうが、訪問看護が未経験だろうが、いつでも利用者さんとご家族にとって、最高で最強の看護師でいなければならないのです。
「しましまさんなら、何とかしてくれる」的な。
しごレト編集部:まさに“自分が現場の最後の砦”という緊張感が伝わります。
病院では医師や先輩がすぐそばにいる安心感がありますが、訪問看護ではすべての判断と行動を一人で担う――まるで現場そのものが小さな病棟で、しましまさんがその中心に立っているようですね。
一方で、自由度が高く「濃いオリジナリティが出せる」という言葉がとても印象的です。
その自由さが、しましまさんならではの看護を形づくり、利用者さんやご家族が「しましまさんだからこそ」と信頼を寄せる理由なのだと感じました。
5. 「もう辞めたい」と思った時の踏みとどまり方と転機
しごレト編集部:訪問看護は、孤独な判断や体力的負担など想像以上にハードだと感じます。そんな中でしましまさんが「辞めたい」と思った時に、それでも現場に踏みとどまり、続けようと決意できたのはどんな瞬間だったのでしょうか?

しましまさん:
今でも毎日が綱渡りです。4年目になりますが、正直言って「楽しい」と思えるほどの余裕はまだありません。
ただ、退職した場合、当然ですが「もうあの利用者さんたちに会えないのか。もうああいう、凄くどうでもいいことで、利用者さんと笑ったりできないのか」などと思うと……まだ辞めるの止めとくか、と踏みとどまって、奮起したりもします。
また、私の勤務する訪問看護ステーションは風通しが良く、スタッフ同士で隠し事をしない職場風土です。
「あーーーー辞めてえ」と、あふれんばかりに思った時はすぐ管理者に「もう辞めたくなりました」と心の内をさらけ出し、恥も外聞もなく、話を聞いてもらっています。
もう何回泣いたかわかりませんが……泥臭くもまだここに残っています。
しごレト編集部:仕事のハードさを超えて「まだ会いたい」「一緒に過ごしたい」と思える関係性こそ、訪問看護の魅力であり、しましまさんの看護の本質を支えているのだと感じます。
さらに、管理者に素直に「辞めたい」と打ち明けられる環境も素晴らしいですね。
その正直さと職場の受け止める力があるからこそ、泣いてもなお立ち上がり続けられるんですね。
6. 利用者さんやご家族との関係づくりで意識していること
しごレト編集部:訪問看護は、病院よりもずっと生活に近い場所で、深く人と関わるお仕事ですよね。だからこそ、利用者さんやご家族との距離感や信頼関係の作り方がとても重要だと思います。しましまさんが現場で特に大切にしていることは何でしょうか?

しましまさん:
私という人間を開示して、親しみを持ってもらうこと。
「看護師さん」という誰がやっても同じ、代わりがきく役割としてではなく、
利用者さんやご家族に自然と「しましまさん」と呼んでもらえるような唯一無二の存在となり、
人と人とのつながりを積み重ねていくことです。
しごレト編集部:「看護師さん」ではなく「しましまさん」と名前で呼んでもらう――その言葉から、ただケアを提供するだけではなく、一人の人間として関係を築く姿勢が伝わってきます。
医療者としての枠を超えて、心から向き合うことで、利用者さんやご家族も安心して自分を開ける。
その信頼があるからこそ、深いケアや本音のやりとりが可能になるのですね。
7. キャリアを通して変化した将来像
しごレト編集部:看護師として働く中で、自分のキャリアや将来像が少しずつ変わっていくことは多いと思います。しましまさんも、訪問看護を始めてから価値観や将来の描き方が変わったと感じる瞬間があったのではないでしょうか。どのような変化があったのか、ぜひ聞かせてください。

しましまさん:
私は元々、看護師になりたくてなったわけではなく、消去法で選んだ職業です。
そういうわけで、食うに困らないそこそこの稼ぎさえ手に入れば、特にやりたい看護や分野もありませんでした。
訪問看護師としてのキャリアを積んでいく中で、病院での治療を受けても治らない・良くならない人、薬の副作用でかえって心身が害されている人など、「現代医療の限界や弊害」を数多く目の当たりにするようになりました。
苦しんでいる全ての人を救うことはできない。
でも、ご縁のある人にだけでも「しあわせだな」と思ってほしい、その手助けをしたいと思うようになりました。
私は訪問看護を通して、「しあわせ配りやさん」になりたいのです。
しごレト編集部:“しあわせ配りやさん”という言葉、とても素敵ですね。
消去法で選んだ仕事が、今では人の幸せに深く関わりたいという目標に変わった――
まさに訪問看護の現場で、人の生き方や可能性に向き合い続けたからこその想いだと感じます。
しましまさんの言葉から、ただ医療行為を提供する以上に、人生そのものに寄り添う看護師としての覚悟が伝わってきます。
8. 訪問看護に向いている人・向いていない人
しごレト編集部:訪問看護は、病院とはまったく違う環境で判断や行動が求められるお仕事ですよね。だからこそ、人によって「向き・不向き」が大きく出る世界だと思います。しましまさんのこれまでの経験から、どんな人が訪問看護に向いていて、逆に難しいと感じる人はどんなタイプだと感じますか?

しましまさん:
訪問看護に向いている人は喜怒哀楽、どんな局面においても、全てを受け入れて楽しめる、心のスタミナがある人。工夫が好きな人です。
逆に訪問看護に向いていない人はマニュアル至上主義。誰かに頼らなければ決断できない人。常に損得勘定が優先される人。人の話を聞く気がない人です。
しごレト編集部:「心のスタミナ」という表現が印象的です。
訪問看護は、マニュアルに沿った流れ作業ではなく、その時々の状況や利用者さんの想いに柔軟に対応する力が必要なんですね。
喜びや悲しみも含めて受け止め、工夫を楽しめる人こそが、この仕事を長く続けていけるのだと感じました。
しましまさんの言葉から、訪問看護の現場は「その人らしい判断と行動」を積み重ねる仕事なのだと、改めて実感しました。
9. これから訪問看護に転職を考えている看護師さんが、やっておくべきこと
しごレト編集部:訪問看護に興味を持っている看護師さんにとって、最初の一歩はとても大きな決断ですよね。初めて現場に入る前にどんな準備をしておくと、自分も利用者さんも安心してスタートできるのでしょうか?

しましまさん:
余計なことは考えなくていいので、とにかく心と身体の体力をつけてほしいです。
訪問看護は身体が資本であり、まずは自分の心身の健康が保たれていないと、利用者さんの状態を良くすることは絶対にできません。
利用者さんに心配されるような看護師では、質の高いケアを行うことはできないのです。
そして
利用者さんの状態変化など、何でもまず医師に相談するのではなく、自分は看護のプロとして何ができるのか」をあらゆる面から考えてほしい。考えることをやめないでほしいです。
しごレト編集部:「まずは心と身体の体力を」と言い切るところに、訪問看護のリアルさを感じます。
知識や技術よりも先に、自分自身が健康で安定していることが、利用者さんへの安心や信頼につながるのですね。
確かに、看護師自身が疲弊していたり体調を崩していては、目の前の人を支えるどころではないはず。
10. 「あなたに会えてよかった」と言われる看護を実現するために
しごレト編集部:しましまさんのケアの根底には、利用者さんからの「あなたに会えてよかった」という言葉がきっと大きな支えになっているのではないかと感じます。その一言をいただける看護を実現するために、どんなことを一番大切にしているのでしょうか?

しましまさん:
利用者さんの波長に合わせた、オンリーワンのコミュニケーション。
ぽろっと溢れた本音を丁寧に掬い上げ、いろいろな角度から看ます。
また「単に優しいだけの、無責任な看護師になっていないか」とも、常に考えています。
守りたいものを守り抜くには、愛のある厳しさが必要不可欠ですから。
しごレト編集部:「オンリーワンのコミュニケーション」という言葉、とても心に残ります。
ただ寄り添うだけではなく、利用者さんが何気なく漏らした本音を見逃さず、そこに必要なケアを重ねる。
そして“愛のある厳しさ”を持つことで、優しさだけでは届かない深い安心感を生み出しているのですね。
しましまさんの姿勢は、看護の枠を超えて、人と人が本当に向き合うための大切なエッセンスそのものだと感じました。
最後に
しましまさんのお話を通して感じたのは、訪問看護の奥深さとやりがいでした。
病院で10年勤務した後、家族の事情から「仕方なく」飛び込んだ訪問看護の世界。しかし、利用者さん一人ひとりの人生に寄り添い、薬に頼らず回復へ導くケアを重ねるうちに、看護の本質に出会ったと語ります。
認知症で歩行も困難だった方が、自宅で果物を収穫できるまで回復したエピソードは象徴的でした。
利用者さんの“生きる力”を信じ、じっくり向き合いながらその力を引き出していく――現代医療では得がたい手応えが、訪問看護にはあります。
もちろん、訪問看護は孤独で責任の大きい仕事です。
判断もケアもすべて自分次第。けれど「利用者さんの人生はその人のもの」という信念を持ち、笑顔や本音を引き出す日々が、しましまさんにとって大きな喜びと成長の源になっています。
「しあわせ配りやさんになりたい」という言葉どおり、しましまさんの看護はただ優しいだけではなく、愛のある厳しさと確かな専門性に支えられていました。
訪問看護に挑戦したいと考えている方にとって、しましまさんの経験は心強い指針になるはずです。
一人ひとりの生活に深く関わり、その人らしい最期や暮らしを支える――看護の原点を実感できる場所が、訪問看護なのだと教えてくれるインタビューでした。
プロフィール
しましま

経歴:2012年 東北福祉大学 健康科学部保健看護学科を卒業し、看護師・保健師資格取得。横浜市の二次救急病院(けいゆう病院)に新卒で入職。
結婚および妊活のため、病棟は入職後1年でリタイアし、外来・検査室全般で経験を積む。
2022年 けいゆう病院退職後、訪問看護ステーション(forピースケア訪問看護ステーション)へ転職。現在も訪問看護師として活躍中。
ブログリンク:『不良看護師です。』 https://ameblo.jp/shima-shima-neko0213/
