
「セルフケア理論ってなんとなく知ってるけど…実際の現場でどう使えばいいの?💭」
「看護計画に書くときに、セルフケア要件ってどれに当てはまるのか迷う…」
「看護システムって、どれがどのパターンなのかパッと整理できない💦」
そんな疑問やお悩み、ありませんか?😊
この記事では、
-
セルフケア理論ってそもそもどういう考え方?
-
3つのセルフケア要件(普遍的・発達的・健康逸脱)を具体的に解説✨
-
全代償的・部分代償的・支持教育的の3つの看護システムも整理
-
実習や現場での活用例や記録への落とし込みポイントも紹介📝
が分かりますよ♪
セルフケア理論は「患者の自立支援」にフォーカスした理論で、
アセスメントや看護計画での視点を持つと、実践力がぐっと深まります💡
この記事では、セルフケア理論の基本から、現場で使える実践ポイントまでを
やさしく丁寧に解説していきます😊
看護学生さんや新人看護師さん、実習指導に関わる方にもおすすめの内容です✨
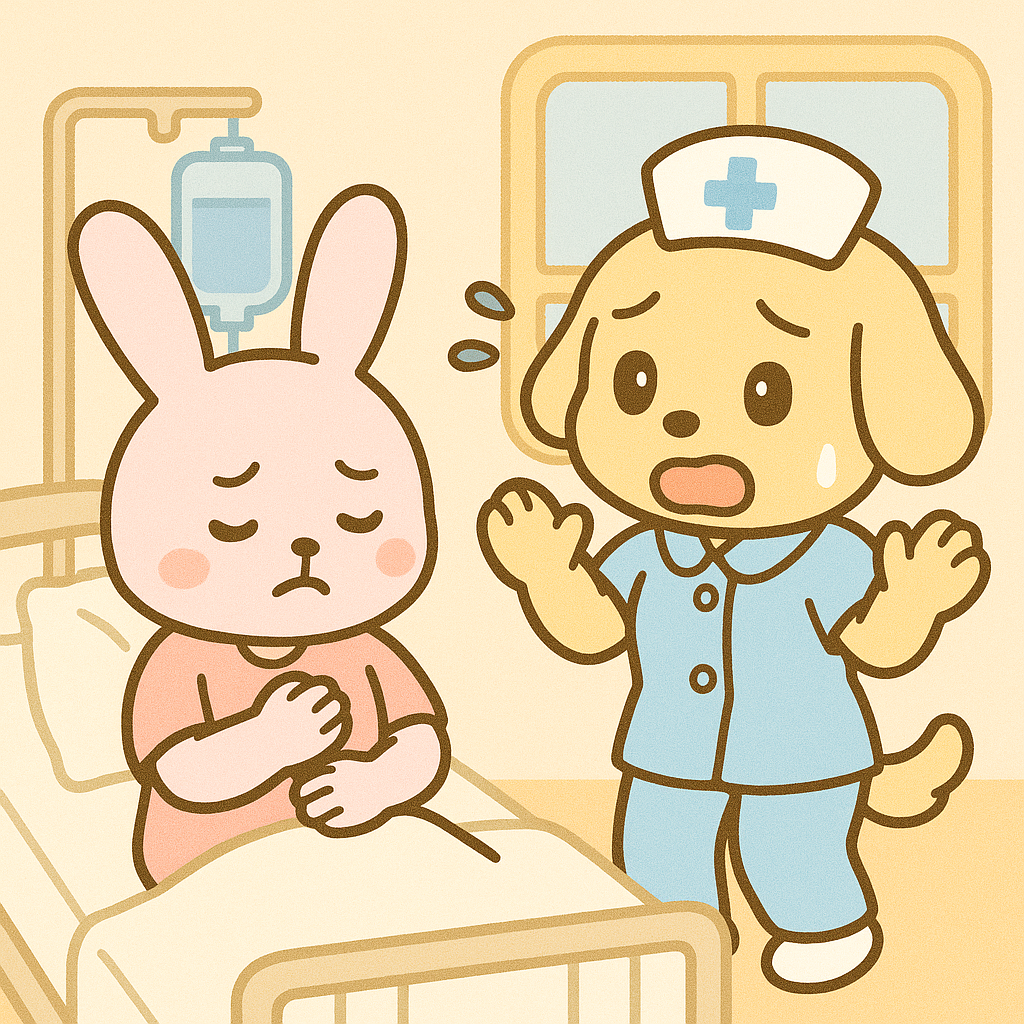
🧠セルフケア理論ってなに?基本の「き」からわかる入門ガイド📖
「セルフケア理論」という言葉、学校や研修では聞いたことがあっても、
実際に患者さんと関わるなかで「どう使えばいいの?」と感じている看護師さん、多いのではないでしょうか😊
この章では、まずセルフケア理論とはどんな考え方なのか、
そしてオレムという人物が提唱した理論の構造や、
いま改めて注目されている理由まで、わかりやすく整理していきますね💡
💬そもそも「セルフケア理論」ってどういう考え方?
セルフケア理論は、アメリカの看護学者ドロセア・オレムによって提唱された看護理論で、
その考えの中心は「人には自分自身の健康を守るためにセルフケア(自己管理)を行う力がある」という前提に立っています✨
ただし、そのセルフケアを自分だけで十分にできないときに、
「看護師が援助する必要がある」というところに看護の役割があるんですね😊
この理論では、
✅ セルフケアを行う力(能力)
✅ セルフケアが必要な内容(要件)
✅ 看護師がどう支援するか(看護システム)
という3つの視点を通して、患者さんへのアプローチを考えることができます。
🧱オレム看護理論の3つの要素とは?
オレムのセルフケア理論には、次の3つの柱があります👇
| 要素 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ① セルフケア要件 | 健康を保つために必要なこと | 栄養摂取、清潔保持、排泄など |
| ② セルフケア能力 | セルフケアを行う力・スキル | 知識、判断力、運動能力、意欲など |
| ③ 看護システム | 看護師がどのように援助するかの枠組み | 全代償的・部分代償的・支持教育的 |
1.セルフケア理論🌟
セルフケア理論では、人が健康を維持するために必要な3つのタイプのセルフケア要件を定義しています:
普及セルフケア要件(8項目)
-
十分な空気摂取の維持
-
十分な水分摂取の維持
-
十分な食物摂取の維持
-
排出過程と排出物に関するケアの提供
-
活動と休息のバランスの維持
-
孤独と社会の相互作用のバランス維持
-
人間の生命、機能、安寧に対する危険の予防
-
人間の潜在能力、既知の能力制限、および正常でありたいという欲求に応えた、社会集団の中の人間の機能と発達の促進
発達的セルフケア要件
人間の成長・発達過程や妊娠・出産、成人などのライフサイクルの各段階で必要となるケア
健康逸脱に対するセルフケア要件
疾患や障害によって特別なニードに対するケア
2. セルフケア不足理論 ⚡
セルフケア不足理論は、個人が必要なセルフケアを十分に行うことができない状態について説明しますこの状態が発生する原因には以下があります:
-
知識や技術の不足:正しいケア方法がわからない
-
身体的制限:疾患や障害による身体機能の低下
-
心理的課題:刺激の低下、うつ状態
-
社会的課題:支援体制の不備、経済的困難
3. 看護システム理論 🏥
看護システム理論では、セルフケア不足の程度に応じて3つの看護システムを提供します:
| 看護システム | 対象 | 看護師の役割 | 患者の役割 |
|---|---|---|---|
| 全額無償の看護システム | セルフケアが全くできない患者(昏睡状態など) | 全てのケアを代行 | 受動的 |
| 一部代償的看護システム | 一部のセルフケアは可能な患者 | 不足部分を補う | 部分的に参加 |
| 支援・教育的看護システム | セルフケア能力はあるが指導が必要な患者 | 教育・支援・指導 | 本体的に参加 |
この3つはセットで理解することが大切です✨
たとえば、糖尿病患者さんの場合
→「食事管理をする必要がある(セルフケア要件)」
→「血糖値の知識や自己注射スキルが必要(セルフケア能力)」
→「看護師は教育的に支援する(看護システム)」
というように、理論に沿って看護を展開していくんですね😊
🌟なぜ今、セルフケア理論が注目されているの?
近年の医療現場では、「自立支援」や「在宅復帰」が重要視されるようになってきていますよね🏠✨
セルフケア理論は、まさにその患者さんの生活を支える看護にピッタリな理論なんです!
✔ 高齢化が進むなかで「自分のことはできるだけ自分でやりたい」というニーズが増えている
✔ 入院期間が短くなり、「退院後のセルフケア力」が求められている
✔ 患者中心のケア(パーソンセンタードケア)との親和性が高い
こうした背景から、看護師として「どこまで援助し、どこを本人に任せるか」を考える視点がとても大切になってきているんですね🩺
セルフケア理論は、「援助しすぎない看護」、「患者さんの力を引き出す看護」を考えるうえで大きなヒントになりますよ✨
🧩3つのセルフケア要件とは?実例でサクッと理解しよう✨
セルフケア理論の中でも特に覚えておきたいのが、「セルフケア要件」です💡
これは、「患者さんが健康を維持・回復するために必要なことって、どんなこと?」を考えるための視点になります。
オレムはセルフケア要件を次の3つに分類しています👇
-
普遍的セルフケア要件
-
発達的セルフケア要件
-
健康逸脱セルフケア要件
「名前だけで覚えるのは大変…💦」という方も安心してくださいね♪
この章ではそれぞれの要件をやさしく解説して、実際の看護にどう活かすかまで見ていきます😊
💡①普遍的セルフケア要件って?〜日常生活に関わる基本項目〜
普遍的セルフケア要件は、すべての人が生きていくうえで共通して必要なことを指しています✨
これらの要件は相互に関連しており、どれか一つが欠けていても健康な生活は困難になります
年齢や病気に関係なく、みんなが持っているニーズなんです。
| 項目 | 内容 | 具体的な実例 |
|---|---|---|
| ①十分な空気摂取の維持 | 呼吸機能を適切に、酸素を十分に摂取すること | 深呼吸の実施、換気の良い環境で過ごす、呼吸器疾患の管理 |
| ②十分な水分摂取の維持 | 体内の水分バランスを正しく言うこと | 1日1.5~2Lの水分摂取、脱水予防、電解質バランスの維持 |
| ③十分な食物摂取の維持 | 栄養バランスの取れた食事を正しく摂取すること | バランスの良い食事、正しい食事量、栄養補助食品の活用 |
| ④排泄過程と排泄物に関するケアの提供 | 正しい排尿・排便を行い、清潔を保つこと | 定期的な排便習慣、正しい水分・食物繊維摂取、陰部清拭 |
| ⑤活動と休息のバランスの維持 | 適度な運動と十分な休息のバランスを整えること | 一日中の適度な運動、7~8時間の睡眠、リラクゼーション |
| ⑥孤独と社会的相互作用のバランスの維持 | 一人の時間と人の交流のバランスを守ること | 家族・友人との会話、趣味活動、プライベート時間の確保 |
| ⑦人間の生命、機能、安寧に対する危険の予防 | 身体的・精神的な危険から身を守ること | 転倒予防、感染予防、ストレス管理、安全な環境の確保 |
| ⑧正常でありたいという欲求に応じた機能と発達の促進 | 自分らしく生活し、能力を発揮すること | 身だしなみを整える、役割の維持、自己実現への取り組み |
看護師がアセスメントするうえで、患者さんがどの項目に困っているのかを見ていくと、必要なケアが見えてきますよ😊
👶②発達的セルフケア要件〜年齢や発達段階で変わるケア〜
発達的セルフケア要件は、年齢やライフステージによって異なるニーズに関するものです🎓
例えば…
| ライフステージ | 要件の例 |
|---|---|
| 新生児 | 体温調節の未熟さ、母乳による栄養摂取のサポート |
| 思春期 | 自己イメージの形成、ストレス対処の学習 |
| 高齢期 | 運動機能の低下、孤独感への対応、認知機能の変化 |
このように、「発達段階で起こる問題を予測し、それに合わせた支援を行う」のがポイントです🌱
つまり、看護師は患者さんの年齢や成長課題を踏まえて「今必要な支援は何か?」を考える必要があるんですね!
🩺③健康逸脱セルフケア要件〜病気やケガのときのセルフケア〜
こちらは、病気や障害、入院など「通常の生活ができない状態」によって生まれるセルフケアのニーズを指します。
たとえば…
| 状況 | 必要となるセルフケア |
|---|---|
| 糖尿病 | 食事制限、血糖管理、インスリン自己注射など |
| 手術後 | 傷の管理、安静の維持、感染予防 |
| 精神疾患 | 日常生活のリズムの調整、服薬管理、社会参加支援 |
この要件では、「いまこの患者さんは何ができなくなっているか」「どんな援助が必要か」をアセスメントすることが重要です👀
特に慢性疾患の患者さんでは、生活にセルフケアを組み込む支援が求められる場面も多いですよね!
📝3つの要件をどう見分ける?アセスメントのコツ🧠
実際の現場では、「この患者さんの困りごとは、どの要件にあてはまるのかな?」と迷うこともあるかもしれません。
そんなときは、以下の視点で整理してみるのがおすすめです👇
| 質問 | 該当する要件 |
|---|---|
| その人が元々持っている基本的ニーズ? | 普遍的要件 |
| 年齢やライフステージに起因する問題? | 発達的要件 |
| 病気・障害・外傷などによって生じた困難? | 健康逸脱要件 |
この視点を使ってアセスメントをすると、ケアの優先順位や看護計画の方向性も立てやすくなりますよ😊

🧭看護システムはどう活かす?3パターンの関わり方をマスター👩⚕️
セルフケア理論の中で、看護師としてとくに押さえておきたいのが「看護システム」の考え方です✨
これは、患者さんのセルフケア能力に応じて、看護師がどのように関わるかを3つのパターンで分類したものです。
患者さんの“できること”と“できないこと”を見極めることで、
「今のこの方にはどんな関わり方が最適か?」が見えてきますよ😊
この章では、それぞれの看護システムの特徴や活用のタイミングを、具体例と一緒に解説していきますね!
🏥看護システムとは?〜理論の実践モデル〜
「看護システム」とは、オレムが定義した看護師の援助のかたちを示す枠組みのことです🧩
患者さんがセルフケアをどの程度自分でできるかによって、以下の3つに分かれます👇
| 看護システム | 関わりのレベル | 対象となる患者 |
|---|---|---|
| 全代償的 | 看護師がすべて行う | 意識障害・重症の患者 |
| 部分代償的 | 一部援助しつつ本人の力も使う | 高齢者・術後の患者など |
| 支持教育的 | 本人が主で、看護師は教えたり励ましたりする | 慢性疾患や退院前の患者など |
「この患者さんには、どの関わりが適しているかな?」という視点を持つことで、
ただ“お世話”をするだけでなく、回復や自立を促す看護ができるようになりますよ✨
🛏全代償的システム:すべてを代わってケアするケース
全代償的システムは、患者さん自身でセルフケアがまったくできない場合に、
看護師がすべてを代行してケアを行うシステムです。
-
対象となるシーン:
-
意識睡状態や意識障害、体重の筋力低下などで患者さん自身がほとんどセルフケアをできない場合
-
-
看護師の役割:
-
すべてのケアを代行(例:全身清拭、体位変換、排泄・食事・呼吸管理、服薬や治療の実施など)
-
患者さんの安全と安楽を守ることが中心
-
-
患者さんの役割:
-
自分でできることが非常に限られている
-
-
実際の事例:
-
意識睡やせん錯、術後瞬時、重症疾患、小児、新生児など
-
この場面では「どこまでが医療処置で、どこからが看護なのか」を意識しながら、
患者さんの尊厳を守るケアを意識することがとても大切です😊
一方で、回復してきたら「部分代償的」に移行するタイミングを見極めることも、看護師の大事な役割です✨
🤝部分代償的システム:できることは本人に、足りないところを支援
部分代償的システムは、患者さんがセルフケアの一部を行える状態で、
できない部分だけを看護師が補うスタイルです。
-
対象となるシーン:
-
一部のセルフケアは可能ですが、全てを1人で行うのは難しい場合
-
例:骨折や手術直後で一部の動作が困難なとき、ADLの一部に介助が必要な患者さんなど
-
-
看護師の役割:
-
患者さんが自分でできない部分のみを補い、できることは尊重して自立を維持
-
身体介助・移動介助・服薬管理の一部サポートなど
-
-
患者さんの役割:
-
可能な範囲で自分のセルフケアを行い、不足部分のみ看護師のサポートを受ける
-
-
実際の事例:
-
脳血管疾患後のリハビリ期、骨折患者の更衣や移乗の介助、慢性疾患と向き合う中で一部ADL支援が必要な場合
-
🧠 ポイントは、「やればできそうなことは見守る」「失敗も学びの一部」として捉えること。
手を出しすぎないことで、患者さんの自信回復や自立促進につながるんです✨
🧑🏫支持教育的システム:患者の自立を支援する看護
支持教育的システムでは、セルフケア能力はあるけれど、
知識や経験が足りない患者さんに対して、
看護師が指導・助言・サポートを行います📚
-
対象となるシーン:
-
セルフケアの鋭いや能力はあるが、知識技術や未熟、または不安がある場合
-
例:糖尿病や高血圧など慢性疾患の患者さん、自己管理が今後必要な方
-
-
看護師の役割:
-
情報提供や教育、心理的サポート、効果的な学習環境の提供を行い、患者さんの自己管理能力を高めます
-
服薬・食事・運動指導、自己血糖測定のレクチャーなど、実践を後押しする
-
-
患者さんの役割:
-
本体的にセルフケアに取り組み、学びや疑問点を自発的に共有。
-
-
実際の事例:
-
生活習慣病患者への教育入院、退院指導、自己注射・自己血糖測定、家族への教育的支援
-
このスタイルでは、ただ「教える」だけではなく、
患者さんが安心して取り組めるように「寄り添いながら支える」ことが大切です💞
看護師のコミュニケーション力が特に問われる場面ですね!
3パターンの看護システムの特徴比較表
| システム名 | 主な対象シーン | 看護師の役割 | 患者さんの役割 | 主な支援内容・実例 |
|---|---|---|---|---|
| 全額負担システム | 意識睡・憂鬱・新生児など自立不能 | 全てのセルフケアを代行 | 受動的 | 体位変換、清拭、呼吸・食事・排泄の全面介助 |
| 一部代償システム | 一部のみ自立可能な患者、リハビリ中 | できない部分のみを補う | 可能な範囲で自立する | 更衣や入浴の一部補助、服薬管理の支援 |
| 教育をサポートするシステム | 慢性疾患等で今後自己管理が必要な患者 | 教育・指導・心理のサポート | 主体的に学び自立に挑戦 | セルフケア教育、自己注射の指導、家族指導 |
🔍それぞれのシステム、いつ使う?判断のヒント🧠
患者さんと関わるうえで「今、どの看護システムが適しているか?」を判断するのは、実はすごく大事なんです✨
以下のような視点で、簡単に整理できます👇
| 質問 | システムの例 |
|---|---|
| 患者さんがほとんど何もできない状態? | 全代償的 |
| 一部は自分でできるけど、援助が必要? | 部分代償的 |
| 自立しているけど、学ぶ必要がある? | 支持教育的 |
🔁 さらに大事なのが、「患者さんの回復段階に応じて柔軟にシステムを切り替えること」です!
その場の状態をよく観察して、支援の度合いを調整していけるのが、
セルフケア理論を活かしたプロフェッショナルな看護なんですね😊
🛠現場での活用ポイント💡セルフケア理論を看護にどう活かす?
セルフケア理論は、ただの理論で終わらせるにはもったいないくらい、
現場でのアセスメント・看護計画・実践にそのまま使える内容なんです✨
でも実際には、「教科書で習ったけど、どの場面でどう使えばいいの?」と感じている方も多いのではないでしょうか?
この章では、セルフケア理論を活かしたアセスメントの視点や、記録の書き方、
さらに具体的な事例まで紹介しますので、「なるほど!」と納得してもらえると思います😊
🧠セルフケア理論の視点を持つとアセスメントが変わる!
セルフケア理論を意識して患者さんを観察すると、
「この人は何が“できて”、何が“難しい”のか」という視点が自然に育ってきます🌱
例えば、同じ“食事が摂れない”という訴えでも…
| セルフケア能力 | できていないこと | 看護師の視点 |
|---|---|---|
| 身体的能力 | 手が震えて箸が持てない | 運動機能の補助が必要 |
| 精神的状態 | 食欲がわかず食べない | 不安や抑うつへのケア |
| 知識・理解 | 塩分制限の必要性がわからない | 教育的アプローチが必要 |
このように、“同じ症状でも背景はさまざま”なんです!
だからこそ、オレム理論の枠組みを使うと、患者の個別性を見逃さない看護ができます😊
📚実習や臨床での事例紹介(慢性期/精神科など)
ここでは、セルフケア理論を実際に使った看護事例をご紹介します📝
▶ 事例①:慢性期(糖尿病患者さん)
-
問題:血糖管理がうまくいかない
-
アセスメント:健康逸脱セルフケア要件あり/セルフケア能力は中程度
-
看護システム:支持教育的
-
看護介入:血糖測定の方法やインスリン注射の指導、失敗時の声かけで自信をつける
▶ 事例②:精神科(統合失調症の患者さん)
-
問題:服薬が不規則、生活リズムが乱れている
-
アセスメント:普遍的要件と健康逸脱要件の混在
-
看護システム:部分代償的〜支持教育的
-
看護介入:服薬管理の補助から始めて、最終的に自立を目指す
こうした事例に触れることで、「あ、私の患者さんにも応用できそう!」と感じてもらえるはずです💡
📝記録や看護計画にどう落とし込む?使えるテンプレート紹介
セルフケア理論を記録や看護計画に反映させると、
“なぜその介入をしたのか”がロジカルに説明できるようになります🧠✨
たとえば記録の例👇
| 看護問題 | セルフケア理論との対応 | 看護計画例 |
|---|---|---|
| 食事摂取量の低下 | 普遍的セルフケア要件の不備 | 患者に応じた食事支援+選択肢の提示 |
| 自己注射の失敗 | 健康逸脱要件/能力の不足 | インスリン自己注射の手順指導+リハーサル |
| 排泄動作の不安 | 部分代償的支援が必要 | 排泄誘導+トイレまでの見守り支援 |
このように、「要件+能力+看護システム」の3点セットで書く癖をつけると、看護計画もブレなくなりますよ✍️
🎓セルフケアを支える「教育的関わり」の実践ポイント
セルフケア理論の実践のなかでも、特に多いのが教育的支援です📘
患者さん自身にセルフケアを実践してもらうには、次の3つの力を育てることが必要です👇
| 必要な力 | 看護師の関わり例 |
|---|---|
| 知識 | パンフレットや図解での説明、言葉の選び方に配慮する |
| 技術 | 実際に一緒にやってみる、成功体験を積ませる |
| 意欲 | 「できた!」を引き出す言葉がけ、成功をほめる❤ |
この関わりには「ただ伝える」だけでなく、寄り添って一緒にやってみる姿勢がとっても大切なんです😊

🧸まとめ|セルフケア理論を理解すると、看護がもっと深まる💞
ここまで、「セルフケア理論ってそもそも何?」という基礎から、
看護現場での活かし方までを一緒に学んできました📘✨
「理論=難しい」という印象があるかもしれませんが、
セルフケア理論は、患者さんの“できる力”を大切にする看護を考えるための
とっても実践的で温かい理論なんです😊
この章では、要点を簡単に振り返りながら、
今後の看護にどう活かしていけるかを一緒に整理していきますね!
📝理論の理解で患者との関わり方が変わる
セルフケア理論を知ると、私たちの「看護の見方」が少しずつ変わってきます💡
-
ただ「できないこと」を補うのではなく、「どうすればできるようになるか?」に目を向ける
-
援助しすぎず、必要なところだけ支える「ちょうどいい距離感」を意識できる
-
セルフケア能力に応じて、患者の成長を引き出す関わりができる
つまり、患者さんの可能性を信じる看護ができるようになるんですね✨
これは看護師にとって、すごく大切な視点ではないでしょうか?
🔑これからの看護に求められる「セルフケア支援力」とは?
高齢社会・短期入院・在宅医療の広がり…
時代の流れとともに、看護師には「自立支援」がますます求められています🏠
これからの看護で必要なのは、「セルフケア支援力」=
🔸 患者のセルフケアを見極める力
🔸 支援が必要な場面を見極める力
🔸 自立を引き出す教育的関わりのスキル
この力を育てていくには、まさにオレムのセルフケア理論がピッタリなんです😊
「教科書に載っているから覚える」ではなく、
“使える理論”として自分のものにすることで、
より豊かな看護ができるようになりますよ🌱
💬看護学生・新人看護師さんへ伝えたいこと✨
もし今、「理論って難しいなぁ」「現場に出たら忘れちゃうかも…」と思っている方がいたら、
ぜひこう考えてみてください👇
セルフケア理論は、目の前の患者さんの“生活”を支えるための地図🗺
理論は難しい言葉が並んでいるけど、
その根っこにあるのは、「患者さんらしく生きる力を支える看護」なんです。
これからも、ひとり一人の患者さんと向き合う中で、
この理論の考え方がきっと役に立つはずです😊
困ったとき、迷ったとき、ふとセルフケア理論を思い出してみてくださいね❤






