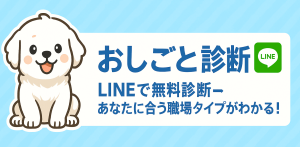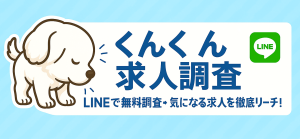「高齢者のケアでポジショニングが重要だと聞いたけれど、具体的にどのように行えばいいのか分からない」「褥瘡や関節拘縮を防ぐための正しい方法を知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、ポジショニングは患者さんのQOLを向上させるために欠かせないケア技術であり、褥瘡予防や呼吸状態の安定、介助者の負担軽減にもつながります!
ポジショニングの基本的な目的や具体的な実践方法、高齢者ケアにおける重要なポイントを5つに絞って分かりやすく解説しますね。
ポジショニングとは?定義と目的をおさらいしよう!

ポジショニングとは、簡単に説明すると患者さんの体位や姿勢を適切に調整することを指します。
特に、自力で動くことが難しい患者さんにとって、ポジショニングは非常に重要なケアの一環です。
これを行うことで、身体の負担を軽減し、快適な状態を保つことができます。
看護におけるポジショニングの役割
ポジショニングの定義は、患者さんの状態に応じて体位や姿勢を工夫し、管理することです。
具体的には、長時間同じ姿勢を続けることによる身体の負担を軽減し、褥瘡や拘縮の予防を目的としています。
また、ポジショニングを適切に行うことで、呼吸や循環機能の改善、さらには精神的な安定感をもたらすことができます。
つまり、ポジショニングは身体的なケアだけでなく、患者さんの心のケアにもつながる重要な技術なのです。
例えばポジショニングの重要性と言ったら何を思い浮かべますか?
ここでは褥瘡と呼吸循環についての影響を確認してみましょう。
褥瘡予防
褥瘡は長時間同じ姿勢でいることによって、皮膚やその下の組織が圧迫され、血流が悪くなることで発生します。
褥瘡の好発部位の確認をしましょう。

もちろん、原因はこれだけではありませんが、ポジショニングは大きく影響を与えます。
褥瘡を防ぐためには、体圧分散が非常に重要です。
体圧分散とは、身体が接触している面積を広げることで、特定の部位にかかる圧力を減少させることを指します。
エアーマットなど患者さんに合ったマットレスの選択や、時間ごとに体位を交換することによって圧迫による血流が悪くなるのを防止します。
呼吸や循環機能の改善
患者さんの呼吸や循環機能を改善するためにも重要な役割を果たします。
適切な体位を保つことで、肺が広がりやすくなり、呼吸が楽になります。
特に、上半身を少し起こした姿勢や、側臥位にすることで、肺の換気が促進され、酸素の取り込みが効率的になります。
また、体位を変えることで血液の循環も改善されます。
例えば、血圧が一時的に下がった場合に下肢挙上をしたりしますよね。
これは、下半身の血液を重力を使って上半身に誘導することが目的です、
このように、ポジショニングは単に快適さを提供するだけでなく、呼吸や循環機能の改善にもつながる重要なケアの一環なのです。
ポジショニングが患者さんに与える影響
ポジショニングは、患者さんの体位を適切に調整することで、さまざまな良い影響をもたらします。
特に重要なのは、患者さんのQOLの向上です。
快適な姿勢を保つことで、痛みや不快感が軽減され、リラックスした状態を維持できます。
これにより、患者さんはより良い気分で過ごすことができ、日常生活の活動にも積極的になることが期待できるのです。
QOLの向上
ポジショニングは、患者さんのQOLを向上させるための重要な要素です。
適切な体位を保つことで、身体の痛みや不快感を軽減し、リラックスした状態を作り出します。
これにより、患者さんは日常生活をより快適に過ごすことができ、活動的な生活を送ることが可能になります。
例えば、仰向けや側臥位でのポジショニングは、呼吸を楽にし、食事や会話をしやすくする効果があります。
また、体位を変えることで、血流が改善され、筋肉の緊張が緩和されるため、身体的な疲労感も軽減されます。
結果として、患者さんはより良い気分で過ごし、生活の質が向上するのです。ポジショニングは、単なる身体的なケアにとどまらず、患者さんの心の健康にも大きな影響を与えるのです。
看護師と患者双方の負担軽減
ポジショニングは、看護師と患者さんの双方にとって負担を軽減する役割も果たします。
患者さんが快適な姿勢を保つことで、身体的な痛みや不快感が減少し、ストレスが軽減されます。
これにより、患者さんはよりリラックスした状態で治療やケアを受けることができ、看護師の仕事もスムーズに進むのです。
また、看護師にとっても、適切なポジショニングは身体的な負担を軽減します。
患者さんが安定した姿勢を保つことで、体位変換や移乗の際の力が少なくて済み、看護師の身体への負担が軽減されます。
さらに、ポジショニングを通じて患者さんの状態を把握しやすくなるため、看護師はより効率的にケアを行うことができます。
こうした相乗効果により、看護師と患者さんの双方が快適に過ごせる環境が整うのです。
ポジショニングが必要とされる場面
ポジショニングは、患者さんや利用者さんが快適で安全に過ごすために欠かせない技術です。
具体的にどのような場面でポジショニングが必要とされるのか、いくつかのシチュエーションを見ていきましょう。
1. 長時間の臥床時
病院や介護施設では、長時間ベッド上で過ごすことが多い患者さんがいます。
このような場合、同じ姿勢を続けることで身体にかかる圧力が集中し、褥瘡ができやすくなります。
そこで、定期的に体位を変えるポジショニングが必要です。
例えば、仰向けから横向きに変えることで、圧力を分散させ、皮膚の健康を守ることができます。
2. 食事の介助時
食事をする際にも、適切なポジショニングが重要です。
特に、嚥下に問題がある方には、頭を少し前に傾けた姿勢が推奨されます。
これにより、食べ物が気道に入るリスクを減らし、安心して食事を楽しむことができます。

また、座位を保つためにクッションを使うことで、身体の安定性を高めることも大切です!
3. リハビリテーション時
リハビリの場面でもポジショニングは重要です。
運動療法を行う際、正しい姿勢を保つことで、筋肉の緊張を和らげ、動きやすくなります。
例えば、立ち上がりや歩行の練習をする際には、身体の軸を整え、重心を意識することで、より効果的なリハビリが可能になります。
4. 移動や移乗時
患者さんを車椅子に移動させたり、ベッドから椅子に移乗させたりする際にも、ポジショニングが必要です。
適切な体位を保つことで、転倒や怪我のリスクを減らし、介助者の負担も軽減されます。
力任せに車いすへの移乗を行っている看護師さんをたまに見かけますが、正しいポジショニングを行うことにより、患者さん、看護師さんへの双方への負担の軽減、アクシデントの予防が期待できます。
23年度の国家試験でもイラスト問題で片麻痺患者さんの車いすへの移乗が出ていましたね。
5. 精神的な安定を図る時
ポジショニングは、身体的なケアだけでなく、精神的な安定にも寄与します。
快適な姿勢を保つことで、患者さんはリラックスしやすくなり、不安感やストレスを軽減できます。
特に、認知症の方や精神的なサポートが必要な方にとって、安心できる姿勢を提供することは非常に重要です。
このように、ポジショニングはさまざまな場面で必要とされ、患者さんの快適さや安全性を確保するために欠かせない技術です。
正しいポジショニングを実践することで、患者さんの生活の質の向上だけでなく、介助者の負担も減らすことができます。
高齢者ケアでの重要性
ポジショニングは、高齢者のケアにおいて非常に重要な役割を果たします。
適切な体位を保つことで、身体的な健康だけでなく、精神的な安定も促進されます。
具体的に見てみましょう!
1. 日常生活動作の支援時
高齢者が日常生活を送る中で、ポジショニングは非常に大切です。
例えば、トイレや入浴などの際に、適切な姿勢を保つことで、転倒のリスクを減らし、安全に動作を行うことができます。
ポジショニングを工夫することで、身体の負担を軽減し、より自立した生活をサポートすることが可能です。
2. 社交活動やコミュニケーション時
高齢者が他の人と交流する際にも、ポジショニングは重要です。
例えば、椅子に座っているときに、背筋を伸ばして安定した姿勢を保つことで、会話がしやすくなります。
また、目線を合わせることで、相手とのコミュニケーションが円滑になり、社会的なつながりを深めることができます。
これにより、孤独感の軽減にもつながります。
3. 痛みや不快感の軽減時
高齢者は、関節や筋肉の痛みを抱えていることが多いです。
ポジショニングを適切に行うことで、痛みを和らげることができます。
例えば、クッションを使って身体の圧力を分散させることで、特定の部位にかかる負担を軽減し、快適な姿勢を保つことができます。
これにより、日常生活がより楽に過ごせるようになります。
4. 睡眠の質を向上させる時
高齢者にとって、良質な睡眠は健康に欠かせません。
ポジショニングを工夫することで、快適な睡眠環境を整えることができます。
例えば、枕やクッションを使って頭や首を支えることで、呼吸が楽になり、より深い眠りを得ることができます。
良い睡眠は、日中の活動にも良い影響を与えます。
5. 環境への適応を促進する時
高齢者が新しい環境に適応する際にも、ポジショニングは役立ちます。
例えば、介護施設に入所した場合、適切なポジショニングを行うことで、安心感を持って新しい生活に慣れることができます。
身体的なサポートがあることで、精神的な不安を軽減し、よりスムーズに新しい環境に適応できるようになります。
このように、ポジショニングは高齢者のケアにおいて多くの面で重要な役割を果たします。
適切な姿勢を保つことで、身体的な健康を維持し、精神的な安定を図ることができるのです。
高齢者が快適に過ごせるよう、日常的にポジショニングを意識して行うことが大切です。
急性期と慢性期での違い
ポジショニングと言っても対象者によって求められる条件がが違います。
患者さんのADLはもちろんのことですが、治療内容によっても変わってきますので簡単に急性期と慢性期で求められるポジショニング技術についてまとめてみました。
1.急性期
急性期では、症状が急激に変化することが多いため、ポジショニングも迅速に行う必要があります。
また、患者さんの状態を常に観察し、必要に応じてポジショニングを変更します。
例えば、呼吸状態が悪化した場合には、すぐに体位を変えて呼吸を楽にすることが大切です。
急性期は治療が進むにつれて、患者さんの状態が急速に改善することがあります。
そのため、ポジショニングも頻繁に見直し、最適な体位を保つことが重要です。
2.慢性期
慢性期は、病気が長引いている状態で、患者さんの状態が比較的安定しています。
患者さんの生活の質を向上させるために、長期的なポジショニングが求められます。
また自分で調節できる患者さんには、安楽な体位のとり方の指導や、自分で調整しやすい環境を整えるのも大切なことです。
慢性期では、病気の再発や合併症を防ぐために、適切なポジショニングが必要です。
例えば、褥瘡の予防や関節拘縮の防止のために、定期的に体位を変えることが求められます。
このように、急性期では接触的な治療の一環としてポジショニングが求められる一方、慢性期では予防や改善といったように目的が変化してきます。
ポジショニングの目的と効果:患者ケアの質を向上させる方法
ポジショニングは、患者ケアにおいて非常に重要な役割を果たします。ここでは、ポジショニングの主な目的と、それがもたらす効果について説明しますね☆
ポジショニングの主な目的
ポジショニングの目的は、患者さんが快適で安全な姿勢を保つことです。具体的には、以下のような目的があります。
- 身体の安定性を確保する: 患者さんが安心して過ごせるように、体位を調整して身体のバランスを保ちます。これにより、転倒や怪我のリスクを減らすことができます。
- 圧迫を軽減する: 同じ姿勢を長時間続けると、特定の部位に圧力がかかり、褥瘡(じょくそう)ができる可能性があります。ポジショニングを行うことで、圧迫を分散させ、皮膚の健康を守ります。
- 関節の可動域を維持する: 定期的に体位を変えることで、関節の動きを促進し、拘縮(こうしゅく)を防ぎます。これにより、患者さんが自分で動ける範囲を広げることができます。
- 呼吸や循環を助ける: 正しい体位は、呼吸を楽にし、血液の循環を良好に保つためにも重要です。特に、呼吸器系に問題がある患者さんには、適切なポジショニングが必要です。
ポジショニングがもたらす効果
ポジショニングを適切に行うことで、さまざまな効果が得られます。以下にその主な効果を紹介します。
- QOLの向上: 快適な体位を保つことで、患者さんのストレスや不安を軽減し、より良い睡眠や食事を促進します。これにより、全体的な生活の質が向上します。
- 痛みの軽減: 正しい姿勢を保つことで、身体の特定の部位にかかる負担を減らし、痛みを和らげることができます。特に、慢性的な痛みを抱える患者さんには大きな助けとなります。
- リハビリテーションの効果を高める: ポジショニングはリハビリテーションの一環としても重要です。適切な体位を保つことで、運動機能の回復を助け、リハビリの効果を最大化します。
- 合併症の予防: 褥瘡や関節拘縮、呼吸器系の問題など、さまざまな合併症を予防するために、定期的なポジショニングが不可欠です。これにより、患者さんの健康を守ることができます。
このようにポジショニングは心身の改善や予防も期待できます。
使い方次第では場所を選ばずにできる最強のケアなのです!
看護師が実践するポジショニングの具体的基本的な手法
看護師が実践するポジショニングは、患者さんの快適さと安全を確保するために非常に重要です。
ここでは、基本的な手法やポイント、クッションや補助具の活用法について、簡単に説明していきますね。

基本的なポジショニングの手順
ポジショニングを行う際の基本的な手順は、以下のようになります。
1.患者さんの状態を確認する:
まずは、患者さんの身体状態や好みの体位を確認します。
これにより、どのようなポジショニングが最適かを判断します。
2.体位変換の準備をする:
患者さんに声をかけて、これから体位を変えることを伝えましょう。
安心感を与えるために、ゆっくりとした動作を心がけましょう。
3.体位を変える:
頭部から足元へと順番に体位を変えていきます。
例えば、仰臥位から側臥位に移る場合、まずは頭を向けたい方向に動かし、次に肩や骨盤を支えながら体を回転させます。
4.ポジショニングを調整する:
体位を変えた後は、クッションや補助具を使って、安定した姿勢を保つように調整します。
必要に応じて、体位を微調整して快適さを確認します。
5.最終確認を行う:
最後に、患者さんが快適に感じているかどうかを確認し、必要に応じて再調整します。
仰臥位・側臥位・座位のポイント
- 仰臥位: 仰臥位では、頭部が高すぎないようにし、首や背中が自然なカーブを保つことが大切です。
膝の下にクッションを置くことで、腰への負担を軽減し、リラックスした姿勢を保つことができます。

- 側臥位: 側臥位では、体幹がねじれないように注意が必要です。クッションを使って、肩や骨盤をしっかり支え、体が安定するように配置します。
また、下肢が交差しないようにし、接触面積を広げることで圧迫を軽減します。

- 座位: 座位では、股関節、膝関節、足関節をそれぞれ90度に保つ「90度ルール」を意識します。
これにより、体重が均等に分散され、安定した姿勢を維持できます。
背もたれを使って、背中をしっかり支えることも重要です。
 クッションや補助具の活用法
クッションや補助具の活用法
-
- クッションの選択: 体圧分散効果のあるクッションを選ぶことで、特定の部位への圧迫を軽減できます。
- ピローの使用: ピローを使って、頭や背中、膝の下に配置することで、自然な姿勢を保つことができます。特に、円背のある患者さんには、背部を支える大きなピローが効果的です。
- スライディングシート: 患者さんを持ち上げずに移動させるためのスライディングシートを使用することで、身体への負担を軽減し、スムーズな体位変換が可能になります。
- ポジショニング・グローブ: 体位変換時に摩擦を軽減するためのポジショニング・グローブを使用することで、患者さんの皮膚を守りつつ、スムーズに体位を変えることができます。
- 番外編:ぬいぐるみ:専用のクッションなどは値段も高く、また在宅ではいくつも取り入れるのが難しいこともあるでしょう。
私が勤めていた慢性期~終末期の病院では、入院患者さんのほぼ全員が意思疎通も難しい寝たきり患者さんだったので、枕もクッションも足りず、最終的には家で使わなくなったぬいぐるみや、タオルを代用として使用していました。
目的別ポジショニングの工夫
ここでは目的別の正しいポジショニングについて再確認をしていきましょう!
誤嚥防止のための姿勢調整
誤嚥防止のポジショニングは、特に高齢者や嚥下障害を持つ患者にとって非常に重要です。適切なポジショニングを行うことで、食事中の誤嚥リスクを低減し、安全に食事を摂ることが可能になります。以下に、誤嚥防止のためのポジショニングの基本と実践方法について詳しく説明します。
ポジショニングの基本
1.姿勢の安定性:
食事中は、患者さんが安定した姿勢を保つことが重要です。下半身と体幹を安定させることで、上肢や頭頸部がリラックスし、食物の取り込みや嚥下がスムーズに行えます。
- リクライニング角度:
食事時のリクライニング角度は、通常30度から60度が推奨されます。30度では自力摂取が難しいため、介助が必要です。45度以上の角度では自力摂取が可能になることが多いです。
- 頭頸部の位置:
頭頸部は軽度に屈曲させることが望ましく、顎を引く姿勢が誤嚥を防ぐのに役立ちます。具体的には、胸部と顎の間に3~4横指の間隔を保つことが目安です。
2.ポジショニングの実践方法
- ベッド上でのポジショニング:
ベッドをフラットにし、患者さんが正中に位置するようにします。ズレ防止のためにクッションを使用し、足底がしっかりと接地するようにします。
- 食事前の準備:
食事前に環境を整え、患者さんが集中できるようにします。食事介助者は患者の目線を合わせ、食事を楽しむための五感を活用することが重要です。
- 介助の方法:
食事介助は、患者の舌中央にスプーンを入れるようにし、食物の取り込みや咀嚼を助けます。水分は流入速度が速く、誤嚥のリスクが高まるため、特に注意が必要です。
3.注意点
- 麻痺のある患者への配慮:
麻痺がある場合は、健側を下に側臥位にして安定させることが重要です。これにより、重力を利用して食物が健側に流れるようにします。
- 食後のポジショニング:
食事後は、患者さんが安楽な姿勢を取れるようにポジショニングを調整します。これにより、胃食道逆流の予防にもつながります。
誤嚥防止のためのポジショニングは、患者さんの安全を守るだけでなく、食事を通じてのQOLを向上させるためにも非常に重要です。適切なポジショニングを実践することで、患者さんが安心して食事を楽しむことができるようになります。
関節拘縮を防ぐためのケア
拘縮予防のためのポジショニングは、特に高齢者や長期間寝たきりの方にとって非常に重要です。ここでは、わかりやすくポイントを説明しますね。
1.ポジショニングの基本
- 安定した姿勢を作る:
体をしっかり支えることで、関節が動きやすくなります。クッションやタオルを使って、体の隙間を埋めると良いです。これにより、体重が均等に分散され、圧力がかかる部分を減らせます。
- 体の向きを考える:
寝ているときは、頭から足までの順番で体を動かすと、患者さんが驚かずにリラックスできます。まずは頭を動かし、その後に肩や骨盤を支えながら動かします。
- 関節の位置を調整する:
膝や股関節は軽く曲げて、自然な形を保つようにします。これにより、筋肉の緊張を和らげ、拘縮を防ぎます。特に、膝の裏に隙間ができないように注意しましょう。
2.具体的なポジショニングの方法
- 仰向けのとき:
頭部や上肢をしっかり支えるために、クッションを使います。腕が体に圧迫されないように、腕の下にもクッションを入れると良いです。足も少し曲げて、リラックスした状態を保ちます。
- 横向きのとき:
横向きに寝る場合は、体がねじれないようにクッションで支えます。下側の腕や脚が圧迫されないように、しっかりとクッションを配置します。
3.注意点
- 同じ姿勢を長時間続けない:
同じ姿勢を続けると、筋肉が固まってしまいます。定期的に体位を変えることが大切です。これにより、筋肉の緊張を和らげ、拘縮を防ぎます。
- リラックスできる環境を整える:
- 食事やリハビリのときは、患者さんがリラックスできるように環境を整えましょう。ストレスが少ないと、体も動きやすくなります。
これらのポイントを意識して、日常生活の中でポジショニングを行うことで、拘縮を予防し、快適な生活をサポートできます。大切なのは、患者さんが安心して過ごせるようにすることです。
自分に合った仕事を探すなら…「おしごと診断」
「今の仕事もやりがいがあるけど、ちょっと自分には合わない気がする…」と思ったら、「おしごと診断」をしてみましょう。あなたに合った仕事や職場が分かりますよ♪
関節拘縮予防はどうしたらいい?
関節拘縮がおこると、着替えが大変になったり、褥瘡のリスクも高くなりますし、何よりも患者さんのQOLが低下してしまいます。
PTに依頼して行ってもらうのが一番ですが、時間制限があったり、中にはPTがいない病院に勤務されたり、訪問看護の方は看護師がリハビリも行わなければならないこともあるでしょう。
簡単に誰でもできるリハビリを紹介します!

1.とにかく動かす!
患者さんがご自分である程度手指を動かせる状況であれば、グーパー運動を取り入れたり、指先を使った細かな運動を行うことが大切です。
例えば、認知機能に問題がなく誤嚥の可能性が低い方には、指先でつかめる程度の小さなものを箱から箱へ移したり、柔らかい小さなボールを握ってもらうなどです。
その他の関節なども自分でできることはご自分でしてもらう等、ADLを下げないように促すのも大切な予防策です。
2.温める!
患者さんが自力で動かせないほどの拘縮が進んでいる場合には、温めた後に受動的運動を行う、ハンドマッサージを取り入れ少しづつ可動域を広げていく必要があります。
温めることによって関節周りの組織が柔らかく動かしやすくなって動かしやすくなります。
痛みのない範囲内で可動域いっぱいに動かしましょう!
3.可動域を狭めない!
常にリハビリができる状態ではないと思うので、自発的に動かせない患者さんには、リハビリができないときなどタオルなどを握らせ可動域が狭くならないように対策を取っておきましょう。
4.重力を利用する!
拘縮した筋肉や関節は、時間をかけて伸びる性質があるため、重力を利用してゆっくりと伸ばしていく方法も有効です。しかし長時間同じ体制をとることは褥瘡の原因となるので時間を決めて行いましょう!
ポジショニングにおける注意点と成功のためのポイント
ポジショニングは、患者さんが快適で安全に過ごせるように体位を整えることでしたよね。
ここでは、ポジショニングを行う際の注意点や成功のためのポイントを説明しますね。

ポジショニング実施時の注意点
身体のズレや摩擦を防ぐ方法
ポジショニングをする時、患者さんの体がずれたり、摩擦で肌が傷ついたりしないように気をつけることが大切です。具体的には、以下のような方法があります。
- クッションや枕を使う: 体の下にクッションや枕を入れて、体がずれないようにサポートします。これにより、圧力が分散されて、肌への負担が減ります。
- 体位を変えるタイミング: 同じ姿勢を長時間続けると、体がずれやすくなります。定期的に体位を変えることで、摩擦を減らし、快適さを保つことができます。例えば、2時間ごとに体位を変えるのが理想です。
- 優しく動かす: 患者さんを動かすときは、急に動かさず、ゆっくりと優しく行うことが大切です。これにより、摩擦を減らし、患者さんが不安を感じにくくなります。
- 個々のニーズを理解する: 患者さんによって、体の状態や好みは異なります。どの姿勢が楽か、どの部分が痛いかをしっかり聞いて、個別に対応します。
- 体の変化に注意する: 患者さんの体の状態は日々変わることがあります。例えば、むくみが出たり、筋肉の緊張が変わったりすることがあります。そうした変化に気づいたら、すぐにポジショニングを見直すことが大切です。
- サポートを活用する: 必要に応じて、他のスタッフや専門家と連携して、最適なポジショニングを考えます。チームで協力することで、より良いケアが提供できます。
成功するポジショニングのコツ
1.チームでの情報共有の重要性
ポジショニングを成功させるためには、チーム内での情報共有がとても大切です。看護は一人では完結しないので、みんなが同じ情報を持っていることが必要です。例えば、患者さんの状態やケアの内容をしっかり共有することで、よりスムーズに対応できます。
- コミュニケーションを大切に: チームメンバー同士で気軽に話し合える環境を作ることが重要です。何か気になることがあれば、すぐに相談したり、報告したりすることで、みんなが同じ方向を向いてケアを進められます。
- 情報の整理: 患者さんの状態やケアの進捗を記録しておくと、後から見返すことができて便利です。例えば、申し送りノートやデジタルツールを使って、情報を整理しておくと良いでしょう。
2.継続的なアセスメントと改善
ポジショニングは一度やったら終わりではなく、常に見直しが必要です。患者さんの状態は日々変わるので、定期的にアセスメント(評価)を行い、必要に応じて改善していくことが大切です。
- 定期的なチェック: 例えば、毎週または毎月、ポジショニングの効果を見直す時間を設けましょう。どの方法がうまくいっているのか、どこに改善の余地があるのかを確認します。
- フィードバックを活用: 患者さんやチームメンバーからの意見を大切にしましょう。彼らのフィードバックを取り入れることで、より良いポジショニングが実現できます。
- 柔軟に対応: 患者さんの状態やニーズに応じて、ポジショニングを柔軟に調整することが求められます。新しい情報やトレンドに敏感になり、必要な変更を迅速に行うことで、より良いケアが提供できます。
これらのポイントを意識することで、ポジショニングを成功させるための基盤が整います。チーム全体で協力し合い、常に改善を目指す姿勢が大切ですね!
ポジショニングを活用したQOL向上の実例
さてここまで、ポジショニングの重要性をお話してきましたが、実際にどのような成功例があるのかを診てみましょう!
 実際のケア現場での成功事例
実際のケア現場での成功事例
- POTTプログラムによる食事支援
POTTプログラムは、患者のポジショニングを適切に行うことで、食事時のQOLを向上させることを目的とした取り組みです。
このプログラムでは、患者の姿勢を調整し、食事介助法を工夫することで、自力摂取を促進し、食事を楽しむことができるようにします。
実際に、POTTプログラムを導入した施設では、患者が自力で食事を摂ることができるようになり、満面の笑顔を見せるケースが多く報告されています。これにより、患者のQOLが大幅に向上したとされています。
- 褥瘡予防とQOLの向上
ポジショニングは、褥瘡予防にも重要な役割を果たします。
適切な体位を維持することで、圧迫による皮膚の損傷を防ぎ、患者の快適さを保つことができます。褥瘡が発生しないことで、患者は身体的な苦痛から解放され、精神的にも安定した状態を保つことができるため、QOLの向上につながります。
特に高齢者や寝たきりの患者においては、ポジショニングによる褥瘡予防がQOLを維持するための重要な要素となります。
- 在宅ケアにおけるポジショニングの活用
訪問看護の現場でも、ポジショニングを活用したQOL向上の事例が見られます。
訪問看護師は、利用者の状態に応じた体位を調整し、快適な姿勢を保つことで、日常生活の質を向上させています。
例えば、下肢の拘縮がある患者に対しては、適切なクッションを使用して脚を支えることで、痛みを軽減し、動作の改善を図ることができます。
このように、訪問看護におけるポジショニングは、利用者の生活の質を向上させるために欠かせない技術となっています。
これらの実例からもわかるように、ポジショニングは看護においてQOLを向上させるための重要な手段であり、患者の身体的・精神的な健康を支える役割を果たしています。
自立支援と心理的安定
上記にあげた食事支援はまさに自立支援につながると思いませんか?
食事介助では、介助者の都合で食べる順番を決められてしまったり、ご飯と一緒におかずを食べたい、逆にこのおかずはご飯と一緒に食べたくないなど、患者さん各々にも食べ方のこだわりもあるでしょう。
自立支援が成功すると、心理的安定にもつながります。
自立が完全体ではなかったとしても、全くできなかったことができるようになるということは自己肯定感も高まり、「これができたんだから、これも挑戦してみよう!」という気持ちにもなりやすいですよね。
気持ちをプラスに持っていくことによってQOLの向上にもつながります。
また、寝たきりで自分で寝返りができない場合にも適切なポジショニングを適切なタイミングで行ってもらえると、苦痛が軽減します。
私自身、出産の際に手術を受けたのですが、翌朝まで仰臥位でいるように言われた際、本当に苦痛でした…。
腰やお尻が痛いのに動けないということは想像以上に辛いことなんだと思う出来事でした。
あと、なぜか仙骨部に軽度の褥瘡を作ったことがあります。
もともと寝相はいい方ではあるのですが、子供に両側から挟まれて寝て身動きが取れずに寝ていたんだと思います。
なんか、仙骨部が痛い…と思っていたら、表皮剥離をしていました。
寝るたびに仙骨部があたると痛くて、褥瘡の辛さも知りました(ものすごく軽度なのに!)
体位の変更ができないこと、軽度とは言え褥瘡ができると全然眠れず…
ポジショニングによって心理的安定が図れるんだ!とこの記事を書きながら思い出しました。
家族や介護者へのポジティブな影響
適切なポジショニングの効果は患者さんだけではなく、家族や介助者へも良い効果をあたえます。
例えば、自立に繋がること。これは家族や介助者に大きな喜びを与えますし、介護負担も軽くなります。
また、患者さん自身の心理的安定も家族には安心感につながります。
そして、介助時も正しいポジショニングを行うことで介助者への負担も大きく軽減します。
床に座り込んだ患者さんをベッドや車いすへ移すのってものすごく大変!って経験をされた方もいるのではないでしょうか?
しかし、正しいポジショニング、例えばベッドから車いすへの移乗の場合、ベッドの高さを少し変えてみるだけでも立ち上がりのための労力が軽くなることがあります。
座位をベッド上でとらせていても、下にすぐにずり落ちる、左右に傾く、そのたびに直して…というのはなかなか大変なことです。しかし、クッション等を使用し、膝下にクッションを入れる、左右に傾かないようにクッションを入れるだけでも体位を保つことができますよね。
正しいポジショニングで患者さんも介助者もハッピーに★
しかし、場合によっては褥瘡予防、拘縮予防をできたりと長い目で見るとケアが増えることを防ぐことにも繋がります。
また、食事の全介助から、自力摂取になってくれたらすごく楽になりますよね。
そしてなにより、患者さんのQOLが上がるのが一番!
内服による苦痛の軽減は医師の指示が必要になりますが、ポジショニングは医師の指示はいらないことがほとんどです(術後などは別として…)
介助者が介助者の判断でその場でできるということも魅力的ではないでしょうか?
先述したように、ポジショニングに明確な正解はありません。そして継続的に行っていく必要があります。
だからこそ、チーム一丸となって実施と評価、訂正を行っていく必要があります。
試行錯誤は必要なケアとなりますが、患者さん、介助者の負担軽減のためにも今一度ポジショニングについて考えてみませんか?
求人の深掘りなら…「くんくん求人調査」へ
気になる求人や病院があれば、LINEで送ってくださいね!あなたに代わって、徹底的に調べますよ。求人を検討するときにぜひ♪