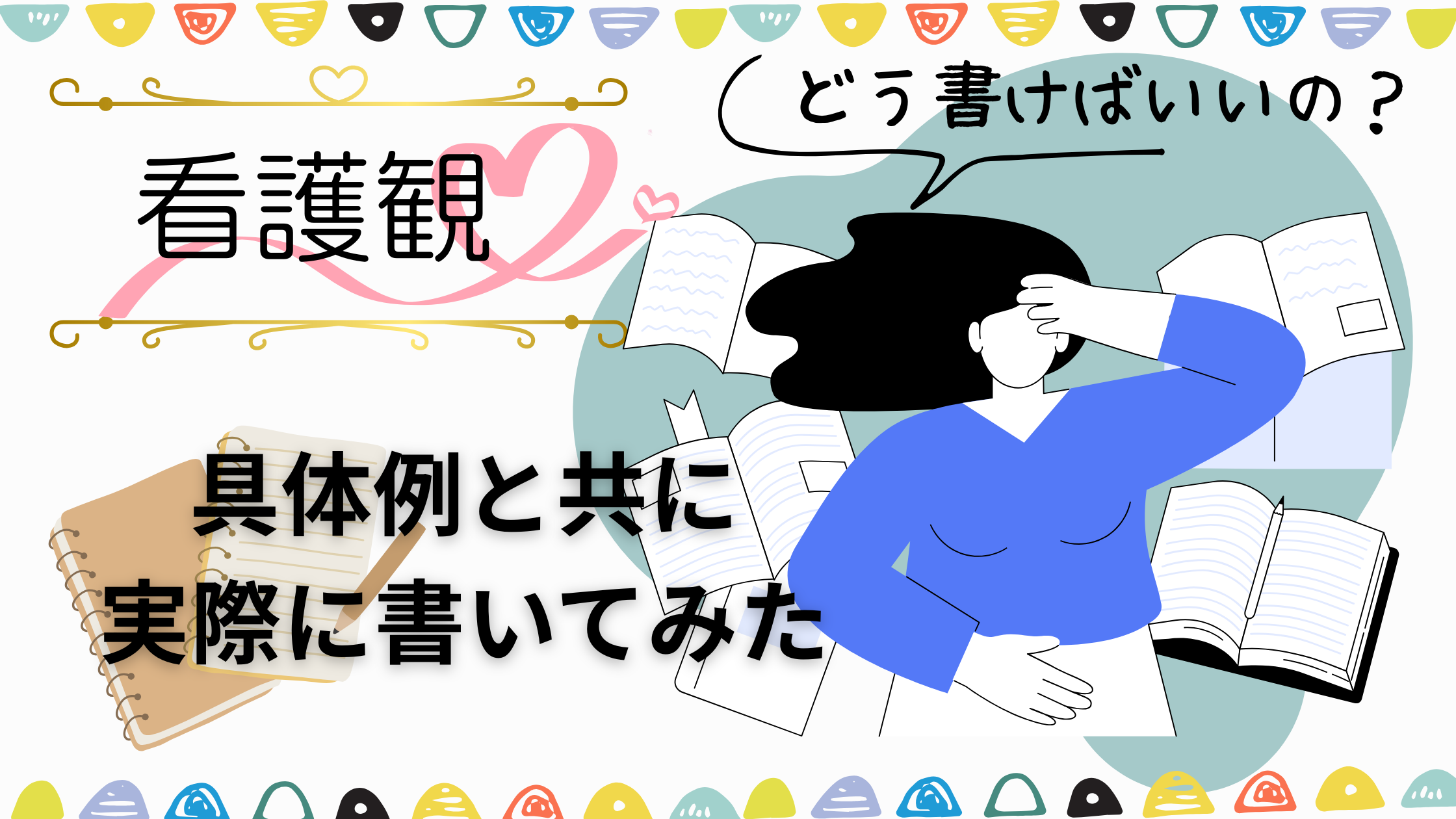
「どんな看護師でありたいか」
「目指すべき看護師像は?」
こうした姿勢や理想を表すのが看護観と言われるものです。
看護師としてあらゆる年代の患者さん、その家族を支援することや集団、地域社会を対象に、健康増進や疾病予防、健康の回復、苦痛の緩和などを行うこともあります。
そうした支援的活動を行う中で大切にしたい考え方の一つであるのが看護観です。
今回この記事では
・そもそも看護観ってなんだろう
・なぜ看護観って重要なのか法
・看護観のメリット/デメリット
などについて解説していきます。
この記事を読むことで、あなただけの看護観を見つけられるはずです。
ブックマークをして何度でも見返してくださいね。
看護観とは?(1.単語の意味)
まずは、「看護観」の意味を知りましょう。
看護観=看護師として患者にどのような看護を行うかについての考え
を指します。
明確な看護観を持つことで、患者個人のニーズに対応し、身体、精神、感情を総合的にサポートすることができます。
看護観は個人が置かれている立場、状況によって異なります。また、経験を積む上でより考えが深まり揺るがないものになっていくものです。
また、就職や転職の際にも、自分に合った価値観を共有できる医療機関を選ぶ上での指針として役立つとされています。
一方、面接官は看護観を持っていることやそれを踏まえた回答から人間性を見ているとも言われています。
看護観はなぜ重要なのか (重要性)
看護観を重要視しておくと、患者さんの身体的にサポートするだけでなく、精神的、感情的な側面からも健康を総合的にサポートすることができます。
結果として、患者さんに必要な看護を提供することができるのです。
患者中心のケアを提供するための指針となる (重要性)
患者さんに対して「自分が求められている役割は何なのか」を患者さんの目線に立って考えることで、患者さんの気持ちの変化をキャッチして寄り添うことができ、患者さんの気持ちを理解できるようになります。
このとき、患者さんの疾患や障害はもちろん、価値観や人生観など固有の状況も加味して考えることが大切です。
その結果、患者さん中心のケアが提供できるのでのQOL向上や満足感につながります。
看護師としてのモチベーションや行動の基盤となる (重要性)
一貫した看護を提供するには、看護の目的や意義を常に明確にしておくことが重要です。
忙しい時、迷ったときや不安に思うときにぶれない軸として機能してくれます。
専門職としての成長と自己研鑽を促す
キャリアを重ね、進化を続けることで見えてくる道もあります。だからこそ看護師として成長し、キャリアプランを考えるにも看護観は大切です。
また、人生観や経験、周囲の人との関わりによって看護観は変化していくものなので、今の自分に合う看護観を己を磨く中で見つけていきましょう。
まだ経験が浅い場合には、先輩の経験や思考を参考にすると自分の看護観のアップデートにつながりますよ。
看護観のデメリット
看護観の重要性は理解できたと思います。
しかし、看護観を意識しすぎることで生じるデメリットの存在も忘れてはいけません。
以下で解説していきます。
デメリット①固定観念にとらわれて柔軟な対応が難しくなる場合がある
主観的・客観的な情報から患者さんの異常や変化を見つけ適切なアセスメントを行うことが重要です。
しかし、「前は大丈夫だったから今回も大丈夫」などの根拠のない思い込みを持つことで異常の発見が遅れることがあります。(他の要因として経験年数なども影響している場合もあります。)
このように固定観念や感覚の無視によって異常を見逃してしまうリスクが生じます。
少しでも異常や変化を感じたのなら、一人で判断せず先輩看護師や医師に経過報告や情報共有を行ってください。
デメリット②チーム医療における意見の衝突を引き起こす可能性
看護師1人1人が持っている看護観の違いによって意見の相違や方向性のずれが生じることがあります。
老若男女の患者の命を現場では預かります。
だからこそ、意見の衝突などは仕事の継続が難しいと感じるほど人間関係で悩む理由の一つと言われています。
現場では「命を預かっている」大きなプレッシャーが要因となっているのです。
そのような環境下で適切なチームワークを発揮していくには、衝突をなるべく起こさないよう
「どのようなスタンスで患者に向き合っていくのか」という看護観を看護師同士で理解し合うことや擦り合わせることが大切です。
擦り合わせることが難しい場合は、最低でも互いの看護観の理解は欠かせないでしょう。
というのも、看護観は人により様々です。
1対1でじっくりと向き合うことを優先する方、効率を求めた対処を大切にする方など。
もちろん、すべて正解です。
重要なのは、チームとして看護するために考えの違いでの衝突を防ぐことです。
間違えやすい!?似た他の単語との違い
看護観と似ている単語も存在します。
勘違いしてしまうと、混乱してしまい正しい看護観への理解が進まず、もったいないので類似の単語の意味を解説していきます。
看護観と看護理論の違い
まずは端的に二つの単語の意味を見てみましょう。
看護観=看護師として患者にどのような看護を行うかについての考え
看護理論=看護という事象について記述し説明するもの
看護観は自分の姿勢や理想像を表すもので、看護理論は一連の概念や定義、関連を表しています。
看護観とは、看護の仕事に対する自分の姿勢を言葉にしたもので、「自分はどんな看護師でありたいか」を表し、必ず「患者さん目線」でなければなりません。
一方、看護理論は看護における知識を体系化し、関連した現象をより明確に説明するための枠組みとされています。業務を行ううえで守るべき「道徳」や「規範」を指します。
患者さん一人ひとりに最適な看護を行うために、守るべき原則や取るべき行動指針が定められています。
看護倫理は、大きく分けて「倫理原則」「倫理綱領」「臨床倫理」の3つから成り立っています。
「倫理原則」
自律尊重:患者自身の決定や意思を大切にし、行動することを尊重し、それを制限や干渉し妨げないこと
無危害:患者に身体的損傷(転倒や転落、ケガなど)を与えないよう危険を予防すること
善行:患者のために最善を尽くし、患者の利益になる行動をとること
公正と正義:すべての患者に平等に医療を提供すること、限られた医療資源を提供できる人数の範囲で平等に配分、提供すること
「倫理綱領」(https://kango.mynavi.jp/contents/nurseplus/career_skillup/20220726-2151818/ より)
人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する
対象となる人々に平等に看護を提供、信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する
人々の権利を尊重、秘密を保持し、人々が自らの意向や価値観にそった選択ができるよう支援する
対象となる人々に不利益や危害が生じているときは、人々を保護し安全を確保する
自己の責任と能力を的確に把握し、実施した看護について個人としての責任をもち、常に個人の責任として継続学習による能力の開発・維持・向上に努める
より質の高い看護を行うために、多職種で協働しよりよい保健・医療・福祉を実現・行動する
研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与する
看護職自身のウェルビーイングの向上に努めるべく、常に品位を保持し、看護職に対する社会の人々の信頼を高めるよう努める
人々の生命と健康をまもるため、さまざまな問題について、社会正義の考え方をもって社会と責任を共有し、よりよい社会づくりに貢献する
様々な災害支援の担い手と協働し、災害によって影響を受けたすべての人々の生命、健康、生活をまもることに最善を尽くす
「臨床倫理」
アドボカシー:権利擁護や代弁などを指します。看護実践において、患者の権利を擁護し、患者の価値や信念に最も近い決定ができるよう援助し、患者の安全や医療の質の保証、意思決定支援に関わる重要な概念
責務:法的責務と道徳的責務があり、法的責務は、免許や業務を規定している保健師助産師看護師法に基づく。
道徳的責務は、日本看護協会が定めた「看護職の倫理綱領」(2003年)や「看護業務基準(2021年改訂版)」(2021)などに示されている。
協力:看護を必要する個人、家族、集団、地域等に対して安全で質の高いケアが提供できるよう、様々な人と協働すること
様々な専門職・非専門職とチームを組んで業務を遂行することが多く、近年では、患者・家族もチームの一員として考え、メンバー全員が互いに配慮しあい、価値や目標を共有し目的達成のために共に貢献します。
ケアリング:ケアされる人とケアする人の双方の人間的成長をもたらすことが強調されている用語
対象者との相互的な関係性や関わり合い、看護職の理想・理念・倫理的態度、気づかいや配慮が看護職の援助行動に示され、対象者にとって何らかの意味を持つ
看護観の具体例と書き方【簡単5ステップ】
実際に看護観を考えるときには、順を追って考えていくことが大切です。
そうすることで、自分にしかない看護観を持つことができます。
今回は5つのステップに分けて解説していきますので、これまでの自分を振り返りながら看護観を見つけていきましょう。
ステップ①:自分の看護経験を振り返る
過去の経験で自分の看護観に影響を与えたと思う印象的な出来事をピックアップします。
このとき、当時の自分は何を、どう感じたのかを振り返ることが大切です。
出来事は1つに絞らず、複数用意しておくと良いでしょう。
経験から「何を大切にしているのか」「心掛けていること」が見えてくるはずです。
日頃何気なく行っている行動や考えにヒントがあり、答えがあります。
言語化することで明確にし、患者さんのためになっているか、独りよがりではないかなども考察できるとより研ぎ澄まされた看護観を見つけることができます。
ステップ②:自分が大切にしたい看護の価値観を明確にする
ステップ1で振り返った経験から「あなたがなぜ、その看護観を大切にしているのか」という根拠を示す必要があります。
その看護観を大切にしている理由や、看護観を考えるきっかけになった経験、具体的なエピソードなどから価値観を明確化していきましょう。
理由や具体例が一貫していることが大切です。
ステップ③:看護観のエピソードを盛り込む
ここでは、経験や出来事を具体化していきます。具体例をいくつかご紹介します。
過去の印象的なエピソードは説得力の向上にもつながりますので具体化をしておきましょう。
看護観のエピソードの例としては、次のようなものがあります。
・患者が気まずい思いをしたときに、フォローの意味を込めて笑顔で対応を行った
・患者さんの気持ちを想像して会話をしたり、相手の言葉を少し待ったりするよう意識する
・患者が何を考えているのか、何を望んでいるのかを深く観察して的確に察知し、応えていた
・患者さんの状態は目まぐるしく変化に対応すべく、どのような状態への変化が考えられるかを推測し、適切なアセスメントを継続的に行った
などが一例になるでしょう。
ステップ④:看護観の信念や目標を結びつける
看護観の目標には、看護師としてのモチベーションを維持し、質の高いケアを提供し続けることが挙げられます。看護観の具体例としては、次のようなものがあります。
患者や患者家族の気持ちに寄り添う
信頼関係を築き患者に安心を与える
個別性(その人らしさ、身体的特徴など)を重視する
患者のQOLや自然治癒力を高める
こうした目標や思いを持つことで、思いやりをもって患者や周囲に接したり、円滑なコミュニケーションをとることができます。また、観察力を磨いたり、臨機応変に対処する力を培うきっかけにもなります。
ステップ⑤:最後に要約してまとめる
上記の4つのステップをまとめましょう。
どんな経験をして、どんなことを感じ、大切にした軸は果たして何なのか。
自分が患者にケアするときに体現したい看護を言語化することで、どんなことがあってもぶれない看護観を形成することができます。
看護観は経験を重ねて変化していくものですので、現状の看護観に縛られすぎず、更新していくことも忘れずに。
看護観を考える際の注意点とよくあるミス
せっかく看護観を考えたのに、振り返ってみたらしっくりこないのではもったいないですよね。
そうなる前に気をつけたいポイントやよくあるミスパターンをご紹介していきます。
方向性に迷った時も、一度立ち止まって振り返りたい時にも、こちらも項目を役立ててくださいね。
注意点①:自分の経験や価値観に基づく具体性を持たせる
看護観に正解はないものの具体的な内容にする必要があります。
「誰にでも優しい看護師」のような漠然とした内容では目標になりにくいです。
例えば、「どんな状態の患者さんでのあるがままの状態を受け入れ、個人の状態に適した看護を行うこと」のように具体的に掘り下げましょう。
自分だけにわかるような抽象的な表現は、文章にしても他者に伝わりづらいため、具体的かつ誰が見てもわかるような内容にしておきます。
これまでの経験を振り返り、学んだことや大切にしたいことを洗い出して言語化してみると、自分らしい看護観が見えてきます。
注意点②:患者中心の視点を忘れない
患者さんが求める看護をどうしたら提供できるかを看護観を考える際には大切にしましょう。そもそも看護は、患者さんを「支援するため」に行います。患者さんにとって不要である、迷惑になってしまう看護では意味がありません。
例えば「会話を大切にする」という看護観であれば「患者さんの気持ちを引き出すために会話を大切にする」と、言い換えてみると患者さん主体の言葉になりますよね。
考えるのが難しい場合には、自分が患者の立場ならどんな看護をしてほしいかと視点を変えて考えてみるのがおすすめです。
注意点③:志望先の理念に合わせて伝える
合わない看護観を持つ医療機関で働き続けるのはあまり有益とは言えません。
例えば、就職や転職活動の際に自分の看護観をアピールする場合には、転職・就職先の理念と自分の持つ看護観がマッチしているかを事前に確認してください。
理念に対して、どのような看護を提供したいのか、どのような看護師として活躍したいのかといった看護観が大きく乖離していると、ミスマッチと判断されかねません。
一方で、病院側の理念と看護観のマッチ度が高ければ、採用率が上がるだけでなく、長く働くことができます。
ただ、注意したいのが、自分の看護観を大きく変えてまでミリをするのではなく、転職・就職先の理念と結びつけられる要素を見つけておくことが大切です。
よくある注意点①:他者の考えをそのまま引用する
同じ経験をしていても、取り巻く環境や視点が異なるので、同じ看護観につながるとは限りません。
看護観を考える際には、他人の真似にならないよう注意しましょう。
仮に真似てみて看護観を構築しても、やりにくさや違和感を感じてしまうでしょう。
看護観に正解はないため、自分自身の経験と言葉から、「どのような看護師になりたいのか」を考えることで、目標を見失わない看護観を見つけられます。
よくある注意点②:看護技術や知識だけに偏る
これまで得てきた技術や知識はもちろん大切です。
しかし、「であろう」などで進めてしまうことは観察力に欠ける看護と言えます。
看護師にとっての観察力とは、単に患者のバイタルサインを確認することだけではありません。 数値やデータなどを分析して、患者自身がいまどのような状況に置かれているのかを把握することが大切です。
状況を把握したら、症状から予想される問題や、服用している薬・検査結果などをもとに判断します。
状況から優先順位をつけて行動することを技術と知識に加えましょう。
看護観を育てるために重要なこと3つ
①:自己の看護実践を振り返ること(リフレクション)
看護におけるリフレクションの効果として、経験したことを振り返って深めていくことで、その経験の意味がわかるだけではなく、それまで気づかなかった‶自分が大切にしていたこと″がわかります。
看護実践を振り返ることは、その価値や意味を見出して次の実践に生かすプロセスです。
学びの質を高め、人材の強みを引き出し、組織のラーニング力を高めることがリフレクションの目的とされます。
ゆえに新人看護師の研修や、新たな役割に移行するリーダー・師長などの新人看護管理研修などでもリフレクションが活用されています。
以下がリフレクションの進め方の一例です。
事例を書く
事例を語る
事例を探求的に振り返る
事例のアウトカムを捉える
現象の意味や価値を考える
次の実践でどのように活用するか考える
発表する
リフレクションの基本スキルとしては、気づき、説明、批判的分析、総合及び評価の5つが挙げられます。
②:患者との関わりを重視し、相手の価値観を尊重すること価値観を尊重すること=患者や家族の意思を尊重して看護を提供すること
を意味します。必要なケアや情報提供を行うために、看護師は患者や家族の価値観や人生観、疾患や障害など、その人固有の状況を考慮することが求められます。
患者や家族の価値観を尊重する具体的な方法としては、以下のようなものがあります。
信頼関係を築く
意思を尊重して看護を提供する
患者や家族が納得し、快く受け入れてくれることを待つ
患者や家族が大切にしている者を尊重する姿勢を持つ
これまでの行動や意思決定を支えている価値観・宗教観から、今後の行動や療養生活における意思決定の基準を推測する
また、次のような能力やスキルも大切にしましょう。
基本を踏まえて個人個人を考慮する能力
患者の異変に気づく観察力
適切な処置ができる技術
患者の家族の不安や恐怖心を軽減させる心の看護を提供できる能力
③:継続的な学びと多職種連携の経験
患者の観察や多職種間の仲介役、情報を共有して連携を図ることは多職種連携に置いて欠かせない要素です。
多職種連携は、医師や看護師、薬剤師、理学療法士、ケアマネジャー、介護士などの異なる専門職が、各々の専門性を発揮しながら協働していくことを指します。
多職種連携において看護師が果たす役割には、次のようなものがあります。
患者の観察や多職種間の仲介役を担う
患者の治療・療養上必要な情報を共有して連携を図る
患者や家族の理解者として、他職種の意見に対する反応や、必要な支援の提案を行う
今後の支援の確認と目標を共有し、カンファレンスの運営を行う
多職種連携を進めていくには、何よりも互いを尊重することが重要です。
自らと異なる専門職の専門性を理解し、患者又は利用者等及びその家族の希望についてチーム全員で取り組み、患者や利用者が中心であるという前提を共通認識としなければなりません。
まとめ
看護観とは、看護師として、患者にどのような看護を行うか、大切にしていること、仕事に対する自分の姿勢などについての考え方を指します。就職や転職の際にも聞かれることも多く、実務外でも役立つものです。
これまでの行動や経験から構成されるもので、あくまでも患者さん目線で考えることがなによりも重要となっています。
独りよがりにならないよう、異なる価値観や経験を柔軟に取り入れて看護観をアップデートしていきましょう。
そうすることで、患者さんやその家族に寄り添った適切な行動をとることにつながります。
身体的な健康と心の健康、どちらにも対応できる看護観を見つけてくださいね。
