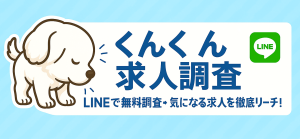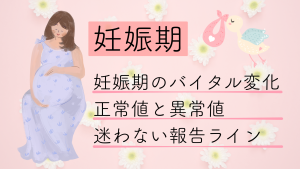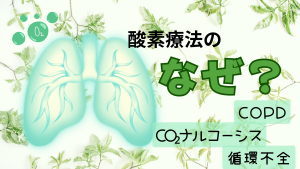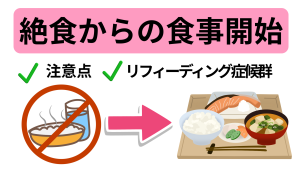「プランにつながるアセスメントが書けない!」
「Pの位置づけが分からない!計画って看護計画となにが違うの?」
「行ったケアはどこに書くの?アセスメント?」
などなどSOAPの書き方難民の方いませんか?
看護記録を正しく短時間に書くには、SOAP/SOAPIEの簡単な書き方のコツを押さえることが重要です!
看護記録の書き方、特にSOAP/SOAPIEについて、シンプルな4つのコツを紹介します。
これらのコツを活用することで、看護記録の記入がスムーズになり、業務の効率化が期待できます!
「SOAPの各項目には何を書けばいいの!?看護計画を立てるコツは!?」といったお悩みも解決できるペーパーペイシェントを設定した例も紹介!
さらに、SOAPや看護計画を書くためのA6サイズのあんちょこの配布もしています★
この記事を読めば、あなたも看護記録のプロになれる⁉

看護記録の目的と重要性
看護師の負担になることNo.1と言っても過言ではない看護記録。
なかにはたいして書くことないのに義務から書いている看護師さんもいるのではないのではしょうか?
今一度、看護記録とは何なのかをおさらいしましょう!
看護記録の目的は「患者さんの状態や看護実践の一連の過程を示す」ため!
患者さんの状態や行った看護を残しておくことによって、過去にさかのぼって病歴を知ることができます。
たとえば今は症状が出ていなくても、前回の入院時に誤嚥性肺炎を繰り返していたら、その患者さんは誤嚥性肺炎を起こすリスクが高いことが分かりますよね。
ADLが下がっていたら転倒歴はないけど今回の入院では転倒のリスクが高くなるとか…。
過去の看護記録を見直すこともとても大切です!
看護記録は今の状態を記録することだけに留まらず患者さんが持っているリスクについても知ることができるものです。
そのリスクを把握しているだけで発症させない対策がとりやすくなります。

①看護実践の証明
看護記録は、看護師が実際にどのようなケアを行ったかを示す「証拠」になります。
これは、医療訴訟などの際に重要な証拠資料として機能します。
②情報共有と持続性の確保
看護記録は、他の医療スタッフとの情報共有を可能にし、患者さんへのケアの一貫性と継続性を確保するために重要です。
これにより、患者さんに対するケアが途切れることなく提供されます。
③ケアの質の評価と向上
記録された看護実施内容を振り返り、評価することで、看護ケアの質を向上させることが期待できます。
④患者さんの状態の把握とケア計画の基礎
患者さんの状態や病状を詳細に記録することで適切なケア計画を立てるための基礎資料となります。
これにより、患者さんの健康状態を的確に把握し、必要なケアを提供することが可能になります。
看護記録の重要性は「法的な公文書となる」こと!
看護記録は、健康保険法や医療法に規定されている公的な記録で、法的公文書の性格を有しています。
近年は患者さんとの法的トラブルのニュースも多く見かけるようになりました。
インフォームドコンセントも浸透し、「お医者さんにすべてお任せします」という時代ではなくなりました。
また、医師の指示通りに注射を行った看護師がその薬物が原因で死亡に繋がったと過失に問われるケースも多く見かけます。
なんとなく書いていた看護記録ですが、法的公文書であるということを念頭に置いて書かないといけませんね。

法的及び倫理的な役割
看護記録は法的な公文書としての役割を持ち、患者さんのプライバシーを守るための重要な書類でもあります。
正確な記録は、患者さんの状態や看護実践の一連の過程を示すものともなります。
また裁判などになった時に適切な処置を行っていたことの重要証拠となります。
だからこそ自分を守るために丁寧に各項目を書く必要があります。
看護記録の書き方とSOAP/SOAPIEの基本
ほとんどの病院がSOAPで、SOAPIEを使用している病院は少ないのではないでしょうか。
ここではそれぞれの役割と違いについて説明していきます。
SOAPとは
SOAP形式は、情報を整理し、明確に伝えるための効果的な方法です。

Subjective(主観的情報)
- 患者さん自身が訴える症状や感覚、病歴、家族歴、社会歴など、患者さんから直接得られる情報を記録します。
これは患者さんの主観(発言)に基づく情報であり、例えば「痛みがある」「息苦しい」などの訴えが含まれます。
Objective(客観的情報)
- 看護師や医療スタッフが観察や検査を通じて得た客観的なデータを記録します。
これには、バイタルサイン(血圧、脈拍、体温など)、身体検査の結果、検査データなどが含まれます。
Assessment(アセスメント)
- 主観的情報と客観的情報を基に、患者さんの状態を評価し、診断を行います。
このセクションでは、患者さんの問題点や健康状態に関する考察が行われ、必要に応じて看護診断が含まれることもあります。
Plan(計画)
- 評価に基づいて、今後の治療方針やケア計画を立てます。
これには、具体的な治療法、看護計画、フォローアップの予定などが含まれます。
これにより、医療チーム内での情報共有がスムーズになり、患者さんに対するケアの質が向上します。
SOAPIEとは
SOAPまでは一緒ですが、ここにIとEが加わったものになります。
Intervention(介入)
- 実際に行った看護ケアや治療の詳細を記録します。
これには、患者さんに対する具体的な介入内容や実施した処置が含まれます。
Evaluation(評価)
- 介入の結果を評価し、患者さんの反応や治療の効果を記録します。
これにより、ケアの効果を確認し、必要に応じて計画を修正することができます。
SOAPとSOAPIEの違い
SOAPIEは、介入とその結果を評価することで、ケアの効果を確認し、必要に応じて計画を修正するプロセスを含んでいます。
これにより、患者さんのケアの質を向上させるためのフィードバックループが形成されます。
IとEがついたれたことにより、実施したケアの詳細とその結果を記録することができ、より包括的な記録を作ることができるんですね。
ここで、「だったら看護記録にIとEも入れたほうがよくない?」って考えませんか?
しかし、「SOAP」方式の方が「SOAPIE」より多いのはなぜ?

そこには「SOAPIE」に隠されたデメリットがあるからなんです!
どんなデメリットあがあるのか見てみましょう!
SOAPIEのデメリット
- 記録作成に時間がかかる
- SOAPIE形式は、介入(Intervention)と評価(Evaluation)の要素を追加するため、記録作成に時間がかかることがあります。
特に、詳細な記録が必要な場合、忙しい医療現場では負担となることがあります。
- 複雑さによる混乱
- SOAPIE形式は、SOAPに比べて構成要素が多いため、記録を作成する際に複雑さが増し、慣れていないスタッフにとっては混乱を招く可能性があります。
特に、各要素の区別が明確でない場合、記録の一貫性が損なわれることがあります。
- トレーニングの必要性
- SOAPIE形式を効果的に使用するためには、スタッフに対する十分なトレーニングが必要です。
これには時間とリソースが必要であり、特に新しいスタッフや経験の浅いスタッフにとっては、習得に時間がかかることがあります。
- 情報過多のリスク
- 詳細な記録を求めるSOAPIE形式では、必要以上に多くの情報が記録されるリスクがあります。
これにより、重要な情報が埋もれてしまい、迅速な意思決定が難しくなることがあります。
たしかにSOAPだけでも書くのが大変なあなた!
ここに毎回IとEまで付いたら全然記録が終わらない地獄にはまってしまいます!
そこで登場するのは「看護計画」!
実際現場でもS.O.Aは書くけどPを書かない人が多いのではないですか?
その代わりにPの所に「行った看護」を書く方いませんか~?
行った看護はIの項目なんですけど、病院の書式がSAOPだから、とりあえずPに書いておこ!って人~!

実際にPは計画として位置づけられていますが、看護計画のような計画とは少し意味合いが違ってきます。
ですので行った看護をそこに書くのは間違っていないです。
しかし、「行った看護で終了」してしまっている場合には不正解になります。
SOAPの上でのPは今後の看護に繋がることを書いていく必要があるからです。
つまり、PにIとEも隠れていると考えればよいでしょう。
例えば口腔内が汚れている患者さんに口腔ケアをしたとしましょう。
アセスメント:誤嚥性肺炎のリスクが高まる
計画:
口腔ケアを実施。
しかし嚥下機能の低下により唾液やケア時の水分でむせこみあり。
吸引付き歯ブラシの使用とケア用スポンジは固く絞り優しくふき取ることによりむせこみは見られなくなった。
「〇〇を行った結果××だったため△△したらこのような結果になった。」
このように記録に残すと良かった場合には、そのケアの方法を継続して行おう!となりますし、期待した効果が生まれなかった場合には違う方法で試してみよう!と今後の看護ケアにつながっていくわけです。

多くの看護師を長年悩ませているSOAP方式…
15年以上前からSOAPよりもFocus Chartingに切り替えている病院もありますよね。
この2つの書き方の違いは、SOAPは患者さんの「問題点」に焦点を当てた書き方。
一方のFocus Chartingは患者さんに「行った看護」に焦点を当てた書き方。
どちらの書き方にもメリットとデメリットがあるんですよね…。
例えばSOAPはアセスメントを行ったうえでケアを行うので、このような観察⇒判断⇒ケアが一連として読み取りやすいです。
しかし、緊急時などは、いちいちアセスメントをしている場合ではありません。緊急時には向かない記録方法なんですね。
その点Focus Chartingはアセスメントの項目がありませんので、緊急時の箇条書きがそのまま記録になりますが、詳しいお話は、また今度…。
悩みあるある
よくある「SOAPあるある」をまとめてみました!
当てはまるものはありますか??
アセスメントに自信がなくて全然進まない…

あとで看護記録を書こうとして、どの患者さんさんが何を言っていたのかごちゃごちゃになりわからなくなる

毎日同じようなことばかり書いている。

看護記録を一新させるために転職も!まずは気軽にポチッとおしごと犬索
LINEにあなたの状況や希望を書いてもらえれば、あなたに合う仕事を見つけられます♪
看護記録の構成要素と記入ポイント
看護記録と聞くとついSOAPなどの日々の記録のみを思い浮かべますが、アナムネから看護師が書くものすべてが看護記録となります。(もちろん個室代とかは省きます!)
看護記録の必須項目
看護記録の必須項目は、患者さんのケアを適切に記録し、情報を共有するために重要です!
下のフローチャートをご覧ください。

患者さんの基本情報
- 患者さんの氏名、年齢、性別、病院の識別番号、入院日などの基本的な情報が含まれます。
(この辺りはアナムネにあたりますね。)
バイタルサイン
- 体温、脈拍、呼吸数、血圧などのバイタルサインは、患者さんの健康状態を把握するために重要です。
(バイタルサイン表が別にある場合、アセスメントに必要ではない場合、SOAP内にバイタル情報を書く必要はありません)
主訴と症状
- 患者さんが訴える主な症状や問題点を記録します。
これには、痛みの程度や場所、その他の症状が含まれます。
判断と評価
- 医師や看護師による診断結果や患者さんの状態に関する評価を記録します。
医師が判断した場合には必ず「医師により〇〇と診断される」と誰が診断したのかを書きましょう。
治療計画と介入
- 患者さんに対する治療計画や実施した介入内容を詳細に記録します。
これには、投薬、処置、看護ケアなどが含まれます。
患者さんの反応と結果
- 介入後の患者さんの反応や治療の結果を記録します。
これにより、治療の効果を評価し、必要に応じて計画を修正することができます。
コミュニケーションと教育
- 患者さんやその家族とのコミュニケーション内容、教育や指導を行った内容を記録します。
これには、患者さん、および家族の理解度や同意の確認も含まれます。
看護記録の記入上の注意点
記録の正確性や一貫性を保ち、患者さんへのケアの質を向上させるために不可欠な注意点を上げます。
正確性と客観性を保つ
- 記録は事実に基づいて正確に行い、主観的な意見や推測を避けることが重要です。
観察した事実を明確に記述し、患者さんの状態を客観的に記録します。
タイムリーな記録
- 患者さんにケアを提供した直後に記録を行うことで、情報の正確性を保ちます。
その時に時間の確認をしっかりと行いましょう。
明確でわかりやすい表現
- 誰が読んでも理解できるように、明確で簡潔な言葉を使用しましょう!
専門用語や略語は、院内で標準化されたものを使用し、誤解を招かないようにします。
責任の明確化
- 誰がどのケアを行ったのかを明確に記録し、責任の所在をはっきりさせます。
担当者の名前や役職を具体的に記載することが重要です。
倫理的配慮
- 患者さんのプライバシーや尊厳を守るため、記録内容に配慮します。
人権を侵害するような表現や、患者さんを呼び捨てにすることは避けます。
カルテの開示請求も考え、見られても問題のない言葉を選びましょう。
変更や修正の記録
- 記録を変更する場合は、元の記録を消さずに訂正し、変更の理由と日時を明記します。記録の改ざんは厳禁です。
消えるボールペン、修正ペン等も禁止です。
書き間違いや変更のある時は、二重線をひいて、訂正印を押します。
看護記録の書き方の手順
ここが皆さんが一番悩まれているところだと思います。
うまくアセスメントにつながらない。看護ケアにつながらないなど…
看護記録を書く上でのポイントをまとめました!
情報収集
患者さんの主訴や身体的、心理的、社会的状況を含めた全体像を把握します。
すべては情報収集から始まると思ってください!
忙しくてなかなか一人ひとりに時間をさけないという課題もありますが、ここでの情報の質でグンと看護記録は書きやすくなります!
- 主訴(痛い、苦しい、不安など)
- バイタルサイン(体温、脈拍、血圧など)
- 身体症状(痛み、呼吸状態、皮膚の状態など)
- 精神状態(不安、抑うつなど)
- 生活環境や社会的支援の状況
- 検査データ
痛みや呼吸苦などの患者さんの感じ方によってうまく判断できないときはスケールなどを使用し、患者さんに「10段階のうち、今の状態は〇〇」というように示してもらうと評価がしやすくなります。

””日本ペインクリニック学会より引用””
情報の分別
- 主訴(S)や客観的視点で観察(O)したことにつながるデータ(O)を紐づける
その際、客観的視点は「苦しそうにしている」「痛そうだ」ではなく、
⇒「努力呼吸をしている」「顔をゆがめている」といったように看護師の感情や予測ではなく状況を書くようにしてくださいね。
また先述したスケールも活用できます。
看護診断(アセスメント)
分析した情報から、患者さんの抱える問題や潜在的なリスクを特定します。
- SとOを踏まえて…
- 現在考えられる原因
- その原因に対し必要と思われる看護
- 今後出てくる可能性がある症状
以上のことをアセスメントしましょう。
目標設定
- 看護目標は具体的で測定可能なものにしましょう!
Specific(具体的):何を達成するかを明確にする。
Measurable(測定可能):達成状況を客観的に評価できる。
Achievable(達成可能):現実的な範囲で実現可能な目標。
Relevant(関連性がある):患者さんの状態やニーズに関連する。
Time-bound(時間設定がある):達成の期限を設定する。
- 目標は「いつまでに患者さんがどのような状態になる」ということを書きましょう!
例えば…
- 長期目標「痛みが消失する」
短期目標「48時間以内に痛みの強さを10段階評価で7から3以下に軽減できる。」 - 「1週間以内に自己導尿の手技を正確に実施できるようになる。」
- 長期目標「患者さんの不安が消失する」
短期目標「1週間以内に、深呼吸やリラクゼーション法を1日2回実施することができる。」
などです。具体的に目標を設定することにより評価もしやすくなります。
まれに看護師としての自分の目標を書く人がいますが間違いです。あくまで患者さんが主体です。
看護計画の立案
- 看護問題
看護問題を明確にします。 - 看護目標
誰でも同じように評価できるようにしましょう。
例えば「痛みが和らぐ」ではスケールで7から3で和らぐと評価する人と、1で評価する人が出てきます。
「緩和する」と曖昧な目標にするのだったら、「消失、完治する」と言い切ってしまいましょう。(消失、完治が難しい時こそスケールが役に立つ事が分かりますよね!) - 観察計画O-P
バイタルサインなど問題に関連した観察項目を書きます。
病的な症状のみに留まらず、患者さんや家族の理解度や認識など生活背景も考慮した内容も含みます。 - 援助計画T-P
患者さんの問題解決のための看護介入内容を書きます。
看護師だけでは解決できない問題(処方など)は、医師の支持を仰ぐことを記載しましょう。 - 教育計画E-Pまずは患者さんに教育の必要性を理解してもらう必要があります。
そのほか、患者さんが自ら行える対処法についての教育内容を段階的に書いていきます。
家族の支援がうけられる場合には家族も含め指導を行います。
看護介入の実施
実際に看護計画に基づいて、観察や看護ケアを行っていきます。
評価
評価する日をあらかじめ決めておきましょう。
例えば1週間だったら「1週間の段階でここまでは目標に近づいているが、ここまでには至っていない」などです。その場合にはどうしたら早く目標を達成することができるか計画内容を変更しましょう。
また順調に進んでいない場合、早期に目標達成した場合には評価日を前に評価と修正、または終了をしましょう。
看護記録の例

ここでは
- 疼痛のある患者さんの疼痛緩和の計画
- インスリン導入の患者さんの教育計画
- 認知症で薬がうまく飲めない患者さんの社会資源の利用も検討した計画
の3つをペーパーペイシェントを使用して立案しました。
★疼痛によりADLが下がっている患者さん
患者さん情報
名前: 山田太郎
年齢: 65歳
診断: 大腸がんによる慢性疼痛
痛みの部位: 腹部
痛みの程度: NRSスケールで7(強い痛み)
現在の治療: オピオイド系鎮痛薬を使用中
看護問題
「大腸がんによる慢性疼痛に伴うADLの低下」
上記には
- 疼痛
- ADL低下
という2つの問題が隠れています。
NRSスケール7と、疼痛が原因でADLが低下しているので、ここでは「疼痛」を#1の問題にします。
看護目標
#1の問題が「疼痛」であるので、この場合考えられる看護目標は「疼痛の軽減・消失」となります。
O-P
- バイタルサイン
- ペインスケール
- 顔貌(苦悶様、渋面、無表情)
- 痛みに対する言動
- 痛みの部位と性状
- 痛みの持続時間
- 痛みの随伴症状と増悪因子・緩和因子
- 食欲、悪心 ・ 嘔吐、便秘などの有無
- 鎮痛薬使用の効果
- 睡眠状態
- ADL
- 家族関係、サポートの状態
- 疾患に対しての理解度
- 検査データ
T-P
- 安楽な体位をとる。
- 患者さんや家族の言葉を傾聴し、共感的な姿勢を示す。
- タッチングやマッサージを行う。
- 薬剤管理(自己管理できない場合や静脈注入による鎮痛薬の投与の場合)を行う。
- 食事が進まない場合には好みに合わせた食事の工夫を行う。
- 排便コントロールを行う。
- 気分転換をしたり人との適度な交流を図る。
- 好きなことができる環境を調整する。
- ペインスケールMAX時(または過去最高の場合)には医師に報告をする
E-P
- 疼痛をがまんしないよう説明する。
- 薬の作用、副反応、使用方法(必要に応じて)を説明する(薬剤師より)
★血糖の自己測定と自己注射の手順を覚える必要がある患者さん
患者さん情報
名前: 山田次郎
年齢: 70歳
診断: 糖尿病
自覚症状:なし
現在の治療: 看護師による血糖測定とスケールを実施
今後の予定:退院へ向けてインスリンの導入
看護問題
- 血糖の自己測定とインスリン注射導入に対して不安がある
看護目標
- 自己測定、自己中の主義を身に着け不安が解消される
O-P
- 糖尿病に関する認識、理解の状態
- インスリンに関する認識、理解の状態
- 高血糖や低血糖に関する認識、理解の有無
- 今後の生活における不安の状態
- 自覚症状の有無、程度
- 食事や飲水状態
- 排泄状態
- 体重の増減の有無
- 家族の協力状況
- 退院後の運動量や食事の状況
- 検査データ
- E-Pに対する理解度
T-P
- 患者さんの理解度に合わせた教材の作成
- 血糖測定、自己注射の手技を獲得できるように介入する
- 理解度や手技、家族の状態を含め必要であれば他部門との連携をとる
E-P
- 糖尿病の一般的な症状の説明
- インスリンの作用、副反応についての説明(薬剤師より)
- 教材を使用し、手技の説明
- 低血糖予防や発症時の対応についての説明
- 糖尿病の合併症の説明
- 使用した針などの廃棄の方法
- 栄養指導(栄養士より)
- 不安や疑問点は質問するように説明
★認知症により内服管理が難しく入退院を繰り返している患者さん
患者さん情報
名前: 山田三郎
年齢: 85歳
診断: 心不全
自覚症状:なし
現在の治療: 内服治療、食事療法、飲水管理
今後の予定:自宅退院
看護問題
- 認知度の低下により服薬やできず入退院を繰り返している
看護目標
- 服薬管理を行うことができる
O-P
- 認知症の進行状況
- 心不全のレベル(NYHA心機能分類など)
- 入院前の薬剤管理の状態
- 食事摂取量
- 飲水量
- 排尿状態
- 浮腫の有無
- 同居家族の有無と生活状態
- 本人と家族の希望
- 社会支援の利用状況
- 検査データ
T-P
- 疾患に関する教材を用意する
- 薬剤の一包化やカレンダー等を使用し内服を分かりやすくする
- 家族・本人の希望があれば社会支援の導入や変更を検討するため地域連携室へ手配を依頼する
E-P
- 家族も含め疾患に対する知識の提供
- 飲水制限の必要性
- 体重測定の必要性
- 家族も含め、協力を頼める人に服薬指導(薬剤師)
- 疾患について・内服の重要性を説明
- 社会支援の説明(地域連携室やケアマネ)
看護記録の法的側面と注意点

看護記録は、患者さんのケアを記録するだけでなく、法的な観点からも非常に重要です。
法律関係が苦手という看護師さんも多いのではないでしょうか?
国家試験でも毎年出題されるほど大切な分野なのでしっかりと確認しましょう。
看護記録に関する法律
- 医療法
- 医療法は、医療機関における診療に関する諸記録の作成と管理を規定しています。看護記録もこの「診療に関する諸記録」に含まれ、適切な記録の作成が求められます。
- 保健師助産師看護師法
- この法律は、看護師の業務や資格に関する基本的な規定を定めています。看護記録の作成は、看護師の業務の一環として重要視されています。
- 個人情報保護法
- 看護記録には患者さんの個人情報が含まれるため、個人情報保護法に基づき、情報の適切な管理と保護が求められます。患者さんのプライバシーを守るため、情報の開示や取り扱いには慎重な対応が必要です。
- 健康保険法
- 健康保険法に基づき、保険医療機関は療養の給付に関する記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられています。看護記録もこの一環として管理されます
これらの法律は、看護記録の作成、管理、保存に関する基本的な枠組みを提供し、患者さんのケアの質を保証するために重要です。看護師はこれらの法律を遵守し、適切な記録を行うことが求められます。
看護記録の保存期間と目的
保存期間
- 看護記録は、医療法では2年間の保存が義務付けられています。
- 一部の保険医療機関では、看護記録の保存期間が3年間とされている場合もあります。これは、保険医療機関及び保険医療養担当規則に基づくものです。
保管目的
- 医療の継続性の確保: 看護記録は、患者さんのケアの継続性を確保するために重要です。過去の記録を参照することで、医療従事者は患者さんの状態や治療経過を把握し、適切なケアを提供することができます。
- 法的証拠の提供: 看護記録は、医療ミスの疑いが生じた場合に、医療行為の正当性を証明するための重要な証拠となります。保存期間を設けることで、必要に応じて過去の記録を参照することが可能です。
- 医療の質の向上: 看護記録を保存し、定期的に見直すことで、看護の質を評価し、改善点を特定することができます。これにより、医療サービスの質の向上が図られます。
診療記録の保存期間
- 診療記録(カルテ)は、医師法および関連する規則により、5年間の保存が義務付けられています。これは、診療録が医療の継続性を確保し、法的な証拠としても重要であるためです。
- 診療記録の保存期間は、診療が完結した日から5年間とされており、電子カルテも同様の保存期間が適用されます。ですので、治療が継続して行われている場合は5年が経っても保存が必要となります。
これらの保存期間は、法的な要件を満たすために重要であり、医療機関はこれに従って記録を適切に管理する必要があります。
診療記録との兼ね合いから、看護記録も5年保存している病院は多いです。
看護記録の誤りと影響
看護記録の誤りは、患者さんのケアにおいて重大な影響を及ぼす可能性があります。
看護師自身、また病院にとって悪影響を与える可能性があるので、正しく書きましょう!
看護記録の改善方法とテクニック
この章では具体的な改善方法と簡単に書くためのテクニックを紹介します!
看護記録の改善方法
標準化とテンプレートの活用
- 看護記録の標準化を進めることで、記録の一貫性と効率性を向上させることができます。
テンプレートを使用することで、記録の漏れを防ぎ、時間を節約できますよ。
リアルタイム記録の推進
- 患者さんのケアを行った直後に記録を行うことで、情報の正確性を確保します。
リアルタイムでの記録は、情報を忘れることなく残すことが可能になりますよね!
レバ子ちゃんのように「誰が何言ってたんだっけ?」と言ったこともなくなります♪
看護記録のテクニック
オープンクエスチョンの活用
- 患者さんからの情報を引き出すために、オープンクエスチョンを活用しましょう。
これにより、患者さんの状態やニーズをより深く理解し、記録に反映させることができます。

観察ポイントの明確化
- 記録すべき観察ポイントを明確にすることで、必要な情報を漏れなく記録できます。疾患や症状に応じた観察ポイントを事前に把握しておくことが重要です。
定型文の活用とカスタマイズ(電子カルテ)
- よく使う文章を定型化し、電子カルテの単語登録機能を活用することで、記録のスピードを向上させます。必要に応じて、個別の患者さんに合わせてカスタマイズすることも重要です。
これらの改善方法とテクニックを活用することで、看護記録の質を向上させ、看護師の業務負担を軽減することができます。
看護記録の評価基準
看護記録に正確なマニュアルがあってそれに従って書きましょうという病院は少ないのではないでしょうか?
電子カルテではフォーマット化されているため整っていることもありますが、アナログな病院では書く人の個性が輝いてしまっていますよね。
きちんと看護記録にも評価基準が設けられているのです。
皆さんは、どのくらい正しく書けていますか?
正確性と完全性
- 記録は事実に基づき、正確であることが求められます。
すべての必要な情報が漏れなく記載されていることが重要です。
これには、患者さんの状態、提供されたケア、観察結果などが含まれます。
ですので、看護師あるあるで紹介した事例のように「こんなこと言ってた気がする」と記入するのは絶対に禁止です!
患者さんが発した言葉通りに書きましょう。
一貫性と明確性
- 記録は一貫しており、誰が読んでも理解できるように明確に記述されている必要があります。
専門用語や略語は、標準化されたものを使用し、誤解を避けることが求められます。
法的および倫理的基準の遵守
- 記録は、関連する法律や倫理基準に従って作成される必要があります。
患者さんのプライバシーを保護し、情報の機密性を維持することが重要です。
患者さん中心の視点
- 記録は、患者さんのニーズや視点を反映していることが求められます。
患者さんの意見や希望が適切に記載されていることが、患者さん中心のケアを実現するために重要です。
これらの評価基準を満たすことで、看護記録は質の高いケアの提供を支える重要なツールとなります。
看護師はこれらの基準を意識し、日々の記録業務に取り組むことが求められます。
看護記録の短縮テクニック
個人の対策だけでは短縮の限界があります。
病院をあげての対策にはなりますが、少しでも残業を減らすため取り入れることを検討してみませんか?
用語の標準化
- 看護記録に使用される用語を標準化することで、記録の一貫性を保ち、誤解を防ぐことができます。例えば略字です。院内で統一された略字を使用することによって短縮化が図れます。また院内で標準化された用語を使用することで、異なる医療従事者間での情報共有が円滑になります。
テンプレートの導入
- 記録のテンプレートを使用することで、必要な情報を漏れなく記載することができ、記録の質を向上させます。テンプレートは、特定の疾患やケアプロセスに応じてカスタマイズをして使用します。
クリニカルパスの利用
- クリニカルパスを利用することで、患者さんのケアプロセスを標準化し、記録の一貫性を確保します。
クリニカルパスは、特定の疾患や手術に対する標準的なケアプランを提供し、記録の指針となります。
この場合、観察項目、行った看護等が全てチェックで済むので、時間短縮だけでなく、指示の実施漏れも改善されます。
ただし、イレギュラーな事が起こり、パスの流れから逸脱した場合には、通常の看護記録に移行しましょう。
教育とトレーニング
- 看護師に対する教育とトレーニングを通じて、標準化された記録方法を習得させることが重要です。これにより、記録の質を向上させ、標準化の取り組みを支援します。
これらの方法を通じて、看護記録の標準化が進められ、医療の質と安全性の向上に寄与することができます。
標準化された記録は、医療チーム内での情報共有を円滑にし、患者さんのケアの質を高めるための重要な基盤となります。
看護記録、看護計画の書き方のあんちょこ
A4サイズで印刷してもらうとA6サイズになります。ノートなどに貼って活用してくださいね!
看護記録のトラブルシューティング
では正しい看護記録の書き方をここまで説明してきましたが、正しい看護記録を書かなかった場合どんなことが起こるのでしょうか?
情報の不正確さ
- 患者さんの状態や処置に関する情報が不正確であると、誤った治療やケアが行われる可能性があります。例えば、誤った薬剤情報が記録されると、誤投薬のリスクが高まります。
記録の不完全さ
- 必要な情報が記録されていない場合、医療チーム内での情報共有が不十分となり、患者さんのケアに支障をきたすことがあります。これにより、重要な症状の見逃しや適切な介入の遅れが生じる可能性があります。
タイムリーでない記録
- 記録が遅れて行われると、情報の正確性が損なわれる可能性があります。特に、急変時の対応においては、リアルタイムでの記録が重要です。
記録の誤りの影響
他の患者さんと間違えて事実とは違うことを書いてしまったり、情報の確認不足で正しい内容が記載されていなかったら⁉
患者さんの安全性への影響
- 誤った記録は、患者さんの安全を直接的に脅かす可能性があります。例えば、誤ったアレルギー情報が記録されていると、アレルギー反応を引き起こす薬剤が投与されるリスクがあります。
医療訴訟のリスク増大
- 記録の誤りは、医療訴訟の原因となることがあります。正確で詳細な記録は、医療従事者が適切なケアを提供したことを証明するために重要です。
医療チーム内のコミュニケーションの障害
- 不正確または不完全な記録は、医療チーム内での情報共有を妨げ、チーム全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
看護記録の誤りを防ぐためには、正確でタイムリーな記録を心がけ、定期的な見直しと教育を行うことが重要です!
これにより、患者さんの安全性を確保し、医療の質を向上させることができますよ。
SOAP形式は、医療や看護の現場で情報を整理し、患者さんのケアの質を向上させるための重要なツール!

- 情報収集
- アセスメント
- 看護の実施
- 評価
といたってシンプルです。
アセスメントでつまずく方が多いと思いますが、情報収集をしっかり行えばアセスメントもしやすくなります!
情報取集のコツは
- オープンクエスチョン!
- 観察項目を事前に決めておく!
でしたね!患者さんからの主訴は重要な情報源!検査の数字ももちろん大切ですが、患者さんの言葉をしっかりキャッチしましょう。
観察項目を決めておくのも観察し忘れの防止になります。持続で観察が必要なものに関しては表にし、分かりやすくまとめるのも1つの手です。多くの看護師の目で観察し、気になることがあったら観察項目に入れておくのもいいですね。
もし、気になる求人があれば、「くんくん求人調査」に!
LINEに気になる求人や病院を送ってもらえれば、忙しいあなたに代わって調査します♪