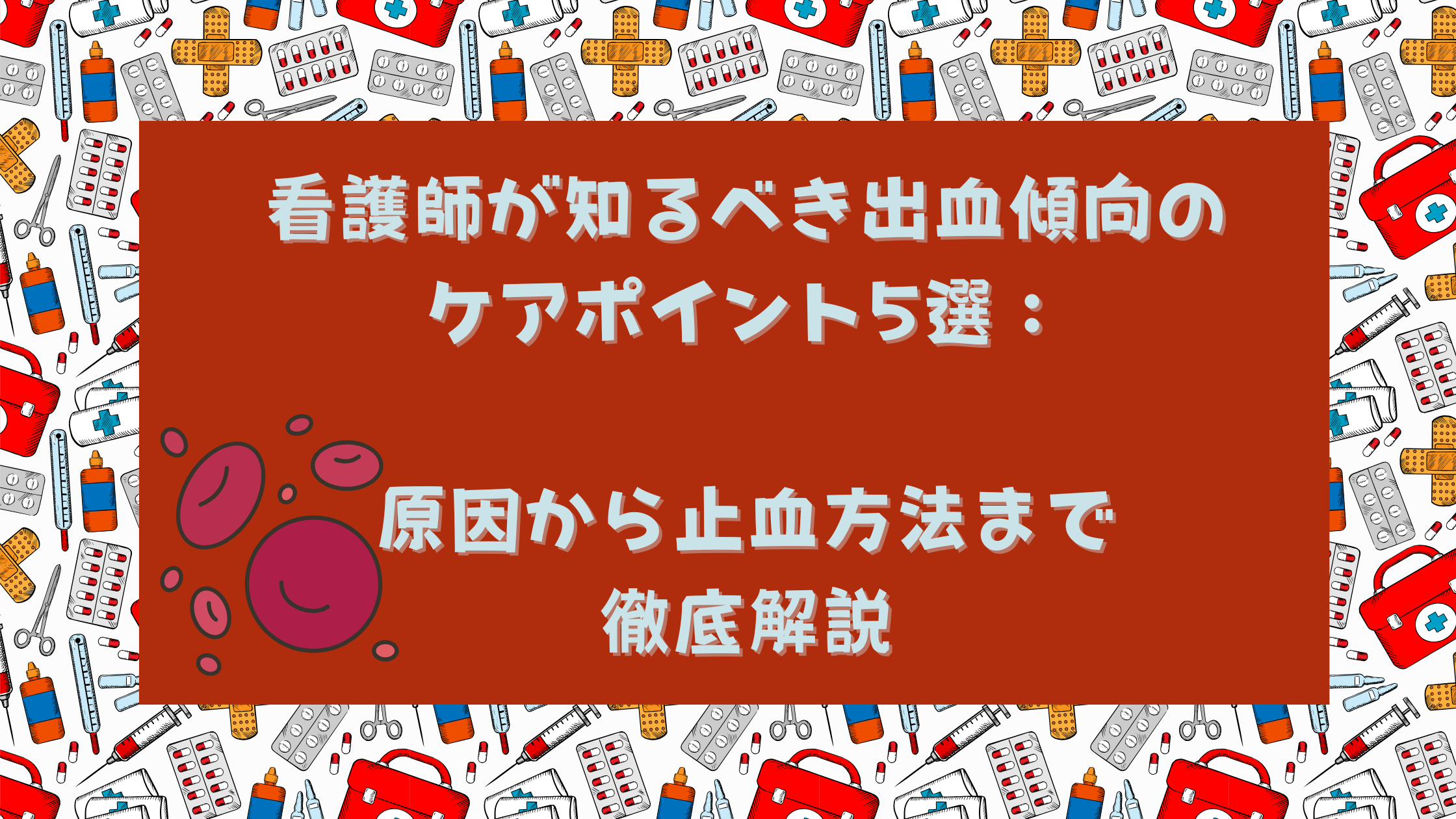
「出血が止まりにくい患者さん、どうケアすればいいの?」🤔 「止血の方法や原因について、もっと詳しく知りたいな!」
そんな疑問、持っていませんか?👋
実は出血傾向のケア、いくつかの大切なポイントがあるんです!✨
- 原因をしっかり特定すること 🔍
- その方に合った止血方法を選ぶこと 🩹
- 不安を和らげる精神的なサポート 💕
- 患者さん自身でできるセルフケアの支援 💪
この記事では、看護師さんが必ず押さえておきたい出血傾向のケアポイントを5つに絞って、原因から止血テクニックまで、わかりやすく解説していきますね!📝
明日からのケアに役立つヒントがきっと見つかりますよ!😊

出血傾向のケアポイント 🩸 看護師さんのための優しいガイド
「出血傾向」って聞くと、ちょっと心配になりますよね💦
出血傾向とは、血液が止まりにくい状態のことを指します。
血管、血小板、凝固因子などの異常が原因で、出血しやすくなったり、止血が困難になることがあるです🩸
出血傾向ってどんな状態なのでしょうか?🩸
「出血傾向」という言葉を聞くと難しく感じるかもしれませんが、簡単に言うと「血が止まりにくい状態」のことです😊
健康な方であれば、ケガをしても血はすぐに固まって止まりますが、出血傾向がある場合は血がなかなか止まらなかったり、ちょっとした刺激でもアザができやすくなったりします💦
出血傾向の原因をチェック!🔍
出血傾向の原因は大きく3つのパターンに分けられます。
原因を理解することで、適切なケアにつなげることができますよ👍
- 血小板の異常 💫
- 血小板は血管が傷ついたときに集まって血を止める大切な役割があります
- 血小板数が10万/μL以下になると止血に時間がかかります⏱️
- 5万/μL以下だと、ちょっとした刺激でも出血しやすくなるので要注意です⚠️
- 白血病などの血液疾患や抗がん剤の影響などが原因として考えられます
- 凝固因子の異常 🧬
- 凝固因子は血液を固めるために必要なタンパク質です
- 血友病(第VIII因子や第IX因子の欠乏)などの先天的な病気や肝疾患が原因になります
- ワルファリンなどの抗凝固薬を服用している方も注意が必要です💊
- ワルファリンを服用されている患者さんには、納豆などビタミンKを多く含む食品は控えるようご指導ください🙅♀️
- 血管の異常 🚿
- 血管の壁が弱くなったり、もろくなったりすると出血しやすくなります
- 老人性紫斑(加齢による血管の脆弱化)やビタミンC不足による壊血病などが考えられます
出血傾向の症状にはどんなものがありますか?😥
出血傾向の症状は様々ですが、主な観察ポイントをご紹介します👀
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 青あざができやすい | ちょっとぶつけただけでも、すぐに青あざができてしまいます |
| 鼻血、歯茎からの出血 | 鼻血がよく出る、歯磨きすると歯茎から血が出ます |
| 皮下出血(紫斑) | 皮膚の下に、赤い点々や紫色の斑点ができます |
| 下血、吐血 | 便に血が混じる、血を吐きます |
| 黒色便(タール便) | 黒くてネバネバした便が出ます |
| 血尿 | 尿に血が混じります |
| 関節内出血 | 関節の中に血が溜まって、腫れたり痛んだりします |
| 過多月経 | 生理の出血量が多い、生理が長引きます |
| 手術後の出血 | 手術や抜歯をした後、なかなか血が止まりません |
出血傾向、どうやって診断するの?🏥
出血傾向が疑われる場合は、問診で詳しく症状や病歴、家族歴をお聞きします👂
特に過去の出血経験や服用中のお薬について確認することが大切です!
- 血液検査(血小板数、PT、APTTなど)で血小板の数や凝固因子の働きを調べます📋
- 必要に応じて、CT検査や内視鏡検査、骨髄穿刺なども行われます
出血傾向の治療法について💉
治療法は原因によって異なります。例えば:
- 血小板減少の場合: 血小板輸血や免疫グロブリン製剤の投与など
- 凝固因子欠乏の場合: 凝固因子製剤の投与など
- ワルファリン服用中の場合: ビタミンKの投与(ただし、効果を弱める可能性があるのでご注意を)
がん薬物療法による血小板減少の場合は、セルフモニタリングとセルフケアのご指導も重要です🌟
看護師としてできること、知っておきたいこと📝
出血傾向のある患者さんに対して、看護師として何ができるのか、ポイントをまとめました:
- 患者さんの出血傾向の有無をしっかり把握しましょう!問診時に既往歴や内服薬を確認します
- 出血しやすい部位(鼻、歯茎、皮膚など)の観察をしっかり行いましょう👀
- 抗凝固薬を服用されている患者さんには、薬の効果や副作用、食事の注意点をご説明しましょう📝
- 出血が見られた場合は、止血処置を行うとともに、速やかに医師に報告しましょう🏥
- 患者さんやご家族の不安を軽減できるよう、心のケアも大切にしましょう❤️
- 口腔ケアでは柔らかい歯ブラシや、スポンジブラシの使用をお勧めします🪥
出血傾向がある患者さんのセルフモニタリングのポイント💡
患者さんが自宅で血の状態を自分でチェックできるよう、以下のポイントをお伝えください:
| 観察項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 皮膚の状態 | 新しい青あざや紫斑がないか確認する |
| 鼻血 | 鼻血が出やすい時間帯やきっかけを記録する |
| 歯茎からの出血 | 歯磨きの際の出血状況を記録する |
| 便の状態 | 血が混じっていないか、黒色便が出ていないか確認する |
| 尿の状態 | 血が混じっていないか確認する |
| 月経の状態 | 月経量が多くないか、期間が長引いていないか確認する |
| その他の出血 | 手術や抜歯後の止血状況、原因不明の出血を記録する |
| 全身の状態 | 倦怠感や息切れ、めまいなどの貧血症状がないか確認する |
| 服用薬 | 薬の名前と血の状態を一緒に記録する |
これらの情報を記録することで、医師や看護師に状態を伝えやすくなりますよ😊
日常生活での注意点 🏠
出血傾向がある患者さんがより安全に過ごすための注意点です:
- 怪我の予防: お家の中の整理整頓や滑り止めマットの使用をお勧めください
- 出血しやすい行動を避ける: 鼻を強くかんだり、硬い歯ブラシでゴシゴシ磨いたりしないようご指導ください
- 内服薬の管理: 抗凝固薬は指示通りに服用し、自己判断で中断しないようご説明ください
- 歯科受診: 歯科治療が必要な場合は、事前に主治医に相談するようお伝えください
- 緊急時の対応: 大量出血や止血困難な場合は、すぐに医療機関を受診するようご指導ください
これらの注意点をお守りいただくことで、出血のリスクを最小限に抑え、安心して日常生活を送っていただけますよ🌈
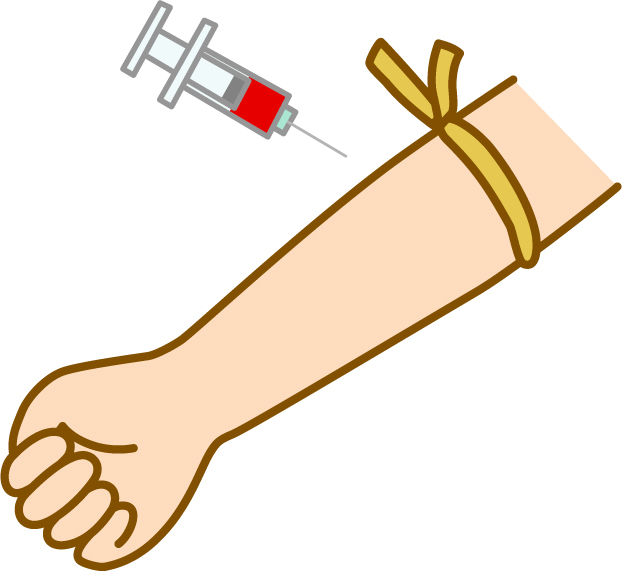
看護師が知るべき診断方法🩺
患者さんの状態を正確に把握するためには、適切な診断方法を知ることが重要です。
ここでは、看護師が知っておくべき診断方法を解説します♡
出血傾向の診断方法🔍
出血傾向が疑われる場合、以下の検査を組み合わせて原因を特定します。
| 検査項目 | 目的 | 基準値 |
|---|---|---|
| 血小板数(PLT) | 血小板の数を調べ、一次止血の異常を確認。 | 18万~35万/μl |
| 出血時間 | 血小板機能や血管の状態を評価。 | 1~5分 |
| プロトロンビン時間(PT) | 外因性凝固経路の異常を確認。 | 80~130% |
| 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) | 内因性凝固経路の異常を確認。 | 28~38秒 |
| フィブリノーゲン(Fib) | 血液凝固に必要なタンパク質の量を調べる。 | 190~330mg/dl |
| フィブリン分解産物(FDP) | 血栓の有無を確認。 | 5.00μg/ml以下 |
| 毛細血管抵抗試験 | 毛細血管の脆弱性を調べる。 | – |
これらの検査結果を総合的に判断し、出血傾向の原因を特定します。
出血傾向の観察ポイント📝
出血傾向のある患者さんを観察する際は、以下のポイントに注意しましょう。
| 出血部位 | 主な症状 |
|---|---|
| 皮膚 | 点状出血、紫斑。ぶつけてもないのにアザができやすい。 |
| 鼻 | 鼻血が頻繁に出る。 |
| 口腔粘膜・歯肉 | 歯磨きで出血しやすい。 |
| 消化管 | 血便、吐血。 |
| 尿路 | 血尿。 |
| 眼底 | 眼底出血。 |
| 筋肉内 | 大腿部などに好発。CT検査が有用。 |
| 関節内 | 関節内出血。 |
これらの症状を見逃さないよう、日々の観察を徹底しましょう。
看護師としての対応🌸
出血傾向のある患者さんへのケアでは、以下の点を意識してください。
- 転倒予防:滑りにくい靴や手すりの設置など、環境を整える。
- 口腔ケア:柔らかい歯ブラシを使用し、歯肉を傷つけないようにする。
- 栄養指導:ビタミンKを含む食品を積極的に摂取するよう促す。
- 精神的ケア:出血に対する不安を和らげる声かけを行う。
患者さんが安心して治療を受けられるよう、細やかな配慮を心がけましょう♡
出血傾向の治療と看護のポイント 💕 患者さんに寄り添うケアガイド

治療のポイント 💊
原因に応じた治療
出血傾向の治療は、まずは原因を特定することが第一歩です!それぞれの原因に合わせたアプローチが大切ですよ 💯
- お薬による治療 💊
- 止血剤や凝固因子製剤:出血を止めるお薬を使います
- デスモプレシン(DDAVP):軽い血友病の方の出血に効果があります
- アミノカプロン酸やトラネキサム酸:血の固まりが溶けるのを防ぎます
- 凝固因子製剤:足りない凝固因子を補充します
- バイパス製剤:特殊な血友病の方に使用します
- ホルモン療法:女性の過多月経を軽減するのに役立ちます
- 血小板輸血 🩸 血小板数が少なくなった場合に行います
- 遺伝子治療 🧬 血友病などの遺伝性疾患に対する新しい治療法です
緊急時の対応
たくさん出血してショック状態になっている場合は、素早い対応が命を救います!
- 輸液・輸血 💧 血液量を回復させるために大切です
- 止血処置 🩹 出血している部分を押さえて、必要なら手術で止血します
手術が必要な場合
止血のために手術が必要と判断されたら、迅速に準備をしましょう。
患者さんやご家族への丁寧な説明も忘れずに 🙏
看護のポイント 🩺
アセスメントと観察
患者さんの状態をしっかり把握するために、以下の点に注目しましょう!
- 出血部位の確認 👀
- お肌や粘膜の出血はありますか?
- トイレの後、紙に血がついていませんか?
- お口の中に小さな出血点はありませんか?
- バイタルサインの測定 📊
- 血圧が下がっていませんか?
- 脈が早くなっていませんか?
- 検査データの確認 📋
- 血小板数は正常ですか?
- 凝固時間(PT、APTT)はどうでしょうか?
患者さんへの問診のポイント
優しく聞いてみましょう:
- 「歯磨きのとき、血が出ることはありますか?」
- 「お尻を拭いた紙に血がついていますか?」
患者教育
患者さんが安心して生活できるように、以下のことをお伝えしましょう ✨
- セルフケアの指導 🪥
- 柔らかい歯ブラシを使いましょう
- 転ばないように気をつけましょう
- 出血時の対応方法 🆘
- 出血したら、その部分をしっかり押さえましょう
- 止血できない場合は、すぐに病院に連絡しましょう
- 日常生活の注意 🏠
- 歩きやすい靴を履きましょう
- 体を締め付ける服は避けましょう
- 便秘にならないよう気をつけましょう
- 市販薬について ⚠️
- アスピリンやイブプロフェンなどのお薬は胃からの出血を引き起こすことがあるので注意しましょう
精神的サポート
出血があると不安になるものです。患者さんやご家族の気持ちに寄り添い、安心感を与えましょう 💞
出血部位別の看護ポイント 📝
| 出血部位 | 看護のポイント |
|---|---|
| 鼻出血 | 鼻をつまんで止血、冷やすとよいですよ。頻繁に起こる場合は医師に相談を 👃 |
| 口腔内出血 | 柔らかい歯ブラシを使用し、出血部位に触れないように。血小板が少ない場合は歯磨きを控えめに 🦷 |
| 術後出血 | ドレーンから出る液の色や量をこまめにチェック。異常があれば医師に報告を 🏥 |
| 深部出血 | 関節や筋肉の痛みや腫れに注意。必要に応じて画像検査を 🔍 |
緊急時の輸血 🚑
緊急時には輸血が必要になることも。安全のために以下の点に注意しましょう:
- 血液バッグの取り違えに注意
- 患者さんの確認を必ず行う
- 口頭指示は必ずメモをとり、復唱して確認
看護計画の例 📝
| 観察計画(OP) | ケア計画(TP) | 教育計画(EP) |
|---|---|---|
| 出血傾向の原因疾患についての知識、認識 | 食事内容を振り返ってもらい、出血傾向を改善する食事を一緒に考える | 原疾患と出血傾向の関係を説明する |
| 治療や服薬に関する認識、考え | 患者さんの自己管理能力を判断し、必要なら家族の協力を求める | お薬の作用と副作用を説明し、自分で管理できるよう支援する |
| 入院前の食事内容 | – | 食事療法の必要性を説明し、おすすめの食品を紹介する |
| キーパーソン、協力者 | – | 定期受診の必要性を説明する |
| 出血を誘発する因子、リスクの程度 | 皮膚や粘膜の乾燥を防ぐケア | – |
| バイタルサイン、意識レベルの変化 | – | – |
| 血液検査データ(血小板、PT、APTTなど) | – | – |
終末期の出血傾向について 🌷
終末期には、臓器の機能が低下して出血しやすくなることがあります。
患者さんの苦痛を和らげるケアが最も大切です。優しさと思いやりをもって接しましょう。
患者さんの不安を軽減し、安心して治療を受けられるように、私たち看護師は常に寄り添うことが大切ですね。
出血傾向があっても、安心して日常生活を送れるよう、知識と温かい心でサポートしていきましょう!
出血傾向のある患者さんへの予防ケア 💕 看護師さんのための実践ガイド
転倒予防、お肌への配慮、お口のケア、食事の工夫、リスク管理という5つの視点から、具体的なケア方法をお伝えします。
患者さんをより安全に、そして安心してケアしていきましょう!😊
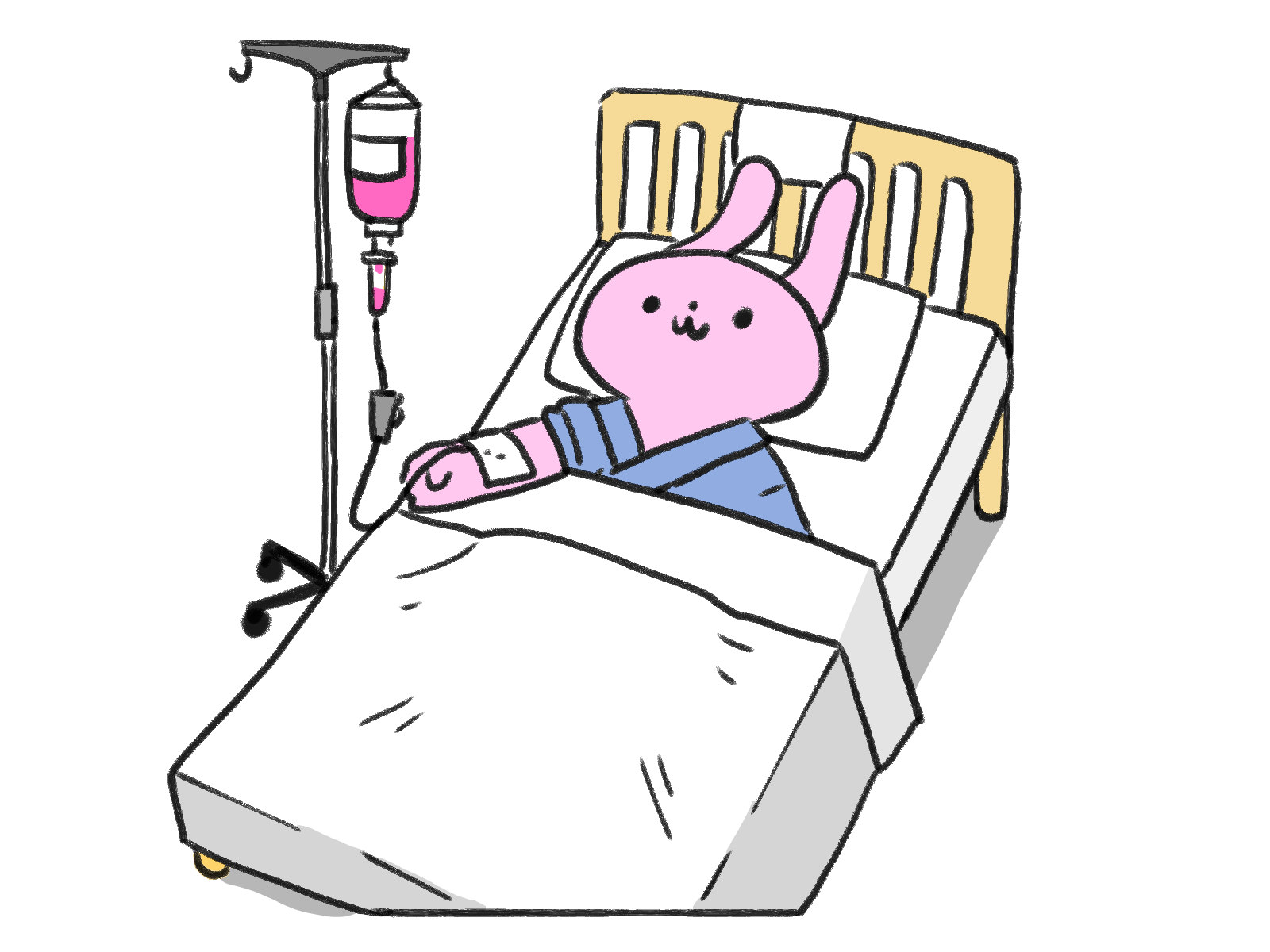
転倒予防で安心・安全を確保!🚼
転倒は出血を引き起こす大きな原因のひとつです。
患者さんが転ばないように、私たち看護師ができることを見ていきましょう!
- 環境整備: ベッド周りには余計な物を置かないように整理整頓を心がけましょう。夜間は足元灯をつけたり、必要に応じて付き添ったりすることも大切です💡
- 履き物: 滑りやすいスリッパは避けて、底がしっかりした脱げにくいものを選びましょう。患者さん自身が履きやすいものを選ぶのもポイントです👟
- 動作: ベッドから起き上がる時や歩く時は、ゆっくりと動作するように声かけしましょう。急な動作はふらつきやすく、転倒の原因になります🚶♀️
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 環境整備 | ベッド周りの整理整頓、夜間の照明、付き添い |
| 履き物 | 滑りにくい、脱げにくい履物 |
| 動作 | ゆっくりとした動作の推奨 |
デリケートなお肌を優しく守ろう ✨
出血傾向のある患者さんのお肌はとてもデリケートです。
外部からの刺激を最小限にして、優しくケアすることが大切ですよ。
- 衣類: 体を締め付けるような衣類は避けて、ゆったりとした肌触りの良い素材を選びましょう。下着のゴムなどにも注意してあげてくださいね👕
- 爪: 患者さんの爪は短く切って、角を丸く整えましょう。患者さん自身が体を掻いて皮膚を傷つけないように、定期的なチェックを忘れずに😊
- 入浴・清拭: 入浴や清拭の際は、ゴシゴシ擦らず、泡立てた石鹸で優しく洗い、タオルで柔らかく押さえるように拭きましょう。乾燥を防ぐために、保湿剤の使用も検討してくださいね🛀
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 衣類 | ゆったりとした、肌触りの良い素材を選ぶ |
| 爪 | 短く切って、角を丸く整える |
| 入浴・清拭 | 擦らず優しく、保湿剤を使用する |
お口の中から出血を防ぐ!ソフトな口腔ケア 🦷
口腔ケアは、感染予防や患者さんが快適に過ごすためにとても重要です。
出血傾向のある患者さんには、特別な配慮が必要なんですよ。
- 歯ブラシ: 毛先の柔らかい歯ブラシやスポンジブラシを使って、優しく丁寧に磨きましょう。力を入れすぎないのがコツです!🪥
- ブラッシング: 出血している部分には触れないように注意しましょう。もし出血してしまったら、すぐに歯科医に相談してくださいね。
- うがい: 刺激の少ない液体歯磨き剤でうがいをしましょう。アルコールが含まれているものは避けた方が良いですよ🚿
- 血液データ: 血小板数が20,000/μL以下の場合は、歯磨きを中止して、お口の中を湿らせたガーゼで優しく拭う程度にしましょう。必ず医師に相談して、指示を仰いでくださいね📝
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 歯ブラシ | 毛先の柔らかいもの、スポンジブラシ |
| ブラッシング | 出血部位を避け、優しく丁寧に |
| うがい | 刺激の少ない液体歯磨き剤 |
| 血液データ | 血小板数20,000/μL以下で歯磨き中止、医師に相談 |
食生活を見直して、体の中からケア 🍴
便秘は、排便時に力むことで内出血を引き起こす可能性があります。
日々の食生活に気を配って、便秘を予防しましょう!
- 食物繊維:
野菜や果物、海藻類など、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取しましょう。
食物繊維は便秘解消に効果的ですが、食べ過ぎるとお腹が張ってしまうこともあるので、患者さんの状態に合わせて量を調節してくださいね🥗 - 消化の良い食事:
消化の良い食事を心がけ、胃腸に負担をかけないようにしましょう。
患者さんに合わせて、柔らかく煮込んだり、細かく刻んだりするなどの工夫も必要です🍲 - 下剤:
必要に応じて下剤を使用しますが、浣腸はできる限り避けましょう。
浣腸は患者さんに負担がかかるだけでなく、肛門からの出血を招く可能性もあるのです💊
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 食物繊維 | 野菜、果物、海藻類 |
| 消化の良い食事 | 柔らかく煮込む、細かく刻む |
| 下剤 | 必要に応じて使用、浣腸は避ける |
リスク管理で危険を未然に防ごう 📝
患者さんの状態を把握し、出血リスクを評価することは、看護師さんのとても重要な役割のひとつです。
- 内服薬: 抗血栓薬(ワーファリンなど)を服用している場合は、特に注意深く観察する必要があります。手術や抜歯の際には、必ず医師に相談するように伝えましょう💊
- 検査データ: 血小板数、PT、APTT、フィブリノゲンなどの凝固データを確認し、異常があればすぐに医師に報告しましょう📊
- 既往歴: 過去の病歴やアレルギー歴なども確認し、出血リスクにつながる情報がないか注意深く聞き取りましょう📋
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 内服薬 | 抗血栓薬の確認、手術や抜歯時の医師への相談 |
| 検査データ | 血小板数、PT、APTT、フィブリノゲンなどの凝固データ確認 |
| 既往歴 | 過去の病歴、アレルギー歴などの確認 |
これらの予防策を実践することで、出血傾向のある患者さんも安全に、そして安心して過ごせるはずです。
患者さんの状態をよく観察し、適切な看護を提供していきましょうね!💕
お一人おひとりの患者さんに寄り添った、心のこもったケアが何よりの予防策です。
みなさんの温かい看護で、患者さんの安心した笑顔を増やしていきましょう!😊
出血傾向の患者への対応方法🚑
出血傾向の患者さんへの対応は、予防と早期発見、セルフケアの指導、出血時の対処、そして日常生活での注意点が重要です。
以下に具体的な方法を解説します♡

出血予防のポイント✨
出血を防ぐためには、日常生活での工夫が欠かせません。
| 項目 | 方法 |
|---|---|
| 転倒予防 | ベッド周りに物を置かない、滑りにくい靴を履く、夜間は照明を使用する |
| 衣類の選択 | 体を締め付けない服や下着を選ぶ |
| 歯磨き | 柔らかい歯ブラシを使用し、歯肉を傷つけないようにする |
| 排便 | 食物繊維を摂取し便秘を防ぐ。必要に応じて下剤を使用するが浣腸は避ける |
| 運動 | 血小板減少時は激しい運動を避け、安静を心がける |
出血時の対処法🚨
出血が起きた場合は迅速な対応が必要です。
- 出血部位の特定:出血箇所を確認し、適切な止血を行います。
- 圧迫止血:太い血管からの出血の場合は、心臓に近い側を圧迫。ただし、長時間の圧迫は避ける。
- 精神的ケア:患者さんの不安や恐怖を和らげる声かけを行う。
日常生活での注意点🛡️
患者さん自身が出血を防ぐ行動を取れるように支援します。
- 転倒防止:段差をなくし、歩きやすい環境を整える。
- 切り傷防止:電気カミソリを使用し、皮膚を強くこすらない。
- 観察:皮膚や口腔内、便や尿の状態をチェックし、異常があれば医療者に報告。
口腔ケアの注意点🦷
出血傾向がある患者さんの口腔ケアでは、以下を心がけましょう。
- 毛先の柔らかい歯ブラシやスポンジブラシを使用。
- 出血部位には触れない。
- 血小板が著しく減少している場合は歯磨きを中止し、医師と相談。
患者さんが安心して生活できるよう、セルフケアの指導や精神的なサポートを行いましょう。
また、出血傾向の原因疾患に応じた治療や薬物療法の管理も重要です。
薬物療法:出血を止める薬と予防する薬 🩸💊
患者さんにも分かりやすく説明できるように、ぜひ参考にしてくださいね!

線溶阻害薬 🛑
線溶阻害薬は、血液を溶かす働きを抑えて、出血を止めるお薬です。手術後や異常出血の際によく使われます。
- 作用: α2-アンチプラスミンがプラスミンの働きを抑え、フィブリンの分解を防ぐことで止血を促します。線溶亢進に伴う出血傾向に適していますが、線溶抑制型のDICには禁忌ですのでご注意ください ⚠️
- 投与量: 通常、成人は1日に750〜2,000mgを3〜4回に分けて服用します。年齢や症状により投与量が調整されますので、医師の指示に従いましょう。
- 副作用: 血栓症、吐き気、下痢、頭痛などが報告されています 😣
- 看護のポイント: 深部静脈血栓症を合併している場合や線溶抑制型のDICの場合は、臓器障害を悪化させる可能性があるため禁忌となっています。十分にご注意ください!
- 患者さんへの説明例: 「このお薬は、血液を固める働きを助けて出血を止めるお薬になります。もし、足が腫れたり胸が痛くなったりした場合は、すぐにお知らせくださいね。」 🙇♀️
デスモプレシン 💧
デスモプレシンは、特定の出血性疾患に使われるお薬で、血液を固まりやすくする作用があります。
- 作用: 血管内皮細胞からvon Willebrand因子を放出させ、止血を促進します。von Willebrand病、軽度~中等度の血友病A、血小板機能異常などの出血を治療・予防するために使われることがあります 🩹
- 投与方法: 点鼻スプレーや内服薬があり、通常は就寝前に使用します。投与前に鼻をかむなどして、鼻腔内をきれいにしておくと、薬の吸収が安定しますよ!
- 投与量: 通常、1日1回就寝前にデスモプレシン酢酸塩水和物として10μg(1噴霧)から鼻腔内に投与を開始し、効果不十分な場合は、1日1回就寝前に20μg(2噴霧)に増量します。1日最高用量は20μg(2噴霧)までです 🌙
- 過剰投与のリスク: 過剰投与すると、水分貯留や低ナトリウム血症のリスクが高まりますのでご注意ください。頭痛、吐き気、痙攣などが起こる可能性があります。
- 副作用: 主な副作用としては、頭痛や顔の赤み、ほてりなどが報告されています。重篤な副作用としては、脳浮腫や昏睡、痙攣などを伴う重篤な水中毒があるため、注意深く観察することが大切です。その他、鼻炎や発汗、鼻出血、発熱なども報告されています 🌡️
- 投与時の注意: 投与後は、水中毒の症状(倦怠感、頭痛、吐き気など)に注意し、症状が出たらすぐに医師に連絡しましょう。血圧低下は、デスモプレシンの副作用というより、中枢性尿崩症による脱水が原因の可能性があります。デスモプレシンを投与する際は、過度の飲水を避けるよう指導することも大切です。特に、夕食後から翌朝までは極力飲水を控えるようお伝えください。発熱や喘息などで飲水量が増加する場合には、特に注意が必要です ⚠️
- 患者さんへの説明例: 「このお薬は、出血を止める働きを助ける薬です。夜中にのどが渇いても水を飲みすぎないようにしてくださいね。もし、頭痛や吐き気がしたら、すぐにお知らせください。」 💦
血液凝固因子製剤 💉
血液凝固因子製剤は、不足している凝固因子を補うために使用されるお薬です。
- 種類: 血漿由来製剤と遺伝子組換え型製剤の2種類があります。血漿由来製剤は、献血で得られた血漿から作られており、VWFを含むものと含まないものがあります。遺伝子組換え型は、ヒト血漿を材料とせずに作られています 🧬
- 投与方法: 出血時補充療法、定期補充療法、予備的補充療法などがあります。血漿製剤は、凝固因子の欠乏による病態の改善を目的に投与します。特に、凝固因子を補充することにより、止血の促進効果が期待できます。
- 投与量: 必要投与量(単位)=体重(kg)×目標ピークレベル(%)×0.5で計算されます 📊
- 副作用: アレルギー反応や血栓症のリスクがありますので注意が必要です。
- FFP(新鮮凍結血漿): 凝固因子を補充するために使われる血漿製剤です。使用時は37℃の湯で融解します 🧊➡️💧
- 血漿分画製剤のリスク: 血漿分画製剤は、ウイルス等の除去・不活化処理が行われていますが、完全に除去できるわけではありませんので、リスクがあることも知っておきましょう。
- 血液凝固の仕組み: 血液中の凝固因子が次々と活性化されて、最終的にフィブリンという網の膜ができて、血小板血栓を覆って止血が完了します 🩸
- 患者さんへの説明例: 「このお薬は、血を固める成分を補う薬です。注射後はアレルギー反応が出ることがありますので、しばらく様子を見せてくださいね。」 👀
ワルファリンとビタミンK 🥬⚠️
ワルファリンは、血液を固まりにくくするお薬ですが、ビタミンKを多く含む食品と相互作用があります。
- 注意点: 納豆、クロレラ、青汁など、ビタミンKをたくさん含む食品は避けるよう指導しましょう。これらの食品は、お薬の効果を弱めてしまう可能性があります。緑黄色野菜は、小鉢程度なら大丈夫なようです 🍃
- 相互作用: ワルファリンは、納豆、クロレラ、青汁、抹茶、緑黄色野菜など、ビタミンKを多く含む食品と一緒に摂取すると、効果が弱まってしまいます。これらの食品は避けるよう指導されています。緑茶は通常量なら問題ないようです。グレープフルーツジュースは、降圧薬との相互作用が知られています 🍊
- 看護のポイント: ワルファリンを服用している患者さんが、ビタミンKを多く含む食品を摂取しなくなった場合は、医師に報告することが大切です。PT-INR値をチェックして、出血傾向がないか確認することも重要です 📝
- 患者さんへの説明例: 「ワルファリンを飲んでいる間は、納豆や青汁などは控えてくださいね。これらの食品はお薬の効果を弱める可能性があります。」 🙅♀️
お薬手帳の重要性 📘
お薬手帳は、服用している薬を正確に伝えるために、いつも持ち歩くようにしましょう。緊急時や複数の医療機関を受診する際に役立ちますので、とても大切です!
その他 ✨
- 個人用医薬品記録(PMR): 処方薬、市販薬、サプリメントなど、すべての薬を記録しておくことはとても重要です。慢性疾患をお持ちの方、高齢者の方、複数の医療機関を受診される方、手術や入院を控えている方、旅行者の方など、様々な方にとって役立ちます。薬剤師さんにご相談いただき、PMRを活用しましょう! 📝
患者さんへの説明は、親しみやすい言葉で伝えることがポイントです!
専門用語は避けて、分かりやすく丁寧に説明してあげましょう 😊
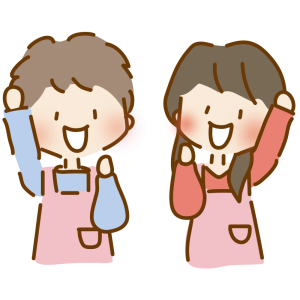
出血傾向ケア、今日からあなたも名人に!
今回の記事では、看護師の皆さんが知っておくべき出血傾向のケアポイントを5つに絞って、原因から止血方法まで徹底解説しました。これで、あなたも出血傾向の患者さんのケアに自信が持てるはず!
でも、これで終わりじゃないんです!医療の世界は常に進化しています。今日学んだ知識を土台に、明日からのケアでさらにスキルアップを目指しましょう!
もっと学びたいあなたへ!
- 最新のガイドラインや研究論文をチェック!
- 先輩看護師や専門家との情報交換で視野を広げよう!
- 院内研修やセミナーに積極的に参加してスキルアップ!
常に学び続ける姿勢こそが、患者さんにとって最高のケアにつながります。これからも一緒に頑張りましょう!





