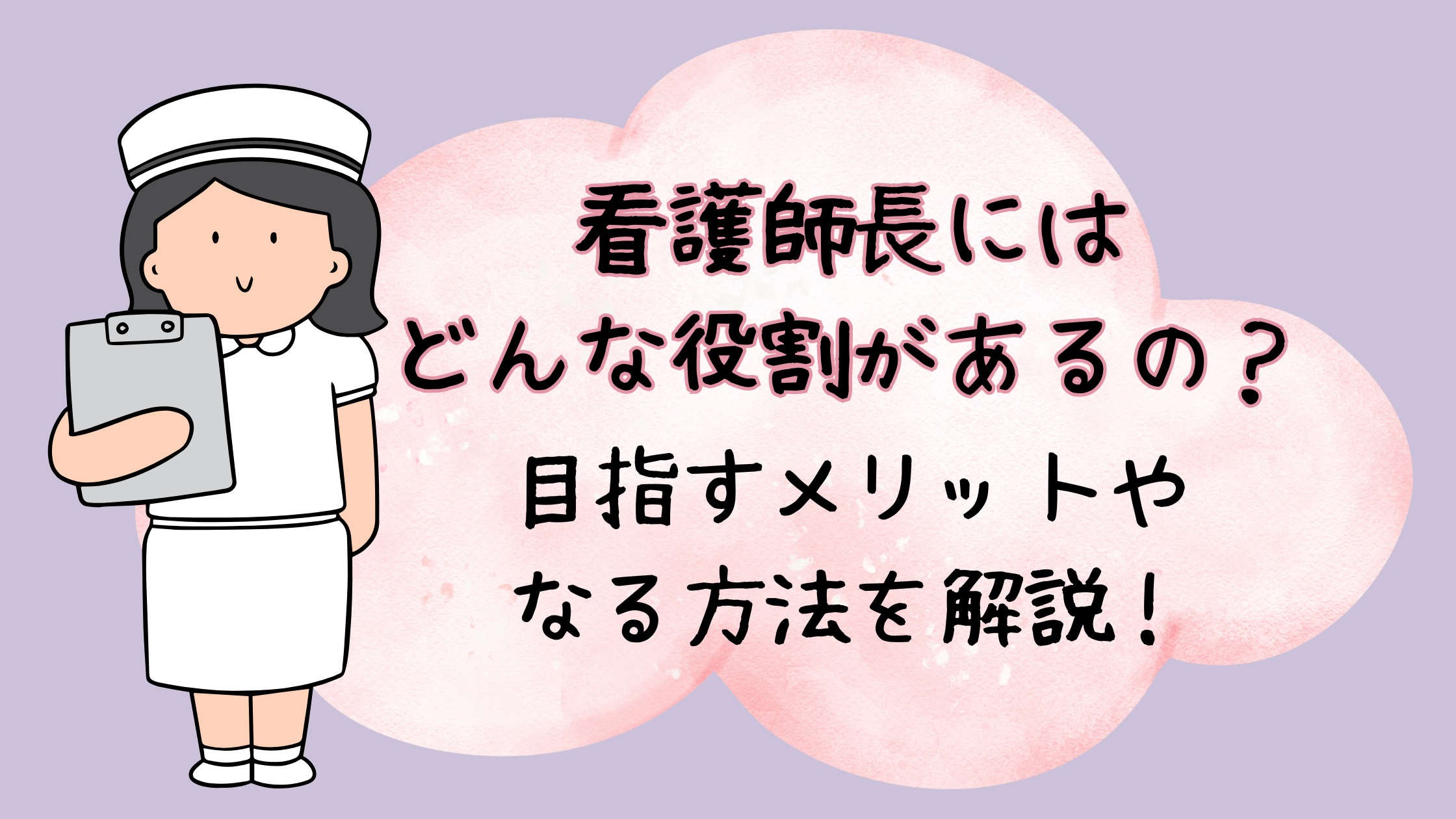
看護師長とは看護部門を統括する管理職で、病棟や外来などで看護主任と看護部長の中間に位置するポジションです。
通常の看護業務に加え、看護師の配置やシフトの管理、教育・指導、業務調整、患者さんやその家族への対応に至るまで、自己判断を行いながら幅広く業務を担当します。
「いつかは目指したいと思っているけれど、実際はどんな仕事をしているのだろう」
「私にもなれるのかな」
その思いのヒントを探してみてくださいね。
この記事では、
・そもそも看護師長とはどんな役割を持つか
・求められるスキルや能力
・看護師長のメリット
などをポイントを踏まえて解説していきます。
ブックマークもお忘れなく!
看護師長の役割
看護師長は、看護部門全体をまとめ、医師をはじめとする他の部署と連携してチーム医療を円滑に進めていくに欠かせない役割を持ちます。
他にも、
患者さんの状況把握を行い、治療に対する意見を経営陣や医師に伝える
部署内の目標を決め、達成に向けてスタッフの支援
医療事故などを未然に防ぐ予防や対策
経営陣との橋渡し役
などがあります。
看護師長は、所属する部署のトップに立つ存在になるため、より責任や判断力が求められる業務を担います。
一つずつ詳細に解説していきます。
患者の状況把握
患者の状況を把握することで、その場や問題などにおいて適切な対応をするために、次のような役割を担っています。
患者ラウンドで、患者さんに対して適切な医療や看護が提供されているかを把握し、体調の急変などに備えます。
空きベッドや入院状況も把握して、緊急入院や緊急事態に備えることも重要な役割です。
また、現場の看護師だけでは回らない状況になった場合には、一時的なフォローにも入ります。
他にも、患者さんと家族間でのトラブルがあれば、間に入って仲裁することもあります。
部全体の問題や課題を把握する
部署の問題点として、
・看護師のスキル不足によって、入院患者の生活機能が低下してしまう
・退院支援がうまく進まず、病床利用率や高い状態が続いてしまい、緊急用の病床を確保することが難しい
・寝たきりの患者さんの増加
・看護師の人手不足や慢性的な時間外労働
・夜勤やシフト勤務による看護師の生活リズムの崩れ
などが挙げられます。
これらを解決、防ぐことができるよう課題を把握しておくことが大切です。
教育・指導(人材育成)
病院内の看護部門や病棟、看護の現場のマネジメントも大切な役割のひとつ。
現場スタッフの支援や育成、組織体制の管理といった業務に加え、地域社会との連携、看護研究の支援・推進に至るまで担うこともあります。
スタッフの育成やマネジメントとして、
それぞれの職務役割を明確にした上で、役割に応じた看護管理実践を支援することや、実践能力を身につけるための教育プログラムを作成も行います。
その中で、マネジメントラダーの作成と昇格への流れを知ってもらうよう話をします。
また、アドバイザーとして、看護主任を対象とした研修に参加することもあります。
次世代の人材育成をしていくにあたって自身も部下の力を引き出すスキルを身につける研修に参加するなども必要に応じて行う必要があります。
部下の力を引き出すスキルを身につけることは、ピンチも乗り越えられるチーム作りに役立ちます。
医師や患者の架け橋になる
そもそも看護師として、患者さんに最も近い立場で治療や医療行為に携わり、患者や家族の思いや不安を理解するため不安や悩みに寄り添い、医療スタッフに伝えて連携を図ることが求められます。治療計画を策定することもあります。
その中でも、師長がチームの架け橋として果たす役割には、患者さんやその家族、チーム内の医師やスタッフとの橋渡し役として、チーム内の医療スタッフに情報提供することが求められます。
また、患者さんのケアの道筋に創意工夫を重ねるべく、日頃から注意深く観察し、示すサインを逃さないようにします。患者さんの家族に対してもケアが必要なことがあるので、周囲の環境も気にしておきましょう。
特定の患者に関わる時間が限られている医師などに代わり、患者さんの様子や思いなどを医療スタッフに伝えることで、より良いチーム医療の提供に貢献することができます。
橋渡し役として意識したいのは、情報の適切な収集や意見の理解と尊重、情報共有ができるコミュニケーションを取ることです。
果たすには、次のようなスキルや能力が求められます。
適切な情報収集やアセスメントを行うスキル
他職種の意見や考えを理解して尊重する能力
適切な情報共有が行えるようなコミュニケーション能力
また、看護師は医療の中心である患者さんの代弁者となり、医療スタッフをまとめるキーパーソンの役割も担ってい
求められるスキル
看護師長は、部署やチームの運営をスムーズに行うために、スタッフの教育やリスク管理、他部署との交渉などを担います。
そのため、さまざまな人たちと関わりを持つためのコミュニケーションスキルが欠かせません。
他にも、スタッフを引っ張る力や看護師の悩みや不安に寄り添い、解消し、同じ目標に向かって仕事ができる環境を整備する能力も必要になってきます。
コミュニケーション能力
部署の代表として他部署と連携や交渉を行う機会が多く、さまざまな立場の人たちと関わるため高いコミュニケーション能力が求められます。
看護師長に求められるコミュニケーション能力には、以下のようなものがあります。
・上層部からの意見を部署の看護師たちに分かりやすく伝える
・部署やチーム内での良好な人間関係の構築
・スタッフの目標設定、目標達成のサポート
相手との関係の構築が重要視されるので、コミュニケーション能力を活かして業務を円滑に進めることが大切です。
コミュニケーション能力を高めるには、以下を意識できると良いでしょう。
・相手の調子に合わせ、意見を尊重する
・先入観を持たず話を最後まで聞く
・自分の意見や主張をしっかり伝える
・意見を冷静に聞き、判断や評価をしない
・ジェスチャーなど非言語的コミュニケーションを取り入れ、わかりやすくシンプルに伝える
・傾聴の中に共感の要素を交える
また、相手が伝える内容の要点を復唱すると報連相の相違を防ぐこともできます。
リーダーシップ
看護師長は、看護主任や他の看護師の意見に耳を傾けることで部署内のバランスを保ち、良好な関係性を作ることやチームとしてのバランスを保つことも大切です。
また、現場での積極的な指示出しやチームの先頭に立つことも重要です。
研修・学会への参加、資格の取得などもリーダーシップを発揮する上で良い機会と言えます。
リーダーシップを発揮する具体的な業務には、次のようなものが挙げられます。
・部署内の方針や目標の設定、達成に向けたサポート
・業務上の問題点の把握と改善案の提案、実行
所属部署の全体を把握し、まとめ上げ、目標達成のためのサポートを行うために、看護師長としてのリーダーシップが求められます。
リーダーシップを発揮するには、看護に関する知識や技術、判断力や指導力なども備えておきたい能力です。
問題解決能力
部署内を客観的に捉え、問題点に気づき、改善に向けて行動する問題解決能力が求められます。
他にも、患者さんの全体像を客観的・主観的に捉えて、データを適切な診断に生かしたり、看護問題を解決するために立案した看護計画を実施・評価する能力が必要となります。
もちろん、これまでの経験や知識、時には勘で対応することもありますが、データなどの事実に基づいて論理的に考え、問題の本質を見極めて解決していく思考とスキルも備えておきたいところです。
そのためには、普段から看護師の動きや患者さんの症状を把握し、些細な変化にも気づけるように意識することが大切です。
気付いただけでは何も解決しないので、医療現場や労働環境、チームの問題点をまとめ、相談に乗ったり改善案を考えたりする力も重要です。
例えば、問題の原因を冷静に分析・判断し、具体的な行動指針を示すなど、指針を示すことが求められます。
豊富な臨床経験、コミュニケーション能力、スタッフの教育、リスク管理、 他部署との交渉など解決力が必要な場面は多数あるので、状況に応じた対応を取るようにしましょう。
客観視点
医療現場では、さまざまなトラブルやハプニングが起きます。
その際に、問題を客観的に把握できる力や、物事を俯瞰して見ることができる力が求められます。
看護師長は、自身の仕事の遂行にとどまらず、部署の運営やスタッフの教育、リスク管理、他部署との交渉などを行うため、客観的な視点で業務を遂行することが重要です。
例えば、患者さんの訴えに対して、感情や主観的な視点に惑わされずに対応することや状態を客観的に判断し、的確な指示出しが求められます。
現場で問題が生じた場合にも、同様の視点を持ちましょう。
スタッフの目標設定に関しては、改善点を見つけ出し、提案し、設定した目標に対しては、実行の手助けやサポートを行います。
あくまでも客観的に必要だとされるポイントを抑えてサポートすることが重要です。
求められる能力
スキルを身につけるためには、身につけるための能力を高めておく必要があります。
スキル1つ1つは別に見えますが、元を辿ると必要な能力は共通していることも多いのです。
自身を見つけ直すきっかけにもなりますので、ポイントを抑えていきましょう。
冷静さ
看護師長は部署やチームの中心に立ち、運営を管理する立場であるので、冷静さや俯瞰して物事を見ることができる能力が求められます。
スタッフの教育やリスク管理、他部署との交渉などを行うこともしばしば。
そのため、冷静かつ適切な状況判断能力や、大局的に物事を見ることができる能力が重要です。
看護師長として冷静さを保つことで、相手の状況や思いを理解することや変化に気付くこと、俯瞰的な視点が養われます。
また、焦ってしまう状況でも、焦りを自覚することができ、早急な対応につながります。
ただ、一人で解決しようとしすぎず、周りに頼ることも冷静さの大切な視点です。
豊富な知識・経験
部署の看護師の手本となる存在であり、指導役としてスキルや経験を部下に伝える役に説得力を持たせるのは豊富な経験と知識です。
看護師長になるためには、臨床経験が数十年必要であり、主任としての経験も含みます。
昇格試験や研修を数多く受けるだけでなく、看護管理やリーダーシップを磨くラダー研修やセミナーも受講しておく必要があります。
経験や知識があることは、部のトップとして、周囲に安心感を与える要素にもなります。
人を見る力
さまざまな情報を読み取る人間観察力が必要になります。
部下を教育する立場として、相手の表情や言動を観察し、人を見る力が必要です。
そうして相手をよく見ることで、部下の性格や適性を理解でき、適切に褒めることや指導することができます。必要な場合には、主任とともにスタッフの支援を行いましょう。
一人一人との関係性が良好になることで、部署全体がまとまり、チーム医療が円滑に進みます。
医療事故やインシデントの予防や対策にもつながります。
部下の看護師だけでなく、チームの医師、患者さんとその家族など人と話す機会が多いため、併せてコミュニケーション能力も重要になってきます。
看護師長になるには
看護師長になるにはさまざまな方法があります。
大学院を修了する方法や看護部長の推薦を受ける、研修を受けるなどのステップがあります。
今回は経験を積み、昇進を目指す方法とキャリアアップとしての転職する方法をご紹介します。
試験内容などは病院ごとに異なりますが、意欲的に活動していくことが大切です。
臨床経験を積み、昇進
10〜20年ほどの臨床経験と管理職経験が求められます。最低でも10年は必要になると言われています。
基本的な流れとしては、看護主任として数年の実績を積み、昇格試験や研修を受けることが一般的です。
順当に経験を積んでいくとすると、看護師長には40代〜50代の年齢で昇進することが多いとされています。
また、看護師長になるには、認定看護管理者資格の受験も有利です。認定看護管理者資格の受験対象は、実務経験が5年以上あり、そのうち3年以上は看護師長相当の看護管理の経験がある看護師とされています。
臨床経験の中で、看護主任や副看護師長としての管理者経験をはじめ、リーダーシップのスキルも磨きましょう。
転職する
即戦力としての求人に応募して看護師長を目指すこともできます。
規模の小さいクリニックや新規で開業した医療機関などでは、すぐに業務を任せられる人材を確保したい背景があります。
そのため、看護師長を募集することがあります。
看護師長を募集している求人を探して転職するのも、看護師長を目指す上で1つの手段です。
看護師長になるメリット
看護師長は言わずもがな責任の多い役職です。
憧れだけでは務まらないこともありますが、メリットもあります。
年収が上がるなどの待遇面ややりがいや充実感といった気持ちの面までさまざまです。
能力を高く評価してもらえる
社会的な評価が高くなるのが、看護師が役職に就くメリットです。
患者さんやその家族、病院職員などからも、安心できる判断を下す人というような判断が得られることも。
管理職は研修や試験をクリアしなければならず、すべてのスタッフがなれるわけではありません。
だからこそ、看護師長試験に合格したときには、能力を認められたと感じることも多いでしょう。
なれませんので、特別な役職だと言えるでしょう。
管理職に適しているかどうか資質も試されますので、という実感が大きいようです。
環境改善ができる
これまでの労働環境を改善するために、動くことができます。
職場のルールを変更して、スタッフや患者さんが過ごしやすい環境を整える実行力を持つこともできますよ。
職場の看護体制を改善したいと感じている看護師は、役職に就いて積極的に問題解決できることがメリットとなるでしょう。
夜勤が減る
看護部長までキャリアアップすると、ほとんどが日勤になるのが基本です。
夜勤が苦手、年齢を重ねると夜勤が辛くなってきたという看護師にとっては悩みの解消になりそうです。
現場の意見を上に進言できる
病棟スタッフとは違う業務をこなし、病棟の代表としての職務を行うことは、病棟のトップとして認められているということです。
部署内で出た意見を上に伝えることができるのも看護師長の特権ではないでしょうか。
適切な意見を進言するために、客観視することやコミュニケーションを取ることは大切にしましょう。
転職が有利になる
看護師長は一般企業における中間管理職の課長にあたるポジションです。
つまりは、高い能力を持つ人材として認められていることを意味します。
認定看護師や専門看護師、認定看護管理者などの資格を取得するなども転職を有利に進めることにつながりますので、気にしておきたいポイントです。
看護師長の経験を通して、専門分野のスペシャリストや幅広い看護分野で活躍するジェネラリストになる、海外の病院で働くなどの道が見えてくることもあります。
こうしたキャリアアップを目指す転職活動にも有利に働いてくれますよ。
収入があがる
役職手当を受け取ることができるので、収入アップにつながります。
また、業務の専門性も上がるため、基本給が上がることにも期待ができるでしょう。
看護師として幅広い仕事に携わりながら、収入面も確保したいと考える人は、看護師長としての働き方が適しているのではないでしょうか。
実際には、月単位で8万円ほどの差がでる場合もあります。
年間にすると約100万円の差があることになります。
もちろん、病院の規模によって前後してきますが、役職を持たない看護師より給与面での優遇もメリットの一つと言えます。
まとめ
看護師長はチーム医療をまとめるキーパーソンなのです。
なくてはならない役割ですが、誰もがなれるわけではありません。
だからこそ、チームのトップとして、良くも悪くもその病棟・部署の雰囲気を作り上げる点においても重要なポジションです。
よりよい職場環境作りをしたい方は、キャリアを積み上げ、看護師長を目指すのもいいかもしれませんね。
