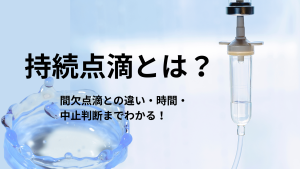患者さんやそのご家族、または医療チーム内でのコミュニケーションに困っていませんか?
「がんの治療中の患者さんが気持ちを話してくれた時、どう返せば良いのだろう…」
「患者さんのご家族とはどうコミュニケーションを取るべき…?」
「医療チーム内で意見を伝えたいけど上手くできない…」
1日の中で色々な人と会話をする看護師にとって「コミュニケーションスキル」は身につけておきたいもの。患者さんやそのご家族に信頼を得たり、伝達ミスを防いでチーム内で仕事がしやすくなったりします。
しかし、すべての人に同じコミュニケーションは通用しません。1人1人に合ったコミュニケーションが大切なのです。
この記事では、以下のような内容を紹介します:
患者さんやそのご家族とのコミュニケーション技術
特別な配慮が必要な患者さんとのコミュニケーションの仕方
医療チーム内での重要なコミュニケーション方法
コミュニケーションスキルを高める方法
どんな人とコミュニケーションを取っても安心できるよう、**「今から実践できるコミュニケーション技術」**を解説していきます。ぜひブックマークして、困った際のお守りにしてくださいね。
看護師にとってコミュニケーションスキルが必要な理由とは?
看護師の仕事は、単に処置やケアを行うだけではなく、患者さんや家族と信頼関係を築きながら、心身のサポートを行うことが求められます。その中で必要なのが、コミュニケーションスキルです。
患者さんの不安を和らげたり、医師との連携をスムーズにしたりと、言葉ひとつで医療現場の雰囲気やチームワークにも大きな影響を与える場面は多くあります。この章では、看護師にとってなぜコミュニケーションが重要なのか、その役割や背景について解説していきます。
日本看護協会が教育で大切にしている「コミュニケーション 能力」
日本看護協会では、看護実践において重要な要素として、コミュニケーション能力や協働力の重要性がたびたび強調されています。
たとえば、看護教育の基本的な考え方の中では「対象を中心とした看護を提供するために、看護師としての人間関係を形成するコミュニケーション能力を養う」ことが明記されています。また、看護職の倫理綱領においても、患者さんとの信頼関係の構築が看護の基盤であるとされています。
こうしたことから、看護師にとっての「人間関係能力」とは、患者さん・患者さんのご家族・医療チームと良好な関係を築き、信頼に基づいたケアや連携を行うための土台といえるでしょう。
伝達ミスや関係悪化を防ぐカギになる
医療現場では、わずかな伝達ミスやすれ違いが、患者さんの安全に直結するリスクを生むことがあります。特に看護師は、医師や多職種スタッフとの情報共有の要となる立場であり、確実かつ丁寧なコミュニケーションが求められます。
報告・連絡・相談がうまくいかなかったことで、処置の遅れや確認漏れが起こるケースもあり、これらは人間関係の悪化や職場の空気にも影響を及ぼすことも。日頃から相手の話に耳を傾け、自分の伝え方にも配慮することは、業務の効率化だけでなく、信頼関係の維持やチームの雰囲気を良好に保つことにも繋がります。
医療現場で求められる「協働する力」
医療はチームで成り立っており、看護師だけで完結する業務はほとんどないでしょう。医師、薬剤師、リハビリスタッフ、介護職員など多職種が連携して患者さんを支える中で、看護師には「協働する力」が強く求められます。
自分の意見をしっかり伝えるだけでなく、他職種の立場や考えを理解しながら、共通の目標に向かって役割を果たすことが大切です。時には意見の違いや立場の差からすれ違いが起こることもありますが、そんなときこそ冷静な対話と歩み寄りが求められます。
協働する姿勢は、チームの信頼を生み、患者さん中心のケアの質を高める大きな原動力となります。コミュニケーションスキルは、こうしたチーム連携の土台でもあるのです。

患者さんと信頼関係を築く上で大切なコミュニケーション技術
看護師にとって、患者さんとの信頼関係は非常に重要なことです。症状や不安を率直に話してもらえるかどうかは、日々のコミュニケーションの積み重ねにかかっています。とはいえ、ただ丁寧な言葉づかいや明るい声かけをするだけでは、信頼を得ることはできません。
この章では、患者さんの気持ちに寄り添い、信頼を築くために欠かせない具体的なコミュニケーション技術を解説します。
【実践例付き】傾聴する|聴く姿勢から返答の仕方まで
傾聴の基本姿勢としてまず大切なのは、身体を患者さんの方に向け、視線を合わせること。うなずきや表情で関心を示すことで、相手は「話を聴いてもらえている」と感じやすくなります。
さらに、「そうなんですね」「それは不安でしたね」といった短いあいづちや共感を込めたひと言を添えることで、相手の気持ちが受け止められているという安心感が生まれます。
そして何より、相手の言葉を否定せず、そのまま受け入れる姿勢を忘れないようにしましょう。驚きや意見を挟みたくなる場面でも、まずは感情をしっかり受け止めることが、信頼関係を築く第一歩になります。
<実践例>
1. 入院中の高齢な患者さん
患者:
「入院が長くなってきて…なんだか家に帰れる気がしなくなってきたよ。」
傾聴的な返答:
「家に帰れるかどうか、不安に思っていらっしゃるんですね。」
「長く入院していると、そういう気持ちになるのは自然なことだと思います。」
→感情を受け止めたうえで、その後に医師と連携し、退院支援の話を進めるきっかけにもなります。
2. がんの治療中の患者さん
患者:
「治療がきつくて、正直もうやめたいって思ってる…。」
傾聴的な返答:
「治療がとてもつらくて、続けるのが苦しいと感じているんですね。」
「どんなときに特につらくなりますか? 話していただけますか?」
→感情をそのまま受け止め、患者さんのペースで話せるよう促します。
傾聴には、患者さんの不安を和らげ、心の整理を助ける効果があります。話を聴いてもらえることで心理的な負担が軽減され、安心感が生まれます。また、「この看護師さんは自分の話をきちんと聴いてくれる」という信頼感に繋がり、より良い関係性を築くきっかけにもなるでしょう。
さらに、患者さんの言葉の中には症状の変化や心のサインが含まれていることがあり、傾聴を通して重要な情報を引き出せることも少なくありません。
【NG例付き】共感する|「分かります」では伝わらない
共感とは、相手の感情や立場を理解し、それに寄り添う姿勢を示すこと。単に「気持ちは分かる」と言うだけでなく、相手がどんな気持ちでそう言ったのか、そこにある背景や心情に目を向けて受け止めることが大切です。
<NG例>
シチュエーション:がんの治療中の患者さんとの会話
患者:
「抗がん剤の副作用がつらくて…髪も抜けてきたし、気持ちも落ち込むばかりです。」
NGな返答:
「分かります。抗がん剤って大変ですよね。」
→“分かります”だけでは、どの部分に共感したのかが不明確です。患者さんからすると「本当にこの辛さを分かってくれているのか」と思われてしまう可能性があります。
<改善例>
共感する返答:
「副作用で体も気持ちもつらい中で、毎日過ごされているんですね。髪が抜けることも、ご自身にとってとても大きな変化だったのではないでしょうか。」
→相手の気持ちや状況に具体的に言及し、評価やアドバイスをせずに、ただ「あなたの気持ちを受け止めています」と伝えましょう。感情を想像し、言葉にして返すことが重要です。
【シーン別】声かけのタイミングと役立つフレーズ集
声かけは、患者さんとの関係づくりの第一歩です。しかし、「どのタイミングで」「どんな言葉をかければよいか」に迷うことも多いのではないでしょうか。
そこで、シーン別に声かけのコツとすぐに使えるフレーズを紹介します。場面に応じて適切な声かけができれば、より深い信頼関係を築くきっかけになります。

<フレーズ集>
1. 【入室時・初対面】まずは安心を届ける
タイミング:
部屋に入るとき、初めて顔を合わせるときは、相手の緊張を和らげるチャンスです。
笑顔と落ち着いた声で話しかけることを意識しましょう。
使えるフレーズ:
・「こんにちは。〇〇担当の△△です。よろしくお願いします。」
・「今日は体調いかがですか?」
・「お変わりないですか? 何か気になることはありませんか?」
→相手が言葉にしやすい雰囲気を作ることが大切です。無理に会話を引き出す必要はありませんが、聞きやすく・話しやすくなる「きっかけ」を渡すつもりで声を掛けましょう。
2. 【処置や検査の前】不安を和らげる
タイミング:
注射、採血、点滴、検査前など、患者さんが緊張しやすい場面です。
使えるフレーズ:
・「少しチクッとしますが、すぐ終わりますよ。」
・「緊張しますよね。でもすぐ終わりますからね。」
・「気になることがあれば、遠慮なくおっしゃってくださいね。」
→手順を簡単に説明し、安心感を与えること。痛みや不快感に対する事前説明があると、患者さんは心の準備ができるはず。
3. 【沈黙・落ち込んでいるとき】無理に話させず寄り添う
タイミング:
患者さんが静かにしているときや、気分が落ちていそうなときは、話しかけるかどうか迷う場面です。こうしたときは、“話すきっかけ”をそっと置くような声かけをしましょう。
使えるフレーズ:
・「無理に話さなくても大丈夫ですよ。ここにいますので。」
・「少ししんどい感じですか?そばにいますね。」
・「何かあれば、いつでも声を掛けてくださいね。」
→無理に言葉を引き出すのではなく、「あなたの気持ちに気づいています」というメッセージを込めることが大切です。
4. 【退室時・別れ際】安心とつながりを残す
タイミング:
ちょっとした別れ際や、勤務の交代時にも気を抜かず声を掛けましょう。
使えるフレーズ:
・「また後で伺いますね。何かあればナースコール押してください。」
・「今日はこれで失礼します。夜は△△が担当しますので、よろしくお願いしますね。」
・「ゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。」
→「一人にしません」「ちゃんと引き継ぎます」という安心感を残す言葉が、患者さんの不安を和らげます。
5. 【日常のちょっとした会話】心の距離を縮める
タイミング:
食事の配膳、検温、移動介助など、日常的なケア中にも自然な会話の機会があります。
使えるフレーズ:
・「ごはんの味、どうでしたか?」
・「昨日より少し表情が明るいですね。」
・「この時期、朝晩冷えますね。寒くないですか?」
→小さな変化に気づき、それを言葉にして伝えることで、患者さんは「見てもらえている」と実感できます。
【事例付き】不安・怒りを抱えた患者さんへの対応の仕方
病院では、患者さんが不安や怒りを抱えることは少なくありません。体調への心配、診断への不満、待ち時間へのいら立ちなど、理由は様々です。
看護師として大切なのは、その感情を否定せずに受け止め、信頼関係を築くこと。では、実際に不安や怒りを抱えた患者さんにどう向き合えばよいか、確認してみましょう。
<事例>
対象:診察の順番に怒りを見せた患者さんへの対応
ある外来で、高齢の男性患者さんが「なぜこんなに待たされるんだ!」と大きな声を上げました。他の患者さんの目もあり、場の空気が一気に張り詰めました。このとき看護師は、まず落ち着いた声で「お待たせしてしまい、申し訳ありません」と謝罪。
その上で「○○さんの前に、緊急の処置が必要な方がいらっしゃったため、順番が前後しております」と事情を丁寧に説明しました。さらに、「体調は大丈夫ですか? お辛いようでしたらお声がけくださいね」と声を掛け、患者さんの気持ちに寄り添う姿勢を示しました。
その結果、患者さんは「そうか…それなら仕方ないな」と納得し、怒りは次第におさまりました。
まずは感情を否定せず、まずは受け止めましょう。その後、謝罪と説明はセットで行い、患者さんの立場に立ち、安心感を与える声かけを意識することがポイントです。
【覚えよう】表情・姿勢などの非言語コミュニケーション
看護師のコミュニケーションは、言葉だけでなく表情や姿勢などの“非言語”も重要です。相手の安心感や信頼感に大きく影響します。
<表情>
やわらかい笑顔は、患者さんの不安を和らげます。反対に、無表情や険しい顔は冷たい印象を与えることも。
<姿勢>
目線を合わせて話す、身体を少し前に傾けるなど、寄り添う姿勢が大切です。腕を組む・見下ろす姿勢は距離感を生むので注意しましょう。
<視線とうなずき>
うなずきやアイコンタクトで「聞いていますよ」と伝えることができます。特に高齢者には有効です。
<声のトーン>
ゆっくり、やさしい声で話すことで、安心感を与えられます。
非言語コミュニケーションは、看護師の信頼を支える大切な技術。日々の意識で自然と身に付くでしょう。
【寄り添う】患者さん家族とのコミュニケーション
患者さんだけでなく、そのご家族との関わりも看護師の重要な役割です。特に入院や手術を控えた場面では、家族も大きな不安を抱えています。
まずは、話を聞きましょう。不安や疑問を口にされたときは、すぐに答えを出そうとする前に、丁寧に話を聞き、うなずきや共感の言葉で安心感を与えられます。
説明するときは専門用語を避けて、具体的で平易な言葉を使いましょう。「〜という処置をします」と伝えるだけでなく、「〜のために必要な処置です」と背景を添えると理解が深まります。
もし、怒りや不満が出た場合は、その裏にある不安や心配の気持ちをくみ取る意識を持ちましょう。まずは受け止め、落ち着いて対応することが大切です。相手の立場に立ち、寄り添う気持ちを忘れずに接しましょう。
特別な配慮が必要な患者さんに対するコミュニケーション
高齢者や幼い子ども、言葉に困難を抱える方など、特別な配慮が必要な患者さんもいます。一人ひとりの状況に合わせた接し方を心掛けることが、安心と信頼に繋がります。
【高齢者】認知症の方との意思疎通で気をつけること
認知症のある患者さんには、ゆっくり、やさしい言葉で話しましょう。早口や長い説明は避け、短く分かりやすく伝えることが大切です。混乱した言動があっても否定せず、「そうなんですね」と共感する姿勢が不安を和らげます。
視線や表情、うなずきといった非言語のやりとりも安心感に繋がる要素。必要に応じて軽く手を握るなど、相手の反応を見ながら距離感に配慮しましょう。
【小児】子どもの不安を和らげるコミュニケーションのコツ
子どもは病院に対して強い不安や恐怖を感じやすく、緊張や泣き出しで意思疎通が難しいことも多いでしょう。そんなときは、まず目線を合わせ、やさしい声で話しかけます。
難しい言葉は使わず、「これから〇〇するね」と具体的で安心できる説明を心掛けましょう。たとえば、ぬいぐるみを使って見本を見せたり、子どもの好きな話題に触れたりすることで、緊張がほぐれやすくなります。

【言語障害】失語症や構音障害のある方との対話方法
言語に障害のある患者さんとは、言葉だけに頼らない工夫が必要です。まずは焦らず、相手のペースに合わせて話しましょう。何度も聞き返さず、相手が言いたいことをくみ取ろうとする姿勢が信頼に繋がります。
表情や身ぶり、指差し、イラストなどを使うと◎。相手の言葉がうまく聞き取れないときも、無理に正そうとせず、「伝えようとしてくれてありがとう」と受け止めるようにしましょう。
【外国人】言語や文化がある場合のコミュニケーション手段
外国人の患者さんとは、言語の違いだけでなく、文化や価値観の違いにも配慮することが大切です。まずは、簡単な日本語やゆっくりした話し方を心がけ、難しい言葉や省略表現は避けましょう。
翻訳アプリや指差しボード、多言語対応の資料などを活用すると、伝わりやすくなります。また、宗教や生活習慣への理解を示す姿勢も、安心感に繋がります。「伝えようとする努力」と「理解しようとする姿勢」の両方が信頼関係の土台になります。
看護師同士・チーム内連携に重要なこと
医療現場では、看護師同士はもちろん、医師やリハビリスタッフなど他職種との連携が欠かせません。日々の情報共有や報告・相談をスムーズに行うことが、患者さんへのより良いケアに繋がります。
報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の基本
看護の現場では、ちょっとした情報の伝達ミスが大きなトラブルになることも…。報告・連絡・相談(ホウレンソウ)は、チーム医療を支える基本です。
報告は事実を正確に、連絡は必要な情報をタイミングよく、相談は早めに行うことがポイントです。曖昧な表現は避け、誰が見ても分かるよう簡潔に伝える力が求められます。日頃から意識してホウレンソウを実践することで、チームの信頼関係も深まります。
アサーティブ・コミュニケーションの活用法
アサーティブ・コミュニケーションとは、自分の意見を押しつけず、相手の立場も尊重しながら伝える手段。看護師同士のやりとりや、医師への報告の場面でも有効です。
感情的にならず、落ち着いた口調で「私は〜と感じています」と主語を自分に置いて伝えることで、相手に防御的な印象を与えにくくなります。相手と対立せずに意思を伝える力は、チームの円滑な関係作りに役立ちます。
医師や他職種との伝達で注意すべきポイント
医師やリハビリ、栄養士など他職種との連携では、限られた時間で要点を正確に伝える力が求められます。相手の専門性や立場を意識しつつ、必要な情報を整理して伝えましょう。
「いつ・どこで・何があったのか」を簡潔にまとめ、主観を交えず事実を伝えるよう心掛けることが大切です。また、不明点がある場合はその場で確認しましょう。
看護師のコミュニケーションスキルを高める方法
コミュニケーション力は、生まれつきのものではなく、意識と工夫で磨くことができます。日々の業務の中で少しずつ実践を重ねることで、自信と信頼につながるスキルへと育っていくでしょう。
院内研修やロールプレイを活用しよう
院内で行われる接遇研修やロールプレイは、実践的なコミュニケーション力を養う良い機会です。実際の場面を想定したやりとりを経験することで、自分の伝え方や反応のクセにも気付くことができます。
失敗を恐れずに練習できる場だからこそ、安心して学べるのも魅力。積極的に参加し、現場で活かせる力を身に付けましょう。
日々の振り返りとセルフチェックを必ずやろう
コミュニケーション力を高めるには、日々の関わりを振り返る習慣が大切です。「あのときの声かけは適切だったか」「相手の気持ちに寄り添えたか」など、自分の対応を客観的に見直すことで成長に繋がります。また、ノートに書いて可視化することで振り返りがしやすくなります。
短い時間でも構いません。“気付き”を積み重ねることが、信頼される看護師への一歩となります。

本を読んで勉強するのも◎
コミュニケーションに関する書籍には、現場で役立つヒントがたくさん詰まっています。看護師向けの本だけでなく、心理学や対人スキルに関する一般書も学びになります。
自分に合った一冊を見つけて、隙間時間に少しずつ読むだけでも、視野が広がります。読書も気軽に始められる学びの方法としておすすめです。
まとめ|少しの意識で現場は変わる
看護師のコミュニケーションは、患者さんとの信頼関係やチーム医療の質に影響します。特別なスキルでなくても、日々のちょっとした声かけや姿勢の工夫で、現場の雰囲気や関係性は大きく変わります。
小さな気付きと実践を積み重ねて、自分らしいコミュニケーションを育てていきましょう。それが最高の医療チームを作ることに繋がり、患者さんにとっても居心地が良い環境になるはず。