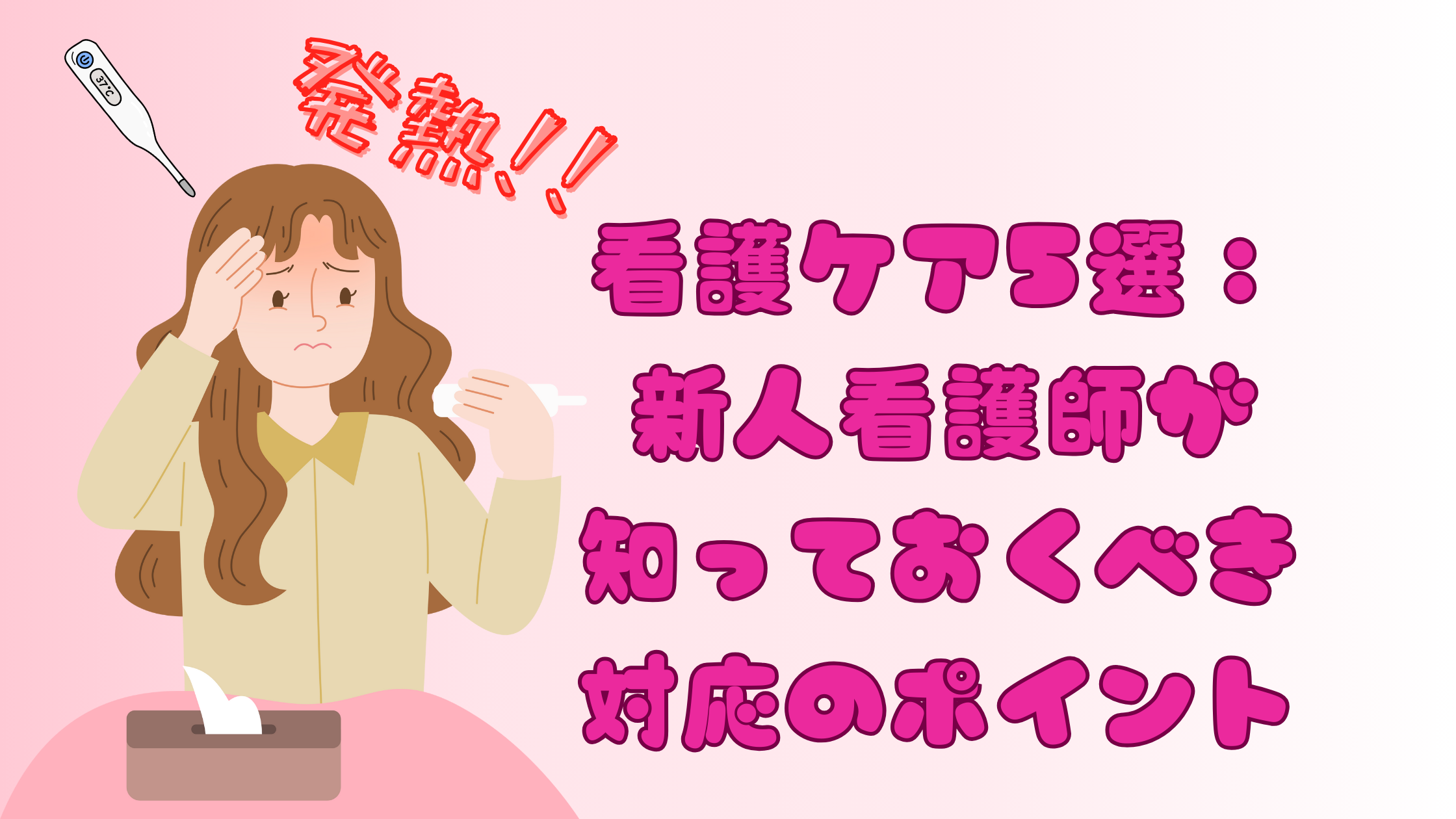
「患者さんが熱出してる!どうしよう…」😰 新人看護師さんなら、そんな不安を感じることもありますよね。
でも大丈夫!発熱ケアのコツさえつかめば、自信を持って対応できるようになります!✨
患者さんの体温が上がったとき、どんなポイントに気をつければいいのか、簡単な5つのステップでご紹介します。
これであなたも発熱ケアのプロに!💪
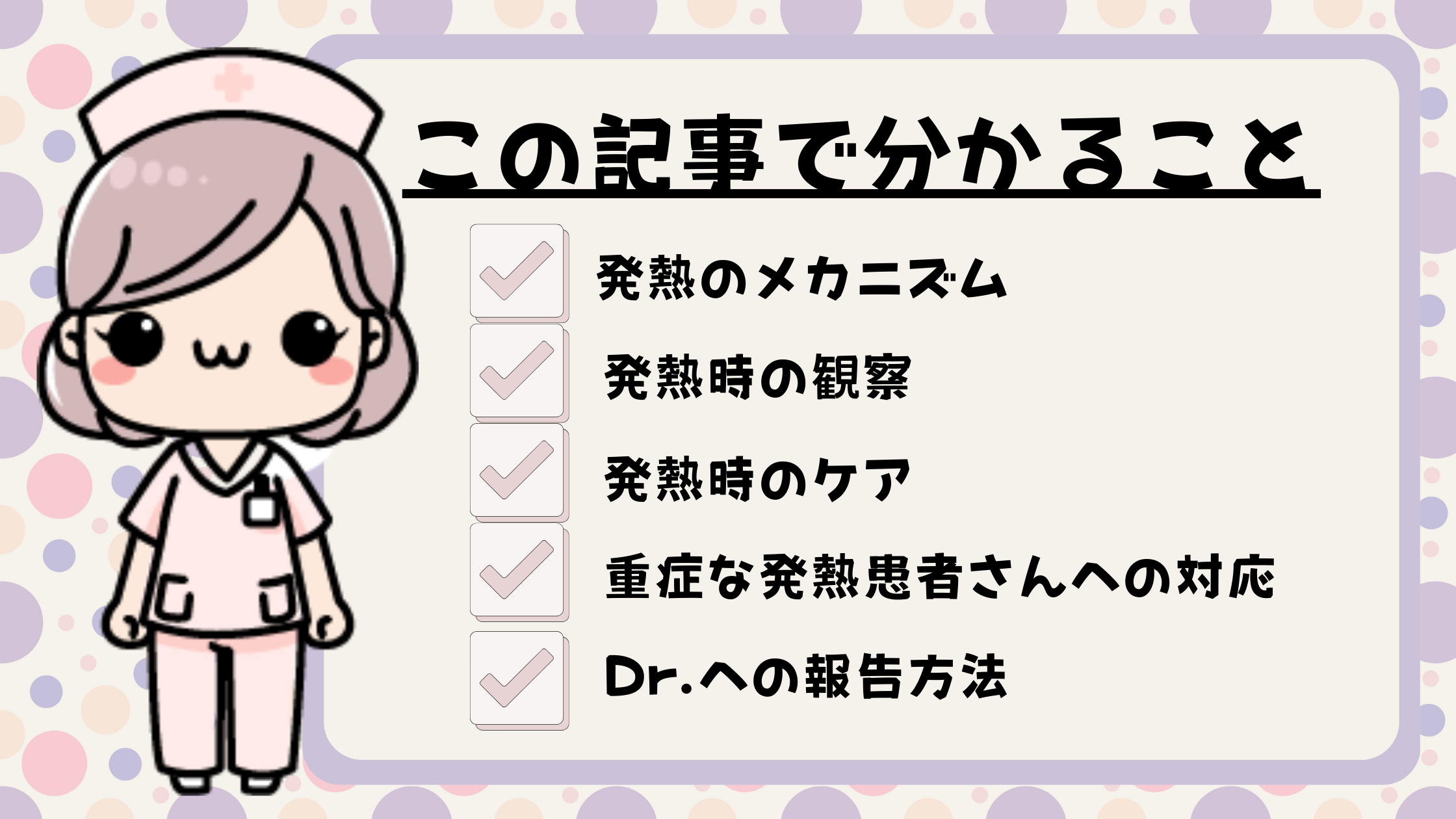
看護師なら知っておきたい!発熱の原因とメカニズム🌡️
発熱は、体温が通常よりも高くなる状態で、感染症や炎症などさまざまな原因で起こります。
ここでは、発熱の定義や体温調節の仕組み、そして発熱の原因について詳しく解説しますね!
発熱ってなに?🤔 定義と体温の基礎知識
-
体温の基礎知識
健康な人の平熱は約36.5~37.5℃で、時間帯や活動状況によって変動します。
例えば、朝は低く、夕方に高くなることが多いです。 -
発熱の定義
一般的には37.5℃以上を発熱としますが、平熱には個人差があるため、普段の体温よりも1℃以上高い場合も発熱と考えられます。
発熱は、体が異物に対抗するための防御反応の一つです。 -
発熱の仕組み
発熱は脳の視床下部が体温の「設定値」を上げることで起こります。
この設定値が上がると、体は熱を産生し、放散を抑えるように働きます。
体温調節のヒミツを探る🔎 身体はどうやって熱をコントロールしてるの?
-
体温調節のメカニズム
視床下部が体温調節の司令塔として働き、体温が高すぎる場合は汗をかいて熱を放散し、低すぎる場合は筋肉を震わせて熱を産生します。 -
体温調節の方法
方法 詳細 輻射 体から熱を電磁波として放出。周囲の温度が低い場合に起こる。 伝導 体表面から接触している物体へ熱を伝達。 対流 空気と熱をやり取りし、熱を移動させる。 蒸発 汗や呼吸による水分蒸発で熱を奪う。湿度が高いと蒸発しにくい。 行動性体温調節 衣服の調節や冷房の使用など、意識的な行動による体温調節。 -
自律神経の役割
交感神経は体温を上げる働き、副交感神経は体温を下げる働きをします。
発熱の原因、実は色々あります!
発熱の原因は多岐にわたり、以下のようなものがあります:
| 原因 | 詳細 |
|---|---|
| 感染症 | 細菌やウイルスが体内に侵入し、免疫反応を引き起こす。例:インフルエンザ、肺炎。 |
| 炎症 | 組織の炎症が原因。例:関節リウマチ、炎症性腸疾患。 |
| 薬剤性 | 一部の薬剤が副作用として発熱を引き起こす。例:抗生物質、抗がん剤。 |
| その他 | 悪性腫瘍、熱中症、内分泌疾患など。 |
発熱は体の防御反応であることが多いですが、原因によっては早急な対応が必要な場合もあります。
看護師としては、患者さんの状態をしっかり観察し、適切な対応をすることが重要です😊
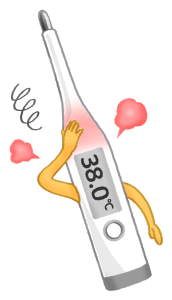
【症状チェック】発熱患者さんの観察ポイント👀 看護師が見るべきサイン
発熱患者さんを観察する際、看護師が注目すべきポイントを解説します!
患者さんの状態を的確に把握するために、以下の項目をチェックしてみましょう✨
全身状態をくまなくチェック!👀 意識レベルから皮膚の色まで
患者さんの全身状態を評価することは、重症度を判断する上で重要です。
| 観察項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 意識レベル | JCSやGCSを用いて評価。呼びかけへの反応や指示に従えるかを確認します。意識レベルの低下は重症化の兆候です。 |
| 皮膚の色 | 蒼白、チアノーゼ、黄疸、紅斑、紫斑などを観察。循環器系や呼吸器系の異常を示唆する場合があります。 |
| 皮膚の状態 | 艶、弾力、乾燥、湿潤、浮腫、病変や創傷の有無をチェック。感染症や栄養状態の指標になります。 |
| SIRSの兆候 | 頻脈、頻呼吸、白血球数増加などがないか確認。菌血症のリスクを示唆する可能性があります。 |
随伴症状を見逃すな!咳、痰、頭痛…何に注目する?
発熱以外の症状から原因を特定することが重要です。
| 症状 | チェックポイント |
|---|---|
| 呼吸器症状 | 咳、痰、呼吸苦、肺副雑音の有無を確認。肺炎が疑われる場合はSpO2や呼吸数もチェック。 |
| 消化器症状 | 腹痛、下痢、嘔吐、悪心の有無を確認。腸管の炎症が疑われる場合は症状の程度や持続時間も把握。 |
| 神経症状 | 頭痛、項部硬直、嘔吐の有無を確認。髄膜炎の可能性を考慮。 |
| 泌尿器症状 | 排尿時痛、頻尿、残尿感、尿の混濁や臭いをチェック。尿路感染症の兆候を見逃さないように。 |
発熱の経過を把握しよう!🌡️ いつから? 熱型は? 解熱剤の効果は?
発熱の経過を知ることで、原因特定や治療方針の決定に役立ちます。
| 観察項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 発熱の時期 | 発熱がいつから始まったかを確認。3日以内ならウイルス感染、4日以上続く場合は細菌感染の可能性。 |
| 熱型 | 間欠熱、弛張熱、稽留熱などのパターンを記録。感染症の種類特定の手がかりになります。 |
| 解熱剤の効果 | 解熱剤の効果や発熱に伴う症状(悪寒、頭痛、関節痛など)の緩和度合いを確認。 |
感染兆候を見つける名探偵🕵️♀️ 創部、挿入部位…どこを見る?
感染症が原因の場合、感染部位を特定することが重要です。
| 観察項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 創部 | 発赤、腫脹、熱感、疼痛、排膿などの感染兆候を確認。術後2~3日以降に起こりやすく、5~7日がピーク。 |
| 挿入部位 | 点滴やカテーテルの挿入部位に発赤、腫脹、疼痛、排膿がないか確認。重症化のリスクがあるため注意。 |
悪寒戦慄🥶 ただの寒気じゃない! 評価のポイント
悪寒戦慄は感染症による発熱時に現れることがあります。体温が急上昇する際に起こるため、保温が重要です。
| 悪寒戦慄の対応 | ポイント |
|---|---|
| 保温 | 湯たんぽや温かい飲み物を用意し、患者さんが楽な姿勢で休めるようサポート。 |
| 観察 | 悪寒戦慄が続く場合は、感染症の重症化を疑い、医師に報告。 |
患者さんの状態をしっかり観察し、適切な対応を行いましょう!
看護師としての観察力が患者さんの回復を支えます💪✨
発熱しちゃった…🥵患者さんへのケアと対応方法💡【看護師向け】
患者さんの発熱時のケアと対応方法を詳しく解説しちゃいます!
患者さんが安心して過ごせるように、具体的な方法を一つずつ見ていきましょう✨

安静第一!🛌 楽な体位でリラックス
発熱時は体力を消耗しやすいので、患者さんがリラックスできる体位を整えましょう。
具体的には、以下のような体位がおすすめです。
- セミファウラー位:背中を少し起こした体位で、呼吸が楽になります。
- 側臥位:横向きの姿勢も、呼吸を楽にする効果があります。
患者さんの状態に合わせて、枕やクッションを使って体を支え、より快適に過ごせるように工夫しましょう。こうすることで、患者さんは心身ともにリラックスでき、回復への第一歩を踏み出せます😊
枕やクッションを使って体を支えると、さらに快適に過ごせます。
水分補給はマスト🥤 発熱時の水分喪失を防ぐには?
発熱時には、汗や蒸発によって体内の水分がどんどん失われていきます。
特に、体温が37℃から1℃上昇するごとに、1日に失われる水分量は100〜150mLも増加すると言われています。
だから、こまめな水分補給が超重要!
- 何を飲めばいいの?:常温の水や経口補水液がおすすめです。
- どれくらいの量を飲めばいいの?:少量ずつ、頻繁に摂取するのがポイント。
特に、高齢者や子供は脱水症状を起こしやすいので、注意が必要です。患者さんの状態を観察しながら、適切な水分補給を促しましょう🍀
体温調節をサポート!🌡️ 発熱初期と解熱期でケアを変えよう
発熱の段階によって、ケアの方法を変えることが大切です。
| タイミング | ケアのポイント |
|---|---|
| 発熱初期 | 悪寒がある場合は、 保温を優先! 暖かい飲み物を用意したり、湯たんぽで手足を温めると良いです☕ |
| 解熱期 | 汗をかき始めたら、薄着にチェンジ! 氷枕や冷却シートを使って、首や脇の下など太い血管が通る部分を 冷やすと効果的です。ただし、患者さんが寒がる場合は無理に冷やさないでくださいね。 |
| 熱が高い時 | 体力を消耗しないように、 冷罨法を!首、脇の下などを冷したり、医師の指示に従って解熱剤を使用しましょう. |
発熱初期(寒気がある時)は体を温め、解熱期(汗をかき始めた時)は冷却を行います。
氷枕や冷却シートを使う際は、首や脇の下など太い血管が通る部分を冷やすと効果的です。
ただし、患者さんが寒がる場合は無理に冷やさないようにしましょう。
清潔を保って気分もスッキリ✨ 清拭と衣類交換のコツ
汗をかいたら清拭や衣類交換を行い、清潔を保ちましょう。
清拭にはぬるま湯を使い、肌を優しく拭き取ります。衣類は吸湿性の高いものを選び、患者さんが快適に過ごせるよう配慮します。
栄養満点ご飯で体力回復🍚 食欲不振でも食べやすい工夫
発熱時は、消化の良い食事を提供しましょう。
- おすすめメニュー:おかゆ、スープ、ゼリーなど、食べやすくて栄養価の高いものがおすすめです。
- 食欲がない場合:少量ずつでも摂取を促し、エネルギー補給をサポートしましょう。
消化の良い食事は、体力を回復させるために不可欠です💪
感染予防で広がりをSTOP!✋ 手洗い、消毒、環境整備
感染拡大を防ぐため、手洗いやアルコール消毒を徹底しましょう。患者さんの周囲の環境も清潔に保つことが大切です。特に共有する物品は使用後に消毒を行いましょう。
不安な気持ちに寄り添う🤝 精神的ケアも忘れずに
発熱は患者さんに不安を与えることがあります。優しく声をかけ、症状やケア内容を丁寧に説明することで安心感を与えましょう。患者さんの話をしっかり聞くことも大切です。
患者さんの状態に応じた柔軟な対応を心がけ、安心して過ごせる環境を提供しましょう!
重症患者さんの発熱🔥看護師が絶対に注意すべきこと⚠️
重症患者さんの発熱は、ただの風邪では済まないことが多いです!患者さんの命を守るために、看護師として注意すべきポイントをしっかり押さえましょう。
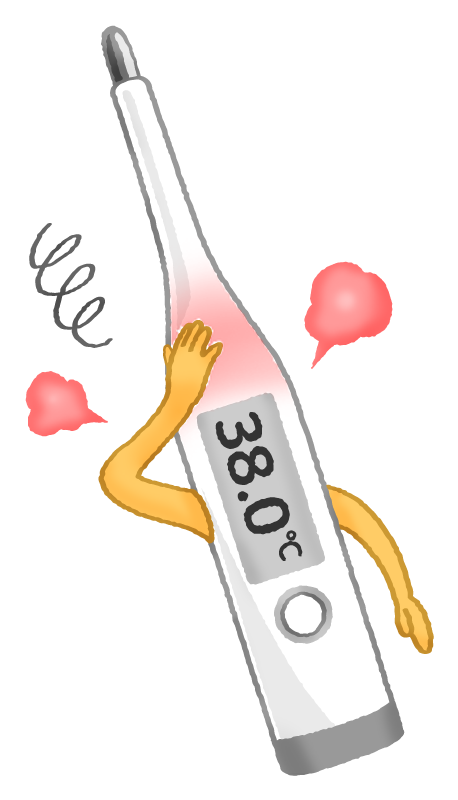
セカンドアタックを防ぐ!🔥 重症患者さんの発熱リスク
発熱は体の防御反応ですが、重症患者さんにとっては新たな臓器障害(セカンドアタック)を引き起こす可能性があります。特にストレス、不安、疼痛が原因となることもあるため、予防的なアセスメントが重要です。
発熱による体の負担
- 体力消耗:発熱によりエネルギー消費が増加。
- 水分・塩分喪失:体温が1℃上がると、1日に失う水分量が100~150mL増加します。
これらの負担がセカンドアタックにつながる可能性があるため、早期発見・早期対応が必要です。
クーリングは慎重に!🥶 シバリングに要注意
発熱時のクーリングは慎重に行う必要があります。
特にシバリング(寒さで体が震える現象)は、逆に熱産生を促し、患者さんの体力を消耗させる可能性があります。
クーリングの注意点
| 注意点 | 解説 |
|---|---|
| 冷やしすぎNG | 体温を37.5℃以下に下げすぎると、組織の灌流が悪化する可能性があります。 |
| シバリングに注意 | シバリングが発生すると、酸素消費量が増加し、患者の負担が増します。 |
| 解熱時に実施 | 体温上昇時のクーリングはシバリングを悪化させるため、避けるべきです。 |
クーリングが有効な場合
- 外的要因による発熱(例:うつ熱)。
- 全身麻酔後や人工呼吸器管理下の患者。
クーリングの種類と方法
クーリングには、いろいろな方法があります💡
| 方法 | 説明 | 注意点 |
|---|---|---|
| 氷枕 | 後頭部を冷やすことで、発熱による不快感を軽減できるよ 。 | 水滴が肌に触れないようにタオルで覆ってね。冷やしすぎにも注意! |
| アイスパック | 局所的に冷やすのに効果的!腋の下や鼠径部など、動脈が体の表面に近い部分を冷やすと効果的 。 | 凍傷に注意⚠。皮膚の状態を観察しながら、冷やす時間を調整してね。 |
| 冷湿布 | 薬剤や冷水を含ませたガーゼやタオルを使用する 。 | 同じ場所に長時間貼り続けると、皮膚トラブルの原因になることもあるから注意が必要。 |
患者さんの状態をしっかりアセスメントして、クーリングが本当に必要かどうか、慎重に判断しましょ😉
クーリングが禁忌な場合
こんな時はクーリングしちゃダメ🙅♀️
- 循環障害がある患者さん
- 血栓ができやすい患者さん
- 開放性の傷がある患者さん
- 寒冷蕁麻疹の患者さん
クーリングを行う際に慎重な判断が必要な患者さん
こんな患者さんには、特に注意してクーリングを行ってくださいね😌
- 意識障害・知覚鈍麻、麻痺がある患者さん:状態を継続して観察できない場合は禁忌 !
- 皮膚が弱い患者さん
- 高齢者:知覚が低下しているから、特に注意が必要!
呼吸・循環管理を徹底!💪 酸素? 輸液? 何が必要?
発熱時は呼吸や循環への影響を考慮し、適切なケアを行うことが重要です。
循環血液量の減少に注意
術後は循環血液量が減少し、血圧低下や頻脈が起こりやすい状態です。以下の症状に注意しましょう:
- 浮腫:血管透過性の亢進による水分漏出。
- 乏尿:尿量が0.5mL/kg/時以下の場合は医師に報告。
呼吸・循環アセスメントのポイント
| 項目 | 観察ポイント |
|---|---|
| 呼吸 | 呼吸数、呼吸音、SpO2、呼吸困難の有無 |
| 循環 | 血圧、脈拍数、心音、浮腫の有無 |
| 全身状態 | 皮膚の色、意識レベル、倦怠感 |
感染源を突き止め、治療につなげる!🔍 血液培養と抗菌薬投与
発熱の原因を特定することは看護師の重要な役割です。血液培養を行い、感染源を特定して適切な抗菌薬投与につなげましょう。
血液培養採取のポイント
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 消毒 | 穿刺部位はアルコール綿やクロルヘキシジングルコン酸塩でしっかり消毒。 |
| 採取量 | 指示された量を守り、好気ボトルを優先。 |
| 採取部位 | 2セット採取する場合は別々の部位から採取。 |
| タイミング | 抗菌薬投与前が理想的。 |
抗菌薬投与後の観察ポイント
- バイタルサイン:投与前後の血圧、脈拍、体温、SpO2をチェック。
- 副作用:アナフィラキシーショックなどの重篤な副作用に注意。
主な抗菌薬の種類
抗菌薬には色々な種類があります🧐
| 種類 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ペニシリン系 | アモキシシリン、アンピシリン | 細胞壁を壊す作用があり、主にグラム陽性菌に有効。アレルギー反応に注意が必要 。 |
| セフェム系 | セファゾリン、セフジニル、セフトリアキソン | ペニシリンと同様に細胞壁を攻撃するけど、ペニシリン耐性菌にも有効な場合がある。 |
| マクロライド系 | クラリスロマイシン、アジスロマイシン | 細菌のタンパク質合成を邪魔するお薬。比較的副作用が少ないから、色々な感染症に対応できる。 |
| ニューキノロン系 | レボフロキサシン、シプロフロキサシン | DNA合成を邪魔するお薬。色々な菌に効果があるけど、最近は耐性菌が増えてきているから慎重に使う必要がある。 |
| アミノグリコシド系 | ゲンタマイシン、アミカシン | タンパク質合成を邪魔するお薬。腎臓や耳に副作用が出やすいから、慎重に使う必要がある。 |
| グリコペプチド系 | バンコマイシン | 細胞壁の合成を邪魔するお薬。点滴で使うことが多くて、腎臓への影響に注意が必要。 |
抗菌薬投与中は免疫力が低下しやすいため、感染予防策を徹底しましょう。
患者さんへの薬剤説明も忘れずに行い、安心感を提供してください♡
🚑💨SOS!医師への報告タイミングと内容📞 看護師が的確に伝えるコツ
医師への報告は、患者の安全を守るために重要な役割を果たします。
タイミングや内容を適切に伝えることで、迅速な対応が可能になります😊
以下では、報告のタイミングや内容、手段、伝え方のコツを解説します。

🚨 報告はタイミングが命!いつ、何を報告する?
報告のタイミングは、患者の状態や緊急性によって異なります。
以下のような状況では、すぐに医師へ報告する必要があります:
| 状況 | 報告のタイミング |
|---|---|
| 急変(バイタルサインの異常、意識レベルの変化など) | 即時報告 |
| 新たな症状の出現(痛み、発疹など) | 状況確認後、迅速に報告 |
| 治療や処置の変更が必要な場合 | 必要性を判断し、早急に報告 |
緊急性が低い場合でも、定期的な経過報告を行うことで、医師との連携を強化💪
📝 報告内容を整理しよう!患者情報、症状、経過…何を伝える?
報告内容は簡潔かつ的確に整理することが重要です。
以下の項目を押さえましょう:
| 報告内容 | 具体例 |
|---|---|
| 患者情報 | 氏名、年齢、病棟、部屋番号 |
| 症状 | 「38度の発熱」「胸痛を訴えています」など |
| 経過 | 「昨日から症状が悪化」「薬剤投与後の変化」など |
| 要請内容 | 「診察をお願いします」「薬の変更が必要です」など |
💡ISBARC(Identify, Situation, Background, Assessment, Recommendation, Confirm)などのフレームワークを活用すると、漏れなく伝えられますよ✨
🗣️ 簡潔&的確に伝えよう!緊急度をアピール
報告時は、以下のポイントを意識して簡潔に伝えましょう:
- 緊急性を最初に伝える:「患者さんが呼吸困難です」「血圧が急激に低下しています」など。
- 具体的な要請を明確に:「診察をお願いします」「輸液の準備をしてください」など。
- データを根拠として提示:「バイタルサインは血圧90/60、脈拍120です」など。
これにより、医師が迅速に判断しやすくなりますよ🎵
🖋️ 報告フレームワークを活用!テンプレートで漏れなく伝える
報告の際にフレームワークを活用すると、情報の漏れを防ぎ、効率的に伝えられます。
以下はISBARCの例です:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Identify | 報告者と患者の情報 |
| Situation | 現在の状況(例:呼吸困難) |
| Background | 病歴や経過 |
| Assessment | 状況評価(例:ショックの可能性) |
| Recommendation | 要請内容(例:診察、輸液準備) |
| Confirm | 復唱確認 |
テンプレートを活用することで、報告の質を向上⤴
医師への報告は、看護師としての重要なスキルです。
タイミング、内容、手段を適切に選び、簡潔かつ的確に伝えることで、患者の安全を守る連携が可能になります!
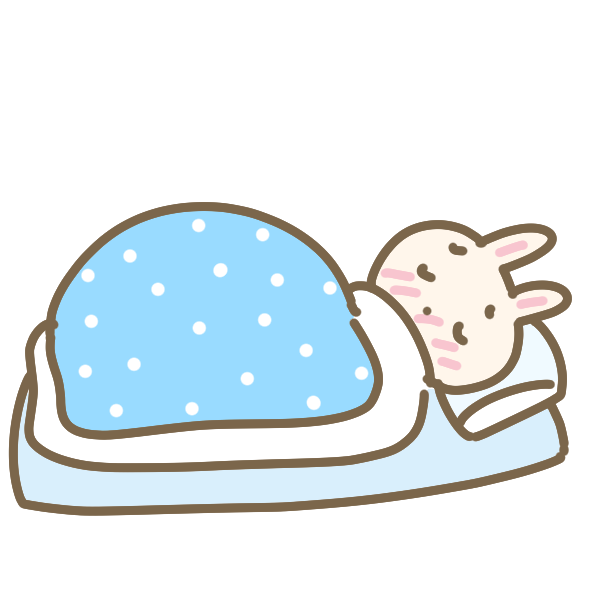
発熱患者さんの「つらい」を「安心」に変えるケアを届けよう!
この記事では、新人看護師さんが知っておきたい発熱時の看護ケアについて解説しました。
今回の情報を参考に、患者さんの状態にあわせた適切なケアを提供し、安心と快適さを届けられるようにスキルアップを目指してくださいね!
発熱ケアは、患者さんの苦痛を和らげるだけでなく、重症化を防ぐための大切なケアです。
今回の学びを活かして、患者さんやそのご家族に安心を届けられる看護師を目指しましょう!
応援しています!





