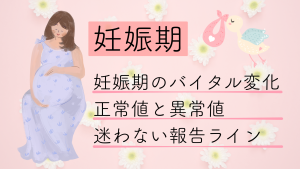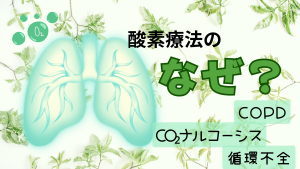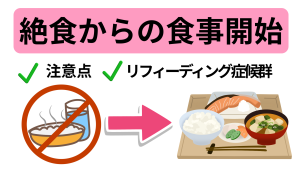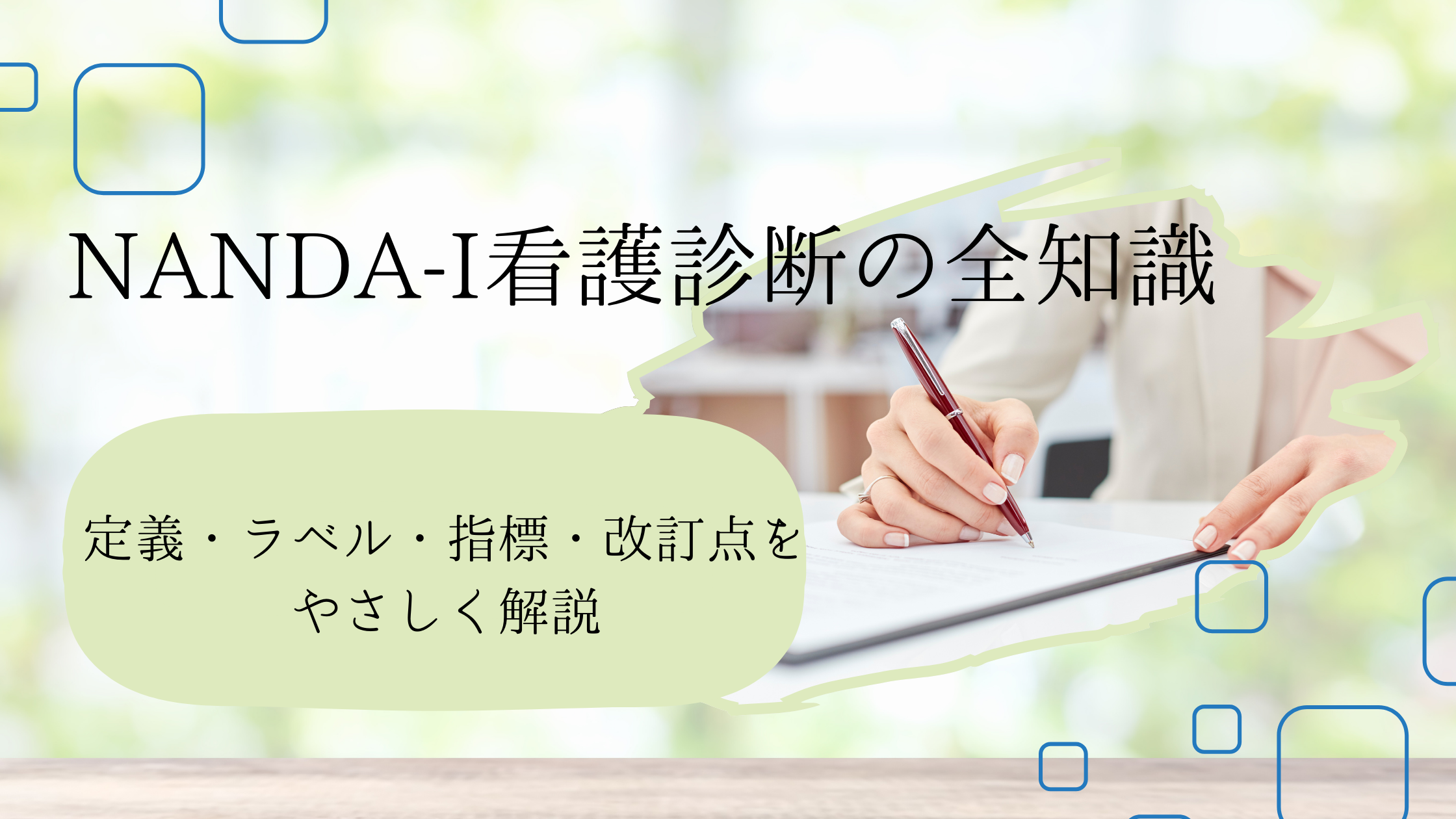
「NANDA-I看護診断って難しくて覚えきれない💦」
「診断ラベルや因子の違いがごちゃごちゃして混乱する…」
「最新版の改訂点も気になるけど、どう現場で使えばいいの?」
そんな疑問やお悩みはありませんか?
この記事では
-
NANDA-I看護診断の定義と基本
-
診断ラベル・診断指標・関連因子・危険因子の違い
-
看護診断の書き方(PES方式)と現場での具体例
-
2024-2026版の改訂ポイント
-
ケーススタディで学ぶ実践の流れ
が分かりますよ♪
結論👉
NANDA-I看護診断は「定義」「診断ラベル」「因子の区別」を理解し、PES方式で書く手順を押さえれば、新人からベテランまで誰でも現場で活用できるようになります✨
この記事では、NANDA-I看護診断の基本から最新版の改訂点までをわかりやすく整理し、実際の症例にどう活かすかを具体例つきで解説していきます。
🧾 NANDA看護診断ってなに?定義と基本をやさしく解説
「NANDAって言葉は知ってるけど、実際どう使えばいいの?」「医師の“病名”と何が違うの?」
—そんなモヤモヤをスッキリ解消しましょう😊
この章では、まず“看護診断そのもの”の正体を押さえ、つぎにNANDA-Iが国際標準になった理由、最後に臨床で必要とされる根拠を順に解説します。肩の力を抜いて読んでくださいね❤

そもそも「看護診断」とは?医師の診断との違い
看護診断は、患者さんの健康状態や生活過程に対する“人間の反応”を見極め、看護介入を選ぶための臨床判断です。
いっぽう医師の診断は、病因・病態(疾患そのもの)を特定する判断。
目的も対象も異なります。
まずは違いを表で直感把握しましょう📝
| 項目 | 看護診断(NANDA-I) | 医師の診断 |
|---|---|---|
| 対象 | 痛み・不眠・不安・転倒リスクなど“人の反応” | 肺炎・心不全・骨折など“疾患” |
| 目的 | 適切な看護介入を選び、成果を評価する | 病因特定と治療方針決定 |
| 根拠データ | 看護アセスメント(主観・客観所見、生活史、環境) | 検査所見、画像、病歴など医療診断データ |
| 時間軸 | 日々の変化に応じて柔軟に更新 | 疾患経過や治療で更新 |
| 記述の型 | 定義・診断指標(特徴)・関連/危険因子で記述(PES方式と親和) | 疾患名や重症度分類で記述 |
| 例 | 〈転倒リスク〉〈非効果的な気道クリアランス〉 | 〈誤嚥性肺炎〉〈大腿骨頸部骨折〉 |
ポイント❤
-
同じ患者でも、医師は「誤嚥性肺炎」、看護師は「誤嚥のリスク」「非効果的な気道クリアランス」のように、視点が補完関係になります。
-
看護診断が定まると、何を優先し、どの介入(NIC)で、どんな成果(NOC)を目指すかがブレにくくなります。
NANDA-Iの歴史と目的|なぜ国際標準になったの?
NANDA-I(NANDA International)は、看護診断を共通言語として整備・改訂している国際学会です。
発端は北米の動きですが、いまや国や領域を超えて活用され、臨床・教育・研究・情報標準の土台になっています🌍
NANDA-Iがめざすこと(要点)
-
看護の可視化:暗黙知になりがちな“看護の判断”を診断ラベルとして標準化。
-
安全で継続的なケア:病棟・在宅・施設のどこでも同じ言葉で引き継げる。
-
質改善・研究:診断→介入→成果を同じ尺度で記録・比較でき、エビデンス構築に役立つ。
-
情報連携:NIC(看護介入分類)・NOC(看護成果分類)、電子カルテ標準と親和性が高い。
国際標準になった理由❤
-
生命現象だけでなく生活・行動・心理社会の反応まで捉える、看護独自の視点を体系化。
-
教育・実習での学習効果、臨床での実用性、研究での再現性が高い。
-
定期改訂で社会や医療の変化に追随できる(例:高齢化、多疾患併存、患者参画など)。
NANDA看護診断が臨床で必要とされる理由
「忙しくて診断まで手が回らない…」そんな日こそ、標準化された看護診断が味方です💪
臨床での価値(実感ベースで)
-
優先順位が明確に:
診断指標と因子で“いま最優先の問題”が浮かび、先にやるべきケアが決まる。 -
ケアの質が安定:
同じ診断なら介入(NIC)と成果(NOC)が紐づくため、経験差によるブレを縮小。 -
申し送りがクリア:
診断名+根拠+目標で、短時間でも本質が伝わる。 -
評価・振り返りがしやすい:
成果指標で改善/未達が見える化。次の一手が打ちやすい。 -
多職種連携に強い:
看護の視点が言語化され、医師・リハ・薬剤と方向を合わせやすい。
“診断がズレない”ためのミニチェック❤(現場でサッと)
-
定義に患者の状態が本当に当てはまっている?
-
診断指標(決め手になる特徴)は十分そろっている?
-
関連因子/危険因子は根拠と一致?思い込みが混ざっていない?
-
優先度は安全・生命・苦痛・回復阻害の観点で妥当?
-
PESの文(問題・関連因子・根拠)が一文で論理的につながっている?
ミニケース例🩺
-
せん妄リスクが疑われる高齢患者:夜間不穏・環境変化・睡眠障害の既往あり
→ 〈急性の錯乱リスク〉を設定し、環境調整・睡眠衛生・家族関与のNICと、落ち着き・睡眠のNOCで評価。 -
COPD増悪後の退院前:喀痰増加・酸素化低下・自己管理不安
→ 〈非効果的な気道クリアランス〉+〈ヘルスリテラシー不足〉。
呼吸介助手技教育・自己管理支援で、SpO₂や咳嗽有効性、自己効力感を追う。
NANDAは“書類上の決まり”ではなく、「最短で最善のケア」に導くための地図です。
新人さんもベテランさんも、同じ地図を使うからこそチームで強くなれますよ❤
「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」
「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!
くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。
🏷️ NANDA-Iの診断ラベルをマスターしよう|13領域と3つの診断タイプ
「診断ラベルって多すぎて覚えられない…」
「実在型とかリスク型って何が違うの?」
そんなふうに感じることはありませんか?🌱
ここでは、NANDA-Iが定める13の領域分類と3つの診断タイプを整理して、ラベル選びの基本をわかりやすくご紹介します❤
NANDA-Iの13領域を一覧でチェック
NANDA-Iの診断ラベルは、患者さんの健康状態や生活に関わる13の大きな領域に分類されています。
一覧にすると次のようになります👇
| 領域番号 | 領域名 | 内容のイメージ |
|---|---|---|
| 1 | 健康増進 | 健康維持・セルフケアの促進 |
| 2 | 栄養 | 摂食・代謝・体重変化 |
| 3 | 排泄と交換 | 尿・便・呼吸・循環のバランス |
| 4 | 活動/休息 | 活動耐性・睡眠・エネルギー |
| 5 | 知覚/認知 | 感覚・認知・学習能力 |
| 6 | 自我認識 | 自尊心・自己概念 |
| 7 | 役割関係 | 家族・職業・社会的役割 |
| 8 | セクシュアリティ | 性的機能・親密さ |
| 9 | 対処/ストレス耐性 | ストレス反応・対処能力 |
| 10 | 原則・価値観 | 信念・意思決定・人生観 |
| 11 | 安全/防御 | 感染・転倒・外傷リスク |
| 12 | 快適 | 痛み・かゆみ・不快感 |
| 13 | 成長/発達 | 発達課題・ライフステージ |
ポイント❤
-
「患者さんの困りごと=どの領域に属するか」を意識すると、診断ラベルを探すときに迷いにくくなります。
-
実習や現場では「11 安全/防御」「2 栄養」「4 活動/休息」がよく使われやすい領域です。
実在型・リスク型・ヘルスプロモーション型の違い
NANDA-Iの診断ラベルは、3つのタイプに分かれています。
| タイプ | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| 実在型 | すでに起こっている人間反応 | 「非効果的な気道クリアランス」「不眠」 |
| リスク型 | 将来起こる可能性が高い反応 | 「転倒リスク」「感染リスク」 |
| ヘルスプロモーション型 | よりよい健康に向けた行動を促進 | 「ヘルスリテラシー向上の意欲」 |
理解のコツ❤
-
実在型=今ある問題をケア
-
リスク型=予防する視点
-
ヘルスプロモーション型=強みを伸ばす支援
診断ラベルの選び方と現場での使い分け
「どのラベルを当てればいいのか迷う…」そんなときは以下の流れをチェック✅
-
アセスメント結果を整理(症状・行動・環境)
-
診断指標と一致するか確認
-
関連因子/危険因子と結びつけられるか
-
領域→タイプの順で絞り込む
-
優先順位をつけて記録
具体例❤
-
COPDの患者さんで痰排出が不十分 → 「非効果的な気道クリアランス(実在型)」
-
手術後で筋力低下・環境変化 → 「転倒リスク(リスク型)」
-
糖尿病患者さんが自己管理に前向き → 「ヘルスリテラシー向上の意欲(ヘルスプロモーション型)」
🔍 診断指標・関連因子・危険因子ってどう違う?使い分けのコツ
「診断指標?関連因子?危険因子?…どれがどれだっけ?」と混乱しやすい部分ですよね💦
この章では、それぞれの定義と違いを整理して、現場での使い分けのコツを一緒に確認していきましょう❤

診断指標とは?観察項目のチェックポイント
診断指標は、その看護診断を裏づける“特徴的なサインや症状”です。
つまり「このサインがあるから、この診断が成り立つ」と言える証拠の部分なんです🔍
例
-
「不眠」 → 入眠困難、中途覚醒、日中の疲労感
-
「非効果的な気道クリアランス」 → 喀痰排出困難、湿性ラ音、SpO₂低下
👉 ポイント:診断指標がなければ、その診断は立てられません。
関連因子と危険因子の役割の違い
次に混同しやすいのが、この2つ。
表にまとめて違いを見てみましょう📊
| 用語 | 定義 | 例 |
|---|---|---|
| 関連因子 | すでに起こっている問題を説明する“原因” | 喫煙習慣、換気不良、誤嚥による気道クリアランス不良 |
| 危険因子 | 将来的に問題が起こる可能性を高める“要因” | 高齢、筋力低下、薬剤による眠気=転倒リスク要因 |
理解のコツ❤
-
関連因子=今起きている問題の背景
-
危険因子=これから起きるかもしれない問題の芽
看護アセスメントにどう活かす?見落とし防止のヒント
診断指標・関連因子・危険因子は、アセスメントのどこで使うかがカギです🔑
活用の流れ
-
アセスメントで得たデータを「症状(指標)」「原因(関連因子)」「リスク(危険因子)」に分ける
-
診断ラベルを当てはめるときに、この3つを必ず確認する
-
PES方式(問題・関連因子・症状)に落とし込むと、診断文がブレにくくなる
実例:褥瘡リスクの患者さんに当てはめてみよう
-
診断ラベル:皮膚統合性障害リスク
-
危険因子:長時間の臥床、低栄養、循環不良
-
関連因子:まだ“症状”は出ていないため記載なし
-
診断指標:リスク診断なので症状はなし
👉 こう整理すると、記録も明確になり、多職種との情報共有もスムーズになりますよ😊
📝 NANDA看護診断の書き方完全ガイド|PES方式と具体例
「診断ラベルは選べたけど、どう文章にすればいいの?」そんな声をよく耳にします👂
ここでは、NANDA看護診断の書き方の基本であるPES方式を中心に、具体的な流れと新人さんがつまずきやすいポイントを整理します❤
PES方式とは?基本の型を理解しよう
PES方式は、NANDA看護診断を書くときの標準的なフォーマットです。
-
P(Problem/問題):診断ラベル
-
E(Etiology/関連因子や危険因子):原因・背景
-
S(Symptoms/診断指標):特徴的なサインや症状
👉 この3つを1つの文につなげることで、診断の根拠が明確になります。
例文
-
「非効果的な気道クリアランス(P) は、喀痰排出困難と換気不良(E) に関連し、湿性ラ音とSpO₂低下(S) によって示される」
新人でも迷わない!看護診断の書き方ステップ
-
アセスメントデータを整理(症状・背景・リスク因子を分ける)
-
診断ラベルを選ぶ(NANDA分類から)
-
PESの形に当てはめる
-
優先順位を考える(安全・生命危機 → 苦痛 → 生活支援)
-
ケア計画にリンク(NICやNOCをセットで考える)
チェックリスト❤
-
P=必ずNANDAの診断ラベルを使用している?
-
E=曖昧な表現(「なんとなく」「多分」など)を避けている?
-
S=観察できる具体的な指標を入れている?
よくある間違いと修正の仕方
看護学生さんや新人ナースにありがちな間違いを整理しました👇
| よくある間違い | 修正ポイント |
|---|---|
| Pに「呼吸困難あり」と書いてしまう | → 正しくは「非効果的な気道クリアランス」などNANDAの診断ラベルを使う |
| Eに「高齢だから」とだけ書く | → 「加齢に伴う筋力低下による呼吸筋の弱さ」など因果を明確にする |
| Sを省略してしまう | → 「SpO₂ 90%、湿性ラ音聴取」など客観的指標を必ず記載する |
記録で押さえるべき3つのポイント
-
一貫性:アセスメント→診断→ケア計画の流れが矛盾していないか
-
具体性:誰が読んでも同じ状況をイメージできる記載か
-
継続性:次の勤務者や他職種がすぐに行動に移せるか
👉 これらを意識すると「読む人に伝わる看護診断」が書けるようになりますよ😊
🆕 2024-2026版のNANDA改訂ポイントまとめ
NANDA-Iは2年ごとに改訂され、医療や社会の変化にあわせて診断ラベルが更新されています📚
「最新版はどこが変わったの?」「実際に現場でどう関わるの?」と気になる方も多いですよね。
ここでは、2024-2026版での追加・改訂・削除ポイントを整理し、看護師が押さえておくべき影響を解説します❤
新しく追加された看護診断
今回の改訂では、社会的背景や新しい健康課題に対応した診断がいくつか追加されています✨
例(イメージ)
-
〈孤独感のリスク〉:高齢化や社会的孤立の増加を反映
-
〈情報過多による健康行動の混乱〉:デジタル時代の健康情報の影響
-
〈気候変動に関連する健康リスク〉:災害や熱中症リスクの増加
👉 新しい診断は、これまで表現しづらかった患者さんの問題を標準化された言葉で伝えられる点が大きなメリットです。
改訂・削除された診断とその背景
一方で、曖昧だった診断ラベルや重複していたものは修正・削除されました。
例(イメージ)
-
「非効果的なコーピング」と「無効なストレス対処」の統合
-
重複していた「皮膚統合性障害」関連ラベルの整理
背景❤
-
実際の臨床現場での使用頻度や妥当性を分析し、より現場で使いやすい形に統一
-
教育現場でも学習しやすいように、用語をシンプル化
改訂内容が現場に与える影響とは?
「診断が増えたり減ったりしたら、どうすればいいの?」と不安に思うかもしれません。
でも大丈夫😊 改訂はより臨床に即した実用性の向上が目的なんです。
現場でのメリット
-
新しい診断により、患者の状態をより正確に表現できる
-
用語の整理で、新人〜ベテラン間の理解が統一しやすい
-
教育資料や電子カルテも順次対応していくため、実習・臨床での混乱が減る
👉 つまり改訂は、「診断を選ぶ迷いを減らし、現場での共有をスムーズにする」方向に働いているんです❤
🏥 ケーススタディで学ぶ!現場で役立つNANDA看護診断の実践例
「実際の患者さんにどう当てはめたらいいの?」
「教科書だと分かるけど、現場で迷ってしまう…」
そんな声をよく聞きます👂
ここでは、高齢者・小児・精神科の3つのケースを例に、アセスメントから診断→ケア計画→評価までの流れをイメージできるようにまとめました❤
高齢者患者のケース:転倒リスクの診断とケア
事例:80歳女性、骨粗鬆症あり。入院中に筋力低下とふらつきが見られる。
-
診断ラベル:〈転倒リスク〉
-
危険因子:高齢、筋力低下、既往歴(骨粗鬆症)
-
ケア計画(NIC):環境整備(ベッド柵・ナースコール)、筋力維持のためのリハビリ介入
-
評価(NOC):転倒発生の有無、歩行時の安定性
👉 ポイント:予防的に働きかけることで、転倒事故を防ぐことができます。
小児患者のケース:不安・恐怖へのアプローチ
事例:7歳男児、入院・点滴治療を経験中。「痛いのいや!ママから離れたくない」と泣き叫ぶ。
-
診断ラベル:〈不安〉
-
関連因子:年齢に応じた理解不足、母親と離れる不安
-
診断指標:泣き叫ぶ、表情の緊張、拒否的態度
-
ケア計画(NIC):遊びを取り入れた説明、母親の付き添い、安心できる環境づくり
-
評価(NOC):処置時の落ち着き、母親と離れた時間の適応度
👉 ポイント:小児は「安心感の提供」がケアの中心です❤
精神科患者のケース:孤独感とセルフケア不足
事例:40歳男性、うつ症状により引きこもり傾向。日常生活でセルフケア低下。
-
診断ラベル:〈孤独感〉+〈セルフケア不足〉
-
関連因子:社会的孤立、気分低下
-
診断指標:交流の欠如、食事・清潔の自己管理不足
-
ケア計画(NIC):グループ活動への参加支援、セルフケアの段階的指導
-
評価(NOC):交流頻度の増加、セルフケア自立度
👉 ポイント:心理社会的な側面を見逃さず、生活の質を支えるケアが大切です。
ケース別に見る「アセスメント→診断→ケア計画→評価」
どのケースも共通する流れは以下の通りです👇
-
アセスメント:患者の状態を多角的に把握
-
診断:NANDAラベル+因子+指標で整理
-
ケア計画:NICに基づき具体策を立案
-
評価:NOCで成果を測定
👉 まとめ❤
この一連の流れを押さえれば、患者さんにあった診断とケアをスムーズに結びつけられます。
✅ まとめ|NANDA看護診断を現場で活かすためのチェックリスト
ここまで、NANDA-I看護診断の定義から診断ラベル・因子の使い分け、PES方式の書き方、2024-2026版の改訂点、そして実際のケースまで見てきました📚
最後に、明日から実践できるチェックポイントをまとめます❤
ポイント枠
今日の学びポイント振り返り👉
-
看護診断=人間の反応を言語化するものであり、医師の診断とは目的が異なる
-
13領域・3つの診断タイプを理解すると、ラベル選びがスムーズになる
-
診断指標・関連因子・危険因子を正しく区別することが、診断のブレ防止につながる
-
PES方式を使えば、根拠のある診断文を書ける
-
2024-2026版改訂では新しい健康課題に対応した診断が追加され、現場での実用性が向上
診断がずれないための5つの確認ステップ
-
定義と患者の状態は一致しているか?
-
診断指標は十分に揃っているか?
-
関連因子/危険因子は根拠と合致しているか?
-
優先順位は「安全・生命・苦痛・生活支援」の順で妥当か?
-
PES方式で一文として論理的に書けているか?
👉 この5つを押さえれば、誰が読んでも納得できる診断になりますよ😊
明日から実践できる!新人〜ベテラン共通のヒント
-
新人さんへ❤:診断ラベルを丸暗記するより、「患者の反応=どの領域?」と考えるクセをつけてみましょう。
-
中堅ナースへ❤:ケア計画とNOC評価までを意識して、次につながる診断に育てましょう。
-
ベテランさんへ❤:チームや後輩への教育にNANDA診断を活用すると、共通言語として役立ちます。
✨ まとめ
NANDA看護診断は、「ただの形式」ではなく、患者さんに合った最適なケアを導く羅針盤です。
新人さんもベテランさんも、この共通言語を味方につけて、日々の実践に自信を持って取り組んでくださいね❤
<参考・引用>
頑張れ看護学生
公益社団法人日本看護科学学会
レヴァウェル看護