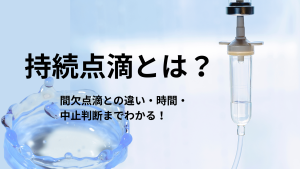実習で“あれ、手洗いどうやったっけ?”と焦ったこと、ありませんか?
「患者さんに触れる前に手を洗わなきゃ」と思っていても、つい時間がなくて流してしまった…そんな経験は多いですよね。
この記事では
- 「衛生学的手洗い」が何か
- その目的と適切なタイミング
- 実践で使える手順・観察ポイント
が分かりますよ♪
結論👉
衛生学的手洗いを“ただの手洗い”で終わらせず、目的・適応・手順を意識することで、感染予防の基本を看護ケアの中で確実に実践できます。
この記事では、看護実習や臨床場面で即活用できる衛生学的手洗いについてやさしく解説します😊
衛生学的手洗いとは何か?
まずは「衛生学的手洗い」が何を指すのか、どんな位置付けなのかを明らかにしましょう。
手洗いの種類と位置付け
手洗いには大きく以下の3種類があります。
- 日常手洗い:一般的な手洗い。石けんと流水で、軽い汚れや通過菌を除去します。
- 衛生学的手洗い:患者に触れるケアの前や無菌操作の前などに行う、石けん+流水(または消毒剤)による手洗いです。
- 手術時手洗い:手術前などに行う、より徹底した手洗い・消毒法です。

どの段階の手洗いかを理解することが大事。
衛生学的手洗いの目的
衛生学的手洗いの主な目的は、医療従事者の手指を通じた交差感染や接触感染を防ぐことです。
具体的には、手指に付着した通過菌(=一時的に付着した菌)を除去し、患者や医療環境への微生物伝播を減らすために行います。
適応・タイミング

衛生学的手洗いを行うべき場面として、例えば以下があります:
- 患者に直接触れる前・触れた後
- 無菌操作(カテーテル挿入・創処置など)の前
- 体液・分泌物・粘膜・傷のある皮膚に触れた後、およびその後に他の部位を触る前
- 患者の周辺物品(医療機器・床頭台・ベッド柵等)に触れた後
手が目に見えて汚れている場合は、特に石けん+流水での手洗いが推奨されます。
手順とポイント:図で理解
ここでは、衛生学的手洗いを実践するための手順と、細かいポイントを丁寧に解説します。
必要な物品・準備
手洗い前の準備として、以下の点に注意しましょう:
- 指輪・腕時計・ブレスレットなどの装身具を外す。これらの裏側や隙間に菌が潜りやすいです。
- 長袖の場合は袖をまくる。手首まで洗えるようにします。
- 液体石けん(抗菌性が望ましい)+流水が基本。固形石けんは細菌汚染の頻度が高く避けた方がいいとされています。
- ペーパータオルまたは使い捨てのタオルを用意。共用タオルは菌の伝播源になります。
手洗いの手順(ステップ別)
以下の手順に沿って洗いましょう。

- 両手を手首まで流水で十分に濡らす。
- 液体石けんを適量(3〜5 mL程度)とり、泡立てる。
- 手のひらと手のひらをすり合わせる。
- 片方の手のひらで反対側の手背(手の甲)を洗う。
- 親指をもう片方の手で包み、もみ洗いする。
- 指先をもう片方の手のひらで立てるようにして洗う。
- 指を組んで指間部を洗う。
- 両手の手首を洗う。
- 流水でしっかり泡と汚れをすすぐ。
- ペーパータオルで手のひら→指先→手首の順に水気を押さえて拭く。濡れた手は微生物の伝播リスクが高まります。
- 蛇口を使ったなら、拭いたペーパータオルを使って蛇口を閉める。蛇口は菌が付着しやすい場所だからです。
洗い残しが起きやすい部位と改善策
実際に洗い残しが多い部位を把握しておくと、洗い残しが少なくなりますよ。

| 部位 | 理由 | 改善策 |
|---|---|---|
| 指間部 | 指を交差させて擦る回数が少ない | 指を組んで丁寧にもみ洗いを意識する |
| 親指 | 親指を包んで洗う動作が省略されがち | 片手で親指をしっかり包んでねじり込むように洗う |
| 手首 | 「手首まで洗う」という意識が弱い | 手首を手のひらで包んで回すように洗う |
| 手背・甲の側部 | 手の凹凸(掌紋・甲部)を意識せず洗ってしまう | 甲側も手のひらでこすり洗い・側面も忘れずに |
手指消毒剤との使い分け・手荒れ対策
設備・状況によっては石けん+流水ではなく、アルコール擦式手指消毒製剤が使用されることもあります。
ポイント:
- 目に見える汚れや体液・分泌物がある場合は、まず石けん+流水。
- 目に見えない汚れで、手洗いの設備がない/時間がない場合はアルコール製剤を適切量(約3 mL)使って20〜30秒擦り込む。
- 手荒れのリスクを考慮し、保湿剤入りの消毒剤やハンドクリームの併用が推奨されます。
実践場面から見る看護の視点
ここからは、看護学生・新人看護師として、臨床・実習場面で使える視点をお伝えします。
ケア前後・「一処置一手洗い」を守る意味
看護ケア・ケア操作・処置の前後には、必ず手洗いや手指衛生を行う「一処置一手洗い」が原則です。
ケア前に手を洗ったとしても、患者に触れた後環境を移動して次のケアを行う時に手指に菌が付着していれば交差感染のリスクになります。
例えば、体温測定をした後、そのまま点滴の準備をしてしまう…そんな時こそ、手洗いのタイミングです。
手袋装用時・患者環境を移動する時の注意点
手袋を着用していても、手指衛生の代わりにはなりません。
手袋の内側に汗や菌が残ること、脱着時に手が汚染されることがあります。
また、患者さんのベッド柵を触った後に次の患者環境に移動した場合、手洗い・手指消毒が必要です。
環境から環境へ移る際の“見えない汚染”を意識しましょう。
看護学生・新人が陥りがちな課題(実習での洗い残し・習慣化不足)
研究では、看護学生でも4年次生でも、学年による衛生学的手洗いの行動差・洗い残し差が有意に見られなかったという報告があります。
これは“知っている”と“確実にやっている”にギャップがあることを示しています。
だからこそ、以下のポイントを意識しましょう:
- どこを洗うか「意識」してから手を動かす
- 慣れてきても、手順を省略せず丁寧に行う
- 実習で「洗い残しがないか」「どこを意識して洗うか」を振り返る習慣を持つ
チーム/施設で手指衛生を促す環境づくり
手洗いや手指消毒が習慣化されるには、個人の意識だけでなく、環境・組織風土も大きく関係します。
具体的には:
- 各病室入口・患者ベッド近くに手指消毒剤が設置されている
- ペーパータオルや液体石けんが常に補充されている
- 上司・先輩から「手指衛生いいね」「今のタイミングで手洗いできてたね」という声掛けがある
- 手指衛生の使用量・回数をスタッフで共有し、達成度をフィードバックする
看護学生として実習先で手指衛生の環境を観察し、「この部署はどう整っているか?」を意識してみると学びになります。
この記事のまとめポイント
この記事での再重要部位👉
- 衛生学的手洗いとは、目的と位置付けを理解すること。
- 手順・洗い残しが起きやすい部位・ポイントを押さえて丁寧に実践すること。
- 実習・臨床場面で「一処置一手洗い」を習慣化し、環境・チームで支えること。

毎回「今、このタイミングで手指衛生をする意味は何か」を自問して、丁寧に実践していきましょうね。
商品検査センター