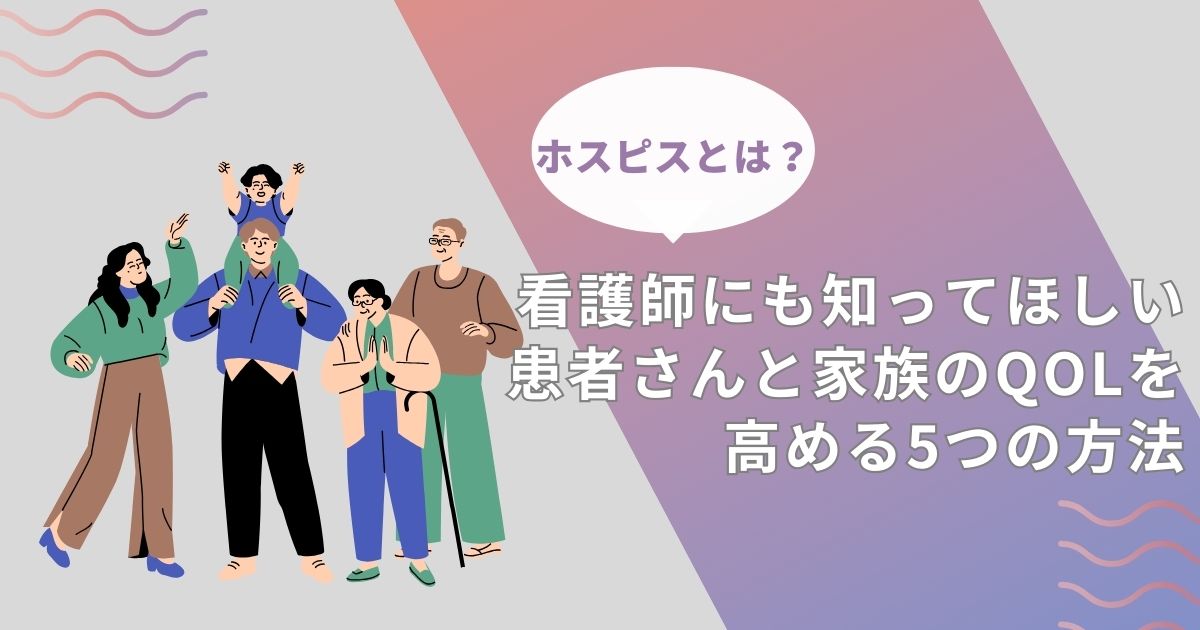
ホスピスや終末期看護について、興味を持っている方は多いと思います。
特に看護師の皆さんにとって、終末期の患者さんやそのご家族に寄り添うことは、非常に重要な役割です。
しかし、ホスピスがどのような場所で、どのようなケアが行われているのか、具体的にイメージできていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、ホスピスや終末期看護の基本についてお話しします。
看護師としての視点から、患者さんやご家族にどのように寄り添うことができるのか、一緒に考えていきましょう。
またホスピスに対して検討している患者さんや家族の方もこの記事を通して「ホスピスとはなんなのか」を理解してみませんか?

ホスピスとは何か?
ホスピスとは、終末期の患者さんが人生の最期を穏やかに過ごすために、身体的・精神的な苦痛を和らげるケアを提供する施設です。
具体的には、がんや難病などで治癒が難しい患者さんに対して、痛みや不安を軽減し、尊厳を持って生活できるようサポートする施設を指します。
ホスピスケアの基本理念
最後の瞬間まで患者さんがその人らしく快適に過ごせるようにサポートするために多職種チームで患者さん、家族に寄り添います。

終末期医療との違い
終末期看護とホスピスは、どちらも患者さんの苦痛を和らげ、尊厳を持って最期の時を過ごすことを目的としていますが、いくつかの重要な違いがあります。
終末期には治療も行いますが、ホスピスは苦痛の軽減に特化しています。
ホスピスの種類:緩和ケアとホスピスの違い
「緩和ケア」と「ホスピス」とありますがどちらも辛いこと(痛みなど)を軽減させてくれる場所というイメージがありますよね。
しかし、この2つが分けられているのはなぜなのでしょう?

緩和ケア病棟の特徴
「緩和ケア病棟」と「ホスピス」の決定的な違いは、入院期間の制限と医療体制です。
緩和ケア病棟は医師が常駐し、短期集中で症状を緩和し(治療を行うこともあり)できる限り元の生活を行えるようにサポートすることを目的としていますが、ホスピスは看護職が中心となり、在宅ではなくホスピス専門施設に入居した場合でも入院期間に制限がなく、患者さんが自分らしい生活を重視したケアを受ける場です。
医療体制とケア内容
ホスピス施設では緩和病棟とは違い、医師が常駐はしておらず訪問診療医が診察を行うことが多いようです。もちろん在宅ホスピスですと往診がメインになりますね。
よって、看護師や介護士が中心となりケアを行います。
看護師は医師からの指示に基づき必要時に症状緩和のための治療を行います。
具体的にどのようなことが行われているのか確認してみましょう。
- 身体的ケア
ホスピスでは、患者さんの痛みや不快感を軽減するために、以下のような身体的ケアが提供されます。
- 鎮痛剤や医療用麻薬の投与
- 酸素吸入や点滴
- 食事や入浴、排泄などの日常生活の介助
- マッサージや清拭などのリラクゼーションケア
- 精神的ケア
患者が抱える不安や恐怖を和らげるために、心理士や宗教家によるカウンセリングが行われます。また、レクリエーション活動や家族との交流を通じて、精神的な安定を図ります。 - 社会的ケア
経済的な問題や相続問題など、患者や家族が抱える社会的な悩みを解決するために、ソーシャルワーカーがサポートを行います。手続きの代行や介護サービスの手配も含まれます。 - 個別ケア
患者一人ひとりの希望に応じた個別のケアが行われ、例えば、好きな食べ物を食べたり、ペットと過ごしたりすることが可能です。ペットと過ごすことができるのはホスピスならではですよね。
ホスピスケアの対象者
ホスピス施設にも期間に特に厳密な期間は設けられてはいませんが、誰でもホスピスケアを受けられる対象になるわけではありません。
そこには条件がありますので見てみましょう。
- 対象者
- 余命が限られている患者さん
ホスピスは、主に余命が6ヶ月以内と予測される患者さんを対象としています。これは、医師による診断が必要であり、患者さんの病状が進行していることが前提です。 - 治癒を望まない患者
ホスピスケアは、治癒を目的とした積極的な治療を行わず、痛みや苦痛の緩和に重点を置くため、患者さん自身が治療を望まないことを理解している必要があります。患者さんが自らの病状を理解し、穏やかに最期を迎えたいと希望することが重要です。 - 特定の疾患を持つ患者
ホスピスの対象には、末期がん患者や、エイズ(後天性免疫不全症候群)などの治癒が見込めない疾患を持つ患者さんが含まれます。これらの疾患により、患者さんはホスピスケアを受けることができますが、他の病気でも医師が適切と判断すれば入院が可能です。
以上がホスピスケアを受けられる人の条件となりますが、医師の診断はもちろんのこと、ホスピスケアを希望するかどうか、患者さんや家族の判断も大きな鍵となります。
余命半年と診断されてからホスピスを希望するかしないか。
またホスピスケアをどこで受けるかを判断しなければなりません。
満足のいくケアを受けるためには早めに検討する必要があることがわかりますね。
在宅ホスピス導入の背景
ホスピスといっても場所は病院や施設だけではありません。
2007年に厚生労働省が策定した「がん対策推進基本計画」では、緩和ケアの重要性が明記され、在宅医療の推進に向けた診療報酬の改定が行われました。
これにより、在宅ホスピスケアの提供が医療制度として認められ、医療機関や看護師が在宅でのケアを行いやすくなりましたが、その制度の浸透には時間がかかり、在宅ホスピスも取り入れられるようになったのは、つい最近のように思います。
近年、患者さんやその家族が「自宅で最期を迎えたい」と考える傾向が強まっています。
日本財団の調査によると、約58.8%の人が自宅での看取りを希望しており、その理由には「自分らしく居られる」「住み慣れているから」といった意見が多く寄せられています。
このようなニーズの高まりが、在宅ホスピスの普及を促進しているのです。
在宅ホスピスの特徴
特徴といえばなんといっても先述した通り、「自宅で最期を迎えたい」というニーズを叶えることができることでしょう。
近年、在宅ホスピスは、主流になりつつあります。
政府も在宅医療の推進を図っており、地域包括ケアシステムの強化が進められています。
このような背景から、在宅ホスピスの需要が増加しており、医療機関や介護施設が連携して在宅でのケアを提供する体制が整いつつあります。
また、在宅ホスピスの普及には、専門的な知識と技術を持つ看護師や介護職の育成も進められています。
日本財団などの団体が、ホスピスケアに特化した研修プログラムを提供し、専門性の高い看護師が増えているのも特徴です。
家族のサポート体制
在宅ホスピスにおける家族へのケアは、患者の緩和ケアと同様に重要な要素であり、家族が抱える心理的、身体的、社会的な負担を軽減するための多様な支援が行われています。
具体的には以下のようなケアが提供されています。

ホスピス施設を選ぶ際のポイント:患者と家族のニーズに応じた選択
1人暮らしの方や、身近に看護をしてくれる方がいない場合には施設を選択することもあるでしょう。
施設選びのポイントもまとめてみましたので参考にしてみてください。

施設選びの基準
- スタッフの専門性
施設が提供するケアの内容や質を確認しましょう。医療スタッフの専門性や経験、ケアの方針、患者のニーズに応じた個別のケアプランがあるかどうかをチェックします。また、緩和ケアの専門医や看護師が常駐しているかも重要です。
- 環境と設備
ホスピスの立地は重要な要素です。家族が通いやすい場所にあるか、交通手段が便利かを確認しましょう。特に、訪問看護や面会が頻繁に行われる場合、アクセスの良さは大きなポイントになります。
施設の雰囲気や環境も大切です。訪問してみて、清潔感や居心地の良さ、スタッフの対応などを実際に感じることが重要です。患者がリラックスできる環境であるかどうかを考慮します。
患者の希望を尊重するためのコミュニケーション
じわじわと悪化する病気もあれば見つかった時には手遅れとなる病気も残念ながらあります。
また余命を診断され、ホスピスの対象になった場合の予測余命は半年という短さもあり、患者さん本人も家族の方もショックを受け判断が難しくなることと思います。
そのような現場を多く看護師としてみてきた立場としておすすめさせていただきたいのがエンディングノートです。
「縁起でもない!」と怒られそうですが、実際にわたしもエンディングノートを用意しています。
年齢に関係なく、病気とも関係なく、「死」というものは生きている限りいつ起こってもおかしくないものなのです。
昨日まで、極端に言えば、今さっきまで元気にしていたのに急に倒れることもあります。
そして余命宣告を受けることもあるでしょう。
その時、患者さんはもちろんのこと、家族の方も冷静に残された時間をどう使うかについて判断できるでしょうか?
「死」というものはどんな人にも必ず訪れるものです。
「死」を受け止めるには多くの段階を経てやっと受け入れることができるものです。
その間にも時間はどんどんと過ぎていきます。
だからこそ、エンディングノートを私は推奨しています。
家族との話し合いの重要性
エンディングノートのことについて触れましたが、それは家族同士でぜひ話し合ってほしいと思っています。
例えば、私はですが、延命はしたくない、検体もお断り、余命宣告された時はすぐに知らせてほしいと家族に伝えてありますし、市販のノートにも書いてあります。
自治体や葬儀場などで配布されていますが、私には財産もありませんし、家族に残すものも何もありません。
なので、市販のノートに伝えたいことだけインターネットを参考にして書き残しています。
私は子育て真っ最中ですので子供への残したものやメッセージも残していますが、子供が大きくなったり、また仕事を辞めた場合には内容も変わることでしょう。
エンディングノートは法的な縛りはありません。
簡単に言うと遺言書ではないのです。
なので何回でも書き直しができますし、気軽に希望を伝えることができます。
特に余命宣告については迷うことが多いと思います。
しかしその迷っている間にも刻々と時間は過ぎていくので、一度話し合いだけではなくノートなどに書いて残しておくのをおすすめします。
QOLを高めるための方法:看護師の役割
ここからは緩和ケア、ホスピスに興味のある看護師向けの内容になります。
患者さん、家族の方も是非ご覧いただけたらと思います。

身体的苦痛の管理
終末期において患者さんが一番辛いと思うのは身体的苦痛でしょう。
その際にどのようにチームで継続的な看護をおこなっていくかがポイントになります。
人それぞれに痛み耐性が違うように、苦痛の受け取り側にも軽度と取るか中程度と取るかばらつきが出てくる可能性もあるでしょう。
苦痛緩和にはスケールを使用し、患者さんに「今の苦痛の程度はどの程度なのか」を判断してもらう必要があります。
有名なところで言うとペインスケールがありますね。
そのようなものを使用し、客観的に判断するようにしましょう。
また、苦痛に対しての反応も同じスケールを使用しどの程度改善したのかを記録しましょう。
精神的サポートの提供
患者さんは身体的な苦痛のみではなく精神的にも助けを必要としていることがほとんどです。
看護師が患者に対して行える精神的なケアは多岐にわたります。
特に終末期の患者に対しては、身体的なケアだけでなく、精神的なサポートも非常に重要です。
以下に、具体的な精神的ケアの方法をあげますね。
- 傾聴
患者さんの話をじっくりと聞くことは、精神的なケアの基本です。
患者が抱える不安や恐れ、悩みを受け止めることで、患者さんが自分の気持ちを表現する機会を与え、心の負担を軽減しやすくなります。
- 情報提供
患者さんが自分の病状や治療について理解できるように、わかりやすく説明します。
情報を得ることで、患者さんは自分の状況を把握し、安心感を得ることができます。
また、今後の見通しやケアの方針についても説明し、患者さんの不安を和らげるようにしましょう。
ただし、情報を理解し受け入れる時間は患者さん個々に違いますし、知りたくないという人もいますので家族などと話し合いを取りながら進めていきましょう。
- 精神的サポート
患者さんが抱える不安や恐れに対して、励ましや慰めの言葉をかけることが重要です。
患者さんの感情を尊重し、必要に応じて適切な言葉をかけることで、心の支えとなります。
- リラクゼーション法の指導
ストレスや不安を軽減するためのリラクゼーション法(深呼吸、瞑想、マインドフルネスなど)を教えることができます。
これにより、患者さんは自分で心を落ち着ける方法を学び、精神的な安定を図ることができる可能性があがります。
- 家族とのコミュニケーション支援
患者さんとその家族とのコミュニケーションを促進することも重要です。
家族が患者さんの気持ちを理解し、支え合うことができるように、コミュニケーションの橋渡しを行います。
- 趣味や活動の支援
患者さんが好きな趣味や活動を続けられるように支援します。
アートセラピーや音楽療法など、患者が楽しめる活動を提案し、心が安らぐような時間を作れるよう努力しましょう。
- グリーフケアの提供
終末期の患者さんは、死に対する恐れや悲しみを抱えることが多いです。
看護師は、患者さんがその感情を表現できるようにサポートし、必要に応じてグリーフケアを提供します。
- 生活の質の向上
患者が快適に過ごせるように、環境を整えたり、身体的な苦痛を軽減するためのケアを行います。
身体的な快適さが精神的な安定にもつながることもあります。
- 文化的・宗教的な配慮
患者さんの文化的背景や宗教的信念を尊重し、それに基づいたケアを提供します。
信仰や価値観に寄り添うことで、患者の心の安らぎを得る手助けをします。
これらの精神的なケアを通じて、看護師は患者が安心して過ごせる環境を整え、心の健康を支える重要な役割を果たします。
患者の個々のニーズに応じた柔軟なアプローチが求められます。
家族への支援と教育
家族への心理的サポートは、在宅ホスピスやホスピス施設において非常に重要な要素です。
患者の終末期において、家族は多くのストレスや不安を抱えることが多いため、適切なサポートが必要です。
以下に、家族への心理的サポートの具体的な提供方法をあげますね。
- カウンセリング
専門の心理士やソーシャルワーカーによるカウンセリングが行われます。
家族が抱える感情や不安について話す機会を提供し、感情の整理を助けます。
個別のカウンセリングだけでなく、家族全体を対象としたグループセッションも行われることがあります。
- 情報提供
患者の病状やケアについての情報を提供することで、家族の不安を軽減します。
医療スタッフが患者の状態や今後の見通しについて説明し、家族が理解を深める手助けをします。
情報を得ることで、家族はより安心して患者を支えることができます。
- 感情の共有
家族が抱える感情を共有する場を設けることも重要です。
ホスピスでは、家族同士が体験を語り合う機会を提供し、共感や理解を得ることで孤独感を軽減
します。これにより、家族は自分の感情を受け入れやすくなります。
- ストレス管理の技術
ストレスや不安を軽減するための技術や方法を教えることも行われます。
リラクゼーション法やマインドフルネス、呼吸法など、心の健康を保つための具体的な手法を学ぶことで、家族は自分自身のケアも行いやすくなります。
- サポートグループ
同じような状況にある家族同士が集まるサポートグループが提供されることがあります。
ここでは、経験を共有し、互いに支え合うことで、心理的な負担を軽減することができます。
- 介護者への配慮
家族が介護者としての役割を果たす中でのストレスや疲労に対しても配慮が必要です。
定期的なチェックインや、必要に応じて短期入所施設やレスパイトケアを提案することで、家族が自分自身の時間を持つことを促します。
- 悲嘆のケア
患者の死後も、家族への心理的サポートは続きます。悲嘆のプロセスを理解し、必要に応じてグリーフケアを提供することで、家族が喪失を乗り越える手助けをします。
これらの方法を通じて、ホスピスは家族が抱える心理的な負担を軽減し、より良いサポートを提供することを目指しています。
家族が安心して患者を支えられるよう、包括的なサポートが重要です。
ホスピス看護師のキャリアパスと将来性
2025年問題をみなさんご存知でしょうか?
高齢社会、政府の自宅での医療促進によって看護師としての働き方も大きく変わるといった内容です。
慢性期は、今後大幅に病床が減少し、在宅看護に移行していくと予測されています。
また急性期も縮小され、残るのは3次救急が中心となり、一部の分野では看護師が余り、一部の分野では足りなくなるという予想が以前からありました。
またコロナ禍もあり、新人看護師たちはペーパーペイシェントで育って来ており、今の看護業界は大きく変化しようとしています。
ホスピス看護師としてのキャリアアップ方法
ホスピス看護師はこれから訪問看護師と同様に需要が多くなる分野とされています。
また、在宅看護師としてホスピス看護師として患者さんと関わってくることもあるでしょう。
看護師としての今までのスキルを活かし、さらに躍進するにはどの様な方法があるのでしょうか?

専門資格の取得でスキルアップ
ホスピス看護師としてもっと専門的な知識や技術を身につけたいなら、資格取得がおすすめです。
例えば、「緩和ケア認定看護師」や「がん性疼痛看護認定看護師」などの資格を取ることで、患者さんや家族により質の高いケアを提供できるようになります。
資格を持つことで、職場での信頼もアップしますよ!
緩和ケア認定看護師を目指すメリット
緩和ケア認定看護師になると、ホスピスや緩和ケアのスペシャリストとして活躍できます。
患者さんの痛みや不安を和らげるケアに特化したスキルを学べるので、より深いサポートが可能になります。
また、資格を持つことでキャリアの幅が広がり、病院内外での活躍の場が増えるのも魅力です。
病院内でのリーダーシップポジションへの挑戦
経験を積んだら、チームをまとめるリーダーや管理職に挑戦するのも一つの道です。
リーダーとして働くことで、他の看護師をサポートしたり、ケアの質を向上させる仕組み作りに関わることができます。
自分の経験を活かして、より多くの人を支える役割を担えます。
学会や研修への参加で最新の知識を身につける
ホスピスケアの分野は日々進化しています。
学会や研修に参加することで、最新の知識や技術を学ぶことができます。
新しい情報を取り入れることで、患者さんにより良いケアを提供できるだけでなく、自分自身の成長にもつながります。
教育者やコンサルタントとしての新たなキャリア
ホスピス看護師としての経験を活かして、教育者やコンサルタントとして働く道もあります。
新人看護師の教育や、他の医療スタッフへの指導を通じて、ホスピスケアの質を広く向上させることができます。
また、施設や地域でのケアのアドバイザーとして活躍することも可能です。
どの道を選んでも、患者さんや家族を支える力をさらに高めることができます。
自分の興味や目標に合わせて、少しずつステップアップしていきましょう。
ホスピス看護師に求められる条件と職場環境の変化
ホスピス看護師には、患者さんや家族に寄り添う「思いやり」と「コミュニケーション力」が求められます。
また、痛みや不安を和らげるための専門知識や技術も必要です。
最近では、在宅ホスピスの増加やチーム医療の進展により、働く場所や役割が広がりつつあります。
柔軟に対応できる力も大切ですね。
日本におけるホスピスケアの現状
日本では、高齢化が進む中でホスピスケアの需要が増えています。
病院内の緩和ケア病棟だけでなく、自宅でケアを受けたいという患者さんも増えており、在宅ホスピスが注目されています。
ただし、ホスピス施設や専門スタッフの数がまだ十分ではなく、地域によって受けられるケアに差があるのが課題です。
海外のホスピス看護師との比較
海外では、ホスピスケアが日本よりも早く普及しており、特にイギリスやアメリカでは、地域全体で患者さんを支える仕組みが整っています。
また、看護師が患者さんのケアだけでなく、意思決定のサポートや家族への教育にも深く関わることが多いです。
一方、日本ではまだ医師主導のケアが中心で、看護師の役割が限定的な場合もありますが、少しずつ変化してきています。
「死」について考えてみませんか?
長い年月「死」についての話はタブーとされていましたが、「終活」という言葉が広まり、自分や家族の死に対して考える機会が以前よりも増えた方もいらっしゃる一方、その思いを家族や、その他大切な方と共有されている方はまだまだ少ないというのが、私個人のイメージです。
「死」とは恐ろしいものだというイメージを持つ方も多いので仕方のないことだと思いますが、誰もが避けられない事実なのです。
養老 孟司氏著書の「死の壁」という本も有名になりましたよね。
この本を読んで私は自分の死へのイメージが大きく変わりました。
死に対して「残された人」のことを考えるようになったのです。
自分の余命が限られているとしたら、その事実を知りたい人は多い一方、家族以外には 知らせたくない人も多いことがわかりました。
余命が限られたら、7割以上の人が自宅で過ごしたいと考えていたが、実現は難しいと 回答した人が多かった。
公益財団法人ホスピス・緩和ケア振興財団が行った「人生100年時代の逝き方」考察より抜粋
ホスピスについて調べるためにこの記事にたどり着いた患者さんや、家族の方の多くは、患者さん本人が自分の病気や余命を受け入れ、「最期の過ごし方」について考えている段階なのではないかと思いますが、もし、まだその段階ではない場合には、一度上記のアンケートの結果をご覧いただきたいと思っています。
私自身も、こんな考え方があるのだなと今一度「最期」について考えるきっかけとなりました。
ホスピスは最期を迎えるための一つの手段です。
ホスピス自体が病気を治してくれたりしてくれるような魔法ではないのです。
また、「7割以上の人が自宅で過ごしたいが難しいと考えている」との回答をしたのは、日本でのホスピスに対する制度の遅れや情報不足が考えられます。
自宅で過ごしたいという意思を持っている方が多いことがわかりますね。
しかし、今の状況では難しいのではないという諦めのような意見にも見て取れます。
この数年で大きくホスピスに対しての制度も考え方も変わると思っています。
普段からの情報収集を行い、目を背けたくなるかもしれませんが「死」について考え、理想の自分の最期の時を迎える計画を立ててみませんか?
また看護師のみなさんも、今後ホスピスという分野に限らずとも、最期を迎える患者さんの看護をする機会があるはずです。
患者さんの本当の希望を叶えるために、ホスピスという制度や、看護について学びなおしてみませんか?
