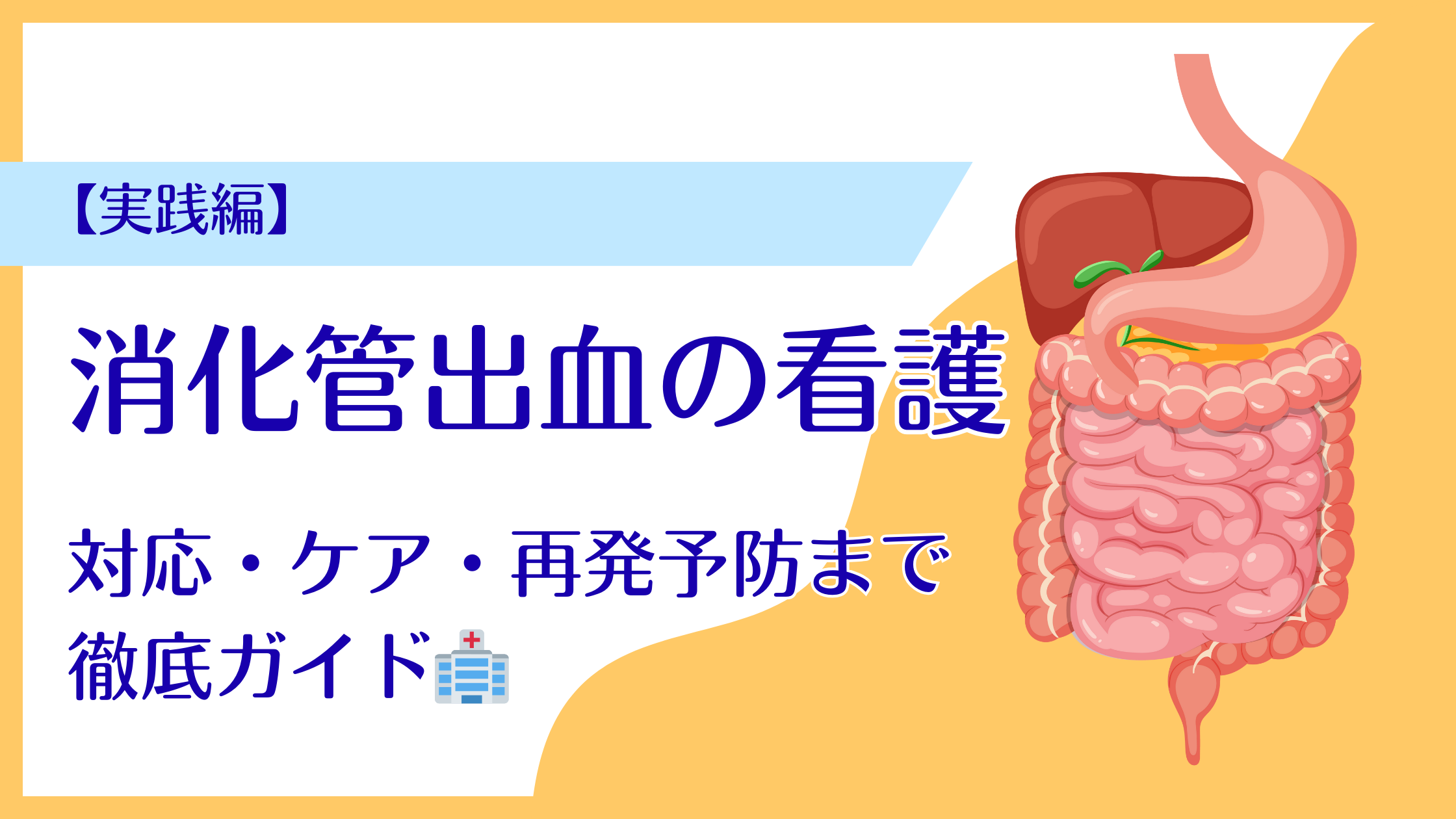
「消化管出血の患者さんを受け持ったとき、何から動けばいいんだろう?」
「絶飲食とか輸血の準備とか、ケアの優先順位が分からない…」
「家族への説明や再出血予防まで考えると不安です💦」
そんな悩みを持ったことはありませんか?
この記事では
-
初期対応で押さえたい絶飲食・体位・誤嚥予防のケア
-
輸液・輸血・内視鏡治療に関わる看護師の役割
-
患者さんと家族への説明・心理的サポートのコツ
-
記録や報告の工夫とチーム連携
-
再出血を防ぐための生活指導とエビデンスに基づく予防策
が分かりますよ♪
ポイント👉
消化管出血の看護で大切なのは 「観察→対応→説明→予防」の流れを整理して行動すること です。
慌てずに優先順位をつけることで、患者さんを安全に支えることができます😊
👉 なお、症状や原因、観察の基本ポイントをまだ読んでいない方は、ぜひ先に
【基本編】「消化管出血の看護【基本編】症状・原因・観察ポイントをやさしく解説🩸」もご覧ください。
この記事とセットで理解することで、知識と実践の両方がしっかり身につきますよ❤

🧰 消化管出血の看護ケア実践ガイド|絶飲食から輸血まで
消化管出血の患者さんを受け持ったとき、看護師が最初に行うのは「症状の観察」と同時に「安全なケア」です。
とくに初期対応では、絶飲食の徹底、体位の工夫、誤嚥予防、そして輸液や輸血のサポートが重要になります。
ここからは、臨床で新人さんが迷いやすいケアの流れを具体的に整理していきましょう✨
🛌 初期対応(絶飲食・安静・体位管理)
-
絶飲食(NPO):
出血部位の刺激を避け、処置や内視鏡検査に備えるために必須です。
飲食再開のタイミングは医師の指示で決まるので、患者さんと家族への説明も忘れずに。 -
安静保持:
出血量が多いと血圧低下やふらつきで転倒リスクがあります。
トイレ歩行も控えてベッド上安静が基本です。 -
体位管理:
吐血時は誤嚥を防ぐため側臥位に、呼吸が苦しい場合は頭部挙上を行います。
👉 なぜ絶飲食なのか」「なぜ安静が必要なのか」を説明できるようにすると、患者さんや家族の安心につながりますよ。
🫁 誤嚥を防ぐための看護ケア
吐血や嘔気がある患者さんでは誤嚥が命に関わります。
-
吸引器を常備し、必要時は迅速に対応できるよう準備。
-
嘔気が強いときは体位を工夫して気道を確保。
-
嘔吐後は口腔ケアを行い、不快感を軽減し誤嚥性肺炎を防ぎます。
👉 「吐物が急に増えて自分だけでは対応が難しい」と感じたら、ためらわずに応援や医師を呼ぶことが大切です。
💉 輸液・輸血・内視鏡治療の看護師の役割
-
輸液管理:
循環動態を維持するためにルート確保を行い、滴下速度や投与内容をこまめにチェックします。 -
輸血管理:
血液製剤の種類や血液型、投与スピード、副作用(発熱・じんましん・呼吸苦など)に注意。
特に開始15分以内は観察を徹底します。
▶輸血の手順と副作用対応:看護師が押さえるべき重要ポイント10選 -
内視鏡治療のサポート:
前処置として絶飲食の確認や同意の確認、検査中のバイタル観察、処置後の穿孔や再出血の有無をモニタリングします。
👉 治療の準備に追われても、看護師の一番大切な役割は「患者さんの変化に気づくこと」。観察とケアの両立が求められます❤
💡アドバイス
消化管出血の実践的なケアは、絶飲食→安静→体位→誤嚥予防→輸液/輸血→処置サポートという流れで整理すると理解しやすいです。
優先順位を意識すれば、新人さんでも落ち着いて対応できますよ。

💬 患者さんと家族への説明・心理的サポート
消化管出血の患者さんやご家族は、「急に血を吐いた」「便に血が混じった」といった状況に大きな不安を抱えます。
看護師は処置や観察を行うだけでなく、安心感を与えるコミュニケーションも大切な役割です。
ここでは、患者さんやご家族への声かけや説明の工夫、心理的サポートのポイントを見ていきましょう✨
🗣️ 不安を軽減するための声かけフレーズ
-
「出血の量や状態はしっかり見ていますから安心してくださいね」
-
「いまは絶飲食ですが、落ち着いたらまた食事再開できる見込みです」
-
「苦しいときは我慢せずにナースコールを押してくださいね」
👉 こうした一言で「見てもらえている」「理解してもらえている」と思えるだけで、患者さんの不安はぐっと和らぎます😊
👨👩👧 家族への説明の工夫とポイント
-
状況を具体的に伝える:
「黒っぽい便が出ていますが、これは胃や十二指腸からの出血を疑うサインです」 -
医師の説明につなぐ:
治療方針や検査内容は医師から説明されるため、その前に「どんな話があるか」を簡単に伝えておくと理解しやすい -
心配を受け止める:
「驚かれたと思いますが、私たちも一緒に見守っていきますので安心してください」
🤝 治療・検査に向けた安心感を与える対応
-
内視鏡検査や輸血に向けた準備をしていることを説明し、「何を待っているのか」 を伝える
-
「処置中もバイタルをずっと見ていますので安心してください」と強調する
-
家族が同席できる場合は、そばにいることで患者さんの安心につながることを伝える
💡アドバイス
患者さんもご家族も、ただ「血が出ている」という状況に動揺してしまうのは当然です。
そんなときこそ看護師が「冷静に観察しつつ、心に寄り添う声かけ」をすることで、信頼関係が築けますよ❤
「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」
「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!
くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。
📋 記録・報告の工夫|チーム連携でズレを防ぐ
消化管出血の患者さんでは、観察や処置の内容を「どう記録し、どう伝えるか」がとても大切です。
同じ状況でも、伝え方があいまいだと医師やチームに誤解を与えてしまい、対応の遅れにつながることもあります。
ここでは、看護師として押さえておきたい記録の視点と、報告・連携の工夫を整理していきましょう✨
📝 報告に必要な観察項目(便・バイタル・出血量)
-
便や嘔吐物の状態:
「色(黒色・鮮紅色・コーヒー残渣様)」「量」「性状」を具体的に -
バイタルサイン:
血圧・脈拍・呼吸数・SpO₂をセットで報告 -
出血量の推定:
便器や吐物を容器に移し、可能ならmL単位で伝える
👉 例:「22時、鮮紅色便約200mL、BP92/58、P112、SpO₂95%、意識清明」
📖 看護記録に残すべきポイント
-
出血の有無と量、観察した時間を明記
-
バイタル変化と症状を時系列で整理
-
実施したケア(吸引、体位変換、輸液速度調整など)とその効果
-
医師への報告内容と指示、実施した処置
👉 後から見ても経過が追えるように「いつ・何を・どうしたか」を意識して記録しましょう。
🤝 チーム間での情報共有の工夫
-
申し送りでは「直近の出血の有無」「量」「バイタル変化」を必ず伝える
-
曖昧な表現(少し、多めなど)は避け、具体的な数値や色を使う
-
急変リスクが高いときは、次のシフトで特に注意すべき点を明確に伝える
👉 例:「便は黒色から鮮紅色に変化、バイタル不安定。次シフトも下血とバイタルの変化に注意してください」
💡ポイント
記録と報告は「客観的に・具体的に・時系列で」が基本。
これが徹底されると、チームの誰が対応してもズレなく動けるようになります❤

🔄 再出血を防ぐ!最新エビデンスに基づく予防とフォローアップ
消化管出血は止血できても「再出血のリスク」が常につきまといます。
患者さんの退院後の生活や服薬管理によっては、再発して再び救急搬送…というケースも少なくありません。
看護師は急性期の対応だけでなく、その後の予防とフォローアップにも関わっていく必要があります。
ここでは、再出血を防ぐために押さえておきたいリスク因子や、生活指導、ガイドラインに基づいたフォローのポイントをまとめていきます✨
⚠️ 再出血リスク因子と看護でできる予防策
-
抗凝固薬・抗血小板薬の内服:
中止や再開のタイミングは医師判断だが、看護師は服薬状況を正確に把握しておく -
肝硬変・門脈圧亢進:
静脈瘤再破裂のリスクが高いため、生活管理や定期的な内視鏡フォローが必要 -
高齢・基礎疾患:
血管が脆弱で再出血しやすい -
生活習慣:
飲酒・食生活・NSAIDsの自己使用など
👉 看護師は「どんな患者さんが再出血しやすいか」を把握し、日常生活の注意点を伝えることが重要です。
🍽️ 食事・生活習慣指導のポイント
-
暴飲暴食を避ける:
胃や腸に負担をかけないように -
アルコール制限:
特に肝硬変患者では必須 -
便秘予防:
排便時のいきみで下部出血を助長することがある -
薬の服用管理:
市販NSAIDsの安易な使用を避けるよう説明
👉 患者さん自身が「なぜこの生活が大事なのか」を理解できるよう、丁寧な説明が必要です。
📅 ガイドラインに基づくフォローアップ
-
上部消化管出血:
再出血リスクが高いため、退院後も数週間〜数か月のフォローが必要 -
下部消化管出血:
憩室出血や血管拡張では再発率が高いため、定期的な大腸内視鏡を行うことが多い -
採血フォロー:
貧血の改善具合を確認 -
生活指導の確認:
外来で再教育されることもあるため、病棟からの引き継ぎをきちんと行う
👉 看護師は退院指導だけでなく、外来や地域とつながるフォロー体制に関わることで「入院と在宅のすき間」を埋められます。
💡ポイント
再出血予防は「薬・生活習慣・フォローアップ」の3つが柱です。
患者さんとご家族が「再出血を防ぐ行動」を理解できるように、看護師の言葉が大切な支えになります❤

✅ まとめ|実践で役立つ消化管出血ケアのポイント
📝 本記事の振り返りポイント
-
初期対応は 絶飲食・安静・体位管理 が基本
-
吐血時は 誤嚥予防 と 吸引準備 を優先
-
輸液・輸血・内視鏡 の場面では看護師が観察・準備・合併症チェックを担う
-
患者さん・家族には 安心を与える説明と声かけ が大切
-
記録・報告は「具体的・数値化・時系列」で共有することが安全につながる
-
再出血予防は 服薬管理・生活指導・外来フォロー を含めた支援が必要
💡 明日から実践できるケアのヒント
-
出血時は「観察→報告→ケア」の流れを意識する
-
声かけや説明を「具体的に」することで患者さんの不安は減る
-
チームに伝えるときは「曖昧な表現」を避け、客観的に
-
退院後の生活習慣や薬の管理にも看護師の視点を活かす
👉 記事①(基本編)では「症状・原因・観察ポイント」を整理しました。
この記事②と合わせて読むことで、“理解+実践”の両面から消化管出血の看護を学べるようになります❤






