
「血液製剤って、赤血球濃厚液に血小板濃厚液、新鮮凍結血漿…色々あって、いざ使うぞ!って時に『あれ?この製剤の保管温度って何度だっけ?』『溶解する時の注意点、何だったかな…🤔』って、一瞬手が止まっちゃうこと、ありませんか?
特に忙しい時ほど、焦っちゃいますよね…!
毎日たくさんの業務がある中で、製剤ごとの細かいルールを全部完璧に覚えておくのって本当に大変ですよね。
この記事では
- 主要な血液製剤の種類と、それぞれの特徴が一目でわかる比較ポイント✨
- 製剤ごとの正しい保管方法と、温度管理の厳守義務🌡️
- 安全かつ確実な溶解の手順と、見落としがちな注意点💧
- 実際の現場で役立つ、取り扱いミスの予防策とヒント💡
が分かりますよ♪
多種多様な血液製剤を安全・適切に取り扱うためには、それぞれの特性をしっかり理解した上で、「①製剤ごとの適切な温度での保管」、「②正しい手順と時間を守った溶解作業」、そして「③使用直前までの徹底した確認作業」という3つの重要ポイントを押さえることが、何よりも大切なんです!💉✨
この記事では、看護師さんが日々向き合う主要な血液製剤について、それぞれの種類別の特徴から、現場で迷いがちな保管方法、そして安全確実な溶解の手順と注意点を、まるっと分かりやすく解説します!
「あ、これ知りたかったやつだ!」が見つかるはずです。ぜひ最後まで読んで、明日からの業務に活かしてくださいね😉👍
輸血の関連記事を読む▼
輸血の手順と副作用対応:看護師が押さえるべき重要ポイント10選
ポイント①:血液製剤の種類と特徴をマスター!📚 これで迷わない!
輸血医療の現場で欠かせない血液製剤🩸
その種類はいくつかあり、それぞれに大切な役割と特徴があるんです。
このポイントでは、基本となる製剤の種類から、ラベルの読み解き方、そしていざという時に役立つ有効期限や管理のコツまで、しっかりマスターしていきましょう!
これで、もう迷うことはありませんよ😉✨

花子のまとめノートより
まずは基本の「キ」!赤血球・血小板・血漿製剤って何が違うの?🤔
輸血と一口に言っても、使われる血液製剤にはいくつかの種類があります。
代表的な「赤血球製剤」「血小板製剤」「血漿製剤」について、それぞれの特徴と役割をしっかり押さえておきましょう!
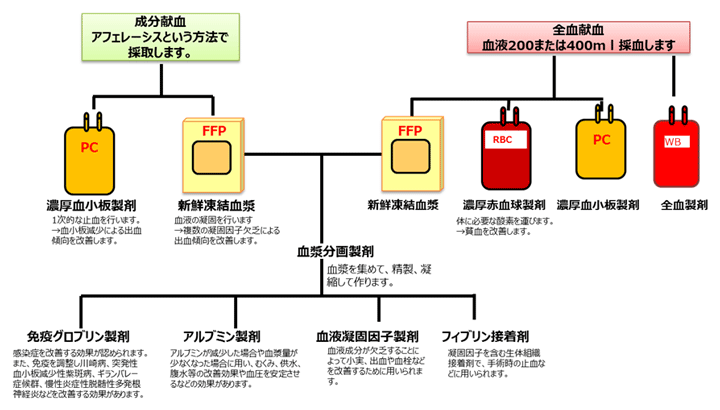
一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会より画像引用
| 製剤の種類 | 主な役割 | 色・見た目の特徴 | こんな時に主に使われます! |
|---|---|---|---|
| 赤血球製剤 (RBC) | 全身の細胞に酸素を運ぶ大切な役割を担います🌬️ | 鮮やかな赤色 | 貧血の改善(手術や外傷による急な出血、慢性的な貧血など)、酸素運搬能の改善が必要な場合 |
| 血小板製剤 (PLT) | 出血した際に血を止める「止血」のエキスパートです🩹 | 淡黄色~乳白色 | 血小板の数が減ってしまったり、働きが悪くなったりして出血しやすい状態の改善、出血予防 |
| 血漿製剤 (FFP) | 血液を固めるための因子をたくさん含んでいます💧 | 淡黄色で透明 | 血液凝固因子の補充が必要な場合(肝臓の病気、DIC、血友病など)、大量出血で凝固因子が失われた場合 |
これらの製剤は、患者さんの状態や目的に応じて使い分けられています。
それぞれの製剤が持つパワーを最大限に活かすためにも、基本をしっかり理解しておくことが大切ですね😊
ラベルの「LR」や「Ir」ってどんな意味?見分け方と重要ポイント💡
血液製剤のバッグに貼られているラベルには、大切な情報がたくさん書かれています。
その中でも特によく見かける「LR」や「Ir」といった記号、どんな意味かご存知ですか?
安全な輸血のために、これらの意味と重要性をチェックしましょう!
LR (Leukocyte Reduced):白血球除去製剤💉
- これは、血液製剤から白血球をフィルターなどを使って取り除いた製剤のことです。
- なぜ必要?: 白血球は、輸血後の発熱反応や、ヒト白血球抗原(HLA)による同種免疫(繰り返し輸血すると血小板の効きが悪くなるなど)、サイトメガロウイルス(CMV)などの感染症伝播のリスクとなることがあります 。これらを軽減するために白血球除去が行われます。現在、多くの赤血球製剤や血小板製剤は、このLR処理がされています。
- Ir (Irradiated):放射線照射血製剤🌟
これは、血液製剤に放射線(ガンマ線やX線)を照射した製剤のことです。 - なぜ必要?:
輸血されたドナーさんのリンパ球が、患者さんの体内で増殖し、攻撃してしまう「輸血後移植片対宿主病(TA-GVHD)」という重篤な副作用を防ぐために行われます 。
TA-GVHDは致死率が非常に高いため、特に免疫力が低下している患者さん、血縁者からの輸血、HLA適合血小板輸血などの場合にこの照射製剤が使われます 。
照射された赤血球製剤は、有効期間が短くなることがあるので注意が必要です(例:照射後28日以内)。
その他ラベルの重要チェックポイント! ✅
ラベルには他にも、
- 血液型 (ABO型、RhD型)
- 製剤名・コード
- 製造番号(ロット番号)
- 有効期限
- 製造施設名
などが記載されています 。
これらは、患者さんに適合する正しい製剤かを確認し、万が一の際に追跡するための非常に重要な情報です。
輸血前には、必ず複数のスタッフで声出し確認を徹底しましょうね!
【一目でわかる!】この症状にはこの製剤!ケース別血液製剤早見チャート📊
「この患者さんには、どの血液製剤が一番いいんだろう?」と迷うこと、ありますよね。
ここでは、代表的なケースごとに、どんな血液製剤が主に使われるのかをまとめた早見チャートをご用意しました!
もちろん、最終的な判断は医師が行いますが、基本的な考え方を知っておくと役立ちますよ👍
| 症状・ケース | 主に使われる血液製剤 | ポイント・理由など |
|---|---|---|
| 急な大量出血・外傷(交通事故など) 🚑🚨 | 赤血球製剤、新鮮凍結血漿、(必要に応じて)血小板製剤 | 失われた血液量と酸素運搬能を補い、止血に必要な凝固因子や血小板を補充します 。 |
| 手術中の出血 😷 | 赤血球製剤、(出血量や内容により)新鮮凍結血漿、血小板製剤 | 手術によって失われた血液成分を補います。 |
| 貧血(鉄欠乏性、腎性、再生不良性など) 😥 | 赤血球製剤 | ヘモグロビン値を上げて、体のすみずみまで酸素を届けられるようにします 。 |
| 血小板の数が少ない、または働きが悪い(特発性血小板減少性紫斑病など)🩸 | 血小板製剤 | 出血を予防したり、止血しやすくしたりします。 |
| 肝硬変などで血液を固める力が弱い 🍺➡️💔 | 新鮮凍結血漿、(場合により)アルブミン製剤 | 肝臓で作られる凝固因子が不足しているため、それを補充します 。 |
| DIC(播種性血管内凝固症候群) 💥 | 新鮮凍結血漿、血小板製剤、(原因治療と並行して)アンチトロンビンⅢ製剤など | 全身の血管内で小さな血栓がたくさんできてしまい、凝固因子や血小板が消費されてしまうため、それらを補充し、凝固と線溶のバランスを整えることを目指します。 |
| 血友病など、特定の凝固因子が生まれつき足りない 🧬 | 新鮮凍結血漿、クリオプレシピテート(第Ⅷ因子、フィブリノゲンなど)、または特定の凝固因子製剤 | 不足している凝固因子そのものを補充します。 |
※上記はあくまで一般的な目安です。患者さんの状態、検査データ、病歴などを総合的に判断して、医師が適切な製剤を選択・指示します。
知っておくと安心!血液製剤の有効期限と管理のコツ🗓️
血液製剤は、その効果と安全性を保つために、それぞれ有効期限と適切な保管方法が定められています。
期限切れや不適切な管理は、患者さんにとって大きなリスクに繋がることも。ここでしっかり確認しておきましょう!
主な血液製剤の保管温度と有効期間の目安
| 製剤の種類 | 保管温度 (℃) | 有効期間の目安 | 管理のポイント💡 |
|---|---|---|---|
| 赤血球濃厚液 (RBC-LR) | 1~6℃(専用冷蔵庫) | 採血後42日間(MAP加赤血球液など) 採血後21日間(CPD加赤血球液など) ※放射線照射後は採血後28日以内など、条件により異なる 。バッグの封が開いた場合は24時間以内 。 |
温度管理が命!🌡️ 払い出し後は速やかに輸血開始。溶血や凝集、色調異常がないか使用前に必ず確認! |
| 血小板濃厚液 (PC-LR) | 20~24℃(室温、専用振盪器) | 採血後5日間(製法により7日間も) ※プール製剤はプール後4時間以内 。 |
必ず振盪しながら保管!🔄 細菌汚染のリスクが高いため、取り扱いは清潔操作で慎重に。温度変化にも注意が必要です。 |
| 新鮮凍結血漿 (FFP-LR) | -18℃以下(専用冷凍庫) | 採血後1年間(凍結状態) ※融解後は製品により異なるが、一般的に24時間以内(1~6℃で保管)。 |
融解後の時間管理が超重要!⏳ 30~37℃の恒温槽で適切に融解し、再凍結は絶対にNG🙅♀️。融解後の細菌汚染にも注意。 |
| クリオプレシピテート | -18℃以下(専用冷凍庫) | 採血後1年間(凍結状態) ※融解後は単独ユニットで6時間以内、プールされた場合は4時間以内(室温保管)。 |
FFPと同様、融解後の管理が大切。室温で保管し、速やかに使用します。 |
血液製剤管理のコツ✨
- 正しい温度で保管するべし! 各製剤に適した温度が保たれているか、温度計の記録と確認を徹底しましょう 。
- 有効期限を必ずチェック! 「先入れ先出し(FIFO)」を心掛け、期限の近いものから使用するようにしましょう 。
- 見た目の異常を見逃さない! 溶血(赤血球製剤が赤黒くなっている)、凝集(塊がある)、色調の変化、バッグの破損や汚染などがないか、使用前に必ず確認しましょう。
- 払い出したら速やかに! 血液製剤が病棟に払い出されたら、できるだけ早く輸血を開始し、規定時間内に終了させることが重要です 。特に赤血球製剤や血小板製剤を長時間室温に放置すると、品質低下や細菌増殖のリスクが高まります。
- 記録は正確に! いつ、誰が、どの患者さんに、どの製剤を使用したか、正確な記録は安全管理の基本です。
これらのポイントを守ることで、血液製剤をより安全かつ有効に活用することができます。日々の業務でぜひ意識してみてくださいね!😊
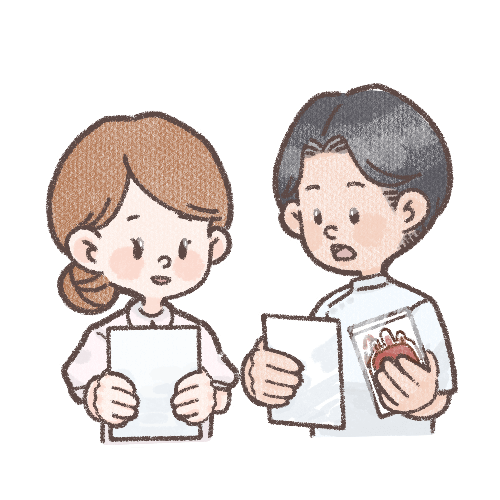
ポイント②:「冷やしすぎ?温めすぎ?」を防ぐ!製剤別・正しい保管テクニック🌡️✨
血液製剤は、患者さんの命を繋ぐ大切なバトンリレーのランナーのようなもの🏃♀️💨
そのバトンを最高の状態で渡すためには、製剤の種類に合わせた「正しい保管」が欠かせません。
温度が高すぎても低すぎても、製剤の品質はあっという間に低下してしまいます😱
ここでは、そんなデリケートな血液製剤の命を守るための、とっておきの保管テクニックを伝授します!
しっかりマスターして、いつでも安心して輸血に臨めるようになりましょうね😉💕
製剤ごとに鉄則アリ!🥶血液製剤の命を守る「適正保管温度」一覧表
血液製剤は、種類によって最適な「お部屋の温度(保管温度)」が全然違うんです!
まるで性格の違うペットをそれぞれ快適なお部屋で飼うみたいに、製剤ごとにも居心地の良い温度があるんですね。
間違った温度で保管してしまうと、せっかくの製剤の効果が薄れたり、思わぬ副作用の原因になったりすることも…😨
そうならないために、主要な血液製剤の正しい保管温度と有効期間の目安を、ここでしっかりチェックしておきましょう!
| 製剤の種類 | 日本赤十字社・主要ガイドライン等に基づく保管温度 (℃) | 有効期間の目安(主なもの) | 覚え方のコツ(イメージ) |
|---|---|---|---|
| 赤血球製剤 (RBC) | 2~6℃ | 採血後28日間または42日間(保存液による) | 冷蔵庫のチルド室くらい❄️ 「赤血球さんは寒がりだけど凍えるのはNG」 |
| 血小板製剤 (PC) | 20~24℃(要振盪) | 採血後4日間~7日間(製法による) | 常温のお部屋くらい🌸 「血小板ちゃんは優しく揺らしてあげて」 |
| 新鮮凍結血漿 (FFP) | -20℃以下(または-25℃以下、-18℃以下など) | 採血後1年間(凍結状態) | カチコチの冷凍庫🧊 「血漿さんは凍らせてパワー温存」 |
| 全血製剤 | 2~6℃ | 採血後21日間 | 赤血球製剤と仲間🤝 「みんな一緒でもやっぱりチルド室」 |
| クリオプレシピテート | -25℃以下(または-18℃以下など) | 採血後1年間(凍結状態) | 血漿さんよりさらに寒がりかも?🥶「クリオさんもカチコチで」 |
※上記は代表的なもので、製剤の種類や製造方法、各国の基準によって多少異なる場合があります。必ず製剤のラベル情報や、所属施設の規定を確認してくださいね!
なんで振るの?🤷♀️ 血小板製剤の「振盪保管」のナゾを解明!
他の血液製剤が冷蔵庫や冷凍庫で静かに保管されるのに対して、血小板製剤だけは特別扱い!
20~24℃という常温で、しかも「振盪器(しんとうき)」という専用の機械で優しくユラユラ揺らしながら保管されますよね。
「なんで血小板だけ、そんなVIP待遇なの?🤔」って思ったことありませんか?
そのナゾには、血小板のデリケートな性質と、大切な役割をしっかり果たしてもらうための工夫が隠されているんです!
主な理由は大きく分けて3つあります✨
- 酸素をしっかり供給して、二酸化炭素を追い出すため!🌬️
血小板も私たちと同じように呼吸(代謝)をしています。
振盪することで、保存バッグ内の血小板に均一に酸素が行き渡り、代謝によって発生する二酸化炭素がバッグの外に排出されやすくなります 。
ガス交換がスムーズに行われることで、血小板は元気な状態を保てるんです。 - pHの低下を防いで、機能を守るため!💪
もし振盪せずに静止した状態で血小板を保管すると、血小板の代謝によって乳酸などの酸性物質が局所的に溜まりやすくなり、保存液のpHが低下してしまいます 。
pHが下がりすぎると(特にpH6.2以下)、血小板の形が変わってしまったり、固まる力が弱くなってしまったりと、輸血の効果がガクンと落ちてしまうんです 。
優しく揺らすことで、pHの急激な低下を防いでいるんですね。 - 血小板同士がくっついちゃうのを防ぐため!🤝➡️❌
血小板は本来、出血した時に集まって固まるのがお仕事。
でも、保管中に勝手に集まって塊(凝集塊)を作ってしまっては大変です💦
振盪することで、血小板同士がくっつきにくくなり、いつでも出動できるスタンバイ状態をキープできるというわけです。
ちなみに、振盪の仕方も大切で、ただ揺らせば良いというわけではありません。
激しすぎる揺れは逆に血小板を傷つけてしまうため、「優しく、絶え間なく」が基本です 。
専用の振盪器は、血小板にとって最適な揺れ方(平らなベッドでゆっくり水平に揺れるような動きなど)をしてくれるんですよ。
このように、血小板製剤の振盪保管は、その繊細な性質を守り、いざという時に最大限のパワーを発揮してもらうための、とっても大切なケアなんです💕
温度管理は生命線!専用保冷庫の正しい使い方と日々のチェックポイント✍️
血液製剤にとって、適切な温度で保管されることはまさに「生命線」!🏥
その大切な役割を担うのが、血液製剤専用の保冷庫(冷蔵庫や冷凍庫)です。
これらの保冷庫がしっかり機能していないと、いくら気をつけていても製剤の品質は守れません。
ここでは、専用保冷庫の正しい使い方と、毎日欠かせないチェックポイントを一緒に確認しましょう!
ここが肝心!専用保冷庫の正しい使い方✨
1.設置場所は慎重に!🌞💦
- 直射日光が当たる場所や、高温多湿になりやすい場所は避けましょう。保冷庫に余計な負荷がかかり、冷却効率が悪くなってしまいます 。
- 壁から少し離して設置し、保冷庫の周りに十分なスペースを確保しましょう。熱がこもるのを防ぎ、メンテナンスもしやすくなります 。
- 水平で安定した場所に設置することが大切です。不安定な場所では、故障の原因になったり、性能が低下したりすることがあります 。
2.庫内は整理整頓で風通し良く!🍃
- 製剤を詰め込みすぎず、冷気がスムーズに循環するように、適度な隙間をあけて保管しましょう 。
- 「先入れ先出し」を意識して、手前に有効期限の近いものを置くなど、整理整頓を心がけましょう。
3.扉の開閉は最小限に!🚪💨
- 扉を開けている時間が長いほど、庫内の温度が上がりやすくなります。
必要なものをサッと取り出せるように、開閉は手早く、回数も少なく済ませましょう 。
4.他のものとは一緒にしない!🚫
- 血液製剤専用の保冷庫には、原則として食品や検体など、他のものは入れないようにしましょう。
汚染のリスクを避けるためです。
毎日欠かさず!愛情たっぷり日常チェックポイント✅
| チェック項目 | 確認ポイント | なぜ大切なの? |
|---|---|---|
| ① 温度計の確認 | 庫内温度が規定の範囲内(例:赤血球用なら2~6℃)に保たれているか? 温度記録は毎日行いましょう 。 | 温度がズレていると、製剤の品質が劣化!😱 定期的な確認で異常を早期発見! |
| ② ドアの密閉状態 | ドアパッキンに亀裂や破損、汚れはないか?しっかり閉まっているか? | パッキンの劣化は冷気漏れの原因!🥶 電気代も無駄になっちゃうかも。 |
| ③ 庫内の清掃状態 | 庫内は清潔か? 液漏れや汚れはないか?定期的に清掃しましょう 。 | 不衛生な環境は細菌汚染のリスクも…😢 清潔第一で製剤を守ろう! |
| ④ 製剤の外観チェック | 保管中の製剤に異常(溶血、凝集、色調変化、バッグの破損など)はないか? | 見た目の変化は品質低下のサインかも? 使用前に必ず確認する習慣を! |
| ⑤ 異音・異常振動の有無 | 保冷庫から普段と違う音や振動はしていないか? | 故障のサインかもしれません!😨 気づいたらすぐに担当者に報告を! |
| ⑥ アラーム機能の確認 | 温度異常を知らせるアラーム機能は正常に作動するか?(定期的なテストが望ましい)。 | 万が一の温度逸脱時に、すぐ気づけるように!🚨 |
| ⑦霜取り・排水の確認 | 冷凍庫の場合、過度な霜がついていないか?冷蔵庫の場合、排水口(ドレンホース)が詰まっていないか? 。 | 霜が厚すぎると冷却効率ダウン!排水詰まりは水漏れの原因にも! |
これらの使い方とチェックポイントを守ることで、血液製剤を最適な状態で保管し、安全な輸血に繋げることができます。
日々の丁寧な管理が、患者さんの安心と安全を守る第一歩ですね😊👍
輸血準備中も油断大敵!払い出し後の製剤、室温での許容時間ってどれくらい?⏳
「さあ、輸血の準備!」と血液製剤を保冷庫から取り出した後、すぐに患者さんの元へ…とはいかない場面もありますよね。
準備に時間がかかったり、患者さんの状態が急に変わったり…。
そんな時、「この製剤、室温にどれくらい置いておけるんだろう?」と心配になることはありませんか?
血液製剤は温度変化にとてもデリケートなので、払い出し後の管理もとっても重要なんです!⏰
製剤の種類によって、室温での許容時間や取り扱いには違いがあります。代表的なものを確認しておきましょう!
| 製剤の種類 | 室温での取り扱い・許容時間の目安 | 特に注意したいポイント☝️ |
|---|---|---|
| 赤血球製剤 (RBC) | 適切な温度管理下(保冷庫など)から取り出した後は、30分以内に輸血を開始するのが原則です 。 60分以内に使用しない場合は、速やかに適切な保冷庫に戻す必要があります 。 |
長時間室温に放置すると、細菌増殖のリスクや製剤の劣化が進みます😱 溶血にも注意! |
| 血小板製剤 (PC) | もともと20~24℃で振盪保管されているため、払い出し後も室温で保管します。**冷蔵庫や保冷バッグには絶対に入れないでください!**🙅♀️ 払い出されたら、できるだけ速やかに輸血を開始します。特にプールされた血小板製剤は、調整後4時間以内が目安です 。 |
低温にさらされると機能が低下してしまいます🥶 輸血直前まで振盪を続けるのが理想ですが、短時間であれば静置も許容されることがあります。ただし、長時間の静置はpH低下のリスクがあるので注意が必要です。 |
| 新鮮凍結血漿 (FFP) | 融解後は、1~6℃の冷蔵庫で保管し、製品によって異なりますが、一般的に24時間以内(一部製品では5日間)に使用します 。 輸血のために病棟へ払い出された後は、4時間以内に輸血を完了できるように計画します 。 |
融解後の時間管理が非常に重要です!⏳ 再凍結は絶対にNG。細菌汚染のリスクもあるため、清潔操作を心がけましょう。 |
| クリオプレシピテート | 融解後は、室温 (20~24℃) で保管します。単独ユニットなら融解後6時間以内、プールされた場合は4時間以内に使用するのが一般的です 。 | こちらも融解後の時間管理が大切!⏰ FFPと違って室温保管なので、間違えないようにしましょうね。 |
共通の心構えとして… ❤️🩹
- 血液製剤を払い出す際は、一人の患者さんごとに行い、複数の患者さんの製剤を同時に準備しないようにしましょう 。取り違えのリスクを減らすためです。
- 輸血の準備が整い次第、速やかに輸血を開始できるように、患者さんの状態やルート確保などを事前にしっかり確認しておくことが大切です。
- もし、払い出し後に輸血開始が大幅に遅れる場合や、使用しなくなった場合は、自己判断せずに速やかに輸血部門や医師に報告・相談し、指示を仰ぎましょう。製剤を無駄にせず、安全に管理するためです。
払い出し後の時間管理は、輸血の安全性を左右する重要なポイントです。
「まだ大丈夫かな?」と安易に考えず、決められたルールを守って、大切な血液製剤を最適な状態で患者さんに届けられるように心がけましょうね!😊✨
ポイント③:安全第一!血液製剤の確実な溶解方法と「うっかり」防止策💧✅
血液製剤の取り扱いの中でも、特に気を使うのが「溶解」のプロセスですよね。
カチコチに凍っている製剤を、適切な温度で、しかも品質を損なうことなく解かす…。
なんだかミッションみたいでドキドキしませんか?💓
でも大丈夫!このポイントでは、FFP(新鮮凍結血漿)をはじめとする血液製剤の確実な溶解方法と、思わぬ「うっかり」を防ぐための秘訣を、分かりやすくお伝えします。
これであなたも溶解マスターです!✨
FFP(新鮮凍結血漿)を温める時、お湯ポチャは絶対ダメ?!🙅♀️ 正しい溶解ステップを伝授!
「急いでるから、熱めのお湯にドボン!しちゃえ~!」…なんて、まさかやっていませんよね?😱
(昔お湯で溶かしている先輩がいました!)
FFP(新鮮凍結血漿)の溶解は、温度管理が命!
高すぎる温度で溶かしてしまうと、大切な凝固因子が熱で変性してしまい、せっかくの輸血効果が得られなくなってしまいます。
逆に温度が低すぎても、クリオプレシピテートという沈殿物ができてフィルターが詰まっちゃうことも…。
では、どうすれば安全かつ確実にFFPを溶解できるのでしょうか?正しいステップを一緒に確認しましょう!
FFPの正しい溶解ステップ 🔢
1.準備するもの
- FFP本体(凍った状態)
- 清潔なビニール袋(FFPを直接お湯につけないため)
- 恒温槽(ウォーターバス)またはFFP専用融解装置
- 温度計(恒温槽の水温確認用)
2.溶解前のチェック! ✅
- FFPのバッグに破損がないか、凍った状態でも丁寧に確認しましょう。凍結状態のバッグは非常にもろく、破損しやすいので要注意です!
- 患者情報、血液型、製剤名、製造番号、有効期限などを複数人でしっかり照合します。
3.いざ、溶解! 🔥💧
- FFPを清潔なビニール袋に入れます(製剤バッグが直接水に触れないようにするため、また汚染防止のため)。
- 恒温槽またはFFP専用融解装置の水温を30~37℃に設定します。この温度がとっても重要!
- FFPの入ったビニール袋を、設定温度になった恒温槽のお湯に浸します。
- 時々優しく撹拌しながら、均一に溶解するようにしましょう。
- やむを得ず恒温槽がない場合は、30~37℃に調整した温湯を準備し、温度計で確認しながら慎重に、そして撹拌しながら溶解します。
4.溶解後の最終チェック! 👀✋
- 完全に溶解したことを目視と触感で確認します。バッグ内に氷の塊が残っていないか、よーく見て、触って確かめましょう。
- 製剤の温度が融解温度(30~37℃程度)に達しているか確認します。
- 融解後のFFPの色調に異常がないか(極端な白濁や変色など)、凝固物がないかなども確認しましょう。
- 融解時に輸血用器具との接続部が汚染されないよう、細心の注意を払いましょう。
お湯ポチャ(直接熱湯に入れるなど)が絶対ダメな理由 💣
- 温度が高すぎる危険性: 40℃を超えるような高温では、FFPに含まれるタンパク質(特に凝固因子)が熱変性を起こし、活性を失ってしまいます。これでは輸血の意味がなくなってしまいますよね。
- 温度が不均一になる危険性: バッグの一部だけが高温にさらされたり、逆に中心部がなかなか溶けなかったりして、品質にムラが出てしまう可能性があります。
- バッグ破損・汚染のリスク: 熱いお湯に直接バッグを入れると、材質が劣化したり、目に見えない小さな穴から汚染されたりするリスクも高まります。
手間はかかっても、正しいステップで丁寧に溶解することが、安全で効果的な輸血への第一歩です!焦らず、確実に進めましょうね😊
溶解したらスグ使うべき?製剤ごとの「溶解後の安定性」と使用期限⏰
「よし、FFP溶けたぞ!さあ、準備万端!」…と安心するのはまだ早いかもしれません。
実は、血液製剤は一度溶解(または加温)すると、時間とともにその品質が少しずつ変化していくんです😢
だから、「いつまでに使い切るか」という使用期限を守ることが、とっても大切になります。
製剤の種類によって、溶解後の安定性や推奨される使用期限は異なります。
主な血液製剤について、目安となる情報をまとめてみました!
| 製剤の種類 | 溶解・加温後の保管条件と使用期限の目安 | ポイント・注意点など |
|---|---|---|
| 新鮮凍結血漿 (FFP) | 融解後、直ちに使用するのが原則です。 直ちに使用できない場合は、2~6℃で保存し、融解後24時間以内に輸血してください。 (施設によっては、室温放置の場合、2時間以内、3時間以内、4時間以内などの規定があることも) |
再凍結は絶対にNGです!細菌汚染のリスクもあるため、清潔操作を心がけ、できるだけ速やかに使用しましょう。融解後の凝固因子活性は時間とともに低下する可能性があります。 |
| 濃厚血小板 (PC) | 血小板製剤は、もともと20~24℃で振盪保管されています。輸血前に加温は不要です。 バッグのシールを開封(輸血セットを接続)したら、汚染のリスクを考慮し、4時間以内に輸血を完了させるのが一般的です。 |
低温にさらされると機能が低下するため、冷蔵庫には入れないでください!🙅♀️ 輸血直前まで緩やかに振盪するのが理想です。 |
| 濃厚赤血球 (RBC) | 通常、輸血前に加温は不要です(急速大量輸血や新生児交換輸血など特別な場合を除く)。 血液バッグのシールを開封(輸血セットを接続)したら、細菌汚染のリスクのため、1~6℃で保管する場合は24時間以内に、室温(20-24℃)で保管する場合は4時間以内に輸血を完了させます。 |
赤血球製剤を保冷庫から出したら、30分以内に輸血を開始するのが望ましいとされています。長時間室温に放置すると細菌増殖のリスクが高まります。 |
| クリオプレシピテート | 37℃で溶解後、室温 (20~24℃) で保管します。 単独ユニット(1袋ごと)なら融解後6時間以内、複数のバッグを一つにまとめたプール製剤の場合はプール後4時間以内に使用するのが一般的です。 |
FFPと異なり、融解後は室温で保管します。こちらも再凍結はNGです。フィブリノゲンなどの効果を期待する製剤なので、時間管理が重要です。 |
| その他の製剤 | 各製剤の添付文書や、施設の規定・マニュアルを必ず確認してください。例えば、特定の遺伝子組換え凝血因子製剤(アディノベイトなど)は溶解後、室温(30℃以下)で3時間以内に使用とされています。フィブリノゲン製剤も溶解後速やかに使用することが推奨されます。 | 製剤によって特性や安定性が大きく異なります。自己判断せず、必ず定められたルールに従いましょう! |
大切なこと💖
- 上記の時間はあくまで目安です。必ずご自身の施設の規定やマニュアル、各製剤の添付文書を確認し、それに従ってください。
- 一度溶解・開封した製剤は、**「できるだけ速やかに使用する」**という意識を常に持ちましょう。
- もし予定通りに使用できなかった場合は、自己判断で保管せず、速やかに医師や輸血管理部門に報告し、指示を仰ぐことが重要です。
時間管理をしっかり行うことで、血液製剤の持つパワーを最大限に活かし、患者さんへ安全に届けることができますね!😊
【ヒヤリハット回避】溶解時の「これやっちゃダメ!」ワースト3とその理由とは?💣
血液製剤の溶解作業は、ちょっとした不注意が大きなトラブルに繋がることも…😱
「いつもやってるから大丈夫!」と思っていることでも、実はヒヤリハットの種が隠れているかもしれません。
ここでは、溶解時についやってしまいがちな「これやっちゃダメ!」な行為をワースト3形式でご紹介します。
理由もしっかり理解して、今日からヒヤリハットを完全回避しましょう!✨
ワースト1:電子レンジでチン!は絶対NG!⚡️
- なんでダメなの?:
電子レンジは食品を温めるのには便利ですが、血液製剤の溶解には絶対に使ってはいけません!🙅♀️
電子レンジのマイクロ波は、製剤を均一に温めることができず、一部分だけが極端に高温になってしまいます。
これにより、FFPなどに含まれる大切なタンパク質(凝固因子など)が熱で変性・破壊され、輸血の効果が全くなくなってしまうどころか、有害な物質が生成される可能性も…。
また、バッグが破裂する危険性もあります。 - 正しい対処法:
必ず30~37℃に温度管理された恒温槽(ウォーターバス)や専用のFFP融解装置を使用しましょう。
ワースト2:熱湯にジャブン!高温すぎるお湯での急速溶解🌡️💨
- なんでダメなの?:
「早く溶かしたいから!」と、沸騰したお湯や40℃を大幅に超えるような高温のお湯にFFPを直接入れるのは非常に危険です!
ワースト1の電子レンジと同様に、タンパク質の熱変性が起こり、凝固因子が失活してしまいます。
また、バッグの材質が熱で劣化し、破損や汚染のリスクも高まります。 - 正しい対処法:
溶解温度は厳守!30~37℃の範囲で、温度計で確認しながら行いましょう。急がば回れ、です。
ワースト3:融解したFFPを「もったいないから」と再凍結🧊➡️❄️
- なんでダメなの?:
一度融解したFFPは、たとえ未使用であっても再凍結してはいけません。
融解と凍結を繰り返すことで、凝固因子の活性が著しく低下し、品質が劣化してしまいます。
また、融解の過程で目に見えない細菌が混入・増殖している可能性も否定できません。 - 正しい対処法:
FFPは使用する直前に必要な量だけを融解するのが基本です。
もし融解後に使用できなくなった場合は、施設のルールに従って適切に廃棄するか、速やかに輸血管理部門に相談しましょう。
2~6℃で保管し、24時間以内であれば使用可能な場合もありますが、これも施設の規定を必ず確認してください。
これらの「やっちゃダメ!」行為は、患者さんの安全を脅かすだけでなく、貴重な血液製剤を無駄にしてしまうことにも繋がります。
一つ一つの作業に潜むリスクを理解し、安全な手順を徹底することが大切ですね!😉
意外と知らない?溶解装置(ウォーターバス等)の正しい使い方と清掃・点検のツボ🛠️
FFPなどの血液製剤を安全かつ適切に溶解するために欠かせないのが、恒温槽(ウォーターバス)やFFP専用融解装置ですよね!😊
でも、毎日使っているその装置、本当に正しく使えていますか?
そして、清掃や点検はバッチリでしょうか?
ここでは、意外と見落としがちな溶解装置の正しい使い方と、清潔を保つための清掃・点検のツボをご紹介します!✨
溶解装置(ウォーターバス)の正しい使い方:基本のキ!
1.使用前には必ずチェック! ✅
- 水位は適切ですか? 水が少なすぎると温度が不安定になったり、空焚きの原因になったりします。多すぎても溢れる可能性が。適切な水位を保ちましょう。
- 水は清潔ですか? 古い水や汚れた水は細菌汚染の原因になります。定期的な水の交換が必要です。
- 温度設定は正しいですか? FFPなら30~37℃が基本です。使用前に必ず設定温度と実際の水温が一致しているか温度計で確認しましょう。
2.製剤の入れ方にもコツが! 💧
- 凍結した製剤は、破損を防ぐためにも丁寧に取り扱いましょう。
- 製剤バッグを直接水に浸けるのではなく、専用のビニール袋に入れるか、専用のホルダーを使用しましょう。汚染防止と、バッグのラベル保護のためです。
- 一度にたくさんの製剤を詰め込みすぎないように注意!お湯が均一に循環しなくなり、溶解ムラができる原因になります。
3.溶解中も気配りを! 👀
- 時々、製剤の様子を確認し、均一に溶解するように優しく撹拌しましょう。
- 溶解が完了したら、速やかに取り出します。長時間放置すると、逆に製剤の温度が上がりすぎたり、細菌増殖のリスクが高まったりします。
4.使用後は必ず清掃! 🧼
- 使用後は毎回、槽内の水を抜き、内部を清掃・乾燥させましょう。
清掃と点検のツボ:長持ち&安全のために! 🛠️
| 清掃・点検項目 | 具体的な内容と頻度の目安 | なぜ大切なの? |
|---|---|---|
| 槽内の清掃 | 使用後毎回:水を抜き、柔らかい布やスポンジで内部の汚れを拭き取る。必要に応じて中性洗剤を使用し、よくすすいで乾燥させる。 | 水垢や細菌の繁殖を防ぎ、常に清潔な状態で使用できるようにするため。細菌汚染は輸血において致命的です! |
| 水の交換 | 毎日または定期的に(施設のマニュアルに従う)。特に汚れが目立つ場合は速やかに交換。 | 清潔な水を使用することで、細菌汚染のリスクを低減します。 |
| 温度計の校正 | 定期的(施設のマニュアルに従う)。標準温度計と比較し、表示温度にズレがないか確認する。 | 正確な温度管理は製剤の品質維持に不可欠!温度がズレていると、気づかないうちに不適切な温度で溶解している可能性も…。 |
| 外観の確認 | 日常的に:電源コードに損傷はないか、本体にひび割れや破損はないか、操作パネルは正常に機能するかなどを確認する。 | 安全な使用のため、また故障の早期発見に繋がります。 |
| アラーム機能の確認 | 定期的(施設のマニュアルに従う):温度異常などを知らせるアラーム機能が正常に作動するかテストする。 | 万が一、温度が設定範囲から外れた場合に、すぐに気づけるようにするため。 |
| メーカー推奨の点検 | 定期的(メーカーの指示や施設のマニュアルに従う):専門業者による定期点検や部品交換が必要な場合もあります。 | 装置の性能を維持し、安全に長期間使用するために重要です。 |
これらの使い方や清掃・点検を習慣にすることで、溶解装置を常にベストな状態に保ち、安全な血液製剤の溶解作業を行うことができます。
日々のちょっとした心がけが、患者さんの安全を守る大きな力になるんですね!😊💪

これでカンペキ!血液製剤取り扱いマスターへの最終チェックリスト✅✨
お疲れ様でした!
ここまで「血液製剤【種類別】取り扱いガイド:保管・溶解の重要ポイント3選」を読んでくださって、本当にありがとうございます😊
きっと、たくさんの血液製剤の種類ごとの特徴から、それぞれの正しい保管方法🌡️、そしてカチコチに凍った製剤を安全に溶かす大切なコツ💧まで、たくさんの知識が頭に入ったのではないでしょうか?💡
この記事でお伝えしてきた、
- ポイント①:血液製剤の種類と特徴をしっかりマスターすること📚
- ポイント②:「冷やしすぎ?温めすぎ?」を防ぐ!製剤別・正しい保管テクニック🌡️✨
- ポイント③:安全第一!血液製剤の確実な溶解方法と「うっかり」防止策💧✅
これらの3つの重要ポイントは、どれも患者さんの命と安全に直結するとっても大切なことです。
最初は覚えることが多くて大変かもしれませんが、一つ一つ丁寧に確認しながら実践していくことで、必ずあなたの大きな力になります💪✨
「輸血の準備、前よりスムーズにできるようになったかも!」
「この製剤の扱いはこうだったな、って自信を持って判断できた!」
そんな風に、日々の看護業務の中でこの記事の内容が少しでもお役に立ち、「あれ、どうだったっけ?」と思った時の頼れるお守りのような存在になれたら、私たちもとっても嬉しいです🥰





