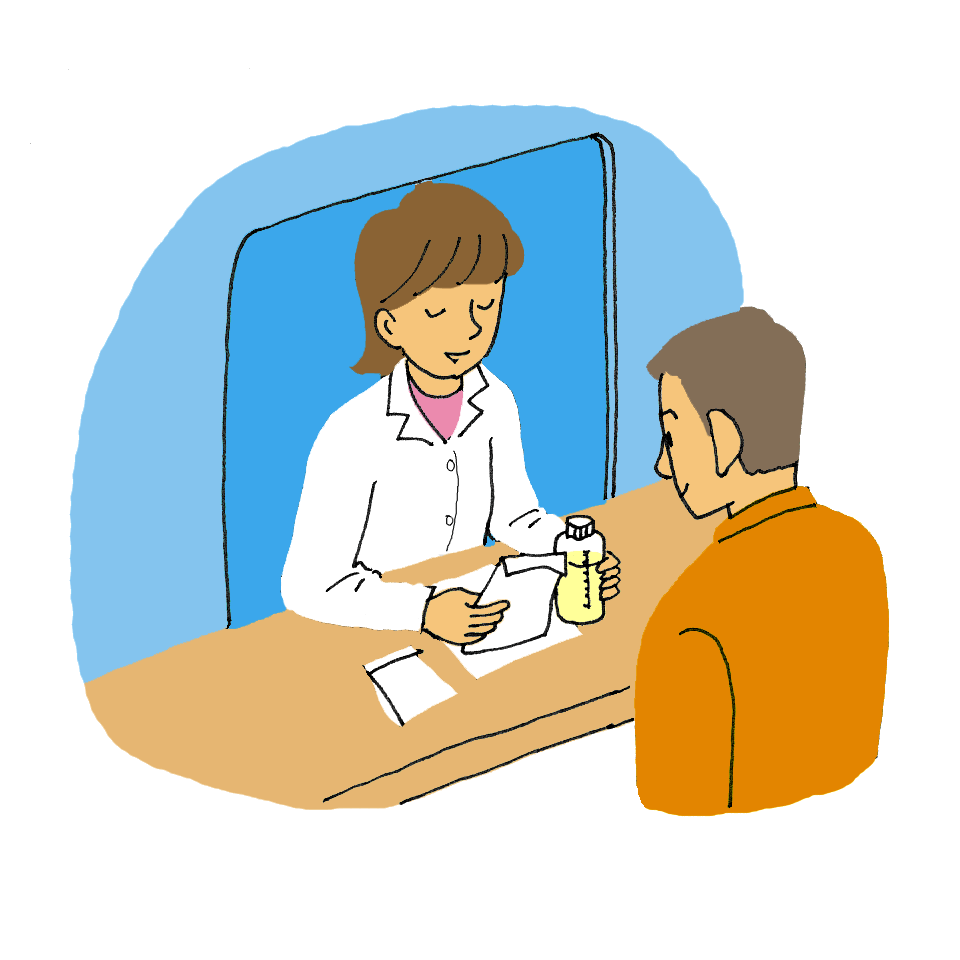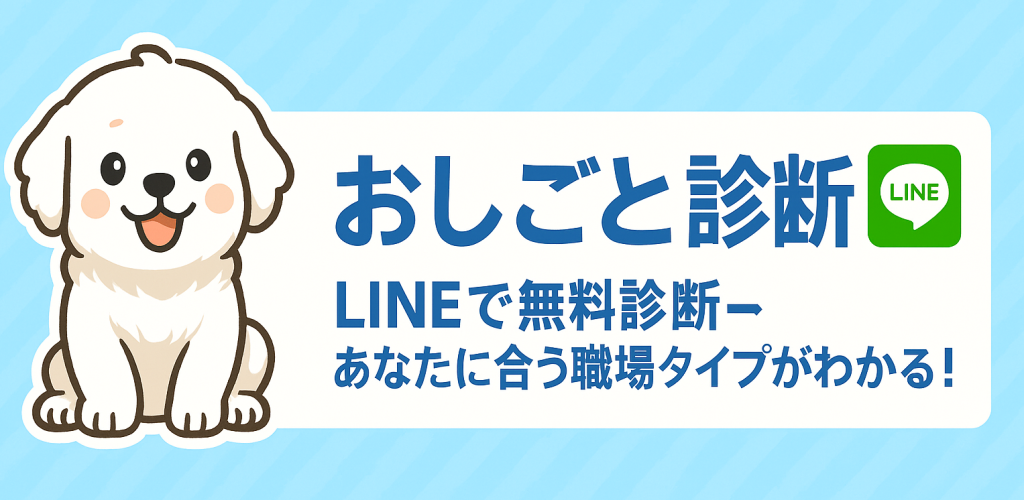実践!6Rの確認タイミングと具体的なチェックリストで与薬マスターに💉✨
6Rの知識はバッチリですね!👏
でも、知識があるだけじゃなくて、実際に「いつ、どうやって」確認するかがすごく大切なんです。
ここからは、新人看護師さんが自信を持って与薬できるように、具体的な確認のタイミングとチェックリストをご紹介しますね!
一緒に見ていきましょう!😉
与薬時の3回確認でミスを徹底防止!🛡️
与薬では、薬剤の取り間違いや用量の間違いを防ぐために、最低でも3つのタイミングで確認を行うのが基本です。
一つひとつの確認を確実に行うことで、より安全に与薬を進めることができますよ。
1.指示受け時・準備前確認
- タイミング:
医師からの指示を受け取った時、または薬剤庫から薬を取り出す前
- なぜ大切?:
与薬プロセスの最初の段階でミスを見つけることで、その後の工程での間違いを未然に防ぎます。
2.薬剤準備時確認
- タイミング:
実際に薬剤を準備する時(例:薬包から取り出す、注射器に吸い上げるなど)
- なぜ大切?:
最も間違いが起こりやすいのがこの準備段階です。
処方箋と現物の薬剤を細部まで照合することで、取り間違いや用量のミスを防ぎます。
3.患者さんへの投与直前確認
- タイミング:
患者さんのベッドサイドで、実際に薬剤を投与する直前
- なぜ大切?:
最後の砦となる確認です。
ここで最終チェックを行うことで、ベッド間違いや患者さんの状態変化による与薬の不適合などを発見できます。

薬剤を元の場所に戻すときの+1確認をするともっと確実ですよ🌟
各タイミングでの具体的なチェックリスト📝
では、それぞれのタイミングで具体的に何をチェックすれば良いのか、リスト形式で確認していきましょう!
このチェックリストを参考に、あなた自身の確認ルーティンを作ってみてくださいね。
1. 指示受け時・準備前確認チェックリスト
2. 薬剤準備時確認チェックリスト
3. 患者さんへの投与直前確認チェックリスト
これらのチェックリストを参考に、ぜひあなた自身の与薬ルーティンを確立してくださいね。
慣れてくるとスムーズにできるようになりますが、どんなに忙しくても、この確認だけは絶対に省略しないようにしましょう!
「もっといろいろな薬に触れたい!」
「抗がん剤とか今まで取り扱ったことがないから勉強するために転職をしたいけど…」
どんなお悩みもおまかせ🌟
lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉
 おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。
おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。
6Rをさらに深掘り!医療安全のための応用知識💡
看護の現場では予測できないことや、もっと深く考えるべき場面もたくさんあります。
ここでは、6Rをさらに一歩進めて、より医療安全を高めるための応用知識をお伝えしますね。
患者さんをあらゆる危険から守るために、一緒に学んでいきましょう!💪
類似薬剤・紛らわしい患者への対策💊👤
与薬ミスの中でも特に多いのが、似ている薬や紛らわしい名前の患者さんに関するものです。
ヒューマンエラーを防ぐための具体的な対策を知っておきましょう。
- 声出し確認の徹底:
薬剤名や患者さんのフルネーム、生年月日などは、声に出して指差し確認しましょう。「〇〇さん、〇〇というお薬ですね」と、五感を使いながら確認することで、脳への情報定着率が高まります。
- 高リスク薬剤の管理:
インスリンや麻薬など、特に少量でも患者さんに大きな影響を与える「高リスク薬剤」は、厳重な管理と複数人での確認が必須です。
専用の保管場所を設けたり、色や形が似ている薬とは離して保管したりする工夫も大切です。
- 個別トレーの活用:
複数人の患者さんの薬を一度に準備する際は、必ず一人ずつ個別のトレーに入れましょう。
途中で他の患者さんの薬と混ざってしまうリスクを減らせます。
- インシデント事例から学ぶ:
過去の与薬ミス事例(インシデントレポートなど)を学び、どのような状況でミスが起きやすいのかを知ることは、再発防止に繋がります。
自分の病院での事例だけでなく、他施設の事例も参考にすると良いでしょう。
緊急時の6R:焦らず、確実に!🚑
救急外来や急変時など、一刻を争う状況では、つい確認がおろそかになりがちです。
しかし、そんな時こそ6Rの原則が重要になります。
焦る気持ちを抑え、最低限これだけは確認するというポイントを押さえましょう。
- R1(正しい患者)とR2(正しい薬剤)の最優先確認:
時間がない中でも、「誰に」「何を」投与するのかは絶対に間違えてはいけません。
医師の指示を複数人で復唱確認したり、可能であれば別の看護師にもダブルチェックを依頼したりしましょう。
- 声出しと指差しの徹底:
忙しい時ほど、基本に立ち返って声出し・指差し確認を徹底します。
周囲に状況を伝えることで、他のスタッフからの気づきにも繋がります。
- 簡潔な情報共有:
周囲の医療従事者と情報共有する際は、薬剤名、用量、投与経路を簡潔に伝え、認識のずれがないかを確認しましょう。
患者さんへの説明と同意 (Right Patient Education / Right Consent) の重要性🗣️🤝
与薬の6Rに加えて、近年では「Right Patient Education(正しい患者への説明)」や「Right Consent(正しい同意)」を含めて、7R、8Rとして考えることもあります。
患者さんの理解と協力を得ることは、与薬の安全性を高める上で非常に大切なんです。
- 分かりやすい説明:
患者さんに、「何の薬を、何のために、どのように使うのか」を分かりやすい言葉で説明しましょう。
副作用や注意点についても、必要に応じて伝えます。
- 質問への対応:
患者さんからの質問には丁寧に答え、疑問や不安を取り除きましょう。
患者さんが納得して薬を服用(使用)することが大切です。
- 服薬状況の確認:
患者さんが本当に指示通りに服薬できているか、また、薬によって体調に変化がないかを定期的に確認しましょう。
アドヒアランス(服薬遵守)の向上にも繋がります。
記録の重要性 (Right Documentation) ✍️
与薬のプロセスにおいて、「Right Documentation(正しい記録)」もまた、非常に重要な要素です。
記録は、与薬の事実を証明するだけでなく、万が一の際に原因究明や再発防止に役立つ、大切な情報源となります。
- 正確な記録:
いつ、誰に、何を、どのくらい、どのように投与したのかを、正確に記録しましょう。
投与後の患者さんの反応(効果や副作用など)も併せて記録すると、より情報が豊かになります。
- 速やかな記録:
投与後、できるだけ速やかに記録を行いましょう。
時間が経つと記憶が曖昧になり、記録漏れや間違いの原因となることがあります。
- 抜け漏れのない記録:
薬剤名、用量、投与経路、投与時間、投与者のサインなど、必要な項目は全て記入しましょう。
電子カルテの場合は、必須項目が設定されていることが多いので、それに従ってください。
これらの応用知識は、日々の業務の中で意識し、実践していくことで身についていきます。
一つ一つの確認を丁寧に行うことが、患者さんの笑顔と安全に繋がる大切な一歩ですよ!
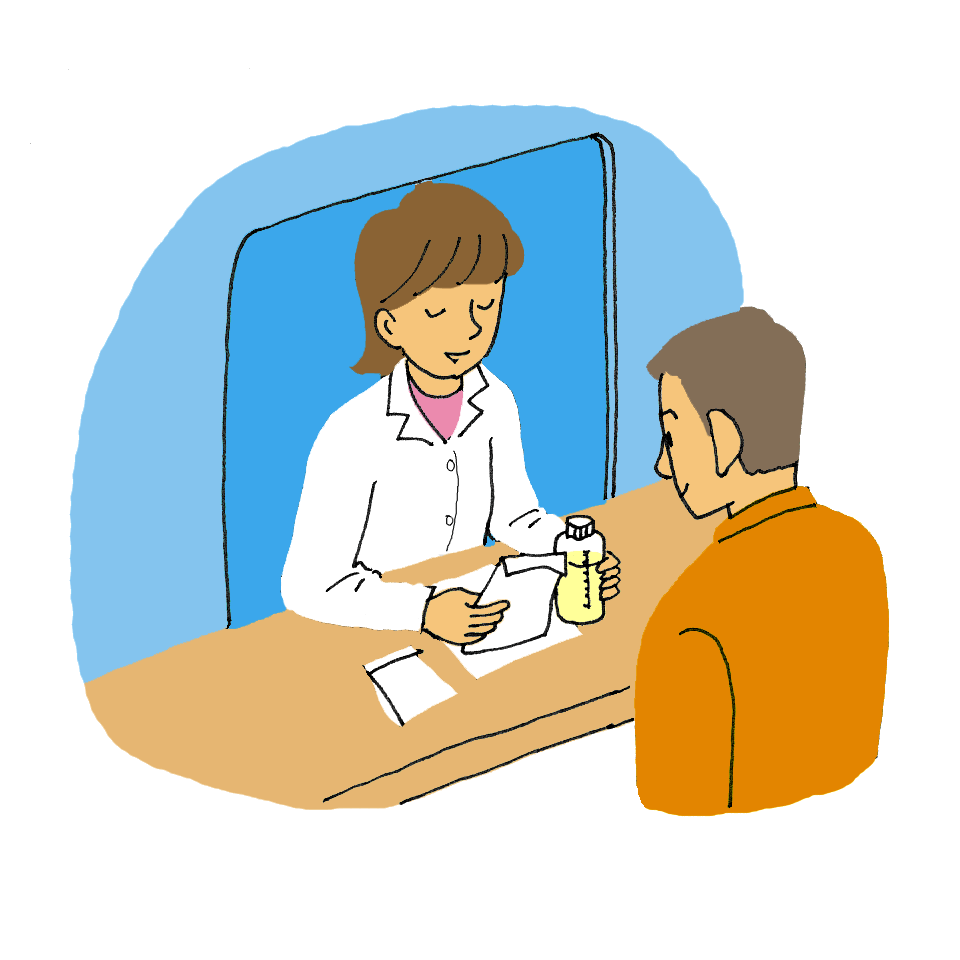
よくある疑問Q&A:与薬の「困った!」を解決しよう💡
与薬の基本や応用知識を学んできましたが、実際の現場では「これでいいのかな?」と迷ってしまう瞬間ってありますよね。
特に新人看護師さんは、ちょっとした疑問でも「誰に聞けばいいんだろう…?」と悩んでしまうかもしれません。
ここでは、与薬に関する“あるある”な疑問にお答えしていきます!一緒に不安を解消していきましょう!😊
Q1. 同姓同名の患者さんがいる場合、どうやって確実に確認すればいいですか?
「〇〇さんと△△さん、お名前は一緒だけど、下の名前が違う…でも似てる!」なんてこと、ありますよね。
そんな時は、単に名前を呼ぶだけでは不十分です。
- A. フルネーム+生年月日の確認を徹底しましょう! 🎂
患者さんにフルネームを名乗ってもらい、さらに「〇〇年〇月〇日生まれの〇〇さんで間違いありませんか?」と、生年月日も確認することで、本人確認の精度が格段に上がります。
可能であれば、リストバンドのバーコード認証や写真付きのネームプレートで視覚的に照合するのも非常に有効です。
電子カルテの画面でも、患者さんの顔写真が表示されるように設定されている場合は、それも併せて確認すると良いですね。
Q2. 医師の指示が不明瞭な場合、どうすればいいですか?
「この薬、何mgって書いてあるんだろう?」「投与経路が書いてない…」😵💫
指示が曖昧だと、そのまま与薬するのは危険です。
- A. 必ず医師に確認しましょう! 📞
曖昧な指示や不明な点があるまま与薬を行うのは、重大な医療事故に繋がりかねません。
どんなに忙しい時でも、必ず指示を出した医師に直接確認し、明確な指示を得てから与薬するようにしてください。
口頭での指示の場合は、必ず復唱確認を行い、可能であればその場でカルテに記載してもらうか、後で速やかに記録に残しましょう。
上司や先輩看護師に相談することも大切です。
(それにしても医師の字が読めないこと多いですよね😨)
Q3. 患者さんが薬の服用を拒否した場合、どう対応すればいいですか?
「この薬は飲みたくない」「もう痛くないからいらない」など、患者さんが薬を拒否することもありますよね。
無理やり飲ませるのは良くありません。
- A. まずは理由を傾聴し、解決策を探りましょう👂
なぜ拒否するのか、その理由を丁寧に聞き出すことが大切です。
「苦いから」「副作用が怖い」「気分が悪い」など、様々な理由が考えられます。
理由が分かれば、服薬の必要性を改めて分かりやすく説明したり、薬剤師と相談して剤形変更(例:錠剤から粉薬へ)を検討したり、他の時間にずらせないか医師に確認したりするなど、解決策が見つかるかもしれません。
それでも拒否が続く場合は、その旨を医師に報告し、今後の対応を相談しましょう。
決して強制せず、患者さんの意思を尊重することが重要です。
Q4. 複数の患者さんの薬を同時に準備する際の注意点はありますか?
バタバタと忙しい時間帯に、たくさんの患者さんの薬をまとめて準備したくなる気持ち、すごく分かります。
でも、ここが一番注意が必要です⚠️
- A. 一人分ずつ確実に、個別トレーで管理しましょう!
複数人の薬を同時に扱うと、取り違えのリスクが格段に上がります。
基本は、一人分の薬を全て準備し、確認が完了してから次の患者さんの薬の準備に取り掛かるようにしましょう。
個別トレーや薬ケースを活用して、薬が混ざらないように徹底してください。
もし途中で中断せざるを得ない状況になったら、必ず準備中の薬を一時的に安全な場所に保管し、再開時に最初から確認し直す習慣をつけましょう。
Q5. 注射薬を調製する際、特に気をつけることは何ですか?
注射薬は直接体内に投与されるため、与薬の中でも特に厳密な管理が求められます。
- A. 溶解液の種類や量、混和の確認を怠らないで! 💉
注射薬の中には、使用前に水や生理食塩水などの溶解液で薄める(希釈する)必要があるものがあります。
その際、正しい種類の溶解液を、正しい量で加えることが非常に重要です。
溶解液を間違えたり、量が違ったりすると、薬の効果に影響が出たり、患者さんに有害な作用が出たりする可能性があります。
調製後は、薬剤が均一に混ざっているか、薬液に異物や濁りがないかも必ず確認してください。
調製の場合は、ダブルチェックを必ず行いましょう。