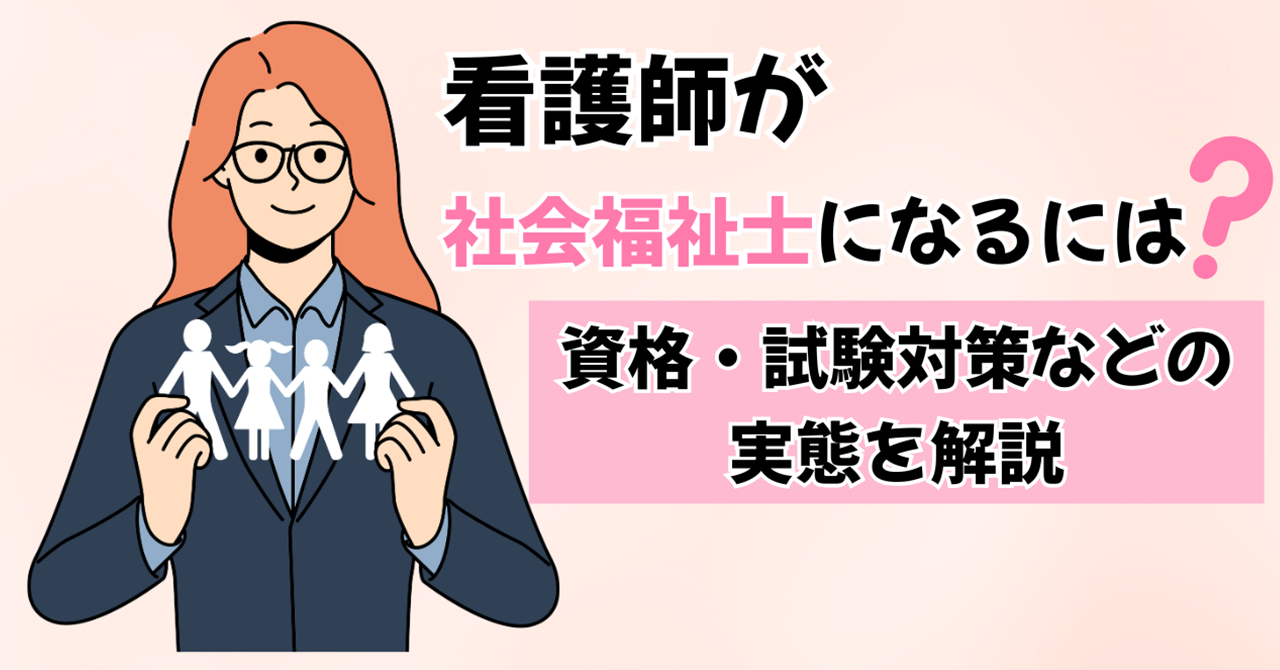
社会福祉士を目指す上で様々な不安を抱えていませんか?
「社会福祉士を目指したいけど、試験が心配…」
「社会福祉士になったら、どこで活躍できるの?」
「忙しい中でちゃんと勉強できるのか…」
現在、社会で社会福祉士が求められ、看護師と社会福祉士のダブルライセンスで活躍している人も多いです。看護師として忙しく働く中での資格取得に不安を抱えてしまいますが、学校を「通信制」にしたり、空き時間に勉強したりとコツコツ努力を重ねれば、きっと合格できます!効率的な勉強を一緒に確認していきましょう。
この記事では、以下のような内容を紹介します:
看護師が社会福祉士を目指す理由
社会福祉士の受験資格と取得ルート
活躍の場
展望とキャリアアップ
Q&A
プロの現場を知る看護師目線で、「社会福祉士の気になるアレコレ」を解説しています。ぜひブックマークして、社会福祉士について調べるときに役立ててくださいね。
看護師が社会福祉士を目指す理由は?メリット・デメリットも
看護師として日々患者さんに向き合う中で、「医療行為の先にある生活支援にも関わりたい」と感じたことはありませんか?その想いを実現する、社会福祉士です。
現在、多くの看護師が社会福祉士の資格取得を検討しています。その背景にある想い、看護師×社会福祉士のダブルライセンスがもたらす具体的なキャリアの可能性、そしてメリット・デメリットを詳しく解説します。
なぜ看護師が社会福祉士の資格取得を検討するのか?
看護師が社会福祉士の資格取得を目指すのは、患者さんへの包括的な支援が求められているから。病気の治療だけでなく、患者さんの抱える生活課題にも対応するために、医療と福祉両方の視点が必要とされています。
また、「医療現場での経験を活かし、キャリアの幅を広げたい」という動機もあるでしょう。退院後の生活支援や地域連携において、社会福祉士の専門性は高く評価されます。超高齢社会では、両方の知識を持つ人材の需要はますます高まることが予想されます。
さらに、自身の専門性を深め、より質の高いケアを提供したいという向上心も背景に。複雑なケースに対応できるようになり、仕事のやりがいも増すため、資格取得は大きなメリットとなります。
看護師×社会福祉士のダブルライセンスで広がるキャリア
看護師と社会福祉士のダブルライセンスは、医療と福祉の両面から患者さんを支える新たなキャリアパスを拓きます。これにより、単なる治療だけでなく、患者さんの生活背景や社会的な課題にも深く踏み込んだ支援ができます。
たとえば、病院内では退院支援や医療相談のスペシャリストとして、患者さんが安心して地域生活へ移行できるよう、医療チームと福祉サービスとの橋渡し役に。また、地域包括支援センターや訪問看護ステーションなどでは、在宅医療と介護、福祉の連携を強化する要として、より複雑なニーズに対応できる人材として重宝されます。
さらに、行政機関やNPO法人、企業など、従来の看護師の活躍の場を超えて、地域全体のヘルスケアシステム構築に貢献する道も開けるでしょう。
今後ますます少子高齢化が進む現代において、医療と福祉の垣根を越えて活躍できるダブルライセンスの専門家は、社会から頼られる存在になるはず。

看護師経験が社会福祉士の仕事でどう活かせる?
看護師として培った経験は、社会福祉士の業務で大いに役立ちます。たとえば、次のような能力が活躍します。
- コミュニケーション能力:
患者さんとの関わりで培った傾聴力や共感力は、相談援助に必須です。 - アセスメント能力:
患者さんの状態を多角的に判断する力は、問題の本質を見極め、適切な支援計画を立てる上で役立ちます。 - 医療知識:
医療機関での連携や、患者さんの状態理解に直結するでしょう。 - 多職種連携の経験:
医師や他職種との協働経験は、福祉分野での連携にも活かされます。 - 倫理観と責任感:
- 人々の尊厳を守るという社会福祉士の職務において、看護師として培った倫理観は重要な基盤となります。
これらの経験は、社会福祉士として質の高い支援を提供する上での強力な土台になるはず!
ダブルライセンスのメリット・デメリットを徹底比較【給料・仕事内容・働き方】
看護師と社会福祉士のダブルライセンスは多くの魅力がありますが、取得には時間と労力が伴います。メリットとデメリットもしっかり把握しておきましょう。
メリット
- 給料面:
専門性の高い職種への転職や、昇進・昇給のチャンスが増える可能性があります。 - 仕事内容の広がり:
医療から福祉まで、より幅広い視点から患者さんをサポートできるので、仕事のやりがいが増します。 - 働き方の選択肢:
夜勤のない日勤常勤や土日休みの仕事を選びやすくなり、ワークライフバランスの改善に繋がります。 - キャリアの安定性:
医療と福祉の両分野でニーズが高まる中、安定したキャリアを築きやすくなります。
デメリット
- 資格取得までの時間と費用:
養成施設への通学や通信教育には、相応の時間と学費がかかります。 - 学習の負担:
看護師業務と並行しての学習は、精神的・肉体的な負担が大きくなります。 - キャリアチェンジに伴う初期給与:
社会福祉士として未経験の職場では、一時的に給与が下がる可能性も。 - 役割の複雑さ:
医療と福祉の境界線で、自身の役割に悩む場面が生じることもあるでしょう。
これらの点を理解し、あなたのキャリアプランに合った選択をすることが大切!
社会福祉士の受験資格と取得ルートを徹底解説
実際に受験資格や取得までの道のりはどうなのでしょう?ここで、あなたの現在の学歴や実務経験に合わせた最適なルートや、忙しい看護師さんでも働きながら資格を目指せる「通信制」の選択肢、さらに養成施設の費用と学習期間の目安などをチェックしていきましょう。
【学歴・実務経験別】社会福祉士になるための主なルート
社会福祉士になるには、さまざまなルートがあります。最終学歴や実務経験によって、受験資格を得るための道のりが異なります。主なルートを紹介するので、あなたの状況に合わせて、最適なルートを見つけてみましょう。
| 福祉系大学卒業者(指定科目を履修) | 大学で指定科目を履修していれば、卒業後すぐに受験資格が得られる。 |
| 福祉系短大卒業者(指定科目を履修) | 短期大学で指定科目を履修した場合、実務経験(相談援助業務)を1〜2年積むことで受験資格が得られる。 |
| 一般大学卒業者 | 福祉系の大学を卒業していない場合でも、一般の大学を卒業していれば、社会福祉士養成施設(1年または2年)を修了することで受験資格が得られる。 |
| 一般短大・専門学校卒業者 | 相談援助業務の実務経験を積んだ上で、社会福祉士養成施設を修了する必要がある。 |
| 実務経験者 | 高卒などで福祉に関する実務経験が長くある場合は、特定の条件を満たした上で社会福祉士養成施設を修了することで受験資格が得られる。 |
看護師におすすめ!働きながら資格取得を目指す「通信制」の選択肢
忙しい看護師にとって、働きながら社会福祉士の資格取得を目指すなら、「通信制」の養成施設がおすすめです。場所や時間に縛られずに自分のペースで学習を進められる点が魅力!次のようなメリットもあります。
- 学習の自由度:
業務の合間や休日など、空いた時間を有効活用して学習できます。通学型のように決まった時間に学校へ行く必要がないため、夜勤など不規則な勤務形態の看護師でも無理なく学習を続けられるはず。 - 費用を抑えられる可能性:
通学型に比べて学費が比較的安価な場合が多いです。また、交通費や引越し費用などがかからない点もメリットでしょう。 - 自宅で学習可能:
多くの学習が自宅で完結するため、通勤時間を学習に充てることも◎。
ただ、自己管理能力が求められること、スクーリング(対面授業)や実習が必須となる場合がある点には注意が必要です。事前に各養成施設のカリキュラムをしっかり確認しましょう。

【効率的な学習計画の立て方】社会福祉士養成施設の費用と期間の目安は?
社会福祉士養成施設の費用と期間は、選択するルートや施設の種類によって大きく異なります。費用と期間の目安は次の通り。
| 費用 | 期間 | |
| 通学制の大学・短大(新卒で目指す場合) | 数十万円〜数百万円(一般的な学費に準ずる) | 2年〜4年 |
| 社会福祉士養成施設(一般大学卒業者、通信制・通学制) | 通信制で20万円〜40万円程度、通学制で50万円〜100万円程度 | 通信制で約1年〜1年半、通学制で約9ヶ月〜1年 |
社会福祉士の資格取得を目指すために、計画的に学習を進めましょう。次のようなことを行うと効率的に進むはず!
- 目標設定とスケジュール作成:
いつまでに資格を取得したいのか具体的な目標を立て、そこから逆算して週ごと、日ごとの学習時間を割り振ります。特に国家試験までの期間を見据え、無理のない計画を立てましょう。 - インプットとアウトプットのバランス:
テキストや講義でのインプットだけでなく、過去問演習や模擬試験など、アウトプットの時間を十分に確保することが大切です。 - 弱点の克服:
苦手分野や理解が難しいと感じる箇所は、重点的に時間を割いて学習しましょう。必要であれば参考書や問題集を追加することも◎。 - 隙間時間の活用:
移動時間や休憩時間など、短時間でも学習できる環境を整え、効率的に知識を定着させましょう。スマートフォンアプリや音声教材なども活用できます。 - モチベーション維持:
一人で学習する通信制では、モチベーションの維持が課題になりがち。定期的に学習仲間と情報交換したり、オンライン学習コミュニティに参加したりして、励まし合う環境を作るのも効果的です。
社会福祉士国家試験の難易度と効果的な対策
社会福祉士国家試験は、決して簡単な試験ではありませんが、適切な対策と効率的な学習方法を知れば、合格はできます。
ここでは、厚生労働省のデータに基づいた試験の合格率と傾向、看護師の皆さんのための効果的な勉強法、そして忙しい仕事と勉強を両立させるための時間管理術を詳しく解説します。
社会福祉士国家試験の合格率と傾向【厚生労働省データから】
社会福祉士国家試験の合格率は、例年30%前後で推移しています。これは、他の医療・福祉系国家試験と比較しても決して高い数字ではありません。
主な傾向として、次のような点が挙げられます。
- 幅広い出題範囲:
精神医学、心理学、社会保障、福祉サービスなど、多岐にわたる分野から出題されます。 - 事例問題の増加:
知識だけでなく、実際の場面での応用力を問う事例問題が増加傾向にあります。 - 法改正への対応:
社会保障制度や関連法規の改正が頻繁に行われるため、常に最新の情報にアップデートする必要があります。
厚生労働省の発表する過去の合格率や試験概要を定期的に確認し、出題傾向を把握するのも資格取得への道です。
※参照:厚生労働省、公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
看護師のための社会福祉士試験対策:効率的な勉強法とは?
忙しい中でも社会福祉士試験を突破するために、効率的な勉強法を実践しましょう。
- 基礎知識の徹底:
まずはテキストや参考書で、社会福祉の基本的な概念や制度をしっかりと理解します。特に、医療との関連性が深い分野は、看護師としての知識を活かせる部分です。 - 過去問演習の徹底:
過去問を繰り返し解くことで、出題形式や傾向に慣れ、自分の弱点が見えてきます。間違えた問題は解説を読み込み、なぜ間違えたのかを理解することが重要です。 - 分野別の重点学習:
苦手な科目や、配点が高い分野には、より多くの時間を割いて重点的に学習しましょう。 - 法改正情報のキャッチアップ:
社会福祉に関する法改正は頻繁に行われます。厚生労働省のホームページや専門誌などで、常に最新情報を確認しましょう。 - グループ学習の活用:
職場の同僚やオンラインの学習グループで情報交換したり、問題を出し合ったりすることで、理解を深め、モチベーションに繋がります。看護師としての臨床経験を事例問題に応用する練習にもなるでしょう。

試験勉強と仕事の両立術|時間管理を徹底的に!
看護師の仕事と社会福祉士の試験勉強を両立させるには、徹底した時間管理が必要!焦らず着実に、自分に合ったペースで学習を進めることが、合格への鍵となります。たとえば、次のような両立術があります。
- 学習時間の「見える化」:
まずは1日のスケジュールを書き出し、どこに学習時間を確保できるかを見える化します。通勤時間、休憩時間、夜勤明けの短い時間など、細切れの時間も有効活用しましょう。 - 短期集中型の学習:
「この30分で〇〇を終わらせる」など、具体的な目標を設定し、集中して取り組むことで効率を高めます。長時間の学習よりも、短い時間でも毎日継続することが大切! - 優先順位の設定:
仕事の忙しさや体調に合わせて、その日の学習内容に優先順位をつけましょう。完璧を目指しすぎず、できる範囲で継続することが重要です。 - オン・オフの切り替え:
勉強する時間と休む時間のメリハリをつけましょう。無理なスケジュールは、心身の負担となり、かえって学習効率を下げてしまいます。好きなことやリラックスできる時間も確保し、ストレスを溜めないように! - 周囲の理解と協力:
家族や職場の同僚に、社会福祉士の勉強をしていることを伝え、理解と協力を得ることも大切です。応援してもらえる環境を作ることで、モチベーション維持にも繋がります。
ダブルライセンスで、どこで働ける?活躍の場と具体的な仕事内容
看護師と社会福祉士のダブルライセンスを持つことで、活躍の場は大きく広がります。医療現場だけでなく、地域や福祉施設など、多様な場所で、より深く人々の生活を支援できるようになりますよ!ここでは、それぞれの具体的な働き方と仕事内容を解説します。
病院・クリニックで活躍|退院支援や患者相談の最前線
病院やクリニックでは、医療ソーシャルワーカー(MSW)として働くのが主な活躍の場。主な役割は、患者さんが安心して退院し、地域で生活を続けられるよう支援することです。
具体的には、患者さんやその家族からの医療費、生活費、介護サービス、転院先に関する相談に応じます。看護師としての医療知識があるため、病状を理解した上での相談対応や、医師・看護師といった医療スタッフとの連携が非常にスムーズに!
医療と福祉の橋渡し役として、患者さんの退院後の生活の質向上に貢献する最前線の仕事です。

地域・福祉施設での働き方|相談支援から地域連携まで
病院を離れ、地域や福祉施設でもダブルライセンスは強力な武器に!地域包括支援センターでは、高齢者の総合的な相談を受け、介護保険サービスや地域の社会資源への繋ぎ役となります。
また、障害者支援施設や児童福祉施設などでは、利用者さんやその家族の生活相談、権利擁護、関係機関との調整を行うのも仕事です。
訪問看護ステーションでは、看護師として医療ケアを提供しつつ、社会福祉士の視点から生活環境の調整や福祉サービスの提案を行うことで、より包括的な支援が可能に。地域住民の生活を多角的に支える、非常にやりがいのある働き方でしょう。
社会福祉士資格取得後の展望とキャリアアップ
看護師が社会福祉士の資格を取得することは、単なるスキルアップ以上の価値を持ちます。それは、あなたのキャリアパスを大きく広げ、社会からの多様なニーズに応えられる専門職へと成長するための大きな一歩となるでしょう。
ここでは、ダブルライセンスを最大限に活かしたキャリアデザインや、将来の社会福祉士への需要、そして看護師経験がどのようにあなたの強みとなるかについてチェックしていきます。
ダブルライセンスを活かしたキャリアデザインとは?
看護師と社会福祉士のダブルライセンスは、キャリアに無限の可能性をもたらします。単一の資格では到達できなかった専門性や役割を担うことで、より深く、多角的に人々の支援に貢献できるはず。
| キャリアパスの方向性 | 具体的な役割・貢献 | 期待される効果 |
| 専門性を深める | 医療ソーシャルワーカー(MSW)として、退院支援や医療費相談のスペシャリストに。精神科看護師が精神保健福祉士も兼ねるように、特定の分野で医療と福祉の両面から深い知識と実践力を発揮する。 | 医療と福祉の連携を強化し、患者・利用者の切れ目のない支援を実現。 |
| 管理職・教育者を目指す | 医療機関や福祉施設でのチームリーダー、部門管理者、あるいは養成施設の教員として、医療福祉連携の推進や後進の育成に貢献する。 | 組織全体のサービス向上に寄与し、未来の医療福祉を担う人材を育成。 |
| 独立・起業を視野に入れる | 地域のコンサルタントや、独自の相談支援事業を展開。医療と福祉の知識を活かし、地域住民の多様なニーズに応える新たなサービスを創出する。 | 自身の専門性を最大限に活かし、社会貢献とビジネスの両立を目指す。 |
| 政策提言・研究に携わる | 医療や福祉の現場での経験に基づき、より良い制度設計や政策立案に関与する。研究機関で社会課題の解決に向けた研究を行う道も。 | 社会全体の福祉向上に貢献し、制度改革を推進。 |
将来、社会福祉士はどう求められる?
日本は超高齢社会を迎え、疾病構造の変化や地域包括ケアシステムの推進など、社会を取り巻く環境は大きく変化しています。このような中で、社会福祉士の役割と需要はますます高まると予想されます。
特に、次のような場面で社会福祉士への強いニーズがあります。
- 地域包括ケアシステムの強化:
医療・介護・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築において、多職種連携の中核を担う社会福祉士の役割は必要です。
退院後の生活支援や、地域の社会資源との連携において、その専門性が求められます。 - 複合的な課題への対応:
高齢者の孤立、子どもの貧困、引きこもり、虐待など、個人が抱える課題は複雑化・複合化しています。
医療知識を持つ社会福祉士は、これらの課題に対し、医療と福祉の両面から包括的なアプローチを提供できるため、その存在価値は非常に高いです。 - 権利擁護の推進:
認知症高齢者や障害を持つ方々など、社会的に弱い立場にある人々の権利を守り、尊厳ある生活を支えるための専門家として、社会福祉士の重要性は増しています。
看護師としての医療知識と経験を持つ社会福祉士は、これらの複雑な社会課題に対応できる「真のジェネラリスト」として、将来にわたって高い需要が見込まれます。
看護師としての経験が社会福祉士としての強みに変わる瞬間
看護師として培った経験は、社会福祉士の大きな強みに!たとえば、患者さんの「声なき声」を聴き取る観察力や、非言語的なサインを読み取る力は、相談援助に非常に役立ちます。医療現場での勤務経験は、医師や他職種との連携をスムーズにし、退院支援の信頼性を高めます。
さらに、病気が個人の生活や家族に与える影響を臨床経験から具体的にイメージできるため、その人らしい生活のためのきめ細やかな支援計画を立案できます。
そして、医療現場で培われた倫理観は、利用者の権利擁護や自己決定支援において、揺るぎない判断の基盤に。これらの経験が、社会福祉士として人々を真に支える力となるのです!

【Q&A】社会福祉士資格に関する疑問あれこれ
社会福祉士の資格取得を検討するとき、多くの疑問が浮かぶでしょう。ここでは、よくある質問を解説していきます。あなたの疑問をすっきり解消しましょう。
Q:社会福祉士と精神保健福祉士、ケアマネジャーの違いは?
A:これらはすべて福祉分野の専門職ですが、それぞれ専門とする領域が異なります。次の表を参考にしてみましょう。
| 社会福祉士 | 病気や貧困、家庭問題など、幅広い生活課題を抱える人々に対し、相談援助や社会資源への繋ぎ役として包括的な支援を行う。専門分野を特定せず、ジェネラリストとして活動する。 |
| 精神保健福祉士 | 精神的な課題を抱える方々(精神障害者など)に特化し、社会復帰や生活支援のための相談援助を行う。精神科医療機関や精神保健福祉センターなどで活躍。 |
| ケアマネージャー | 介護保険制度において、要介護認定を受けた高齢者が適切な介護サービスを受けられるよう、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う。主な対象は高齢者やその家族。 |
Q:実際、社会福祉士の資格は意味ない?
A:「社会福祉士の資格は意味がない」という意見は誤解です。超高齢社会の日本では、社会的なニーズが高く、専門性の公的な証明となり、キャリアの選択肢も広がるでしょう。
特に、看護師とのダブルライセンスは、医療と福祉の両面から深い支援ができる点で非常に価値が高く、活かし方次第で無限の可能性を持つ資格です。
Q:働きながら社会福祉士を目指す時に注意すべき点は?
A:働きながら社会福祉士を目指す際は、計画性と自己管理が鍵!通信制でも必要なスクーリングや実習のために学習時間の確保と職場の理解を得ること、無理のないスケジュールで体調を管理すること、モチベーションを維持する工夫、そして学費や受験費用の確認を欠かさずに行いましょう。
Q:社会福祉士に向いている人・向いていない人の特徴は?
A:社会福祉士に向いているのは、人の話をじっくり聞ける傾聴力、他者と円滑な関係を築けるコミュニケーション能力、冷静な判断力と問題解決能力、そして常に学び続ける意欲がある人!
一方、話を聞くのが苦手な人、感情的になりやすい人、指示待ちで行動できない人、地道な努力が苦手な人には向いていない可能性があります。

Q:「こんなはずじゃなかった」を防ぐ!取得前に確認すべきこと
A:資格取得後に後悔しないためには、まず社会福祉士の具体的な仕事内容を深く理解しましょう。勤務先によって業務内容や働き方が大きく異なるため、自身の希望と合致するか確認することが大切です。
また、給与水準を事前に把握し、特に看護師からの転職では一時的に給与が下がる可能性も考えましょう。最終的に、資格取得後のキャリアパスを明確にイメージすることが後悔を防ぐ上で重要なことです。
Q:看護師からの転職で失敗しやすいパターンとは?
A:看護師から社会福祉士への転職で失敗する主なパターンは、理想と現実のギャップ、給与や待遇面での不満が挙げられます。
また、医療現場とは異なる福祉現場での人間関係構築に戸惑ったり、自身の専門性をどう活かすかビジョンがなく中途半端に感じたりすることも失敗につながってしまいます。これらのリスクを避けるには、事前の情報収集と明確なキャリアビジョンが欠かせません。
まとめ|未来のキャリアのために後悔のない選択を!
看護師が社会福祉士の資格を持つことは、あなたのキャリアに新たな可能性と深みをもたらす、非常に価値ある選択!超高齢社会の日本では、医療と福祉の知識を兼ね備えた専門職の需要は高まる一方であり、あなたの活躍の場はどんどん広がるでしょう。
もちろん、資格取得には努力と時間が必要ですし、キャリアチェンジにはメリットもデメリットも存在します。しかし、本記事で解説した内容を参考に、適性や将来のビジョンをしっかりと見つめ、具体的な情報収集と計画を立てることで、「こんなはずじゃなかった」という後悔を防ぎ、未来のキャリアのための後悔のない選択ができるはずです。
あなたのペースで、そして、納得がいく形で「社会福祉士」を目指しましょう!





